「もくじ」へ戻る
前回へ戻る
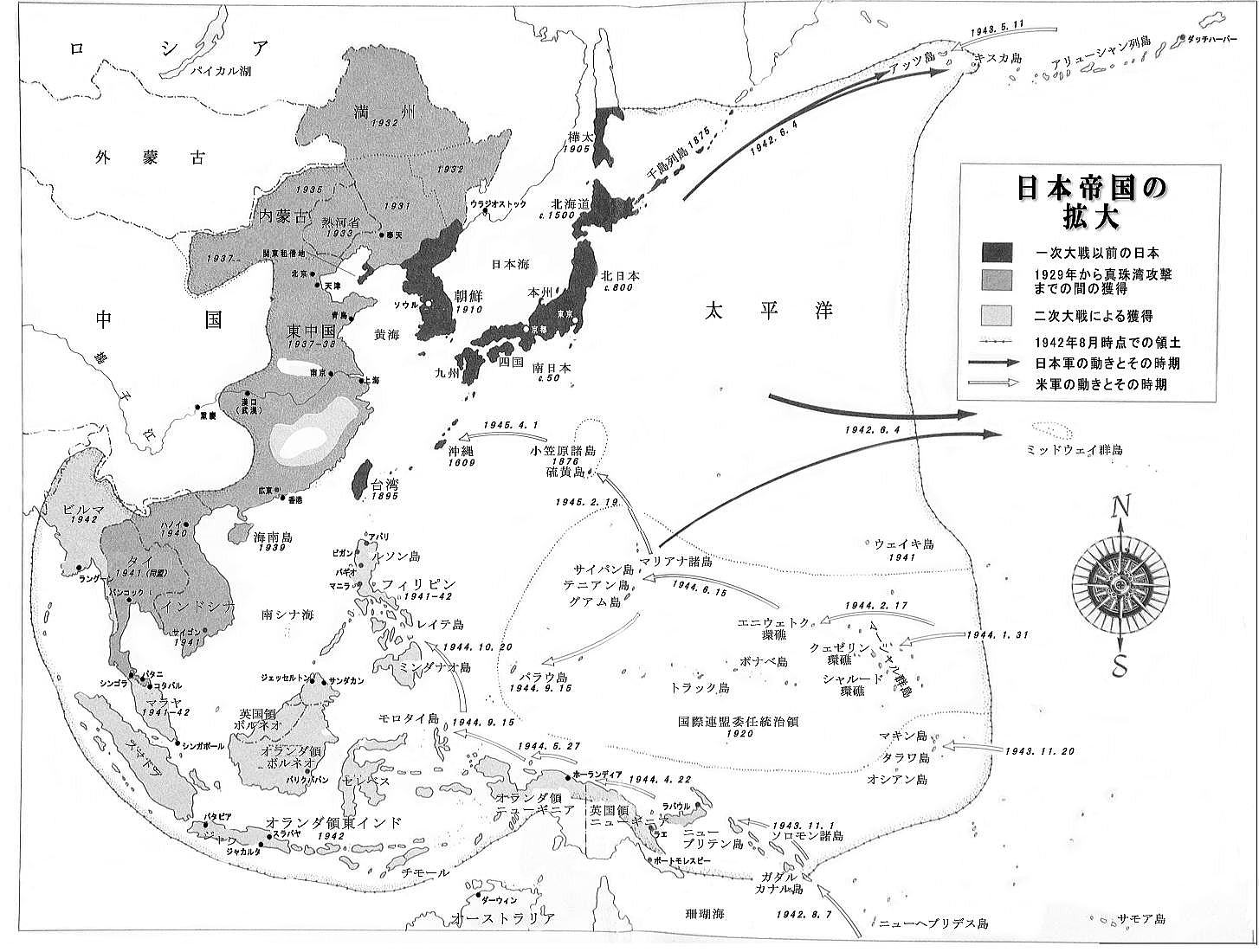
第六部 アジアの枢軸国 真珠湾 (1941) (その1) ゾルゲ逮捕(61) |
同スパイ団の一斉検挙は、1941年9月29日に始まり、特高警察はまず伊藤律〔ただす〕# 1を拘留した。破壊活動家として以前に逮捕、尋問された後、伊藤は意志を曲げて、警察への通報者となっていた(62)。そして、警察は彼に南満州鉄道調査部――1932年のテロの脅威の最中、テロリストと宮廷の間の連絡役を果たした大川周明博士が統括するスパイ機関――の仕事を与えた。その調査部〔東京に置かれていた〕で、同僚の中国専門家、尾崎秀実――ゾルゲスパイ団の一員で先に木戸内大臣や西園寺公一からの情報をソ連に送っていた――を監視するのが彼の職務だった。
- # 1 英語文献では、彼はこれまでその名を「りつ」と呼んで知られてきた。
先の9月11日、警察は、宮城与徳――沖縄生まれの画家で、1933年、米国共産党によりゾルゲを援助するために送り込まれていた――を逮捕していた。宮城はゾルゲスパイ団の中でただ一人、頑固に意志を通し、なんらの告白もしなかった。彼は、尋問の始まった週、特高警察の建物の上層階の窓から、飛び降りるか突き飛ばされるかし、木に引っ掛かって足の骨を折っただけですんだが# 2、最後は、1943年8月、刑務所で死んだ。
- # 2 アメリカ国籍の宮城は、共産党スパイとしてだけでなく、米国のスパイとしても怪しまれていた。反米の好戦感情が高まった最初の年、特高警察にとって、彼が存在しているだけで、ゾルゲスパイ団の他の者の取扱いを極めて複雑にし、また、同スパイ団をより厳しい目で見させたらしい。
警察署で、尾崎は高飛車に、法務省により彼の裁判をまかされる主任検事に会いたいと求めた。そして彼は、自分は刑事も関知しえない国の秘密に内密に絡んでおり、また彼はすでに、真実の全貌を語ろうと納得しているので、彼の裁判には刑事による通常の取調べの手順は該当しないだろうと訴えた。すると彼は直ちに、巣鴨刑務所の拘置部に移送され、そこで、裁判でゾルゲを担当する検事、玉沢光三郎との以後三年間にわたる対話を始めた。最初に尾崎は、スパイ団のあらゆる工作員の名前を明らかにし、彼とゾルゲの両者は、通常に言われるスパイというより、国家間交渉における仲介者であると自己弁護した。数ヶ月後、おびただしい取調べが繰り返された後、彼は、世界全体をおおう単体の社会主義政府を常に信じていたことが誤りであったと告白しはじめた。思索に充分な時間を費やした末の一度ならぬ「転向宣言」にも拘わらず、彼は決して若き理想主義への心底の否定を示しているようなところはなかった。彼の取調官は誰も彼に理解を示したが、最終的には、1944年の東条内閣の崩壊の後、和平派と戦争続行派が国の危うい平衡を保っている時、妥当かつ十分な政治的都合上の理由から、彼は処刑された。
尾崎にすっぽかされ、宮城も同じく行方が分からなくなった後、リヒャルト・ゾルゲは、予感に襲われながら二日間を過ごした。彼は、自分自身にも他のヨーロッパ人のスパイ団員にも、自分たちの使命はほぼ終わったことを認めた。彼はモスクワに形のみの再配置の要請文を書き、上海行きの船便を予約し、それまでの長い時間をベッドの内で、意気消沈し、うたた寝をしたりして過ごした。10月17日の夕刻、スパイ団の無線技師のマックス・クラウゼンが彼の所に立ち寄ると、彼はユーゴスラビア人の写真技師のブランコ・ド・ヴーケリッチと、ひとケースの酒を空にしているところだった(64)。クラウゼンは、ゾルゲがパジャマ姿でグラスを手に、運が尽きたかに歩き回っている姿に衝撃を受け、ニュースの有無を確かめた後、もう一本の酒をそのお通夜に献上して、十分後にそこを後にした。
翌朝5時、内務省の数人の特高警察官と法務省の検事補が、ゾルゲ宅の外で、一台のドイツ公用車が玄関先から走り去るのを待っていた。ドイツ通信社の所長は車中でゾルゲと、警察官も納得のゆかぬ、気が違ったかのような奇妙な会話を交わしていた。ゾルゲは後に尋問の中で、そのドイツ人は、朝5時に、最近の内閣改造について、ただ彼の見解を聞くためにやってきていたと言い張った。
そのドイツ人が引き払うと、警察官らは直ちにゾルゲ宅の玄関先に現れ、1938年のオートバイ事故について聞きたいので同行してほしいと求めた(65)。ゾルゲは、自分は外国人であるとそれを拒否したが、パジャマのまま連行されていった。警察官は、ゾルゲがベッドの脇に開かれたまま残していた、難解な16世紀の日本の歌集に注目した。彼は好んで、それを読もうとし、理解しようとしていたらしかった。
六日後、度重なる苦痛な尋問の後、ゾルゲは自分がソ連のスパイであることを認め、彼は特高警察の手から、逮捕の際に同行していた法務省の検事補に引き渡された。この検事、吉河光貞〔著者は「よしざわと」表記しているが誤記〕は、1951年、米国下院の非米国活動調査委員会のゾルゲ聴聞会の際、アメリカ人聴聞者にはなじみある人物となった。ゾルゲに味方したり、手荒な看守の手に任せたりする代わりに、吉河はその落胆したスパイを、三年間の審問、法廷、判決、そして上告との過程の各々で、尋問ごとに、公判ごとに、そして手順ごとに、あばいて行った。ゾルゲは、1947年11月7日、尾崎の47分後、ついに絞首台に架けられることとなる。
東条の責任 |
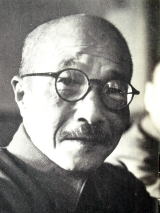 |
| 東条英機首相 |
1941年10月23日、閣僚、両軍総長による東条内閣最初の大本営連絡会議において、東条は、天皇の希望について綿密に説明した(66)。永野海軍軍令部総長が「海軍は、毎時400トンの石油を消費している。情況は切迫している。いずれにするのか、緊急に決定して頂きたい」と言った。杉山陸軍参謀総長は、「すでに四ヶ月間、遅れている。我々は、四日も五日も、研究に日を浪費してなどいられない。急いで動いてもらいたい」と求めた。
東条は返答した。「統帥部が急ぐ必要を強調するのは理解できる。しかし、政府は、この件には慎重な考察を行うように望み、それを責任をもって行いたい。今、海軍、外務および大蔵の新大臣を迎えている。政府は9月6日決定をその通り行う責任を果たしうるのか、それとも、新たな視点から考え直すべきなのかを、諸君に決定していただきたい。統帥部には何か異議がおありか?」 二人の参謀総長は、ともに異議を表さなかった。そして次の一週間、連日の連絡会議で、彼らは、東条が国内のあらゆる分野を代表する権威者を動員し、戦争を反論の余地のないものへと築き上げてゆく様子を目の当りにした。そうした権威者の提案は膨大で複雑だった。彼らは、石油や他の物資の備蓄が戦争を実行可能なものとしているにも拘らず、もし日本が戦争を回避した場合、日本が陥ってしまう縮小の意味する深刻さを対比して描き出し、戦争反対派を一つひとつ、説き伏せていった。そのようにして、「権威者たち」は、〔戦争回避の場合の〕可能な将来の真実で明白な背筋の寒くなる現実を突きつけた。(67)
二人の参謀総長とその副官たちは、日本が石油、ゴム、錫、タングステンそして米を含め、まるまる東南アジアを獲得できるにも拘わらず、もしいま自らの能力を発揮しなかったら、その攻撃能力は、1942年半ばまでにしだいに失なわれてゆき、逆に、米国の南方での防衛能力は優勢となるとの統計について、疑いのないものであると議論を展開した。そしてそれ以降は、日本の軍事的地位の低下はさらに進行し、わずか3年ないし4年のうちに、米国は日本に1890年の境界にまで撤退するよう要求し、日本はただ頭をたれ、それに従う以外に合理的対抗策をもてなくなるだろうとした。
内閣企画院総裁の鈴木は二人の総長を支持したが、それはもっとも悲観的な意味においてであった。すなわち、もしすべてが完璧に進み、すべての計画が達成され、日本が充分な鉄鋼、石油、そして造船能力をもったとしても、それは蘭領東インドが開発でき、共栄圏が自給可能な経済圏となり得るまでのことにすぎない。しかも鈴木は、天候の悪影響、あるいは米潜水艦による損害の過小見積もりや、希望的観測による薄い余裕幅は、形勢を一変させ得る可能性を大いに含むとした。だがそれでも鈴木は、この捨て身の賭けは、戦わずして降伏しないための打開策として望ましいものであると主張した。そして彼は、日本は戦いそして敗戦することで失うものは、何もしないで経済的圧力に屈するよりは、はるかに少ないと予測した。
大蔵大臣の賀屋興宣〔かや おきのり〕――近衛親王の子分――は、それにこう反論した。国民は、軍需を満たすために空腹を望むかも知れないが、軍事的必要はおそらく達成できまい。天井知らずのインフレは本国では予防されるかも知れないが、占領地域では放置され、財産を絞り取ることになる。日本はインドネシアから必要とする軍需資材を得ることができるかもしれないが、インドネシアがヨーロッパから輸入している工業製品を日本が供給することはできない。そして賀屋は、米国が日本を屈服させるためにその国力の強さを使うことには必ずしもならないだろうと、〔対米戦を必要とする〕見解を否定した。
新外相の東郷茂徳――1945年に日本の降伏文書を扱うことになる――は、賀屋に同意した。こうして彼と賀屋は、戦争決定自体を覆すことはできなかったが、東条の政策再検討を、苛立つ軍事戦略家たちをほとんど忍耐し切れなくするほど、長々と述べさせることには成功した。最後に、10月30日、連絡会議は、確固とした宣言をもって休会し、11月1日に再開し、天皇への推薦を結論しえるまで、必要によっては、全日、全夜をも費やすることとされた。(68)
翌10月31日、金曜日、木戸内大臣は吉田茂――前牧野内大臣の娘婿で戦後の首相――と会い、和平派――最終的には日本の降伏を準備することとなる――の結成についての対話を始めた。木戸は、11月1日と2日の二回の会談で、吉田との間の合意に達した。(69)
他方、11月1日、山本五十六長官とその参謀は、彼らの大海令第一号――陸海軍の作戦の統合計画書で、数ヶ月後に実施されることとなる――の最終草案への裕仁の文書上の許可をえた。その極秘計画は、高松親王の祝福もえて、印刷へとまわされ、その後三日で300部が印刷された。
内閣降伏 |
その日、連絡会議前の朝7時30分から8時30分まで、将軍東条は杉山陸軍参謀総長と会って共に朝食をとり、東条は杉山に、選択の第3を支持するように求めた(70)。杉山は約束はしなかったが、食事中、必要に応じて東条にうなずきを送っていた。
連絡会議は、午前9時より、吹上庭園の北側の大本営の建物で開催された。そして会議は16時間半にわたって継続され、閉会したのは深夜の1時30分だった。会議がそんなに疲労困憊するものとなった理由は、新たな論点が持ち上がったからでも、同意できない多々の議論が交わされたからでもなかった。確かなことは、永野海軍軍令部総長と塚田陸軍参謀次長が、ともに外交をすべて断つことを望んでいたのだが、彼らは、〔連絡会議の〕最後の瞬間まで、外交交渉の継続にさほどの異論も出さないで黙っていたからだった。ことに塚田は、いっそう早い交渉の11月13日期限を望み、米国が突然に譲歩の意志を示す場合があっても、その日以降は、作戦司令を撤回しない方針を望んだ。(71)
予期される戦地からは千マイル〔1600km〕も離れた帝国の本土において、40万人の兵士を訓練し招集することは、兵站実務上でも精神面上でも、陸軍の将校クラスに重い負担を与えることであった。塚田は強い語調で言った。「言っておくが、航空機、海上艦艇、そして潜水艦が、衝突し合うことにならないか」。永野海軍軍令総長はしかし、それを違って受け取った。「ささいな衝突は突発事故で、戦争ではない」。だが永野と塚田は、さほど議論することもなく、もし交渉が11月30日の真夜中までに妥結に達したなら、開戦はしないことで合意した。
何が議事を16時間半も引き延ばさせたのかと言えば、東郷外相と賀屋蔵相の執拗な拒絶により、天皇への全会一致の推薦が成しえなかったことだった。さらに、何が彼らの依怙地さを刺激したかと言えば、彼らが、戦争を避けようとしたばかりでなく、戦争が不名誉な形で始まることを避けたいと望んだからであった。日本が米国をあざむこうとしていたとは何ら会議の議事録に記録されてはいないが、おそらく、会議に先立って用意された討議資料には何か〔そうした意味のことが〕があったからであろう。というのは、会議の初期の段階で、杉山陸軍参謀総長が自分のメモに、以下のようにその遣り取りを記録しているからである。
- 〔蔵相〕賀屋 もし、戦争三年目に勝利の可能性があるなら、開戦も意味があるだろうが、永野〔海軍軍令総長〕によれば、これも確かなことではない。さらに、米国と戦争を起こす我々の〔勝利〕の可能性は薄いと私は判断する。ゆえに私は、いまここで戦争を布告することは望ましい考えではないと結論する。
〔外相〕東郷 私も、米国艦隊がやってきて、我々を攻撃するとは信じられない。今、戦争を始める必要があるとは、断言しえない。
〔海軍軍令総長〕永野 「案ずるより産むが易し」という諺もある。将来は予測不可能だ。当たり前と思っていることからは何も得られない。三年間で南方での敵の防衛は増強され、敵の艦船数も増加する。
〔蔵相〕賀屋 ならば、いつ開戦し、いつ勝利できるのか?
〔海軍軍令総長〕永野 今だ。開戦の時は、より後にはやってこない。
賀屋・東郷 我々はこの決定をする前に、外交交渉で最後の試みを何とか行いたい。これは、我国の2600年の歴史において、重大な岐路を意味し、国家存亡の命運がかかっている。我々に外交上の策謀を求めるのは、法外に帰す。それはできかねぬ。
午後5時、疲れ切った東条は、その冷汗ものの全会一致――宮廷人から厳しく求められていた――の決議を天皇裕仁に提出した(74)。裕仁がその論争の経過に踏み込んで聞き及んだ時、東条は裕仁の面前で泣き崩れた。長い時間を検討のために費やしてしまったと東条は言った。交渉期限は、陸海軍のトップ戦略家たちが求めていた時からすでに一ヶ月を経過していた。統帥部は、陸軍および海軍の操縦士――特別に選抜された者たちで、命令のない準備は想定外だった――に最終的な訓練をするために、天皇からの命令を必要としていた。最後に東条は裕仁に、この戦争決定を公式なものとする御前会議を招集するように要望した。そして東条は、天皇自身もこの決定を支持されることを望むと述べた。
自分の治世へのそうした多くの抗議を体験して、裕仁は、いくつかの質問をさらに続けた。
「我々が自らの誇りを維持しうるために、我々が行うことについて、貴殿はいかなる考えをもっているのか?」
「我々はいまそれを検討しております。まもなくご報告いたします」と、いかにも疲れた様子で東条は答えた。
「ローマ法王に特使を派遣し、もし状況が悪化した場合、その情況を救う仲介の役を願ったらいかがか?」裕仁は言った。
そして天皇は、鉄と鉄鋼の製造量および開戦初年の海運輸送力の損失の陸海軍予測について、いくつかの突っ込んだ質問を行った。そして最後に、東条に、それまでに処置された案件への承認を与えた。(75)
第一号命令 |
- 我が帝国は米国に対し常に友好的姿勢を維持してきたにも拘わらす、米国は、東アジアにおける我が国の利益の擁護のために取られた自存と自衛のすべての措置に介入してきた。近年では、米国は我国による支那事変のすみやかな決着を蒋介石政府を支援することで妨害し、そして、我々との経済関係を断つという法外な最終的手段にさえ出ている・・・(77)
二ヶ月前の陸軍大学で実施された山本の特別演習に参加した大将の幾人かは、この真珠湾計画を戦術的にはおそまつな博打とし、戦略的には単なるみせかけとして、いまだ承認していなかった。ある大将は、一時的に米国太平洋艦隊に打撃を与えるのみだとし、ある者は、米国を侮辱するもので、後に日本がフィリピン、マラヤそして蘭領東インドを占領し、強化なった位置から交渉を始める時、その和平交渉を難航させる結果になるとした。
陸軍には、山本の計画を知る者はほとんどいなかった。陸軍の南方計画の総司令官である陸軍大将寺内伯爵は、わずか6週間前に、その秘密を知らされていた。杉山陸軍参謀司令官は、彼のメモ記録によれば、それをたった4日前に通知されていた。将軍東条は、それに関してはおそらく闇のなかだったろう# 3。東郷外相のような文官が知っていたことは、ただ、海軍が米国艦隊に対する「待ち伏せ攻撃」計画をもっているという程度だった。彼らは、その「待ち伏せ」は、フィリピンが攻撃された後、もし、米国海軍が、フィリピンを助けようとまんまと西方へ航行してきた時にのみ――さらには、彼らの開戦への反対の立場から、その前提の上で――実行されると予想していた。裕仁のみが、数人の皇族、両参謀長官、そして何人かの山本の腹心以外に、その真珠湾計画を知っている者であった。(79)
- # 3 戦後の東条の数多くの発言を自分の専門研究分野のひとつとしているロバート・J・C・バトウ教授は、こう書いている。「東条は12月1日の御前会議の一ないし二日前まで、その(真珠湾)計画を採用するとの海軍の決定を知らなかったようである。」(80)
「我々は(マラヤで)、空からの先制攻撃によって敵を圧倒する計画を持っていますが、一日に三、四回の雨が降りますので、我々は軍隊の上陸を奇襲に行うこと専念しております。フィリピンではうまくゆくと存じます。我々は二つの作戦をまとめて研究中で、適宜決定してゆくつもりです。」
裕仁は言った。「東条は、航空隊へ急いで発令したいと気をもんでいるようだが。」
杉山はこう答えた。「飛行士とその支援部隊は、大連、青島、上海その他の地点で待機しており、いつでも離陸可能です。我々は、出撃命令が遅れることによるあらゆる影響も研究済みであり、その対策も用意されております。我々は、たとえ天皇の命令が最後の御前会議の後となろうとも、あらゆる支障を克服することができるものと存じます。私自身、これがもっとも適切な方法と存じます。」
「よろしい。すべてが適切であるのが、最もよい」と裕仁は答え、そして、「国家の正当性の観点では、タイとできる限り早く交渉する(タイ領を横切ってマラヤへと進軍する許可を求め)のが最適だと思う。しかし、軍事的先制性から言えば、タイとの交渉は、できる限り遅らせるのが望ましい。どう考えるか。」
それに杉山が応えて言った。「陛下のおおせの通りであります。しかしですが、もし我々が(すでに開始された交渉をどう進めるのかを)決めない限り、我々の計画にそむくことになります。以前とはことなり、今や状況は切羽詰まっており、我々は極めて慎重でなければなりません。この件を研究し、外相と相談し、そして陛下にふたたび報告いたします。」
「海軍の目標とする日はいつなのか?」と裕仁が尋ねた。
そでまで黙って脇に立っていた永野海軍軍令総長が短く答えた。「12月8日が目標日です。」
「その日は月曜日じゃないですか?」と裕仁が聞いた# 4。
- # 4 日本時間の12月8日、月曜は、アメリカ時間では12月7日、日曜で、もちろん、真珠湾攻撃になるはずの日だった。これまでの米国歴史研究者は、この日は山本長官によって、11月中旬に設定され、裕仁はその日も、あるいはその計画自体も、12月2日になるまで、まったく知らなかったと報告していた。1967年に出版された杉山大将のメモが、ここに記述したような内容を記録し、信頼しうるものとしている。
「他の地域にもみな、同じ日にするのですか?」、裕仁が尋ねた。
杉山参謀総長が答えた。「(さまざまな招集地点からの)距離が大きく異なりますので、すべての我々の攻撃が厳密に同じ日に統一できることはないでしょう。」
裕仁はうなずいた。彼の侍従武官とともに、裕仁は何年間も、東南アジアの地図をながめてきていた。彼はその距離関係や、干満の差や風やサンゴ礁のもたらす困難についても、よく承知していた。裕仁の認可をもらって永野海軍軍令総長は、皇居の門のすぐ外側に位置する日比谷公園の脇の海軍軍令本部に戻った。そこで彼を黒島亀人海軍少将が、瀬戸内海の山本の旗艦から大海令第一号の永野用の一冊を持ってきて、緊張して彼を待ち受けていた(83)。「今、電話で山本と話したところです。もし、総長がこの計画に同意できないなら、彼は任務から降りねばならないと言っています」と黒島は伝えた。
永野はほほえみ、黒島の肩に腕をまわし、そして言った。「山本がどう感じているかはよく解る。もし彼が自分の構想を充分確信しているなら、彼はその実行を許可されるに違いない。そして、それは認可されたぞ。」
黒島は待機させていた飛行機に乗り込み、さっそく、このニュースを山本に伝えるため南へと飛んだ。その夜、旗艦長門の艦上では、杯を交わして、厳かな祝福が行われた。かくして、山本と彼の部下は、裕仁、高松親王、小松男爵の支持をえて、自国に遂に、戦う機会を与えたことに万感を深めていた。
軍事参議院の同意(84) |
- 現下の危局を打開し、自存自衛を全うし、大東亜の新秩序を建設するため、本帝国は、この場において、米英蘭との戦争を決意する。
この目的のため、我軍の行動の期日を、12月初めとする。
杉山陸軍参謀総長は、この戦争に投入される両軍の概略を表した。マラヤに6万から7万の兵力と320機の航空機、フィリピンに4万2千の兵力と170機の航空機、蘭領東インドに8万5千の兵力と300機の航空機、ビルマに3万5千の兵力と60機の航空機。それに対して、インドの30万の兵力と約200機の航空機、オーストラリアの25万の兵力と約300機の航空機、そして、ニュージーランドの7万の兵力と約150機の航空機が敵によって補強部隊として投入されるかも知れない。実戦上、日本は約20万の部隊と戦うことが予想され、そのうちの70パーセントは、 「熱帯気候」 に慣れた有利さを持ち、他方 「訓練不足と一般的に低い戦意」 の不利さを持っている。しかし、敵の航空機は、高性能機と比較的良く訓練された操縦士をもつものがある、と彼は述べた。
総計85万の敵前線部隊と予備兵力に対し、日本は、51個師団と 「約200万の兵力」を繰り出すことができる、と杉山は指摘した。陸軍部隊が戦場で現実に遭遇するかもしれないおおむね20万の兵力に対し、杉山は11個師団、約22万の兵力を用いることを予期していた。 「1個師団はすでにインドシナにあり、5個師団が日本および台湾っで待機および訓練しており、さらに5個師団が中国戦区より移動する。・・・これらは、天皇の大命が発せられたその時、すべてが動く用意が整っている」と杉山は報告した。
杉山は、敵は二カ月ごとに10パーセントの割合で空軍力を拡大し続けており、地上力は毎月4千人の率で強化されているので、ただちに攻撃することを絶対的に必要としている、と説明した。 「しかし、敵の戦力は分散しているので、我々の戦力を集中して奇襲攻撃をかければ、我々は敵の部隊を一つひとつ打破できる。一度上陸さえできれば、我々は必ず勝利できる」と彼は言った。
杉山の報告の後、議場は形式ばった議論に入った。朝香親王――南京略奪を行った裕仁の叔父――は苛立った様子で議場を制した。 「12月初めの行動開始日は、近衛内閣の時期に決定されたものより、約1カ月半遅い。両参謀総長の説明によれば、早く攻撃すればするほどよいようである。私も完全に同意する。12月初めが選ばれた理由は何であるのか? 外交交渉に付き合っていて、何がえられるのか?」
朝香親王に、最年長の近親者で76歳の前陸軍参謀総長の閑院親王が答えて言った。 「・・・国際問題においては、軍事戦略と外交戦略を協調させる必要がある。」
朝香親王は次に、なぜ、両参謀総長は短期戦が有利であるのが明らかな時に、長期戦を計画しているのか、と質問した。閑院親王、永野海軍軍令部総長、そして東条首相の三人が各々それに答えた。それらの回答を通し、いくつか関連した観測が示された。
閑院親王は、米国との交渉の妥結の可能性はわずか30パーセントだが、米国は、その海軍が二つの大洋に分割され、アジアの錫、ゴム、そしえタングステンに依存しているという弱点のために、交渉のみを行っている、と返答した。
永野海軍軍令総長は、日本は一年か二年の戦争には勝てるだろうが、三年、四年の戦争には数え切れない不確定要素があることは確実であるため、短期戦が不可能であることを無念がった。彼が指摘するには、米国は単純に、侵略し、占領し、そして敗北させるには大きすぎた。だが彼は、ドイツが英国を破れば、米国は和平交渉を受入れるようになるので、希望はある、と主張した。
東条首相の見解はこうだった。自分も戦争を早期に始めたかったが、しかし外交交渉が軍事的準備のための時間を生んだのは確かだ。杉山陸軍参謀総長は、マラヤ占領のための海軍と陸軍第25軍の共同計画を検討し、南方における軍事作戦は計画通りに行えるとの確信を表した。
裕仁のもう一人の叔父で才略に長けた東久邇親王が言った。 「軍事にうったえる理由を明確にする必要があるのではないかと思う。国民と世界に向けて、我が聖戦の正当性を説明しその目的を宣言することについて、諸君はどう考えておられるのか? それがあってはじめて、人々は、国の危局の時に、自己犠牲を払うのではないか?」
将軍東条が答えて言った。 「私もまた、戦争を開始する前に、我々の国家的正当性を明確にすることは必須であると思う。私はいま、我が戦争目的を明瞭に宣言する件について考慮中である。しかし、まだ、陛下の前でそうした明瞭な宣言を表せる段階ではない。」
東久邇親王は、東条のさばけた言葉を無視し、穏やかに言い下した。 「言うまでもなく、我々は長期戦を覚悟しなければならない。しかも、そうでありながら我々は、戦争は適時に終結することに関し、いま直ちに考慮を始めねばならない。まさしく、我々は、陛下に従う我々の司令的地位の使用を、ただ日米間の対峙ばかりでなく、世界が陥ることにすらなる混乱を解決する観点において、考慮しなければならない。」
東条が答えた。 「戦争を短期に終らせることは確かに望ましい。我々は問題を様々な角度から検討してきたが、まだ、真実に輝かしい考えには達していない。私は、敵の生死を支配する手段を持っていないのが残念である。戦争の長期化の可能性は80パーセントだ。しかし、以下のような情勢、すなわち、米国艦船の大半の破損――特異な可能性だが、もし米国がフィリピンを日本の占領の後に取り返しを試みた場合には可能――、次に、英国の生命線の支配――つまり、英国を飢えから守っている海上輸送路の支配――、そして、米国の多くの軍事材料である極東の資源の占領と閉じ込めのもとでは、短期戦も考えられる。」
会議の後半で、戦争の責任のすべてを受入れるのは到底無理となった時、軍事参議院会議の軍部メンバー――皇室メンバーではない――は、微妙ながら抵抗を始めた。ある時点で、杉山陸軍参謀総長が言った。 「台風が吹き荒れれば、(我々は困難な気象状況に遭遇する)。我々の先の検討では、我々の準備は10月までに終わらせ、南方への進出はいまの11月に行うのが望ましかった。」
数分後、元帥である閑院親王は、戦争決定は全会一致で承認されているのか、と問うた。何の反論もなかった。閑院は天皇に向い、そして、本決定を推薦すると報告した。裕仁はうなずき、そして、 「内宮へ戻る」と議場を後にした。
彼が去った時、軍事参議院の様々な参列者は、個々に、それぞれの質問――それらは会議の前に文書で幕僚本部に提出され、幕僚本部の担当将官によって事前に文書で回答されていた――を記録のために承認した。こうした文書化された質問と回答は天皇によって検閲された後、宮廷公文書の 「資料類」 として正式に保管された。それらは、会議では有用な実際の討議とは見なされないものの、それらには、いくつかの驚かされるほど腹蔵のない声明が含まれていた。それらは、朝香親王による質問――数ヶ月先には、陸海軍が各命令系統を統一し、全面的に協力することを求めていた――によって口火が切られた。幕僚本部の回答はそれを保証していた。朝香の質問の後、南方面軍司令官の寺内陸軍大将は、以下の質問を出した。 「長期化する戦争を避ける実際の方法は何かあるのか?」。その返答は、 「その点での良い考えはないが・・・」、であった。そして再度、英国はドイツによって占領され、米国は戦争によって疲弊を増す、という希望的観測が述べられていた。
寺内の文書に見られる次の質問は、 「我々の占領地域の統治政策に適用される銘記すべき最重要なものは何か?」だった。
その回答は、 「第一に、資源の確保、第二に、軍事物資と兵員の輸送の自由の確保、第三に、この二点を確保するために、中国で行ったように、我々は躊躇せず、現地人を抑制すべきこと。言い換えれば、中国で行ったように、我々は統治の詳細には関知しないが、既存の組織を用い、現地習慣の尊重を表す。」
次に、土肥原大将―― 「満州のロレンス」 として知られた高齢の諜報専門家――への質問が読み上げられた。土肥原の第二の質問は、 「米国、英国、オランダに対する戦争の公式の理由は何か?」 であった。
その回答は、 「これは、世界観を異にする国々の衝突である。戦争の基本的目的は米国人に自らの意思に反し我々に従うようにさせること、つまり、我々の自給自足をなす共栄圏を構築することである。こうした結果を達成する前に、我々は長期的な戦争に備えなければならない。我々の短期の危急の成果は、包囲を破り、蒋介石の意気をそぎ、南方の資源を掌握し、アジアからアングロサクソンを駆逐し、中国人と南方の人々を、米国や英国の意志でなく我々のそれによるものとし、アジアと欧州とのより近いルートを開き、そして、米国が軍事的に必要とする、ゴム、錫、その他原料の独占的地帯を獲得するものである。」
そうした率直な質問と回答を考慮し、戦争への責任を引き受けながら、軍事参議院は、山本の大海令第一号を言外に承認して、それを表さずに閉会した。
つづき
「両生空間」 もくじへ
「もくじ」へ戻る
Copyright(C), 2013, Hajime Matsuzaki この文書、画像の無断使用は厳禁いたします