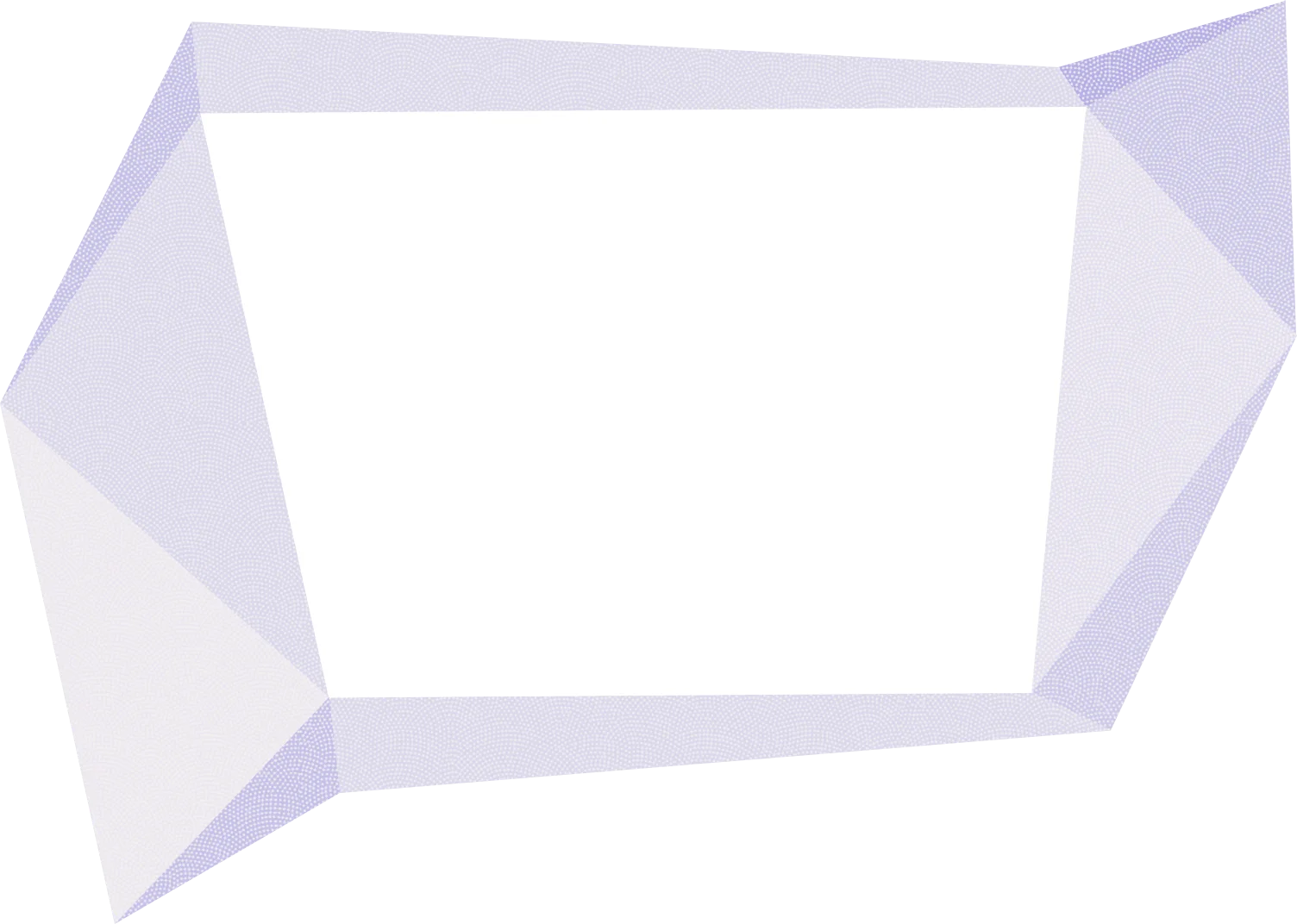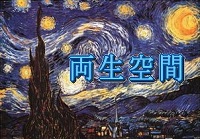今回の「居酒屋談義」は、やがて傘寿〔80歳〕にも達しようとする、かつての一人の土木技術者による独白です。そしてそれは、埼玉県八潮市で発生している道路陥没と事故をきっかけとしています。英語では「シンクホール」(直訳すれば「沈下穴」)と呼ばれる同様な事件は、ここオーストラリアやアメリカでもよく発生し、人々の日常生活に不安の穴をあける問題を起こしています。その多くは、耐用年数を越えたインフラ構造物の老朽化を原因とするもので、言うなれば、物には寿命があり、避けられない道理の結果ということです。それは下水道設備に限らず、上水道でも、鉄道でも、道路でも、どこでも起こり得ます。
想えば六十余年昔、彼を含めた多くの若ムシャが、そうしたインフラ構造物の新たな建設に意義を見出し、その道に進んだのでした。
大学を出たばかりの新米時代、彼が従事した工事のひとつに、東京新宿区高田馬場での、今では新目白通りと呼ばれれている新たな道路の地下に建設された、神田川と妙正寺川の出会いでの暗渠工事がある。都の発注によるもので、二つの都市河川がそこで合流しているのだが、交差する山の手線などの高架橋があって拡幅が難しく、大雨の際にはその上流部で溢水害をよく起こしていた。そこでその解決のため、新たな放射状道路の建設に合わせてその地下に、地下鉄を埋設するに等しい規模のダブルの箱型水路が建造されたのであった。
それから半世紀、この地下構造物はまだまだ寿命には達しておらず、くわえて、そのメンテナンスにも問題はないはずである。
そこでその半世紀昔について、そうした当事者の一人として彼の昔話となるのだが、今だから話せることも含め、その記憶を語り始めればそれこそ話はそうは簡単に片付かない。そんな話のほんのさわりである。
当時、1960年代の末、日本社会は文字通りの高度成長に沸きにわいていた。
その一方、欧米を中心に世界の大学では、いわゆる「大学紛争」の嵐が吹き荒れ、スチューデントパワーが世に名をとどろかせていた。
そして日本もその例外ではなかった。
その時代、世界は冷戦体制で覆われ、地球を二分する東西対立の中、アジアでは熱い火を噴くベトナム戦争が勃発し、その悲惨さは世界の良識を目覚めさせていた。
日本においても、市民をも巻き込んでそのベトナム反戦運動が広がる一方、大きくかつ急速に成長を遂げる社会がもたらす数々の矛盾――インフレや公害問題――に、若き学びの徒もその疑問を行動をもって呈し始めていた。
彼の入学した私学の工科大学もそのスチューデントパワーの例外ではなく、キャンパスにバリケードを築いてストライキを実施するという、激しい紛争を開始していた。
そして彼の属した土木工学科においては、大学の露骨な金儲け主義を体現する定員を大幅に上回る入学者によるいわゆる「すし詰めマスプロ教室」に加え、大学が新たに提示した説得性を欠く授業料値上げに反発した学生たちが反旗を上げた。
彼も、その工学の名に反するような――むしろ運動部の活躍をもって名を知らしめようとしていた――見当違いな大学の運営姿勢に疑問をもっていた者の一人だった。そこで級友たちと共に学科内に学生組織を創設して、アカデミックな充実を要望する声を上げ始めていた。
そうした下地のあったところに、この世界的なスチューデントパワーの火の手がおよび、当大学も、工科系大学にしてはめずらしく、いわゆる紛争大学の一つとなり、土木科は建築科とともにその先鋒となるにいたった。
1964年の初回東京オリンッピクが象徴するように、建設産業は当時の主導産業であり、関係学科は社会的にも重要で受験生の人気も高く、より意欲的な学生を集めていたのだった。
だが1969年1月、そうした大学紛争は、彼らが卒業を迎えようとする時にピークに達し、その頂点である東大紛争を支援するために集結した各大学の学生デモ隊と警察機動隊との大規模な衝突がおこった。彼の大学からのデモ隊もそれの隊列の一部をなしており、クラスメートからも逮捕者が出る事態となった。
それに彼らはすでそれまでに、その就職先も決まっていた。だが、その逮捕劇は、それらを棒に振る結末となった。
時はそうした喧騒著しい時代であった。
そして1969年春、こうした大揺れの大学の中、彼ら四年生は通常なら卒業の時を迎えていた。しかし、終結の見通せぬ紛争に、いつまでも学生を続けているわけにもゆかず、後輩在学生たちからは「敵前逃亡」と批判されつつ、卒業もボイコットして、各々の思いを胸に、大学を後にして行った。
そうして、内心、後ろ髪を引かれる思いでそれぞれの仕事に就いたのだが、日本社会はその経済成長のまっただ中で沸騰しており、それが新たな問題を起こしていた。いわゆる成田新国際空港建設である。
それは、政府の無理強いな建設強行とそれに反発する保守的なはずの現地農民の怒りを引き起こし、それに大学を飛び出した学生たちとが結び付く状況を生んだ。このその後も長くこじれた問題が、今でもその足跡を残す「成田空港建設反対運動」――土地の名をもって「三里塚闘争」とも呼ばれた――である。
そうして、複雑な思いで建設現場で働く彼ら卒業生のもとに、三里塚で運動を続ける級友たちから連帯と支援の要望が繰り返された。例えば、その持ち前の建設技術を生かして、現地の農民たちが計画する新滑走路の延長上に飛行を妨害できる高さの鉄塔を立てるその塔の設計であったり、さらには、現地に合流している者たちは先頭に立って指揮して、予定される滑走路の下に地下壕を掘って、これもその後の滑走路の使用の妨害物にしようとした。
その他方、それぞれの就職先の建設現場で働く他の卒業生たちは、自分の給料から結構な額を、カンパとよばれるそうした運動のための寄附に応じたり、中には、自分の働く現場から、建設資材を“横流し”してそうした運動に提供したりもした。
つまり、同じクラスメート同士でありながら、一部のグループはそうした反権力運動を続け、他のグループは、そうした運動には微妙な距離をとりつつ、社会が必要とするインフラ施設、たとえば、羽田空港の沖合への拡張、各新幹線や高速道路の建設などに従事し、今日の日本社会の基盤を築いていった。
生き方を異にするこうした級友たちは、各々にそうした生き方を送りながら、今日でも旧友関係を維持しており、けっして反目し合った関係にあるわけではない。いうなれば、連続したスペクトラムの各々をそれぞれに成しているだけである。
このように、彼ら、半世紀昔に土木工学の門をたたいた若ムシャたちは、その技術がもたらす、新たに大規模構造物を建設する仕事にあこがれ、その技術を身に着け、そしてそれを実践してきた者たちである。
そういう意味では、日本の社会の物的構造の礎を、表となり、裏となって、築いてきた者たちである。
それが冒頭の事例のように、そうして建設されたあまたのインフラ構造物が、短いものからその寿命を迎え、他方、かつての青き技術者たちも七十代も末に達している。
このように、その構造物面とその人物面の双方において長き時間が流れ、新たな時代を呈し始めている。
片やメンテナンスや保全処置に、他は健康維持に、工学的にも医学的にも、それぞれに新たな課題を抱くに至っている。
側聞するところでは、「土木工学」という名称すらもはや現状に合わないと、「環境工学」とか「防災工学」とかと名を改める事例も出始めているようだ。
時代は留まるところなく変化を続けている。
そしてそこに生きた人間たちも年齢を重ね、はやくも鬼籍に入ったものもいる。
まだ命をつなげられている者として、先に旅立った旧友の冥福を心底より祈り、この表裏つながり合った連帯の長寿を願うばかりである。