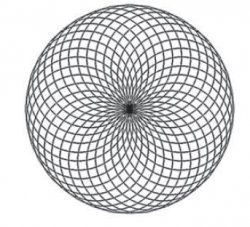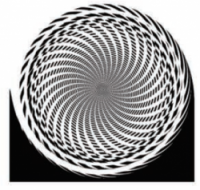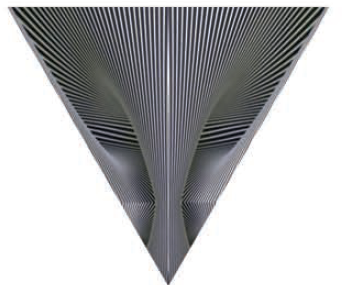今回をもって、本書『Modern Esoteric 〔現代の「東西融合〈涅槃〉思想」〕』の訳読を完結します。そして、『Future Esoteric〔「東西融合〈涅槃〉思想」の将来性〕』と合わせて、これら二部作の一連の訳読についても、2015年1月の着手以来、ほぼ4年間にわたった作業を終えようとしています。 詳細記事
今号の目次
- 新たな生き方の一つのモデル 〈連載「訳読‐2」解説〉 グローバル・フィクション(その83)
- 結 語 〈訳読‐2b〉現代の「東西融合〈涅槃〉思想」(その48)
-
「理論霊理学」の打上げを
(MOTEJI レポート No.20=最終回=) 両生“META-MANGA”ストーリー<第26話> - 「心の持ちよう」の問題 〈連載「訳読‐2」解説〉 グローバル・フィクション(その82)
- ブッダ(仏陀)=その2= 〈訳読‐2b〉現代の「東西融合〈涅槃〉思想」(その48)
- 「ローカル」という共通項 〈連載「訳読‐2」解説〉 グローバル・フィクション(その81)
- ブッダ(仏陀)=その1= 〈訳読‐2b〉現代の「東西融合〈涅槃〉思想」(その47)
- 東西融合への確かな歩み 〈連載「訳読‐2」解説〉 グローバル・フィクション(その80)
- だから「ストリート祭り」をやろうっての?(その2) 〈訳読‐2b〉現代の「東西融合〈涅槃〉思想」(その46)
- カンチェンジュンガ直望トレッキング:フォトレポート編 雪辱の再挑戦
- 究極の体験に見出せる世界 カンチェンジュンガ直望トレッキング:心身究極体験記編
- 著者の肉声 〈連載「訳読‐2」解説〉 グローバル・フィクション(その79)
- だから「ストリート祭り」をやろうっての?(その1) 〈訳読‐2b〉現代の「東西融合〈涅槃〉思想」(その45)
- 私を産んだ<チンポ>(その5) 著者:幸子
- “宇宙植民地”たる地球 〈連載「訳読‐2」解説〉 グローバル・フィクション(その78)
- ユートピア前夜 〈訳読‐2b〉現代の「東西融合〈涅槃〉思想」(その44)
- 私を産んだ<チンポ>(その4) 著者:幸子
- 離身体験と文章表現 〈連載「訳読‐2」解説〉グローバル・フィクション(その77)
- 輪廻転生(その2) 〈訳読‐2b〉現代の「東西融合〈涅槃〉思想」(その43)
- 私を産んだ<チンポ>(その3) 著者:幸子
- 「スライブ」とのタイトル 〈連載「訳読‐2」解説〉グローバル・フィクション(その76)
- スライブ 〈訳読‐2b〉現代の「東西融合〈涅槃〉思想」(その41)
- 輪廻転生(その1) 〈訳読‐2b〉現代の「東西融合〈涅槃〉思想」(その42)
- 私を産んだ〈チンポ〉(その2) 著者:幸子
- 「おばあちゃん」を思い出せ 〈連載「訳読‐2」解説〉グローバル・フィクション(その75)
- 食品支配と脱出(その2) 〈訳読‐2b〉現代の「東西融合〈涅槃〉思想」(その40)
- 私を産んだ〈チンポ〉 著者:幸子
- 身に迫る、信じ難い企み 〈連載「訳読‐2」解説〉グローバル・フィクション(その74)
- 食品支配と脱出(その1) 〈訳読‐2b〉現代の「東西融合〈涅槃〉思想」(その39)
- 「もと空」からのメッセージ(MOTEJIレポートNo.19) 両生“META-MANGA”ストーリー<第25話>
- 『苦海浄土』と『Modern Esoteric』の共通性 〈連載「訳読‐2」解説〉グローバル・フィクション(その73)
- 非-健康産業(その2) 〈訳読‐2b〉現代の「東西融合〈涅槃〉思想」(その38)
- 病で死ぬか、医で死ぬか 〈連載「訳読‐2」解説〉グローバル・フィクション(その72)
- 非-健康産業(その1) 〈訳読‐2b〉現代の「東西融合〈涅槃〉思想」(その37)
- 家主かテナントか(MOTEJIレポートNo.18) 両生“META-MANGA”ストーリー<第24話>
- 瓜二つ議論、あれこれ 〈連載「訳読‐2」解説〉グローバル・フィクション(その71)
- 聖なるシンボル(その2) 〈訳読‐2b〉現代の「東西融合〈涅槃〉思想」(その36)
- 俺の“真言” (MOTEJIレポートNo.17) 両生“META-MANGA”ストーリー<第23話>
- 「考え過ぎ」か「深慮」か、その往復運動 〈連載「訳読‐2」解説〉グローバル・フィクション(その70)
- 聖なるシンボル(その1) 〈訳読‐2b〉現代の「東西融合〈涅槃〉思想」(その35)
- 「幾何学」は復古学か新地平か 〈連載「訳読‐2」解説〉グローバル・フィクション(その69)
- 聖なる幾何学(その2) 〈訳読‐2b〉現代の「東西融合〈涅槃〉思想」(その34)
- 「おごり」以前の世界へ 〈連載「訳読‐2」解説〉グローバル・フィクション(その68)
- 聖なる幾何学(その1) 〈訳読‐2b〉現代の「東西融合〈涅槃〉思想」(その33)
- 誤解される「宗教」 〈連載「訳読‐2」解説〉グローバル・フィクション(その67)
- 喪失する我が宗教心(その2) 〈訳読‐2b〉現代の「東西融合〈涅槃〉思想」(その32)
- 新しいプロジェクトのすすめ(MOTEJIレポートNo.16) 両生“META-MANGA”ストーリー<第22話>
- 「宗教心=帰属意識」か 〈連載「訳読‐2」解説〉グローバル・フィクション(その66)
- 喪失する我が宗教心(その1) 〈訳読‐2b〉現代の「東西融合〈涅槃〉思想」(その31)
- 再度、「米国連銀」のトリックについて 〈連載「訳読‐2」解説〉グローバル・フィクション(その65)
- 秘密家族(その2) 〈訳読‐2b〉現代の「東西融合〈涅槃〉思想」(その30)
- 夜明け前(MOTEJIレポートNo.15) 両生 “META-MANGA” ストーリー <第21話>
- 「イルミナチ」=資本主義のDNA 〈連載「訳読‐2」解説〉グローバル・フィクション(その64)
- 秘密家族(その1) 〈訳読‐2b〉現代の「東西融合〈涅槃〉思想」(その29)
- 「対抗言説」か「偽史」か 〈連載「訳読‐2」解説〉グローバル・フィクション(その63)
- 対抗言説(その2) 〈訳読‐2b〉現代の「東西融合〈涅槃〉思想」(その28)
率直に言って、私は、このブッダ(仏陀)の章の「悟り」とか「ブッダは80歳で他界」の節を読みながら、昨年のクモ膜下出血による臨死体験や、今年のヒマラヤのトレッキングの際の心の動揺やその静穏化の体験などを思い出しています。
そうした一連の体験を、煮詰めて要約した言葉にすれば、《すべては心の持ちようの問題》と、この章が書いているように、言えてしまうから不思議なのです。 詳細記事
もし私が「ブッダ(仏陀)」と題する本章をもう二十年も前に読んでいたなら、私はその言わんとしていることを理解できなかったか、相当に違った思いで受け取ったことでしょう。しかし幸いにも、私はこの章を、この今になって読むめぐり合わせとなり、それゆえ、それをよく理解しながら、楽しみさえしつつ、訳読できています。それほどに、いわゆる人生経験を必要としたということなのでしょうが、ことにこの数年の経験は、それを決定的に分けてきました。
詳細記事
今年(2018年)10月、インド、シッキム州へ、カンチェンジュンガ峰を望むトレッキングに行ってきました。この計画は、昨年の脳負傷によって一時断念したものに、再び挑戦したものです。 詳細記事
エベレスト、K2につぐ世界第三位のカンチェンジュンガ(8598m)。その高峰を、その南壁直下より、氷河のみをへだてて直望できるゴチャラ峠(4950m)。その世界でも稀有な地点を目指すのがこのトレッキングです。 詳細記事
私は一昨年にアメリカ西岸を訪れた際、サンフランシスコに立ち寄り、著者のブラッド・オルセンにお会いしました。ただ、その際、時間が短く、歓談も限られ、彼の人となりを理解するには余りに短時間でした。
本章は、そうした私の不満を埋め合わせて十分な記述であり、本章冒頭で、彼が「一人称で語る」ことの必要を感じていると述べているように、ご本人も、その欠いた部分の埋め合わせの重要さに気付いていたようです。 詳細記事
第五章
ミユキのこと
一人の青年が命を落とすというのは大変なことなのだ。
彼一人のみならず、彼を必要としていた人々の人生丸ごと奪ってしまう。
勤め先では頼もしい上司でもあり、善き隣人でもあり、嬉しそうにカズエにエッチないたずらを仕掛けてくる幼友達ミユキ。
その青年さえ生きていたら、下らんことはすべてチャラになった。 詳細記事
去る6月18日、トランプ大統領が国防省に対し米国宇宙軍の創設を指示した、との報道がありました。報道の限りでは、この「宇宙軍」とは、もはや武器開発の場が地球を囲む宇宙空間におよんでおり、そこでの制空権ならぬ、“制宙権”の確保を意図した構想であるかに伝えられています。つまり、戦争の相手はまだ地球人同士で、ただその場が、近宇宙に拡大されてきているとの想定です。
だがその一方、今回の「ユートピア前夜」の章――ことに「監獄惑星からの脱出」――に含められている、地球は地球外生命(ET)の植民地との議論は、すでに地球は、ETによって、それが分からぬほどにも巧みに占拠、支配されているとの設定に立つものです。つまり、SF映画「スターウォーズ」のごとき対異星人戦争もありかねぬ現実の世界です。しかしこうした議論は、おおかたの向きには、荒唐無稽過ぎる話として唾棄される分野であるでしょう。 詳細記事
第四章
シズの至言
シズの至言。 あんたの名前「シズ」だが、戸籍謄本には「シツ」とある。濁点の無い昔の表記か、ともかく我々には「シズ」で通っていた。我々の父親ということになっていた男トシローを産んだ女、そのあんたの口癖。「戦争があの子(トシロー)をあんなにしてしもた」「あの子は戦争で、あないなってしもうた」。これがあんたの名言至言だ。 詳細記事
結論から先に言うと、「離身体験」と「文章表現」とは、同じものとは言えないまでも、同列の行為ではないかと考えられます。むろん、この両体験は、日常行為としては大いに隔たったもので、後者に比べて前者は、極めてまれな非日常体験です。にもかかわらず、それを「同列」とするのは、いずれも、その体験者を、人生の一種のよどみの底から救い出し、まるで羽根でも生えたように、空から鳥の目で地上の自分の姿を見渡すに等しい効果があることです。 詳細記事
私たちの離身および臨死経験もまた、心や霊性が、身体を離れたり、自分の身体が体験する時間や空間の外部で働くことを明白に示す事例を提供している。こうした事例は、生まれ代わりの概念を間接的に立証している。記録されている最も古い離身体験、または臨死体験の報告は、プラトンの『国家』の中で語られている「エルの物語」にも見られる。エルは、戦闘で「殺された」後、火葬にされる寸前で生き返り、あの世への旅について語った。彼は復帰し、そこで何を見たかを現世の人に告げることで、人間界への使者にならなければならないとされたと述べられており、これは古代ギリシャ人に大きな影響を与えた。 詳細記事
第三章
ユーキチじいさん
ユーキチじいさん、テツよりは利口だったようだが、惜しむらくは、その熱心な稲荷信仰。熱心すぎて、いなりのいーなり。すっかり食われてしまったことだ。
カズエから聞いた話では、じいさん、自分が60過ぎで死ぬというお告げを信じていたが、それを過ぎても死なないので、自分は生き過ぎだと、断じ、自殺したという。80を過ぎていた。猫いらずか何かの服毒自殺だったらしく、カズエは家族からではなく、近所の人の話を小耳に挟んで知ったようだ。
信じ込むというのは怖いなと思う。この話を聞いて、我々なら、先ず、吹き出してしまう。 詳細記事
タイトルの「スライブ」ですが、「スライブ(thrive)」という言葉には、ぴったりとした日本語が見つからず、原文のままを用いています。英英辞書上では、その単語は「(of a child, animal, or plant) grow or develop well or vigorously.」とある。訳せば「子供や動/植物が良く、生きいきと育ち、伸びること」となります。そういう、生命の活性ある姿がこの部のテーマとなっています。
すでにこの部では、「寿命200歳への展望」「意識の科学」そして「身体・心・霊性」の三章については翻訳掲載済みです。
そこで今回以降は、それらに続く「輪廻転生」から始めて、それ以降の章へと進んでゆきます。 詳細記事
一見、望みなしと映る闘いへの、その重要問題の打開法は、私たちの現実へのコンセンサスつまり常識をただ変えることにある。支配者が持つ唯一の武器は、私たちの真の能力についての知識を手の届かないものにさせること。したがって、私たちの人としての可能性を全面的に開花するよう進化することが、黄金の時代を約束する。
「人生における私の使命は、ただ生存するだけでなく、はつらつと成長することです。そうするために、情熱、思いやり、ユーモアそして何らかのスタイルが必要です。」 ――マヤ・アンジェロウ〔アメリカの公民権運動活動家、詩人、女優、1928-2014〕 詳細記事
| == 本書の《もくじ》へ 「もくじ」の中の《本章》へ == |
私を非現実から現実へと導け。私を暗闇から光明へと導け。私を死から不滅へと導け。」――ブリハッド・アーラニヤカ(ヒンドゥー教のウパニシャッド哲学の最初期・最古層の一文献)
輪廻転生への信念は長く、かつ、いまだに継続されており、東洋の宗教的伝統における明瞭な特徴となっている。この教義は、インドの大部分の宗教的伝統――ヒンズー教をはじめ、ヴィシュヌ教、シバ教、ジャイナ教、シーク教、そして様々な東洋ヨガ――の中心的な教えである。同じアイデアはまた、いくつかの古代のギリシャの哲学者たちにもた抱かれた。特定のエソテリックなキリスト教の伝承では、イエス・キリストが輪廻転生について語ったとしている。現代の多くの非キリスト教徒も、前世を信じており、それらには、ニューエイジ派、スピリチュアリズム、サイエントロジー、特定のアフリカの伝統の信者、そして、カバラ、スフィズム、グノーシス主義キリスト教の哲学者などがある。仏教においての生まれ代わりの概念は、しばしば輪廻転生と呼ばれるが、ヒンズー教の伝統やニューエイジ派の信念――生まれ代わるべき「自己」または個々の魂はない――とは大きく異なっている。
第二章
カメさん
カメさん、あんたはどこまで始末悪い人なんや。私がいちばん話したかった相手なのに、私がやっと物心ついたとき、あんたはもう死体だった。黄色い顔して床に転がっていた。歳は六十過ぎだったか。
カメという名が嫌いで、自分で別の名前をつけていたとか。いつの時代にも名前の定まらん人はいるものよ。
カメは、「鶴は千年、亀は万年」に因(ちな)んだ命名かな。六十そこそこでは長寿とはいえなかったけど。
今では私の方が年上になるほど時が流れた。話し合いたい気持ちは募(つの)る一方だが、死人に口なし、やむなく手紙を書こうと思うが、お前さん字が読めんそうや。まあ、誰かに読んでもらって。あんたの子や亭主もそっちにおろうからな。 詳細記事
今回の結末に述べられている、「おばあちゃんが食べていなかったものを食べるべきではない」とは、まさに金言です。
おばあちゃんが食べていた野菜――虫食い痕が目立っていた――、あるいは、おばあちゃんが食べていた魚――養殖物では決してなかった――は、買い物や下ごしらえに手間は要したけれど、食べて危険と警戒されるものではありませんでした。 詳細記事
食品支配と脱出(その2)
業界は、この十年あるいはそれ以上にわたり、人々への通知なしに作物および種子の遺伝子設定を変更してきている。米国では、特定の食品の遺伝子操作について、〔その食品容器に〕表示する義務はない。大手化学企業は、世界の食糧供給の源泉を支配する意図をもって、種子会社のほとんどを所有している。彼らは現在「特許」をとって、種子を所有することができている。有機農家は、その自然栽培の作物への、受粉交配による品種――遺伝子レベルに挿入された有害な化学殺虫剤を含みうる――の混入を防ぐことはできない。私たちは、無自覚のモルモットと同然となっている。一部の推定では、食料品店の食品の70パーセントに遺伝子操作作物の成分が入っている。食品医薬品局(FDA)内の科学者たちは、遺伝子操作食品に特有の健康被害について警告しているが、FDAはそうした科学者の助言を無視し、バイオテクノロジー産業――食品システムを中毒させながら「特許暮らし」を探求――の支援を選択している。遺伝子操作作物(GMO)は世界の栄養源にはならない。それはモンサントらの収益にしか役立たない。 詳細記事
【解説】 このいかにもセンセーショナルな題名の作品は、本サイトの読者の一人からいただいた投稿で、表示のように、その著者については、「幸子」以外は不詳です。
この作品を、フィクションなのか、それとも実話なのかと問う詮索は、まったく無意味でしょう。というのは、これほどにリアルな表現は、まさに実話でしかありえない現実味をもっていながら、他方、こうしたストーリー展開は、どこか並な現実を越えた設定の気配も漂います。いずれにせよ、両者が相まって出来上がった本作品は、読んで見出せる通りに、まさに、日本の深部をえぐり出して見せてくれる、近年にない社会派作の逸品となっています。
現代の日本においてなお、天に昇らなければ愛し合えない男女が存在したのであり、また、自殺に追い込まれる子供たちも跡を絶ちません。日本社会がそれほどに深く精神疾患症状を伴っており、そしてそれはなぜなのか。勇敢にもこの著者は、その謎にいどんでいます。
この作品を読み終えた時、「〈チンポ〉=天皇制」との深奥の等式関係を読み抜けるかどうか。この実に明快なメッセージこそ、この作品の真髄でありましょう。
今回掲載するのはその第一章で、以後、計五回にわたり連載してゆきます。
現在、日本では優生保護法によって断種された人たちが、国を相手とした裁判を行っています。ヒットラーも、ナチ政権下で、同様な考えを実行し、その最たるものが強制収容所と人種抹殺です。
そうした惨いことがなぜ、どのように実行されたのか、それが、食品の安全と背中合わせの問題であるとは、ちょっと関連付けては考えられないことです。 詳細記事
今年2月、水俣病を「わが水俣病」として書いた『苦海浄土』の著者、石牟礼道子さんが亡くなられた。水銀中毒におかされた郷土や海を、「生類(しょうるい)のみやこはいずくなりや」と歌い、破壊された「いのちの連鎖」つまり「生類のみやこ」の尊さを私たちに問うた。
「非-健康産業(その2)」の今回、そうした水銀中毒ばかりでなく、アルミニウムや他の重金属、そしてあまたの化学物質の有毒性の危険が述べられています。そして、どうしてそうした毒が薬として販売されることがまかり通っているのか、そのからくりについても。 詳細記事
非-健康産業(その2)
むごたらしい医学上の詐欺行為がキモセラピーである。この放射性療法と医薬品の併用は、免疫反応を増強するどころか免疫系を破壊し、通常、腫瘍の増殖を可能にしてしまう。患者にはそうであるとさえ告げられているが、死か、それとも「最高の医学権威」による勧告を選ぶかの板挟みにさらされる。だが最新の研究は、全身健康グループが何十年にも渡って主張してきたことを確認してきている。キモセラピーは「治療」ではなく、薬でも、まして予防や治癒をめざすものですらない。それは、たぶん癌症例の1〜2パーセントを除いて、薬効価値さえほとんどない毒である。しかも、このごくわずかな症例でさえ、生活習慣の変化、プラセボ〔にせ薬〕効果、あるいは、目に見えないながら強力な心的効果が原因である可能性もある。 詳細記事
シンボルあるいは象徴を、この章に論じられているほどに受け止めることは、正直なところ「考え過ぎ」とか「こじ付け」ではないか、と思わせるところがあります。しかし、例えば英語には「numerology」(数秘学)といった用語があるように、数字占いの意味付けとなる数字の謎をさぐる研究分野があります。言ってみれば、数学だって、そうした関心を出発点としてきた経緯があるのでしょう。だが現在では、それは科学扱いはされてはいません。本書を含む二部作のテーマである「エソテリック」も、科学界からは、せいぜい「疑似科学」としか扱われていない分野です。
しかし、もし科学を、科学となしえるために不確かな部分を切り落とした骨格のみだと見なすなら、その血や肉についての考察は、すくなくとも可能性として、科学の未開拓分野を含む、将来的なエリアと言えなくもないでしょう。
個人的関心ですが、そうした「考え過ぎ」と「深慮」間を往復させられる運動が、本書を訳読している面白味です。 詳細記事
| == 本書の《もくじ》へ 「もくじ」の中の《本章》へ == |
「地球上のすべての現象は象徴的であり、各シンボルは開かれた門で、魂の準備が整っていれば、世界の内部へと入ることができる。そこは、あなたも私も、昼も夜も、すべてが一体である。」 ――ヘルマン・ヘッセ(ドイツ人作家)
聖なるシンボルは、宇宙の言語である。それには、実際に我々が誰であり、人類や細胞分裂や多くのイメージの根底にある幾何学が何であるのか、その謎を解く力がある。その隠された意味は、各時代を通して、画像、神話、民間伝承、そしてシンボルを使用した神秘主義者によって明らかにされてきた。幾何学の母型と印は、完璧に完全で、不変で、時間を越えた現実性をもって、「神の心」から直接に表出してきている。宇宙は振動であり、これらの聖なるシンボルの原則はすべて、振動である波形現象に直接対応している。科学は宇宙が振動であることに同意している。聖なる幾何学とシンボルは、視覚、時間、宇宙次元での振動として見ることができる。 詳細記事
この章でいう「幾何学」とは、はたして、近代科学以前のそれなのか、それとも、今日の科学はそれをまだ知っていないのか。むろん著者の論点は後者で、その未解明の大自然そして大宇宙に「意図」が秘められているとの視点が、タイトルに「聖なる」が付されている理由です。つまり、この「聖なる」とは「神・聖なる」ではなく、それから「神」をとったもので、そこに「神」を付けてしまうことで、本来の追及の力を失ってしまうという考え方です。 詳細記事
| == 本書の《もくじ》へ 「もくじ」の中の《本章》へ == |
聖なる幾何学(その2)
古代ギリシャ人が強調したように、音や音楽は振動で構成されている。 それは単純には、毎秒の振動が多くなるほど、音質は高くなることを示している。振動を表す単位はヘルツ(略称Hz)である。「432 Hz」は自然音響の原理をなす振動で、宇宙の自然な「主音」である。周波数の432 Hzは、黄金比原理であるフィボナッチのファイ(Φ)比率を表し、光、時間、空間、物質、重力および磁気の特性を、生物学、DNAコード、さらには私たちの意識とも、一体に結び付けることが知られている。過去100年間、私たちの音楽はA-440Hzに再調律され、余分な8Hzが追加され、完全な周波数である432Hzから、微妙なな歪みが生じている。 詳細記事
人間のおごりが指摘されて久しいどころか、そのおごり振りは遂に、自滅的、地球破壊的レベルにすら達している感があります。そしてそれによる災厄を、自然の復讐とか断罪と見る向きもありますが、それも、慣れ親しんだおごりの反転した“逆おごり”意識にすぎないでしょう。
エソテリック論の今回の議論は、「幾何学」という、一見、なんとも懐かしく教科書的な観点によるものです。ことに私など、いわゆる工科系の学生生活を送ってきた者にとっては、この数学的で図形的なアプローチは、どこか古巣に帰ったような感覚を伴います。しかし、さすがにエソテリックな視野はそんなレベルにはとどまらず、むしろ、西洋が西洋たる過ちを重ねてきたその長い過程を振り返っています。今回の「黄金比」の節の終わりで示されているプラトンの言葉、「幾何学は天地創造の前から存在した」は、「神」の名のもとに悪事を繰り返してきた人間のおごりを指摘するようにも聞こえます。 詳細記事
私たちはどうやら、宗教というものを誤解してきたようです。あるいは、とんでもない代物を宗教と思い込まされてきたようです。それに気付くためには、現存するあらゆる「宗教」と称されている事々を完璧に忘れ去る必要があります。そして、既存の「宗教」と呼ばれる事々の引力圏から脱出し、いったん自らを無重力の世界に置いた上で、新たな発想と感性のもとに、別物の《宗教》を考え、創造する必要があります。 詳細記事
| == 本書の《もくじ》へ 「もくじ」の中の《本章》へ == |
喪失する我が宗教心(その2)
以下に述べることは、カトリック教会の告発のように受け止められるかもしれないので、まずはじめに、数千の献身的なカトリック信者や信徒労働者が、救済組織、ミッション、ボランティア、病院、手助けプログラムを続けており、極貧な何十万の人たちを支援している無私の活動があることに留意しておきたい。熱心なカトリック教徒や他のキリスト教徒、そして、あらゆる宗教の個人信徒は、貧困者に食事を与え、病人を慰め、ホームレスを安らがせ、貧乏人に宿泊所を提供し、中毒者や見捨てられた者に愛と思いやりを与え、そして、何も持たぬ数十万人にもそうした活動を行っている。彼らの信じる神が誰であるかを問わず、人々が無私に他者に奉仕することは、つねに、素晴らしいことである。 詳細記事
日本人を、宗教心にあつい人々で無神論者などほとんどいないと言えば、誰もがそれはむしろ逆だと言うに違いありません。ところが、世界中で日本人ほど社会集団への帰属意識の強い人たちはそうはいないと言えば、誰もが賛成するでしょう。しかし、ここでいう「宗教心」と「帰属意識」を同じものだとすれば、上記の表現は意味を持ち始めます。つまり、「宗教」とか「無神論」といった言葉を、少なくとも日本人に関して当てはめれば、それらはどこか違った意味で使われている言葉だと気付かざるをえません。 詳細記事
前回でも書いたように、米国の連邦準備銀行制度は、アメリカの国家機関のひとつではありません。それどころか、アメリカという国家を操るまぎらわしい私的装置でもあります。このからくりを知ることは、ケネディー大統領がなぜ暗殺され、また、今日のアメリカがどうしてそこまで混乱しているのか、その理由をつかむ第一歩となります。 詳細記事
| == 本書の《もくじ》へ 「もくじ」の中の《本章》へ == |
秘密家族(その2)
J・P・モーガン〔1837-1913〕は、20世紀が始まるころ、ロスチャイルド家の客引き役だった。彼は主に、通貨切り下げや株式市場の崩壊といった危機の際、その調整を巧みに助けて、そこから利益を得た歴史を持っていた。1893年と1907年の二度の銀行パニックの際には、経済的安定の幻想工作を妨げる一方で、自社のために富を統合していった。J・P・モーガンはまた、彼の一味がタイタニック号上に爆弾を仕掛けたのではないかと嫌疑された。というのは、彼は、その処女航海に乗船し、連邦準備銀行の設立についてアメリカ最強の批判者と話し合うはずだったが、直前に乗船をキャンセルしたからだった。その有力な批評家は〔タイタニック号が沈没した〕1912年4月15日をもって沈黙することとなり、さらに翌年には連邦準備銀行が設立された。J・P・モーガンはまた、大恐慌から非常に恩恵を受けた。1929年に「暗黒の木曜日」が襲った時、彼は値下がりした株式を「経済を浮揚させる」ために買い上げた。こうして、人々が極度の辛苦に耐えている間に、J・P・モーガンは著しい財政的利益を得て歩み去ったのであった。 詳細記事
本章「秘密家族」を読んで深く気付かされることは、いわゆる「陰謀論」賛同者に広く知られた用語である「イルミナチ」を、ある歴史的に継続されている実体ある組織であるかのように考えて追跡すると、その努力はほぼ無に帰されることです(あるいは、「ナイーブな陰謀信奉者」とのレッテルを張られるのが落ちです)。それは確かにつかみどころのなくカモフラージュされた何かではあるのですが、例えば、何らかの法律の処罰対象としてやり玉にできるような、そうした実体とは考えないほうが賢明なようです。いわば、そうした既存システムによる捕捉が効かないからこそ、その存在の意味があるのです。そういう、《資本主義の本髄》あるいは《資本主義のDNA》こそが「イルミナチ」であって、それをしっかりと体現させている人物や団体があれば、それは立派に、「イルミナチ」と名乗っても良いということです。それこそ、「陰謀論」になぞらえて言えば、資本主義の真髄とは、陰謀の域あるいはDNAの深みに達しないで、どこが資本主義か、ということです。 詳細記事
| == 本書の《もくじ》へ 「もくじ」の中の《本章》へ == |
「この国の人々が銀行や通貨制度を理解していないのはもっともだ。だが、もし彼らがそれを理解した時、次の朝までにも革命が起こるだろう。」- ヘンリー・フォード、1922年
伝えられるところでは、イルミナチは、有力者の小規模な極秘集団で、少なくとも230年間にわたり、世界の出来事の行方を牛耳ってきた。世界の議題を推進するこれらの秘密の家族や集団の代々の世代は、いくつもの名前で知られている。この世界的なエリート集団は、世界で最も豊かかつ力ある人々で構成されている。この世界的エリートの存在に論争の余地はないが、その目的は何であるのか。洩らされた報告書によると、彼らが社会のあらゆる面の管理と支配の議題を議論するため、一貫して、閉鎖された扉の背後で、世界のあらゆる場所で会議を持っていることが確認される。そして彼らの計画は時計のように正確に、メディア、金融、企業、政府、商業、軍事の分野に現れてくる。 詳細記事
いきなりですが、「偽史」という言葉があります。その意味は、事実に基づかない偽物の歴史ということですが、「歴史は嘘を言う」との認識から言えば、あらゆる歴史は偽史ということになります。また、この偽史という用語が使われる場面では、既存の主流歴史観に対する新たな、あるいはそれをくつがえす見解を、それを排する意図から、偽史という断定を与えて切り捨てる手法として使われていることが多いようです。たとえば先日、ウエブ上への転載講座で、ピラミッド建設の謎に関し、宇宙人の関わりという見方に対し、それを妄想として、偽史だと断言しているものがありました。 詳細記事
| == 本書の《もくじ》へ 「もくじ」の中の《本章》へ == |
「生き残り策 I 」の各事項は、何十年もにわたって実行されている。 安楽死政策は、主に貧困層を対象として、現在世界のすべての国で導入されている。気象異常はより致命的に悪化しており、山火事災害はより頻発している。西アフリカの市場では、AK-47〔ソ連製の軍用自動小銃〕が1丁49ドルで売られている。その流通の狙いは、資源にまつわる争いをおこさせ、さまざまな種族間で不信感をあおり、人々を互いに殺させて減少させることである。また、裕福国の市民から福祉やその他の恩恵が取り去られると、彼らは市街の暴力的行動に駆り出され、警察は正当にどんな人をも射殺または逮捕することが許される。現在構想されているその次の段階は、「ソフトキル」計画で熱帯のウイルスを持ち込み、同様に過剰な人間を淘汰することである。 詳細記事