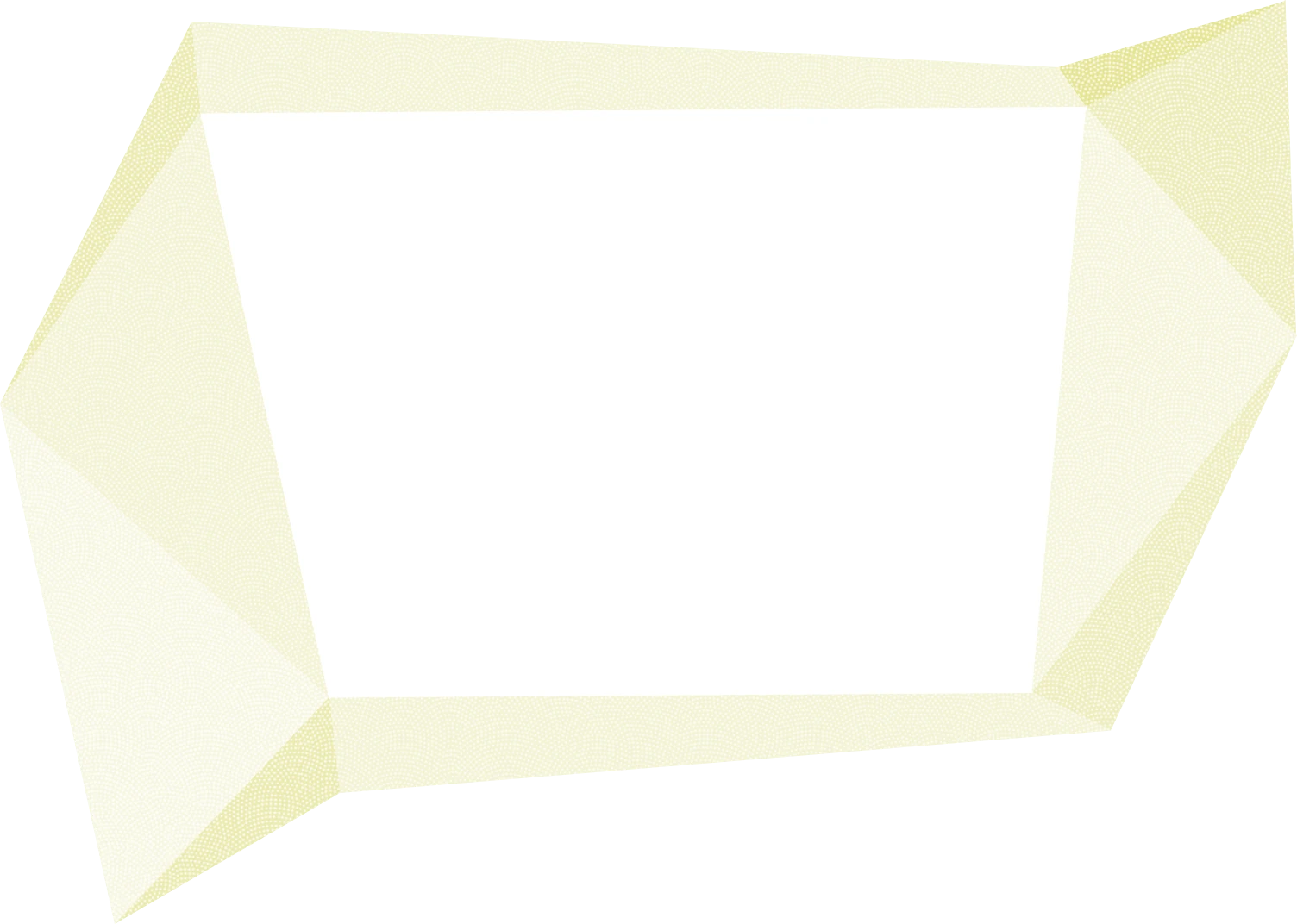私の健康に関して、すでに現実に表れ始めている病的兆候は、坐骨神経痛と前立腺肥大によるものです。
以前にも触れましたが、前者は、このところの「はじり」の効果か、一時よりはかなり軽減しています。一方、前立腺の方は、尿の細りがもう数年にもわたって続いていて(ただし症状は定常化していて進行はみられない感じ)、これは、年二回の定期的血液検査でモニターしてきています。
その血液検査のPSA(前立腺特異抗原)値が、この一年ほどでじわじわと上がっているということから、3月5日、biopsy (生検)を受けました。
その検査の趣旨は「ガン細胞があるかないか」という事実の判定ですから、少なくとも何がしかの可能性は、事前に観念はしていました。そして3月18日、その結果を聞いたのですが、遅進行性ガン細胞がみつかったとの通知をもらいました。
かくしてその何がしの可能性の世界は「有」が100パーセントの事実となり、いよいよ、私にも「来るものが来た」と言うべき段階となりました。
これまでも、考えられる範囲としてこうした事態を想定はしていましたが、それはあくまでも仮想上のことでした。しかし、こうしていわゆる「ガン告知」がなされて事態はリアルと変じ、医学常識的には、自らの命にかかわるべき問題との遭遇に至っています。
そういう意味では、この「私の健康エコロジー実践法」も、これまでの健康についての理念や説法めいた議論では事足らず、その告知にどう対処してゆくのか、迫られる具体的決断にいかに役立ってゆけるかの段階へと至っています。いわば、「平和時」は去り「戦時下」に入ったわけです。まさしく、正念場の到来です。そこで、その名称も、「実遭遇編」と改めました。
専門医の説明によれば、初期の発見がゆえ、私の年齢では完治率は80-90パーセントとのことで、彼は完全摘出をすすめています。ただしそれにはリスクを伴い、ペニスの勃起神経を損ない勃起不能となる危険性があるとのことです。60歳代の場合、患者の希望や現在の能力、施術上の諸要素との兼ね合いはあるものの、その発生確率は50パーセントほどであるとのことです。他方、前立腺の肥大で生じている排尿障害は取り除かれる(訓練は必要)といいます。必要な入院は3-4日、概ねの費用は、民間保険が利いても、5~6千ドル(45-54万円)程度とのことです。
正直なところ、私のこれまでの健康状態については、この連続記事にも書いてきているように、自分の自覚としても、また、一般像との比較としても、この年齢としては、かなり良好なものを維持してきていたのではないか、と考えてきていました。
そこに生じたこの判定は、予想されるものが皆無ではなかったとは言え、やはり、「なんで」という思いが深くあります。自覚症状(それが無いのはこのガンの特徴でもあるようですが)も、以前からの尿の細り以外には何もなく(これは肥大で説明される)、総体として、これまでの上々な状態との認識との間のギャップ感が少なくありません。つまり、この急転直下の遭遇がどうにも不可解なのです。
それに家族的にも、私の近親に前立腺ガンの症例は聞いたことがなく、これは、オーストラリアという環境要因――オーストラリアで近年、前立腺ガンの症例の上昇が顕著――によるものかと頭をかすめるものもあります。
またその一方、先に書いた「人生の出口期」に入っているこの時期、その出口からの出立、つまりその死に方に一般的なものはなく、必ず何らかの具体的傷病がその契機となるはずです。その具体的引き金が、私の場合、こうして前立腺関連のものとして、その「出口」を通過してゆくのかとすると、それほど重大なものであるはずのものがこれなのかと、これに納得できるようでいて、そうもならないものがあります。つまり、自分の前立腺に関し、私のこれまでの生活は、それに対し、命取りになるほどの有害さを与え続けてきたのであったのかと(例えば肺ガンの場合の喫煙のような)、腑に落ちないのです。
それに加え、遺伝的には、どうして、父親のように認知症でなく、母親のように心不全でもなく、祖母や叔父のように消化器系ガンでもなく、私の場合は前立腺なのかと、誰かに説明を求めたくもなっています。
ともあれ、その「出口」に向かって、あらゆる「引き金」の芽を摘み取り、命取りとなる弱点を一点たりとも残さぬように舵取りを行うのも、実際問題としては至難のわざです。そうした現実的不完全性が、私の場合、前立腺という生殖関係臓器に絡んで、この「正念場」となっているのでしょうか。
こうして、私に与えられた宣託となるべき前立腺がらみの設題に、なんらかの選択決定をしてゆくこととなります。
目下、私が下すべき判断は、医師のすすめる全摘手術を片やに、それを選ばない幾つかの代替法も他方に想定して、この難題にはいずれが正解なのか、あるいは、そもそもこうした医学的判定自体の意味とはどういうものなのかも含め、所々諸々、考慮中にあります。
遭遇から三日目。まだ完全な決断には至っていませんが、少なくとも医療機関においては、「何もしない」との選択がしだいに浮上してきています。
その理由は、上にも書きましたが、どうも私の場合のこの前立腺ガン――以下「ZG」と略記――自体が、なんとも不可解なのです。つまり、それはいったい「なにものなのか」という感じなのです。
ひとつは、今日の医学的常識には、ZG細胞という「実体」があって、その存在が病気の原因であり、したがって、それを除去してしまえば、すべては解決するというものがあります。これを医学的な「一元論」と呼びましょう。
私と専門医との関係に関する限り、こうした「一元論」に基づいたと思われるその判定に始まり、対処法としての全摘手術があります。そして常識的には、これを受けるかどうかの選択問題が、わたしのZG問題のすべてであるかのようです。
しかし、本当にそれだけなのか。
というのは、この医学的一元論を根拠とした設定の背景に、漠然としていながら誰にも共通する、ガンによる苦痛とそのあげくの死という、巨大な「恐怖」の存在があるからです。
それが、私のZGに関する限りでは、それほどの重大なものなのかどうか、どうもそれが解せないのです。いわば、この問題を理由に“死刑宣告”が出されなければならない、それだけに相当するものを、いったい私はしてきたのか、という不可解さなのです。むろん無知がゆえにやってきたことはあるでしょうが、ここに至って、改めて考え直してみても、それに相当するほどの重たい原因が、なんとも見出せないのです。
それとも、そもそもガンとは、そういう、降ってわいたようなたまたまの、一種の「事故」ででもあるのでしょうか。
私は、一年前、友人のバエさんが喉頭ガンで亡くなった際の理不尽な経緯をその傍らで目撃し、今の医療、正確には、オーストラリアの医療界のあり方に、深い不信を見出しています。ひとことで言えば、それは、医学という権威をもって、患者やその家族のガンに対する恐怖を逆手どって、その支配を強要してくる、ひとつの専制ビジネスです。
親しい友人の苦痛とその結末の死という惨事を目の当たりにし、自分にも、そういう惨劇が実際に起こるかもしれないという恐怖は強くあります。しかし、患者側にそれだけの恐怖心があるにも拘わらず、その医療側は、当然にそれを熟知しているだろうにも、その苦しみやストレスを、それほどのレベルでくみ取り、対応しているかといえば、それは実務として、NOでありました。それは完璧に事務的に処理され(時に医学的理由すら否定した先延ばしやたらい回しをされ)、制度の建前を巧みに駆使され誘導されて、結局は、その「死」が効果的に生産されたのも同然と受止めさせられました。
つまり、ガンに伴う恐怖とは、純粋な臓器病理学的な問題に加え、そうした患者側の誤解、過大視、信じ込みによる恐怖という心理的ストレスと、医師側がそういう患者側の弱みを利用しているふしもある強要などが重なり合った、ゴーストのような存在であることです。
それに人間の体とはそれこそ、心と身体の合体物で、たとえそれがゴーストであろうと、それを実際に恐怖と感じれば、それは強烈なストレス源となりえ、身体はそれに応じた反応をとり、単なる異形細胞であるガン(良性のガン)が、悪性のガンへと変質してゆくのではないか、と考えられます。
どうやら、現行のガン医療とは、そうしたゴーストすら徘徊する、それ自体が化け物のような存在と化していると、私には受け止められます。
ともあれ、こうした見方はあくまでも私見――少なくとも超少数見解――にすぎず、現行の医療制度にその改善は、予測される範囲の限り、期待するのは無理でしょう。
それに、患者にとってのガンは、目下のしかも自分自身の問題であり、命取りにさえなる危急の大問題です。そのいつかやあらぬ期待にすがっていられる場合ではありません。
つまり、私のZGに関しては、医師のすすめる全摘手術は、そうした「一元論」に立ちながらその恐怖を暗黙に利用すらしているという、見事な《医療トラップ》と見るのが安全なように思えます。
むろん、だからゆえにその医療システムを拒否すること、これはこれで冒険ではあり、何とも心細い孤軍奮闘な試みではあります。しかし、ZGは、もしその実体があるとするなら、その元は私が自分で自分の内に発生させた問題であります。そこで、そうした一連の「恐怖」を、自分なりに落ち着け、制御し、やり過ごしながら、現行医療のゴーストに左右されることなく、この自生のZGを、自分として実感でき納得できる病像になんとか見定めて、その対応を決定してゆきたいと考えています。