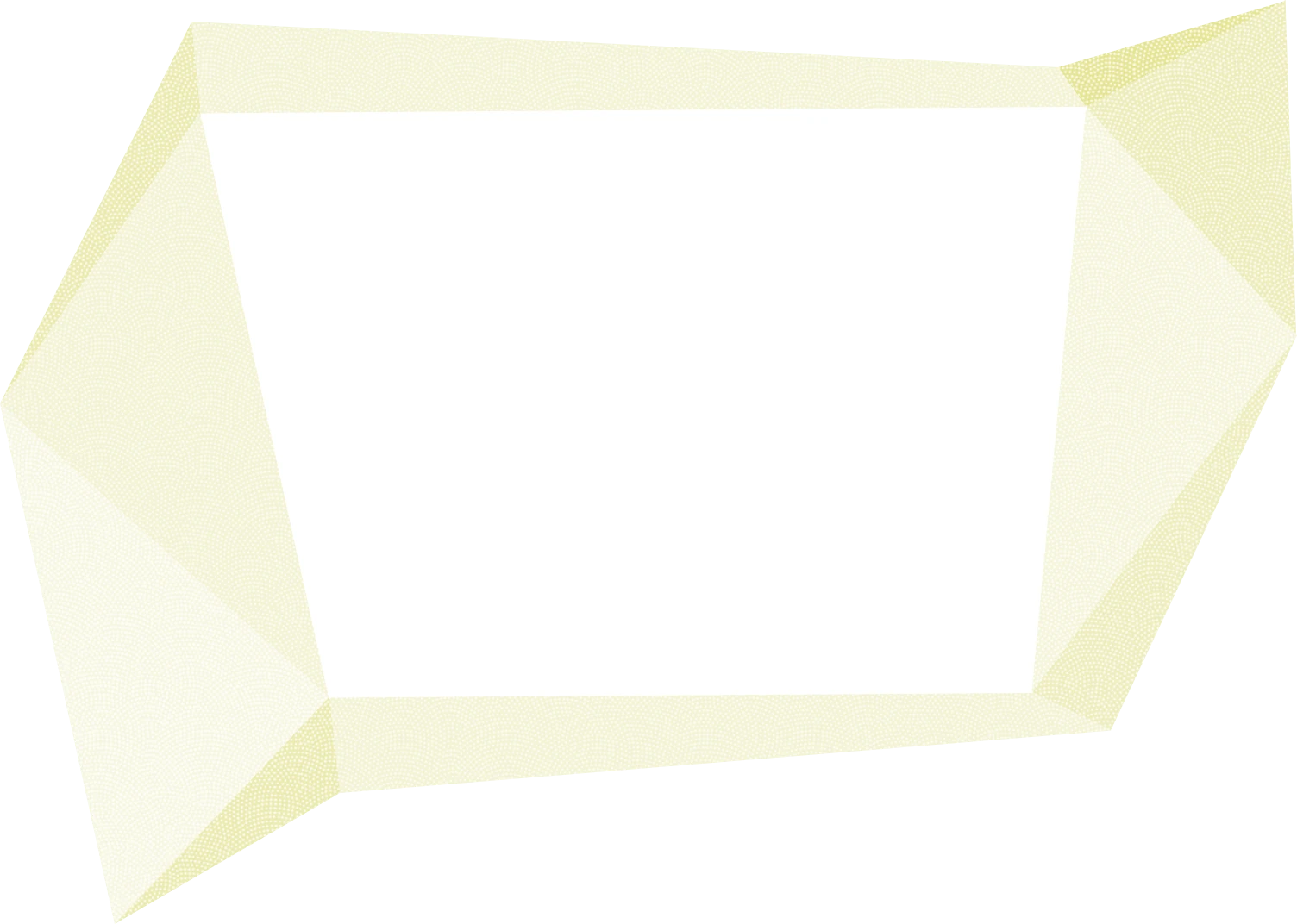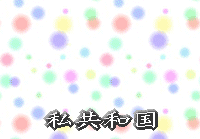戦争が終わって平和が訪れた国には、同じような気運が芽生えるのだろうか。
今回、アフガニスタンを旅して、戦後すぐのころの日本の、私がまだ幼かったころの遠い記憶をよみがえらせてくれた。
確かに、人びとは生きるのに必死である。
街では物乞いをする母子や子供が目に付き、真昼の街道では、炎天下のセンターライン上で、赤子を抱き全身をブカラで覆った女が、片手を出して行き交う車におめぐみを求めている。
郊外の乗合いタクシー乗り場では、嘘八百をならべて客引きをする運転手たちが群がってくる。
走る主要街道の要所、要所の検問には、マシンガンをもったタリバンの兵士が立ち、行き交う車を調べている。乗客が外国人と判ると、パスポートの提示をもとめ、携帯のカメラに収めて記録している。
しかし、どの街にも、異様な活気がある。
街道途上のどの町でも、沿道が市場を成していて、そこを埋める人の数に驚かさせる。いったいどこからこれだけの人が湧いてくるのか、街道をゆく数珠繋ぎの車の間にも割り込んで、商品をかかえたり、野菜を満載した手押し車を押して人、人、人が、行き交う。
タクシー乗り場で、群がる運転手たちに手を焼いていると、巡回の2,3人の連れ立った警察官がやって、その混乱の整理をしてくれる。なんとか話がまとまると、一角のボックスの窓口で何やら書類をもらっている。交渉内容を所轄の誰かが管理しているようだ。
街の両替屋とのやり取りですったもんだしていると、どこからかやってきた英語のできる青年が、通訳もかねて、旅行者の行き当たった問題を解決してくれる。彼らの身分は判らないのだが、ガイドであったり、たまたまの通りがかりの教育ある人だったりのようだ。
街の食堂に入れば、人びとの好奇心の目にさらされるのだが、危険を感じたことは一度もない。それどころか、親しみすら向けてきている。なかには片言の英語を使って、「この街に来てくれてありがとう」と言ってくる。
そうした光景は、私がまだ幼い昭和も20年代、暮らしていた街に見られた光景と重なる。
むろん記憶はおぼろげだし、国や文化も違っているのだから、厳密に言えば相違はいくらでもあるだろう。
しかし、戦争の悲惨が去った平和の日々の中で、残された貧しさや飢えの状態は切実ながらも、だからこそ、必死に歩き出している人々の、同じような息吹がある。
あれもこれも、もちろん、たまたま行き当たった体験であって、氷山のほんの一角にすぎない光景だろう。
だが、「一見は百聞に如かず」の諺を借りれば、現地にあって、それだけ、真実味のある実相を目撃できたのではないかと思う。