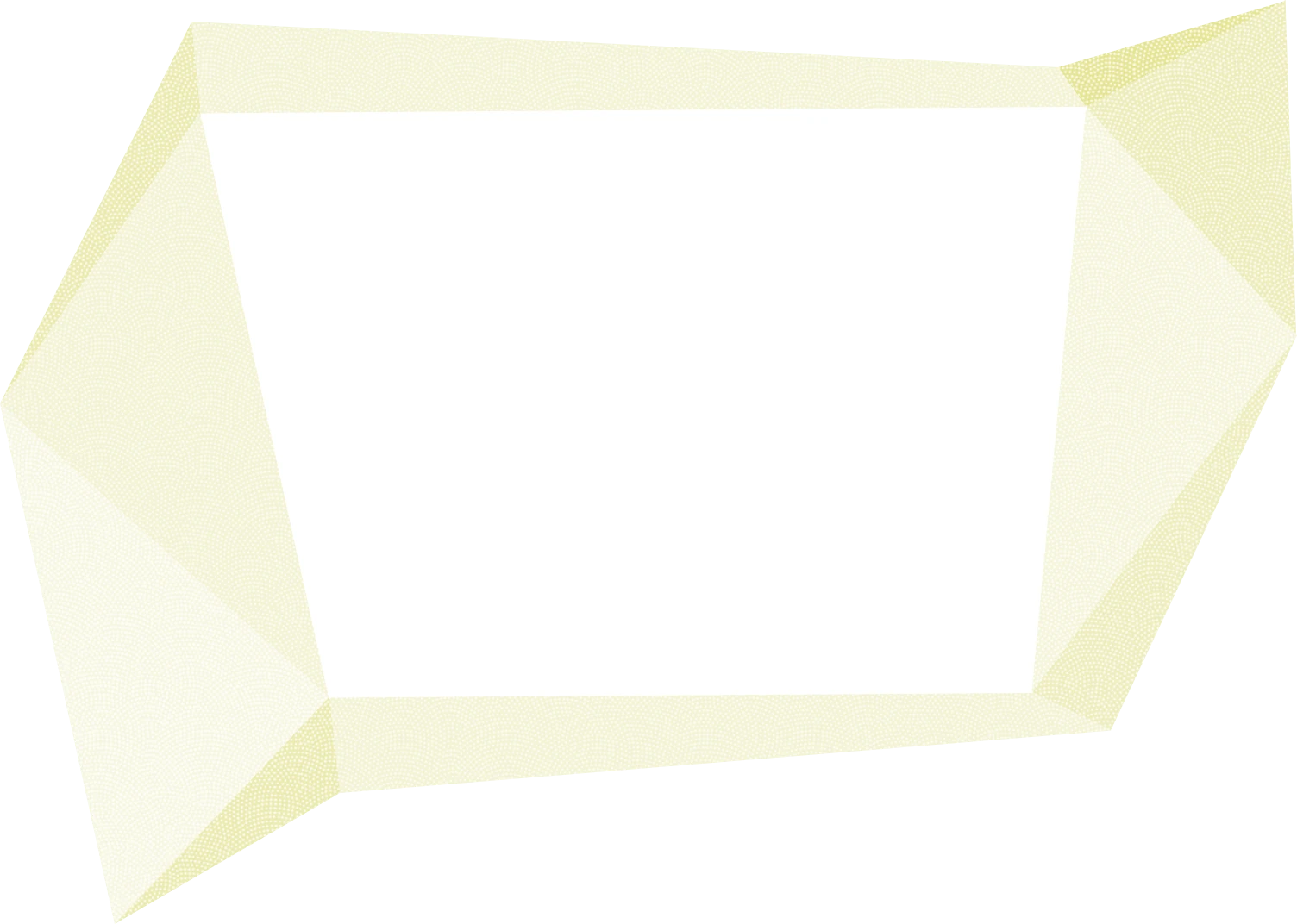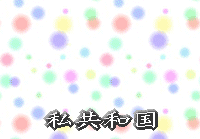健康が何かなんて、なにも改めて説明の必要もないだろう。
そこなのだが、来月で79歳になる、「健康年齢」(日本人平均で男73歳)をもはや大きく越えて「寿命」(同、81歳)にすら近づいている“要介護相当者”にとって、それでも自分が維持できている健康には、ただの運の産物とはしておけないものがある。つまりそれは、自分でそれを意識して求めてきた、そうした「自分作品」と呼んでもいいようなものでありながら、だが、知らずしらずしての天与を授かっていることでもあるような、そんな計りも知れない何かである。
そこでたとえば、健康のためにと毎日心掛けている運動について、それを私は《仕事》と呼んだりもしてきている。
というのは、運動に取り掛かろうとする際の一種のおっくう感、あるいは、今日くらいサボってみてもいいかなあという気分に対し、あえてそれをたしなめて自分を強いる感覚は、どこか、いわゆる「仕事」に際しての感覚と似ているからだ。
こうした「仕事」の場合、それを強いさせるものには様々あるだろうが、なにはともあれ今の世の中、まずそれなしでは、追々、食うに困ることになる。それほどに身に迫るものであるのがこの「仕事」である。
さてそれでは、《運動という仕事》においてはどうなのだろうか。
ちょっと話はずれるのだが、「長生きしたければ退職するな」というアドバイスを聞いたことがある。言い換えれば、「健康でいたければ仕事を続けろ」というメッセージだ。つまり、健康維持の秘訣は「仕事」を続ける事、との教訓とさえ聞こえる。ならば、どんな「仕事」であろうと、健康にいいということなのか。
そこで現実に目を移すと、現在、退職しても働くことを継続する、つまり退職それ自体すらが、事実上、もはや選択の問題ではなくなっている。
つまり、制度上で許される退職では、その後をどう生きてゆけるのか、もう、おぼつかないものとなっている。すでにそれくらい、今の社会保障制度の内容は貧困となっている。要するに、リタイアにいかなる必要や意義があろうとなかろうと、「仕事」を続けることは、あたかも誰しもの「デフォルト」(初期設定)であるかのごときである。一生働いてきて、そのゴール寸前でである。まるで、「すごろく」の「振り出しに戻る」との罰ゲームそのものでないか。
それで、そうして続ける「仕事」とは、健康を維持するために役立つものなのかどうか。おそらく、そんな悠長なことを言って選んでなどいられないのが、今の退職者をめぐる「仕事」の現状だろう。
「長生きしたければ退職するな」とアドバイスしていたのは、確か、90を越えても現役を続けている医師だった。つまり、医者程の仕事なら、その仕事は続けていても健康に害はないだろう。だが、多くの止む無く選んで続ける「仕事」は、そんな都合のいいものばかりではない。
そこで私の場合だが、私にとっての制度上も現実上もの選択は、微妙なところながら、一般にいう「退職した年金生活者」である。
そしてこの「微妙なところ」とは、上に述べたような、運動を《仕事》と受け止める、制度的でも現実的でもない、《メンタル》な領域の効果に注目しているということである。
つまり、事実上の労働持続を強いられる制度や現実の状況を念頭に置きつつ、それでも闇雲にそこに関わることには一線を引いて、そう選択したということだ。
現に、私とパートナーとの間柄——私が店子でありながら大家が退職しないで労働を続けている——に、二重の意味で、自らの身辺に関わる切実な念頭事項にあって、《メンタル》な蘇生力を見出せているからだ。
ともあれ、そうした現実をめぐる《メンタル》効果を含めて、そうであるがゆえに、私は、いわゆる金稼ぎという意味での仕事を続けようとは考えていない。なぜなら、様々な現実を見渡して、当座の金稼ぎに自分を強いることのほうが、結果的な銭失いになる公算が高いと見るからだ。
つまるところ、健康を失ってしまえば、金の出と入の両方にわたって窮することにおちいる。そうした事態は、私の年齢にある者には、命取りすらをも意味する。そしてせっかく稼いだ金も、またたくうちに露と消えてゆく。だからこそ、文字通り、健康は維持すべき〈生命線〉なのだ。
そこで、健康維持の実践に際し、運動を始めるにあたっての「おっくうな気分」については上述した。そうした私的リアリズムにあって、自分を《運動という仕事》に駆らせることは、その〈生命線〉にどう有益なのだろう。
例えば先週、日曜の休みを除いて、6日間連続の8キロをはじることとなった。つまり、手を抜かなかったどころか、実に根を詰めて“仕事”に精を出したわけだ。
そこではっきりさせておきたいのだが、この《運動という仕事》の場合、そこまで根を詰めても、一円の金にもならないのは言うまでもない。だがその一方、まずは命を縮めることにはならない仕事であることだ。予期せぬアクシデントとの遭遇は別として、《運動という仕事》で〈生命線〉を越えることはまずない。たいていの度を過ぎた運動くらいでは、その途中で体のどこかに故障が生じ、その運動自体の持続が難しくなる。つまりそれは、自己制御が可能な仕事というわけだ。
またそれに留まらず、それ以上に決定的なことは、うまく制御された運動は、自分の健康水準を素晴らしいほどに高めてくれることだ。この体験してみなければ分からない実際の効果について、それはたとえば、先の中央アジアの旅を、このほぼ80歳にもなろうというじいさんが若い世代にまじっても実行出来たように(その体験談に語られている)、健康あってのたまものだったことだ。これはまさに、〈生命線〉が持続されていることと言えよう。
つまり私が実感していることは、退職と要介護の間にある「健康年齢」と呼ばれている期間(65歳退職として8年間ほど)にある人にとって、《運動という仕事》はまさに、自分で自分の命を作り出しえているに等しいということだ。したがって、その結果としての長生きなのであって、「仕事」の持続による“金力”のおかげなぞでは決してない。
むろん、それが永遠に持続可能でないことは言うまでもない。つまり、この事実上人生最後のチャンスである「8年間」を、決して誤った使い方で無駄にしてはならない。
ここでさらに、その健康維持の私的リアリズムの詳細に立ち入らせてもらうと、その6日連続8キロの「根を詰めた」週が明けた月曜、さらに久々の10キロをはじり終え、満足げにグランドの芝上に安座していた時のことだ。
その気持ちよく晴れ渡った夕方、西に傾く太陽を見つめていた。
そこで味わえていた充実した爽快感は、とてもじゃないが、並の仕事を終えた時に得られるそれとは比べものにならない。しかも、それでお金が稼げたわけでも、誰かの役に立てれたわけでもないにも拘わらずである。強いて言えば〈貯筋〉がほんの少々できた程度である。
そんな程度に過ぎないものなのだが、それは、単なる身体的な爽快感なぞをはるかに凌駕している。何とも表現は難しいのだが、自分と自分を育んできた世界とが確かにつながっている、何かそうした大きな被抱擁感、連続感、一体感とでも言えるような、今の刹那を超える確かな感触なのだ。そしてそれは、私に何をもたらしてくれるのか得体も知れず、そしてただそれだけのことなのかも知れない。だが、それでいて、感動とさえ言ってよい実感であることだけは確かなのだ。
ともあれそれは、運動に取っ掛かろうとしている時のおっくう感を乗り越えて実行してよかったと、しみじみと感じられる事後幸福感である。まさに、「仕事」を越える《仕事》感である。これが、健康維持にまつわる私的リアリズムの核心といえばまさにその通りである。それは間違いなく、金の問題ではない。
そこでだが、健康とは、それがあってはじめてそうした領域に達してゆける、体験してはじめて味わえる世界を物語っている。しかもそれは私的でありながら、それを越えている。言い換えれば、誰にとってもの《共有資産》と言ってもよいだろう。というのは、そのように健康である人は、誰に対しても、親切で優しくあれるからだ。健康とは、そうした水準にすら通じる、自分自身、ひいては誰もの状態のことである。
それは、上記の〈生命線〉に関して言えば、それが危うくされないばかりでなく、生命の線どころか面や立体となって、そう広がり、深まることさえ意味している。
こうした健康創造に、多くの若い人たちが気付き始めているようだ。
ゆめゆめ、お金と交換できる、売り物の一つなどと見当違いをしてはならない。
他方、私くらいの世代で、手遅れとはならずにこの領域にまで達せられているケースは、あまり多くは見かけられない。すでに、寿命を尽きさせてしまった友も少なくない。
そこで、それがまれであるならなおさら、それがこの先に何をもたらすのか、無二なことであるはずだ。
そこには、単に長生きで終わるのではない、さらに別の領域に至ってゆくような気配がある。
正直言って、このじいさん、それに期待を寄せようとしている。そして、それが「終活」のひとつであっていいか、とも。
【まとめ読み】