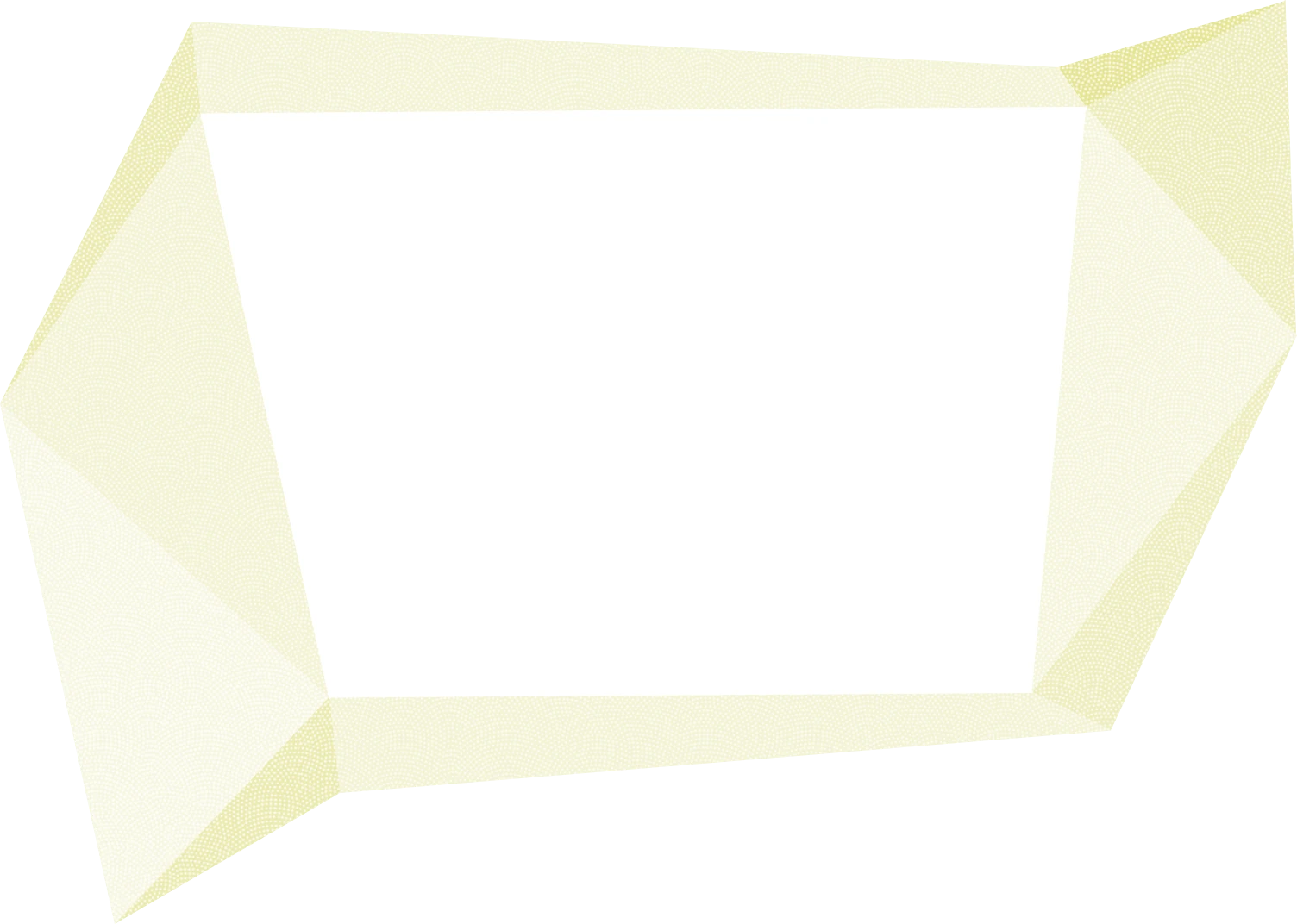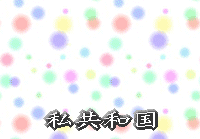これまでに、「健康って何だろう」をテーマに3回(健康って何だろう、続・健康って何だろう、続々・健康って何だろう)にわたって考えてきた。
本稿はそうした考察の延長だが、その「健康」度合いを見る社会的な尺度としてよく用いられるのが、政府統計上の数値である。
たとえば、二種の寿命、すなわち、介護が必要となる年齢と定義される「健康寿命」(2024年で、日本人男72歳、女74歳)と「平均寿命」(男81歳、女87歳)との間の「要介護」期間(男9年間、女13年間)がある。
そこでだが、統計によるこの「要介護」期間年齢にあっても、実際面では、その「健康寿命」の年齢を過ぎてもまだ「介護不要」の場合とか、反対に、それより前に介護を必要とする場合も当然にいろいろありうるわけだ。
そうした統計と実際のかけ離れの一例として、私はそのうちの前者である「健康寿命」後「介護不要」者の一人であり、それどころか、もう「平均寿命」にすら近いと言ってもよい。
つまりそうした統計数値から言えば、私のケースは顕著に例外的なようで、たしかに自分でも、主観上は当然視できている一方、そのうちに悪い宣告が下るのではないかと、一種の綱渡り感は否めない。
そんな心境をもって本稿に臨んでいるのだが、自らが健康維持に取り組んできた日々の体験から言えば、統計値がどうであろうと、むしろその自分の取り組み自体がそもそも自然な在り方であったと実感できる、その実行を適正に表す言葉がないように思ってきた。まさか、“「要介護」例外狙い活動”とは呼べまい。
というのも、先の3記事ではそれを〈仕事〉などと特に〈〉付きで表記して、同じ仕事だとしても、それとは別扱いされるべき活動として取り組んできた経緯を述べた。あるいは、流行りの言葉を借用して「健活」と呼んだりもした。つまり、どこか脇役との感が抜けないのだ。
しかし、そうした活動は、決して、そのような特例かつどこか肩身の狭いものでも、流行りで済ましておいてよいものでもない。もっと必須かつ自然なものである。
確かに現状では、その「健康寿命」後「介護不要」の該当者は多くはないようだが、退職の後、有意機な時を過ごして旅立つまで、本来ならバラ色の期間であるはずだし、誰もがその該当者になれることが望ましいはずだ。ならば、そうした「必須かつ自然なもの」が、実際にはそうではないことの不自然さに、もっと耳目が集まってもよいだろう。
しかも現状では、「老々介護」などという、特例な実態どころか、それが用語として定着するまでともなっており、同じ高齢者であっても、そう介護制度に取り込まれ、しかも、同世代でありながら、介護をする側とされる側などと、内部分化するまでとさえなっている。
言い換えれば、そうした「する側」の人たちが個人的に積んできた、生涯にわたって必要な取り組みが出来うるのだし、つまるところ、そもそも介護制度は次善の策とする、健康維持の習慣を“ファースト”に後押しする、介護以前の制度的取り組みが優先されるべきだと思う。
そこで私は、本末転倒したものでない、そうした本来あるべき取り組みを《健康道》とも呼んで、誰もが日常的に修練してみてはどうかと思う。
ところで、それを「道」というのは、そこには、剣道とか柔道とか合気道とかといういわゆる伝統武道にも似た、身体と精神を統合して臨む、精緻な取り組みの上での共通性があるからだ。ある種の「習い事」から始まる、生涯にわたる研鑽である。
ただそうした取り組みを、ここではこれまでの自分の体験を下地に、高齢者の健康問題の一環として取り上げているのだが、しかしそれは本来、年齢とは関係のない、老いも若きも、誰ものことではないかと思う。
それは若い頃にあっては、そもそも健康自体が自明であるため、むしろその時々の取り組みは、そのパフォーマンスを問う、スポーツとして実行されているのが常であろう。
すなわち《健康道》とは、そうした時期を含め、一生を通して健康な身心が作り出す自らのアウトプットの最大化を達成する、そうした長期の活動やプランのことである。
ともあれそうした「道」は、既成の武道活動でも取り組まれておらず、ほぼ私的努力によっている。それを、もっと組織的な皆民活動として定着することのメリットを担える「道」である。
ひっくり返して言えば、現代の「合理的」とされる行いとは、人の健康という意味では、「不合理」に陥っている矛盾を呈している。いったい、誰にとっての「合理性」だろう。
現状として、《健康道》への差し迫っての関心や必要は、それがもろに現れてくる、まずは高齢者向きのものではあるだろう。しかしそれはむしろ、若い時からの蓄積なくては、時すでに遅しの場合も少なくない。それこそ、「貯金」ではなく、「貯筋」の大事さである。
それに、他の武道とちがって、それは敵手を想定するものではなく、あえて相手といえば、自分自身である。それだけに、誰もに向き、万人が必要とするものと言え、メンタル面でものいっそうの必要に応える、実に現代向きな「道」と言えるだろう。
したがって、この《健康道》の広範囲な浸透は、今日のどの社会にとっても、ひとつのコモンセンスであり、貴重な社会財産ともなるものだ。