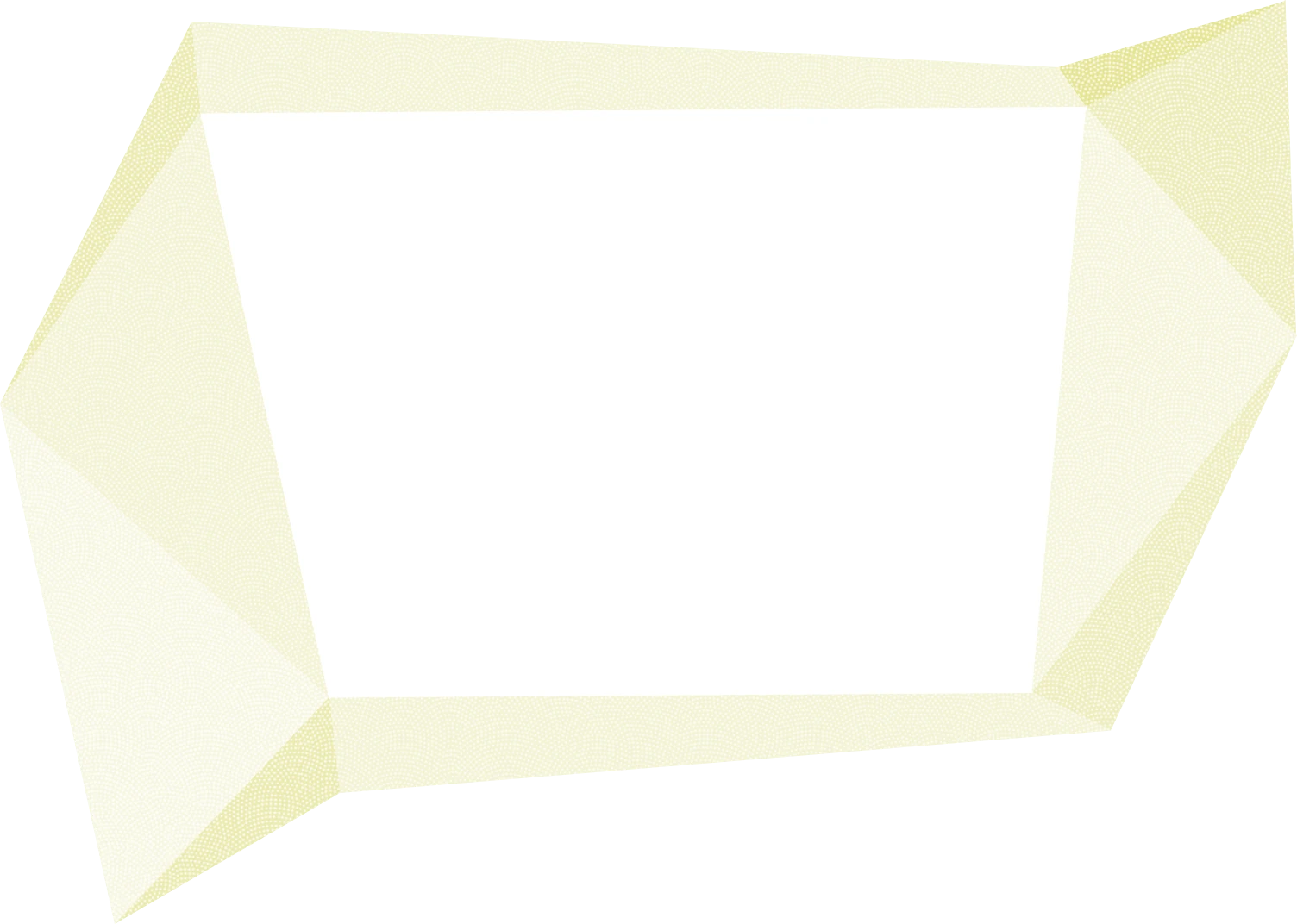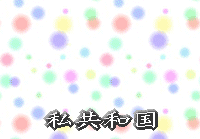前号では、「健康って何だろう」とのタイトルのもとに、退職後の健康増進との観点において、仕事は続けるべきなのだが〈金稼ぎの仕事をしない〉との選択について述べた。今号はその続編で、ことに「人生二周目、ポスト還暦」ではその実効ある内実にどう迫れるのか、そこが関心の焦点である。そうした〈金にならない仕事〉の働き方について、それを二面にわたって、実経験に立ちながら、人の心底にも届きうる作業について、話を述べてみたい。
そこでまず最初に、主題自体からは外れるのだが、いまの時代には取り上げやすい、金銭上の比較の面から入って行こう。
ここに、日本政府総務省統計局による、2024年の統計数値がある。
65歳以上の単身無職世帯の消費支出の平均は月14万9286円というもので、その内訳は以下の通りという。何らかの比較上の手掛かりとなりそうなので引用してみる。
・食料:4万2085円
・住居:1万2693円
・光熱、水道:1万4490円
・家具、家事用品:6596円
・被服および履物:3385円
・保健医療:8640円
・交通、通信:1万4935円
・教育:15円
・教養娯楽:1万5492円
・そのほかの消費支出(諸雑費、交際費など):3万956円
【付記】 この統計値の使用にあたって、ことにこの「住居」の数値の注意点だが、これは、借家、持ち家の両方を含む住宅関係費の平均である。家賃のみの世帯平均では、統計は2018年とやや古いが、4万6233円である。
そこでだが、こうした日本の「65歳以上単身無職者」の統計数値に対し、ここシドニーにおける私の同類の数値を示せれば話はしやすい。しかし、実は私はこの面ではずぼらで、日々の家計記録さえ残しておらず、こうした統計データとの有意な比較はまずもって無理である。
ただ、もしそうした記録があったとしても、当地の生活費、ことに住居費は極めて高く、生活をめぐる支出が、水準的にも構造的にも異なっていて、二社会間の統計的な比較としての意味をなさないほどである。従って、むしろその大きな違いを生む社会的背景に、話の焦点を合わすべきと思われる。
たとえば、昨年より私がパートナーと住む一寝室アパートは、控え目な相場上の家賃で言っても、週6万円、月にすると24万円ほどである。けっして高額地区の物件なぞではなく、ごく平均的な一寝室アパートにしてである。
そこで私は、二人世帯のその家賃の私一人分として、そうした相場額の半分にあたる、週3万円、月額では12万円を“家主”に払っている。こうして、自分の年金収入のほとんど半分が家賃に消えているのだが、これは、上に引用した「住居」費の1万2693円とは、10倍ほどもの開きのある額である。ただ、上の「付記」のように、家賃のみの世帯平均は月5万円弱で、それと私たちの世帯家賃を比較するなら、4倍以上の開きとなる。
いずれにせよ、統計定義上の不統一はあるが、これほどに大きな差は、同じ高齢単身無職世帯にかかる費用にしては、破格な開きと言ってよいだろう。
そこで以下は、こうした社会的背景を改めて描き直す意味も含めて、私たちのだどってきた経緯を振り返ってみたい。
そこでまず、上の“家主”という表現である。
これは、近年その高騰が著しいこの高住居費社会にあって、私たちの場合、パートナーと私が家主と店子となる賃貸関係をなすことで、その高負担問題に対処しているものである。言うなれば、一種の“有産無産両階級合作”をもっての生活防衛上の対処である。
この聞きなれない「対処」とは、要するに、その家賃出費の行き先を、どこかの資産家にではなく、せめて身内にとどめ、少なくとも、自分たちの住居所有のための費用の一部に回してゆこうとするものである。
というのも、私はそもそも資産形成に無頓着な“軽装備人間”がゆえ、家賃を払うこと自体については、やむを得ないとする立場である。他方パートナーは、堅実な性格もあって資産形成意識も高く、高額のローンとそのストレスを背負ってでも家を持った有産者となることを選び、その返済に充てる現金収入のため、日々の仕事に精を出すことをいとわない。そうした二者ではあるのだが、それまでのように第三者所有の家を間借りし続け、その高い家賃を、みすみすその第三者に払い続けてゆくのも、考えてみれば脳が無い。
そこで案を講じ、こうした対照的な二者との違いを生かして、自分たちの住まいとして手ごろな物件を借金購入し、家主と店子の賃貸関係を結んで、住宅問題に取り組んで行くこととしたのである。
つまりこの「対処」とは、こうした高住宅費社会にあって、人柄の違い明瞭な二者ならではが成せる、共同作戦のことである。
ただ、当然にここには、ローン主となるべき者の資格の有無や、時の進行とともに進む当物件の所有権問題、あるいは、両者が取り組む仕事をめぐる〈金になる、ならない〉との分水嶺的違いも伴なって、性格的なこだわりの違いでは済まない、金と資産の所有をめぐる緊張が潜在しているのは確かである。
ところで、二人がこうした「対処」を選ぶにあたっては、そうした社会を形成し、それに責任がある、歴代オーストラリア政府の政策が大きく関与している。
というのは、政権交代が起こる度に、基本的に、自由党政府は有産者向け、労働党政府は無産者向けの政策を実施してきた。
そうして社会に定着してきた住宅政策では、(最下層向け「公営住宅」や「初所有補助金」は別として)いわゆる公的住宅供給政策は行なわれず、高所得層に住宅投資を奨励する税政策を実施して、私有の賃貸住宅を大量に提供させてきている。いわば公的住宅政策のマス民営化である。
見方を変えればこうした政策は、無産者による賃貸住宅需要と有産者の持つ財産形成志向を結び付けたものであって、類似したものはどこの国にも見られよう。
くわえてオーストラリアでは、税を原資とした(自宅所有は認められる)無産者向け年金支給と、雇用主負担による上積年金、そして(相続税のない事実上無制限の)有産者向け財形減税を実施して、両極に分かれたかの諸策を並置し、それが柱となった国民生活経済政策としてきている。
言うなればこうした政策は、存在する階層/階級分化に対して、良く言えば相互共存政策であり、悪く言えば、その固定あるいは拡大化政策である。
さらに近年、そうした枠組みを揺さぶるかのようにインフレが高進し、その状況下での利率上昇によって住宅投資が縮小してその需給バランスが崩れ、上記のように、住宅価格の高騰を招いている。
つまり私たちの選択は、こうした状況を背景として、「対処」されてきたものである。従って、プライベートには、歴代政府のこうした無産者・有産者向けの二股政策を各々に利用したものだが、社会的には、あたかも一つ屋根の下に、無産・有産の両階層/階級が同居しているかのごとくである。そして、高進する住宅価格高騰にあぶり出されるように、こうも独特な、ある意味で社会の縮図のような、一対関係が形成されていきてる。
こうした社会状況のもとでの一産物であるこの「対処」において、そこには、そうした「対処」を選んだ特異な両人が取り組まねばならない、その負担や特異さの重さがゆえのメンタルなきしみがあり、その問題への「対処」も必要であることだ。さもないとこうした関係は、遅かれ早かれ、破綻に向かう憂き目を見ることとなる。それが、冒頭に挙げた〈金にならない仕事〉をより重要とする、外的なプレッシャーである。
一方、こうした特異な関係を、二個人間の心的関係から見れば、二人はこうして、互いに質の異なった経済的負担を負いつつ、異なった政策や制度の活用と家宅財産所有の有無の違いの上に、日々の生活をおくっている。その意味では、大いに等しからぬ二者である。
だがしかし、こうした違いから生じる摩擦や対立を避けたいのは、人情的にも当たり前だろうし、事態を互いに理解し合って不必要に足並みを乱すことなく、現実生活の円滑な処理をこなしうる相互に寛容な関係の形成と持続も、これも当然に望まれることである。
すなわち、このように選択された階層/階級上の違いのもたらす矛盾や差し障りを、相互理解を通じて解決する土台として不可欠なのが、こうしたリアルとメタとの両要素の入り組んだ関係を乗り切ってゆけるに足る身心両面の健全な働きであり、それをいかに用意し、それをどう堅持するかとの〈すべ〉である。
つまるところ、以上のような選択を、さらに心的次元で支えるため、その「身心両面の健全な働き」を生み出す源泉とも言えるのが、この〈金にならない仕事〉にほかならず、それがもたらしうる、柔軟かつ型破りな効果なのである。
これはまた、生きた人間同士の機微繊細なことでありながら、それが金の問題として雑に扱かわれてしまいがちな今日の傾向を、この「柔軟かつ型破りな効果」をもって回避しようとするものでもある。
そこで私は、紆余曲折ながら、そうした必要とねらいを持って、一見、伝統的な「主婦」役とも見まがいそうな、この〈金にならない仕事〉に取り組んできている。
そして、お金を介してでは極めて難しいだろう領域にまで、しだいに立ち入れてきていると実感している。
それはことに具体的〈すべ〉として、固定化された男女の役割を一つひとつ解きほぐして自ら「主“夫”」となる——むろん容易ではなかった——、男の沽券を捨てるにも等しい〈仕事〉である。
ここで一方、そうした考えと体験を通じてきて思うのだが、日本社会の場合、その税制をはじめとする諸制度にしても、そこにはまだ男中心の家族制度の旧弊が残っており、また、社会保障制度にしても、高齢単身者の生活を支えてゆくにはおぼつかない給付状態がある。つまり、上に引用した統計には、無味乾燥な数値の羅列の中に、その生活実態が反映されているはずである。
すなわち、この「住宅」の項の1万2千円なにがしには、その無味な統計数字にもかかわらず、そこには、上辺から下辺まで、さまざまな生活実態をカバーしての平均値であるはずだ。そして、それが(定義的に家賃を含むとしても)月1万2千円との破格な低額であるわけで、たとえ当地と比べて格安な日本社会においてであるとしても、それは到底、自立した単身の賃貸住居暮らしを意味しているものではあるまい。そうした実際の生活がどのようなものであるのか、想像するだけでも、立ちすくまされるものがある。
以上、話は各面に及んで長くなったが、それが〈金にならない仕事〉の社会的背景にという第一面で、ここでその第二の面に移る。
これは多分に個人の判断に属する実際面で、金銭的換算や比較がしやすく、またそれがゆえに、現実生活上では、いろいろ議論に取り上げられることも多い事柄である。
だがそれは要するに、いわゆる「リタイアした無職者」として、豊富な時間を駆使して出来る限り自力に頼るとの、金との関わりで言えば、低コスト戦略とも称すべき方法の実務である。
たとえば、外食や宅配を避け自分で料理する食生活とか、健康増進による医療出費の削減とか、あるいは、日頃の暮らしに必要な専門職の出動も、高額な業者に頼らず出来る限り自前でこなすといった、生活全般での低支出方式の実践である。
またここには、買い物など日常生活に欠かせぬ行動も、車や交通機関などに頼らず、自転車を使ったりあえて徒歩で行ったりする習慣も含む。加えて、そうすることで運動不足をなくす自らのエクササイズの機会とし、そして時間をそのように兼用しつつ、一見不便でみみっちいようでありながら、実は合理性な生活スタイルを体現していることである。
さらにそれは、塵も積もれば山となるとの量的効果が期待できるばかりでなく、その質的効果としても、家事一般、ことに食事など、お金の使用によってとかく他人頼りで味気なくなっていた日常生活が、身近な人の手による、親しみの湧く、温かみのこもった働きに満たされたものにさえ変わりうる行為である。まさにこれこそ、時間に縛られない、「リタイアした無職者」ならではの本物の仕事である。
むろんその実行にあたっては、それだけの実効果を上げるため、けっこうな意欲や工夫が求められるのは確かで、趣味や暇つぶしレベルの行為で片付くものではない。またそれは、実際の効用や出来栄えをなさないと逆効果で、ゆえに、内実や熟達さえもが求められる働きである。つまり、それほどの本腰の投入が求められ、生半可なボランティア気分でお茶を濁ごせる事柄ではない。もちろん、こうした働きを支えるに足る健康の維持は、前編に力説したように、これらすべてに先行する基盤条件である。
かくして、こうした一連の〈金にならない仕事〉の諸々とは、その聞こえの悪さに反し、金稼ぎへの頓着に等しい、あるいはそれを上回って、その内実や熟達への頓着が真摯に求められる諸事である。つまり、〈金になる、ならない〉などの視点を脱した、人間による人間のための、本来の次元の働きと言えよう。むろんそこには、常識も確約された保障もないが、逆にそれは、オープンで限りがない、じつに自由な世界でもある。
さて最後に、以上のように述べてきた、そうした意義をになうはずの〈金にならない仕事〉であるのだが、その他方で、いかんせん、日々刻々と老化の坂を下っている自分の身心を無視はできない。
そこで、残る健康要素を最大限に引き出し、言葉の真の意味での《生き甲斐》つまり《生命の意味》をどう見出してゆくのか、いまの私にとって、〈金にならない仕事〉とは、そういう課題である。
当然にそれは、お金依存を始め、現行の諸制度や慣行などの実在手法の域を超えるものである。またそれだからこそ、金銭圏でのフル体験を獲得、満了し、そこから撤退したリタイア人生の意味を探り実施するにふさわしい、これぞ「人生二周目、ポスト還暦」の〈仕事〉と思う。そして、この〈金にならない〉との否定的語感を越えて、肯定的な世界の開拓として、その成果が期待される。
どうやら、「ポスト還暦」の二周目人生も、来年8月の傘寿を前に、次の周回に入ってゆきそうな気配である。そしてこの20日には、そのプレ出発とも言うべき、79歳の誕生日を迎える。
【まとめ読み】