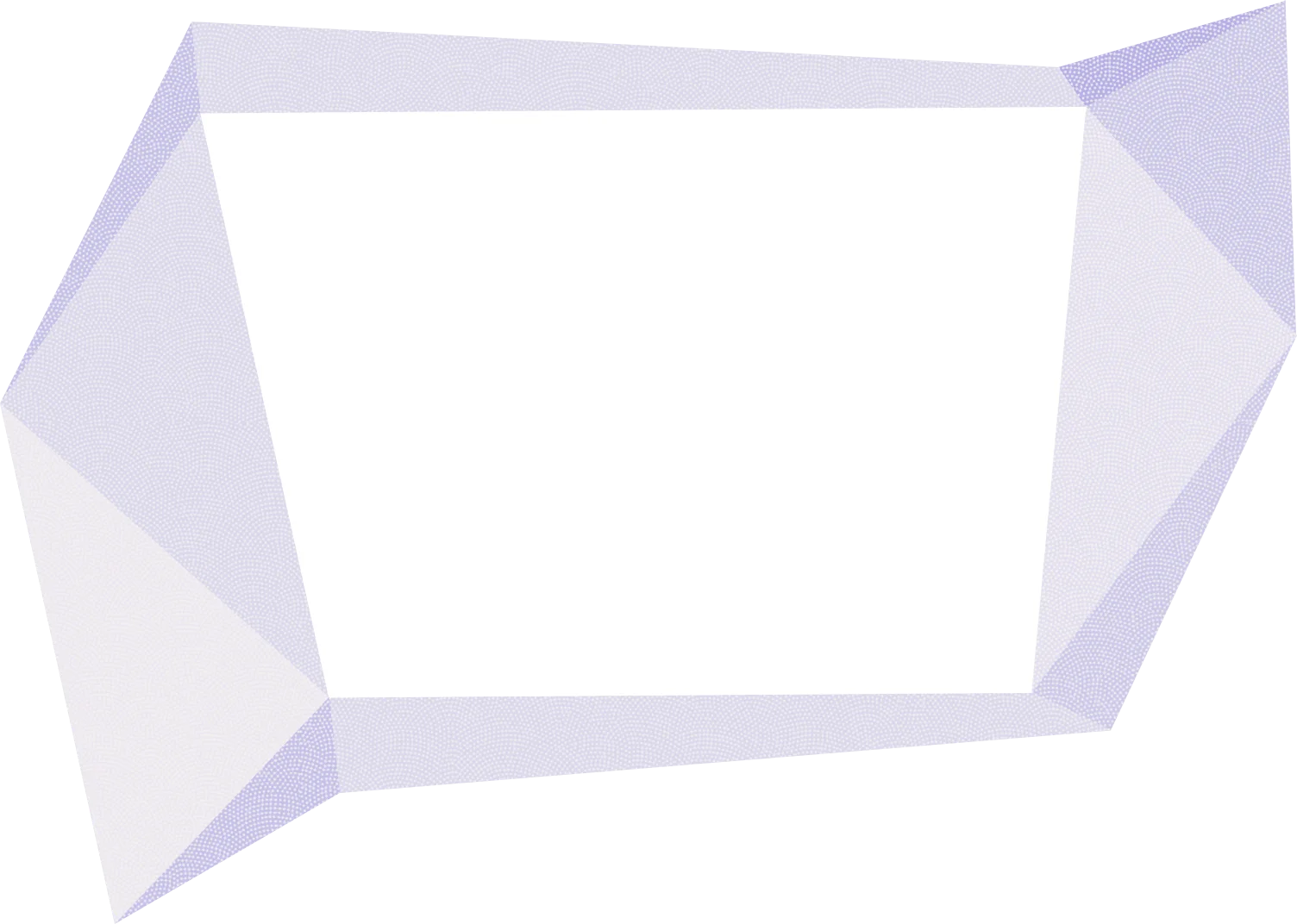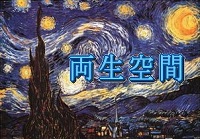本サイトの主要コンテンツのひとつに、『天皇の陰謀』があります。この大冊な本の訳読には、本との出会いからその完成までほぼ13年を要しました。いまでもそれを、必要に応じては、思い返したり読み直したりしているのですが、よくこれだけの、しかも翻訳という門外漢の、仕事を成しえたものだと、率直に言って、思わず自画自賛してしまうところがあります。しかもこの仕事は、今日のように便利な翻訳アプリのない当時、それこそ、一字一句辞書を引きひき訳して行った、遅々たる作業の積み重ねの成果であることです。
それにしても、なぜ、自分でも驚くそうした大仕事に取り組んだのか、そこには、自分の存在にまつわる、「先の戦争」との関わり、つまり私が体験した時代性があります。
私がこの大冊の翻訳に取り掛かったいきさつには、その戦争の直接の当事者ではないものの、昭和21年8月生まれという、まさに戦争が終わった平和の証の生命としての私が出会った、逃げも隠れもできない、一連の残響があります。
加害者なり被害者なり、あるいはその両方の、何らかの関係にある日本人のひとりとして、その残響の私なりの受け止めをその作業を通じて形にしなければ、と思うに至ったためです。
そこでそうした残響に共にとらわれた同時代性という意味で、表題にかかげた「戦後80年所感」を公表した石破首相に、何らかの共通性を見出したいと期待したところがありました。
私は昭和21年生まれの79歳、石破首相は昭和32年生まれの68歳で、11歳の差はあります。ですが、共に直接の戦争体験者ではないものの、戦争世代の思いを後世に引き継ぐべく、共に、戦時と戦後の間に位置する世代であることです。
それに私のその大仕事が完成したのが2013年で、私が68歳の時です。そして石破首相は今年68歳で、当時の私とまさに同年齢です。くわえて、私のその完成と彼の「戦後80年所感」の発表は、それぞれ個人として、「還暦」を迎えての人生上の節目に共通して行われたもので、その意味で、その残響への対応としての、格別の思いを秘めての機会であったのではないかと思えたわけです。
主題からは外れますが、還暦とは、何やらそんな風に、人の人生に明らかな節目を与える区切りのようです。
そこでなのですが、私の場合、この大仕事にはひとつの副産物があります。すなわち、そうしてこつこつと続けたひと作業が終わるごとに、「ダブル・フィクションとしての天皇」という題名のコメントを書き、本文に付随して表わしていることです。つまり、私にとってその翻訳を介してその戦争を体験した「所感」です。
さて、そのように「先の戦争」との時代性を共にしていながら、この「戦後80年所感」と私の「ダブル・フィクションとしての天皇」という両「所感」には、当たり前と言えばその通りですが、確かな違いがあります。
そこでですが、以下に述べることは、そうした違いについでです。
まず、この私の「所感」にある「ダブル」つまり「二重」とはどういうことか、その連載の初回でこう述ています。
一般日本人は、そうした 「天皇の陰謀」 によってあやつられていたばかりでなく、さらにその天皇を利用し、天皇ごと日本全体をあやつってきている、アメリカの 「陰謀」 があるわけです。(後発国の王の弱みや腐敗を逆手どり、それを見逃したふりをしつつ結託し、王と国民の両方を支配する米の “手口” は、今もちっとも変わっていません)。そうした意味では、そこには二重の 「陰謀」 の餌食化があるわけです。
そうした判断から、「陰謀」 との語句は用いず、二重性を重視して、「ダブル・フィクション」 としました。また、もし、「陰謀」 という語句にこだわるなら、「アメリカとの二重陰謀としての天皇」 とせねばなりません。
ここには、この「ダブル・フィクションとしての天皇」という所感を始めるにあたって、一種明解な被害者意識が読み取れます。つまり、その戦争の「餌食」とされたという体験には、それを日本によるものと、アメリカによるものとの「二重性」があったとしているものです。
実のところを申せば、私はこの「訳読」作業に取り掛かる前、同書に出会って以後二年ほど、それを棚ざらしにしていました。というのは、その見るからに重たい書をどう扱えばよいのか思いに余り、それとはなしにですが、見て見ぬふりをしていました。しかしそれもし切れず、やがてその作業におもむろに取り掛かり、それを通じて、一種〈折り重なった〉自分と自国、アジアや西洋との関係を発見するに至ったのでした。
つまり、この大仕事に取り掛かった当初、それは日と米の国家権力という「ダブル」すなわち「二重」の外力の存在であったものが、やがて、もっと〈折り重なった〉ものとして、自分自身に内在化した関係にさえなっていることの発見に至ったものです。
さてそこで他方の、石破首相の「戦後80年所感」です。
私はそれを読んで、最初、現役の首相の持つたとえ「所感」としても、前任者のものとは違って、一歩踏み込んだがあるとの第一印象は受けました。
そうなのですが、しかしそこには、その戦争に巻き込まれた日本を含むアジア諸国の無数の国民への何らの言及もなく、その表面の印象とは裏腹に、「きれいごと」とは譬えないとしても、一種の「学術論」としてこの戦争問題を扱おうとしているとの印象を持ちました。言い換えれば、一種中立した見地を想定した、研究分析の見解です。
つまり、そした見地ならそうした清廉な表現は可能でしょうが、政治家という、国家権力が与えられ、それを駆使できる立場としては、その任期に後がないならなおさら、ある種の勇断を託した現実判断があって当然と思えました。
そうした「戦後80年所感」の中で、彼は、「無責任なポピュリズムに屈しない、大勢に流されない政治家の矜持と責任感を持たないといけない」(斜字は私)と述べています。しかし、政治家である以上、スポーツ選手と同じく、「結果を出す」ことがその使命であるはずです。それを「矜持と責任感を持たないといけない」だけでは、それはほんのその仕事の取っ掛かり当たっての心構えにすぎません。スポーツ選手にしても、プロとして自分の「矜持と責任感」くらいは当然に、まさにそれのもたらす結果に自分を賭けているわけです。
まあ、だからこその、党内基盤の弱い立場がゆえの、閣議決定もできない、個人的見解の公表で「恰好」を付けたのでしょう。だが、もし彼が主流派政治家であったなら、同じことを閣議決定したのでしょうか。
ところで、上記の「ダブル・フィクションとしての天皇」では、上に述べたように、その98回におよぶ一連のコメントの中で、その訳読作業を続けることでの一種の見解の変化に触れています。
たとえば、その第83回「青年期の蹉跌」と題した記事で、以下のように述べています。
もし、このロングランの作業に、ずっとお付き合いいただいている読者がおられたとすれば、この間に、私の姿勢も微妙に変化してきていることに、お気付きかと思います。
まあ、他者の視線の意識はともあれ、その本人としての “自覚症状” を端的に申し上げれば、この 「戦争」 つまり1945年8月に終結した 「中国・太平洋戦争」 への理解の深化にともなう見方の変化です。それなりの全体像がなんとかつかめるようになった結果の、なんとも不可解だったその “怪物” への自分なりの見方の醸成です。還暦を越えるこの年齢になってのようやくの到達で、なんとも恥ずかしい限りですが、少しは、長年の課題の荷を下ろしつつあるとの感はあります。
そこで、ここから先が微妙なのですが、誤解を恐れずに言えば、この戦争へのある種の否定的見方の見直しです。少々象徴的に言えば、 「よくやった」 とでも当時の日本人に声をかけたい、そういう心境の形成です。もちろん、その戦争を賛美する意味では決してありません。先にも、私はこの真珠湾前夜までに至ってくる曲折を、 「切ない」 という表現でもって表しましたが、何か、そういう個人感情を抱かせる、一連の他人事でなさがそこにあります。少なくとも私はそういったものを発見してきています。ことに、同じく先に書いた擬人化した表現―― 「二重 “国” 格」 からくる一種の成長上の歪み――を改めて念頭に置くならば、それはあたかも、日本の “青年期の蹉跌” のようにも見えてくるのです。
つまり、私として、そういうきわめてアンビバレントな心理の出現です。むろんこういう私の変化は、今日の日本の動向である、いわゆる 「右傾化傾向」 と同列のものと受け止められかねないものです。それを承知の上で、それでも、そのように表現したい、私の心境があります。
この第83回が書かれたのは2013年1月で、もうその当時からの日本の「右傾化傾向」が懸念されています。そして今や、この右傾化は日本ばかりでなく世界各国の傾向として、それぞれの国の国際協調離れの方向を顕著にしています。そしてその自国第一主義がへたをすると第三次の世界的戦争の火種になるかの恐れさえ指摘されています。
そうした認識にたつ第98・最終回のタイトルは、「『日本人であることの不快感』と、その解消」です。そこに私はこう述べています。
今回をもって、これまで7年と3ヶ月間にわたった、この 「訳読」 が遂に完結します。
そして同時に、私にとっての、ひとつの長年の疑問も、その問いかけをひとまず終えることができそうです。その長年の問いかけとは・・・、究極的には、 「日本人であることの不快感」 であり、
それを終えることができるとは・・・、自己発展的な、その 「不快感」 の解消です。
大仰に言えば、私は、昭和21年生の最初の戦後世代として、どうやら、戦前世代と戦後の世代をつないで担いできたらしい荷物を、なんとか、下すべき場を見つけた感があります。端的に言うと、 「日本人であることの不快感」 とは、私自身が、かっての戦争での 「残虐な日本人」 の一人であることです。
そして、その 「解消」 とは、それが、二点における、 “植えつけられ” の産物であった、との気付きです。つまり、私――あるいは日本庶民――の本来の属性ではなかった、ということの発見です。
そして、その 「二点」 とは・・・、
第一に、日本人は、敗戦によって、意図的に分断されてきたことです。つまり、支配の普遍原則である divide and rule、すなわち 《分断支配》 です。日本人全体が、軍部を支えて人殺しをし、かつ日本を敗残国に導いた 「悪い」 日本人と、 “平和的だった天皇” と共に軍部に批判的だった 「良い」 日本人、という分断です。もちろん、この分断状況を作為的に作ったのは、戦勝国アメリカの巧みさです。
第二の 「植えつけられ」 とは、日本人が日本人を支配するために、天皇という権威を、歴史的実態を越えて過剰に 「親」 格化して 「神」 格化し、 《親離れできない日本人》 を、意図的に定着させてきたことです。そしてその自立を欠く 「臣民」 としての日本人による 「大親」 たる天皇への忠誠が美化、国教化されてきたことです。
私は、この 「親離れの不足」 を、 「天皇離れの不足」 とか、 「王離れ不全」 ( 「置き去りにされた皇国少年たち」 参照) と呼んできました。
こうした二重に分化した日本があって、それはひいては、 《民主的で合理的で現代的な日本》 と、 《伝統的で文化的で古臭い日本》 といった、しっくりとは落ち着き合えない日本人意識を形成し、逆に、その両方を兼ね備えた、より大きく、包括的で、より生きいきとした日本人自我を作りにくくしてきました。
そこで、上記の第一と第二の両者合わせて、まさしく、 「ダブル・フィクションとしての天皇」 たる虚構であったわけです。
したがって、もし、日本人全体が、この 「解消」 によって、その内部の桎梏を克服し、しかも、不必要な社会的内部摩擦から解放されたならば、その全体的一致感がもたらす、社会的高揚感とその総和エネルギーの量は、日本をして目覚ましい飛躍をさせるものではないかと予想されます。それはまさしく、 「大人化した日本」 の誕生です。
この「『日本人であることの不快感』と、その解消」の見地に立てば、今日の「新保守」とよばれている主張は、この「ダブル・フィクション」を画策しえた一方のフィクションに立ち帰り、あらためて、「親離れ」 つまり「天皇離れ」をしないで、その庇護下に戻ってゆく、非自立、あえて申せば「幼児化」、の見解であることが解ります。
確かに、去り行く石破首相は「矜持と責任感を持たないといけない」とは表明し、今日の「新保守」の動向に、「いけない」との叱咤はしています。
それは、「ないよりまし」としても、今日の情勢を動かす実務にはなりえません。
報道によれば、それは単なる「一般論」であるようですが、連立から離れる公明も、石破となら離れなかったとする、むしろそちらの方が、実務には有効であると思います。
昭和21年生まれの「平和の落とし子」たる私として、いまこそ、「平和」という大同に、小異は従えるはずだと考えます。