前回の「『理論人間生命学』の独自サイト設立準備(その2)」では、新型コロナウイルスについて、それを人類の自覚をさとすかの「点火装置」とたとえた。だが、いまだにその挙動に謎の多いこの病原体について、どうもその役どころはそれにとどまらず、どうやら、人類の向かう方向をリセットさせる「通告者」の使命を果たしているかのようである。ならば、その方向とは? そこで問題は、そのような世界の変曲点たる今にあって、この災厄を体験した私たちが、自らの立つ位置をどのように定め直して行くのか、前回につづく、その考察の続編。
コロナ人為工作説
そこでまず、前回の結論で示した二極――人為か自然か――について、いずれが妥当な見方なのか、それを再考してみることから始めたい。
まず最初は、人為説。
この流行が人為的意図によるもので、それも、そこまでになるとは予想していなかった、いわゆる「ブローバック」――想定外の拡大あるいは逆効果――まで起こしているものであったとするとどうなのであろうか。
こういう問題設定に立てば、まず、その実行者は誰なのかという疑問を生む。
そこでその下手人の出どころを、現在のそれらしき国に求めれば、中国と米国の――人造ウイルスや遺漏をめぐる陰謀説を応酬し合っている――いずれか、ということとなる。
だが、その下手人が、仮に、両国のいずれかとされたとしても、その真偽のほどは、陰謀説応酬の霧中でのそれにしかならないだろう。しかも、それがもたらした、世界に広がる大恐慌レベルの経済崩壊を考えれば、たとえブローバックが生じていたとしても、それは余りに間尺に合わない無分別なたくらみと言わざるを得ない。
だとするなら、そういうレベルではない、さらに深謀に富んだ別の企てがあるのだろうか。
そこで想定されるのが、こうした結果のすべてを見越して計画され実行されている、スケールを異にする企てである可能性である。
それほどに膨大かつ不遜な企てを立案、実行し、しかもそれが自らの目算に合致するような、そうした膨大な力と遂行能力と、そしてそうした途方もない顛末を冷徹に予期する者とは、一体、誰なのだろうか。
それほどの、この想定における「下手人」とは、前回に述べた「自称陰謀論者」たちが論証しようとしている、世界の頂点に君臨する大資本家たちによるマネーの中枢をなす、「資本の意志」としか呼びようのない存在であろう。
ただ、ここで留意しておきたいことは、またしてもの「陰謀説」である。すなわち、世界の頂点に位置する、この隠然とした巨大行為者の存在を主張するそういう発想自体こそが、耳目を集めやすいが根も葉もない「陰謀論」の最たる証拠とする、“究極”の「陰謀説」までもが流布されていることである。
むろん、市井の人々にとっては、そうした頂上人の姿や声すらを、たとえTV上でも、実見聞できる体験はまずない。従って、それを「下手人」とする主張こそが現実離れした空論だと指摘する、そうした説が広く受け入れられやすい。
だからこそ、その頂上の見えざる主は、そこを逆手取ってこの「究極陰謀論」を流す。そうしてその頂上者は、自分たちの存在を秘密裏に置く限り、一般世界への可視化は避けられ、ひいてはその無存在をすら決め込める。
こうして彼らは、陰謀論の際限なき“うやむや化”のループの裏に隠れ続け、自らの「意志」にもとづく世界支配を貫徹している。
ともあれ、今のコロナ禍は、それが人為的なものであるためには、その規模や意図からしても、そうした怪物レベルの作為者なくしては到底考えられない。
そこで、冒頭に述べた全人類規模の「操縦者」が誰かとするなら、この「資本の意志」こそ、その筆頭の下手人候補となろう。
(ところで、こうした頂上作為者の存在については、むろん、陰謀論の応酬レベルで片付けられてはならない問題であり、当「理論」では、機会を改めて――多分次回で――より踏み込んで考察してみたい)。
コロナは自然現象
では次に、新型コロナウイルスによる未曾有の破壊が、まったくの自然現象を発端とするものであるとするならどうなのか。つまり、このコロナ禍という災厄が、《自然の摂理》によるものとするならどうなのか。
そこでまず初めに、このコロナウイルスについて、今までに解ってきている科学的知見について KENKYOFUKAI しておきたい。
『ナショナルジオグラフィック日本版』の電子版2020年4月8日の記事に、以下のよう説明がある。
最近の発見によれば、新型コロナウイルスが自己複製のために宿主の細胞に侵入するには、ウイルスが持つスパイク状のタンパク質が、特定の動物細胞の表面にある「受容体」と強く結合する必要がある。アンジオテンシン変換酵素2(ACE2)と呼ばれるこの受容体は、いわばドアの鍵穴であり、スパイクタンパク質はそれを開ける鍵だ。
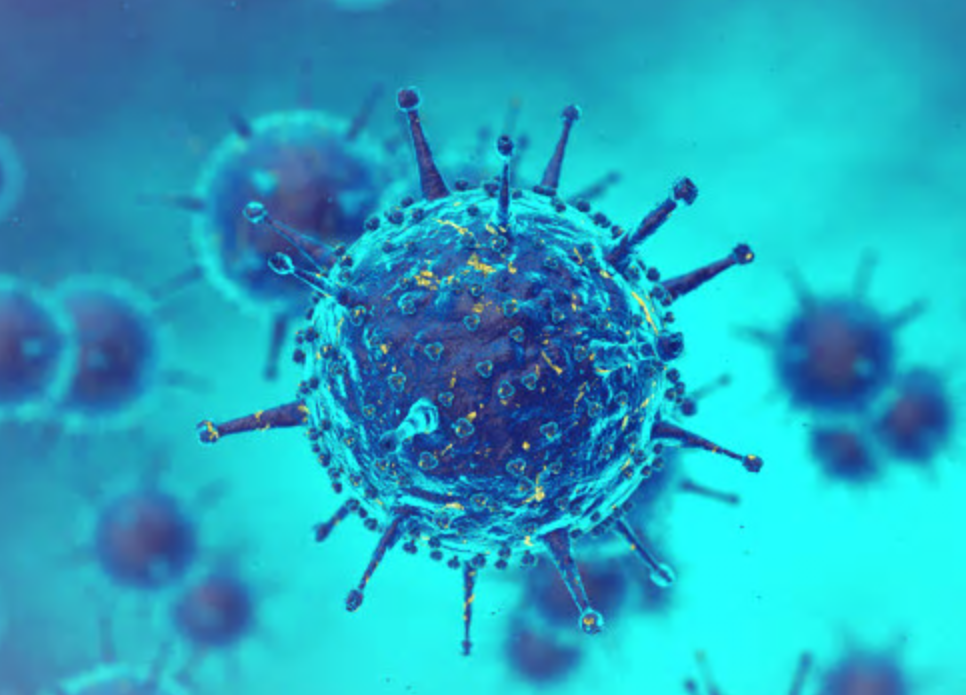
コロナウイルス:ウニの棘状の突起が「スパイク」
そこで、この「鍵と鍵穴」と形容されている、ウイルスの「スパイク」と宿主の細胞の「受容体」についてだが、ここで、予断を排して視点を無垢にすれば、それらは、動物そしてもちろん人間の男女の各々の生殖器を連想させはしないか。しかも、その「鍵と鍵穴の関係」とは、スパイク(凸部)と受容体(凹部)とが「強く結合する関係」ともいう。もしそういうことであるなら、上の擬人化連想をさらに続けると、なにやら、ミクロ世界での“セックス”の話、とでも言えてしまう。
そこで、そうしたいわゆる生殖プロセスに準ずる活動がここに起こっていると見ると、前回でも述べたように、ウイルスとは、生物と情報の“あいの子”であるとの意味の何たるかが、にわかに浮かび上がってくる。
すなわち、コロナウイルスは、自分の凸部を人間細胞の凹部と結合させ、その疑似生殖行為を通じて自分の情報を植え付け、自分の「戦略」を相手の内に発動し、それを発病に至らせる。
これは、さらに擬人化連想をたくましくすれば、射精のような物的注入はせずとも情報の伝達はなされ、まるで受精と出産現象であるかのごとく、それのもたらす「わるさ」すなわち陣痛を引き起こし、それをへた結果の自らの増殖を達成する、ということとなる。
ところで、最近、遺伝のメカニズムや細胞核レベルでの情報伝達が説明される際でも、DNAが果たす「鍵と鍵穴」関係、といった表現によく出くわす。
ということはすなわち、♂と♀というような、生物を構成する二種の異性成体による結合関係、つまり性交関係というものが、どうやら、生物活動の成体段階だけでなく、その細胞核レベルのミクロの世界――生殖活動の中核部分――においても生じているという、生命活動の普遍的原理であるかの関係という着想を引き起こさせる。
ちなみに、この対となった異質要素という構成は、以前に述べた素粒子における「双対性」との概念にも通じることを付け加えておきたい。
要するに、それらはみな、類似あるいは相同しているのだ。
そうであるだけに、この“出産現象”はさらに踏み込んで見ておきたい。すなわち、こうしてコロナウイルスによって情報伝達される「戦略」とは、単に自身の寄生にとどまらず、そこに自らの意図も含めた、みごとな《操作》あるいは《乗っ取り》の機能さえも果たしていると観察できることである。
そしてそれは、現在のパンデミック状態が表面的に語られるような発症や致死に留まらない、そうした疫病感染過程を通じての、宿主すなわち人間の《生存のふるい分け》も果たしていることが見て取れる。
ここで私は、この「ふるい分け」には、さらに含んだ意味を嗅ぎ出してもいいのではないかと思う。つまり、このパンデミックによってふるい分けられた生存の結果なのだが、その犠牲者は、万遍ない均等分布をなしてはおらず、確かに片寄った様相をていしていることだ。
たとえば、その感染による致死率はさほど高くはないが、国や人種や世代によって、その数字に確かな違いがあることだ。
そうした死者のほとんどは、高齢者、しかも、心臓系、呼吸器系、糖尿系など、何らかの既往症をもった人たちである。また、社会的な不平等の被害者、たとえばホームレスもそれに該当する。(若い世代でも少数の死亡例がは出ているが、その特異な死とコロナウイルス感染との病理上の因果関係については、よく説明されていない)。
つまりそういう犠牲者らは、そういう“極刑”を執行された人たちであると言わざるを得ない。コロナウイルスは、そう「操作」しているのだ。
他方、幸いにそう執行されず、生き残った人たちのその生存の理由とは、今日の医学的知見では、免疫の有無が主理由となっている。つまり、免疫反応という細胞次元の活動が様々なウイルス攻撃に対して自然、自動的に働き、抗体を作って防衛してくれているという生体メカニズムである。
そこでだが、免疫の有無が「極刑」の執行を左右するということなら、それは、健康のみならず生存すらの必須条件であるほどに重要な要素ということである。
つまり、今日のパンデミック状態においては、そうした生存必須要素までもの欠乏状態が、それほどに、しかも不公平に、蔓延していたということを物語っている。そう、コロナウイルスは「操作」しているのだ。
私の理解では、免疫作用の有無については、それは自然との隔たり度――普段からの多様なウイルスとの接触体験度――の問題である。つまり、自然との接触が乏しくなればなるほど、免疫を獲得する機会も減る。言い換えれば、そうした「欠乏状態」を、そのように偏った生活習慣の結果と捉えれば、たとえばガンのように、それは「生活習慣病」と呼ぶことも可能となる。
かくして、免疫の有無も「生活習慣病」の概念に含みうるとするなら、健康を保持する生活習慣には、自然との接触ということも必須要素となってこなければならない。言うなれば、そういうことも、コロナウイルスは示唆しているということとなる。
以上の考察に基づき、さらにもう一歩、議論を進めると、医療とは、病人を顧客とするサービス産業であると看取できる。そこで、それをやや皮肉って特徴付ければ、病人が増えればそのサービス需要も拡大し、この産業も繁盛する、とでも言えることとなる。つまり、今の新型コロナウイルスのパンデミックとは、世界的に、医療がそのような「病人様々」産業であるとの実態でありながら、今回のような「いざ」という試練にさらされた時、どの程度にサービスできるものであるかとの「ストレステスト〔荷重試験〕」を実施しているようなものだ。それはまさに、「私たちの命を本当に守ってくれるのか」との問いかけを行ってくれている。
そこでだが、そうした試験結果の判定はまだ時期尚早としよう。しかし、すでに明瞭となってきているその産業の欠落は、病人依存の転換や、さらには、人々の健康深化サービスといった分野に見え始めている。
もしそれが十分に提供されていれば、多くの人々の生活の質は向上し、生きる歓喜にいっそう満たされた日々が送れるようになり、人生観すらガラリと変わることとなるだろう。
これこそが、このパンデミックに託された究極のメッセージではないか。しかもそれでは終わらない。それは社会の経済面で、費用対効果は逆転し、必要な医療支出は抑えられ、その社会の生産性をはるかに高めるだろうと展望される。
ところで、今日のパンデミック状態の中で、高齢者とか既往症の持ち主を、「弱者」と捉える見方がある。確かに、現時点に限った断面においてはその通りだが、時間軸を長くとった場合、「弱者」とは、上述のように、良くない生活・社会習慣の弊害を、長年のうちに、自分の身をもって背負ってきてしまった人たちのことにほかならない。また、「弱者」にいたらぬ「健常者」とて、正直言って、明日は我が身だとの“近接”した心境にあることは否定できないところだろう。
つまり、コロナ禍は、医療体制の「受動から能動への」転換によって、病害の防止は言うまでもなく、社会全体の進歩と相たずさえて、そのような「弱者」を出させない環境作りをも示唆している、と読み解けよう。
「理論人間生命学」ならどう見る
以上のように、本稿は、コロナ禍の「人為か自然か」をめぐる問題を、それぞれの視点より見てきた。
しかしこの問題は、その二者のどちらかを正解とし、他方を誤りとして捨て去って済む問題ではないだろう。
ことに、この災厄を何とか乗り切ったポスト・コロナ世界をどのように再起動させて行くのかを見据える時、「陰謀論」の応酬という情報戦には取り込まれない、私たち人間社会の真の進歩を目指す方途が見出されねばならないだろう。
そこで、この「理論人間生命学」の「理論」としての見解は――今の段階ではまだ初段的なものだが――、それの基本方向としては以下のように考える。
まずその初めに表明しておきたいことがある。それは、今回のパンメデミックとの戦いで、あたかも戦士のごとくに奮闘されている医療に従事されている方々の働きへの、心からの敬意と感謝である。
そして、本稿に挙げられているような、医療システムの欠陥や望まれる目的がフルに果されていない現状についての指摘は、いわゆる“けなし”といったものでは到底なく、そうした献身的働きへの敬意と感謝を、強めこそするが、けっして弱めさせるものではない。
さてそこでだが、こうしたパンデミックとの受動的な闘いの中で見えてきている、明らかな危惧がある。
上述のように、ウイルスは情報体との特色を持ち、それがゆえに、それを相手として人類の打つ手は、明らかに後手に回らされている。
たとえば、政府やビジネス界は、まずは、その敵との接触を断つとの古風な籠城作戦をとるしか選択はなかった。
そしてその成果が見られるにつれ、入り込まれた感染のルートを追跡するために、IT装置を総動員して、しらみつぶしの監視体制を構築しようとしている。
だがいずれもが役立ったとしても、それがウイルス自体の撲滅には直結せず、やむなく、人々の行動を長期に制約して、免疫の広がりに期待する以上のことはもたらしえない。
つまり、こうして、人びとを標的とした監視体制を敷くというのは、間接的な対処に過ぎないにもかかわらず、それは不釣り合いに過大な副産物――閉塞した拘禁社会――を招く結果になりかねない。
そうした対処は、仮に、IT化を装った新構築が成功したかに見えるとしても、ウイルスといういかにも賢い病原体への対処としては根本的ではなく、従って、その感染が繰り返される可能性はいくらでも残されてしまうだろう。
以上のように、新型コロナウイルスは、パンデミックな惨状を世界に突き付けることで、冒頭に述べたように、あたかも「通告者」であるかのように、人類に貴重なメッセージを発している。
それを上記のように受信して想うことは、社会に積み重なった永年の諸弱点の除去には、今や、《情報》に関する技術が切り札になるだろうことだ。そしてそれならではの刷新性を引き出し、それを実用化して、これまでの取り組みでは取り上げ切れなかった旧弊との新手の取り組みを有用にさせることである。そして究極的には、そうしたプロセスをへて至るであろう《情報資源社会》への移行である。
ただし、そうした社会については、そのビジョンはまだまだ具体的ではなく、まだ「多量データ社会」ほどとしてしかイメージ化されていない。むろんそれも必要な一歩だが、要は、私たちは希望を渇望しておらず――あるいは、それが希望だとは気付いてさえおらず――、お仕着せの疑似進歩に押し切られようとしている。
来るべき《情報資源社会》では、そこに私たちの真の希望をどう実現させてゆくかが問われる。そしてその希望とはまさしく、物ではなく、情報に託される。そうした社会の真価は、見失いかけている私たち自身を私たちがどう発見し、それをどう情報化してゆくか、そこにかかってこよう。
思うに、新型コロナウイルスは、見かけほどに人類社会を打ちのめすのが本意ではないだろう。「人間って、それほど弱みだらけでいいの?」そんな声が聞こえてくる。

