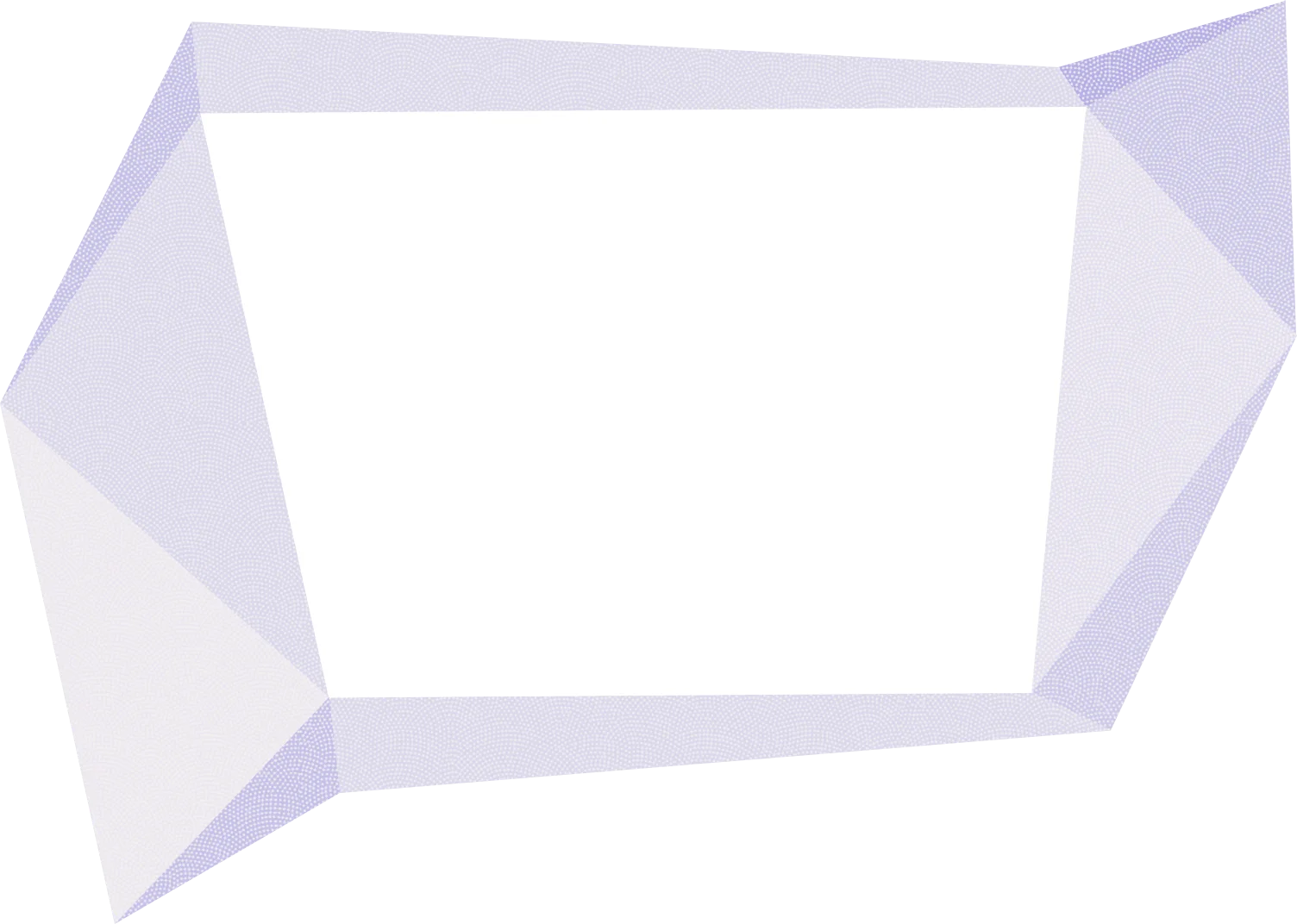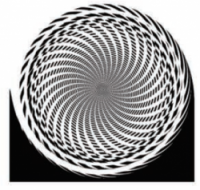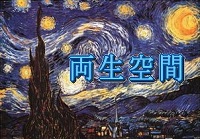| == 本書の《もくじ》へ 「もくじ」の中の《本章》へ == |
「宗教とは、誰か他人の体験を信じること。霊性とは、自分自身のそれを信じることである。」
ディーパック・チョプラ〔ホーリスティック医学博士〕
チョプラの賢明な観測は、私たちが常識とする現実を変化させるには、いくつもの道があることを教えている。自らの経験に立つことは、もっとも説得力ある方法だ。宗教の中核である誰もが打たれる神聖な真理は、自分自身のうちに見出した発見によって立つことに契機を与える。いわば、一つの真理、多様な反応である。
ここで別のシナリオを想定してみよう。近い将来、注目される記者会見において、科学者たちは、死後の世界が、実証を重ねてきた結果、実在するという発見を――事実としてではないとしても、少なくとも十分に検証された科学的仮説として――世界に向けて発表することになるだろう。こうしたテーマは、神秘家によって何世紀にもわたって告げられてきたことだが、いまや、科学が新しい主張としてその裏付けを引き受けようとしている。そしてその記者会見では、研究者たちは、死後の世界は完全に解明されているわけではいないが、誰もが自分の死についての「体験談」といったような経験をするだろうことは、おおむね確信できることであるとするだろう。そうした個々人は、その生涯のあらゆる出来事や行為ばかりでなく、その行動が他の人たちにおよぼした影響を、肯定的であろうと否定的であろうと、経験してきたはずである。ただ通常の防衛機制が、自分自身を隠してしまい、時には他人への同情的態度も持てなくさせてしまって、その生涯の真実が見直されるまで、自らの否定的行動に気付かないままになってしまっている。だが、存命中の人たちが、その死以前に自分の生涯のありのままの真実をさとった時には、生存中の行動や考えが真実に結果をもたらしていることを認識し、そして十分にそのすべてを覚るに至るのである。 詳細記事