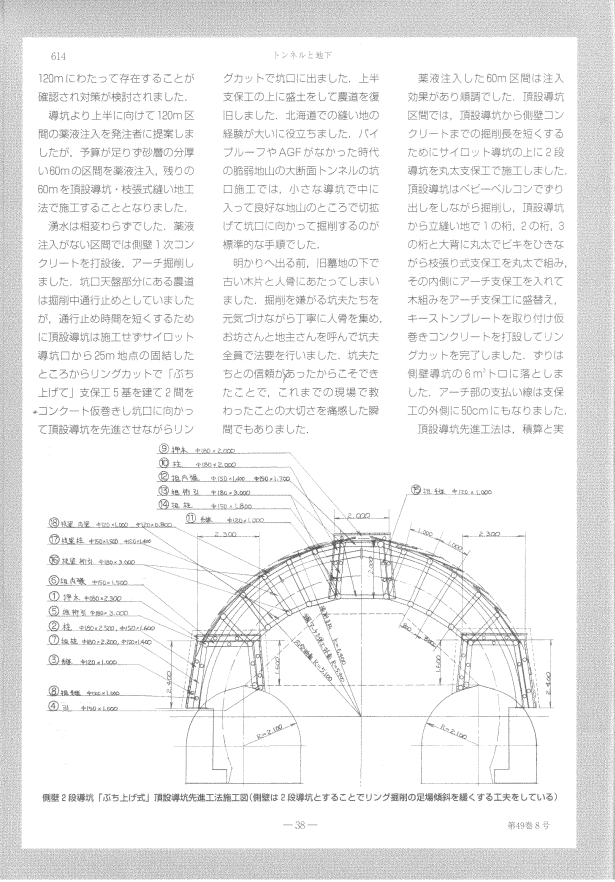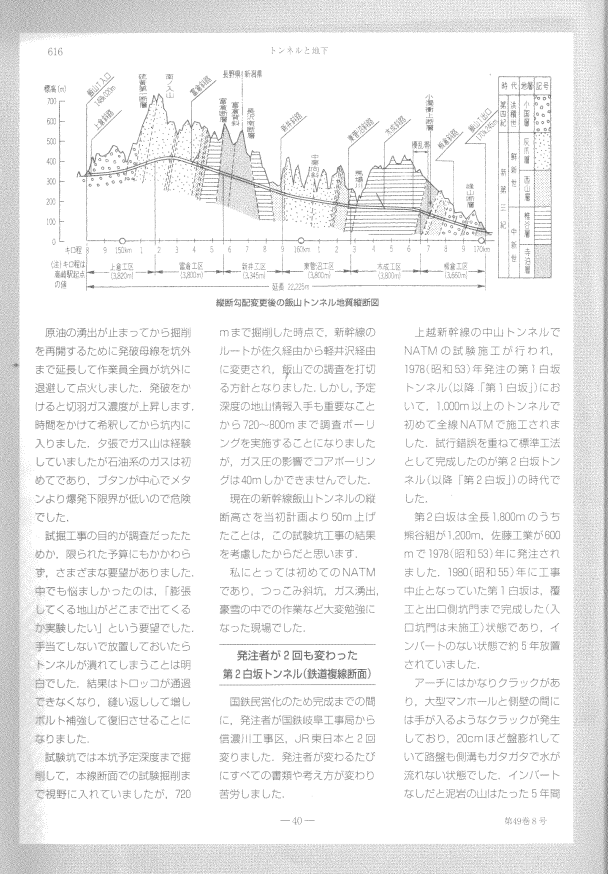人生喜寿にも達すると、かつて、共に土木工学を学んだ同窓の徒たちも、もうそのほとんどが現役を退いている。
その中のひとり、トンネル一筋にその専門を貫いたN氏から、トンネル技術者としての生涯を綴った、専門誌『トンネルと地下』掲載記事の別刷り(文末に添付)をいただいた。
その記事の多くの記載は、携わったそれぞれの工事における技術や施工体験の詳細に充てられていて、門外漢の者には、その内容は理解しずらい。
しかも、十数本のトンネル施工を手掛けながら、死亡者を出す重大事故を一件も起こさず、後には困難に遭遇した企業の要職も果たした40年にわたる体験を、わずか12ページの紙幅に凝縮するのは容易ではない。
だが、その淡々とし、かつ簡潔な文章からは、単なる秀でた技術者に終わらなかった、氏の人間的洞察観が読み取れる。
たとえば、氏の手足となって、切羽(きりは)と呼ばれるトンネル最奥の末端現場で奮闘する人たちを、氏はただ「坑夫」と呼ぶ。その呼び方は、それこそ、人権活動家などの耳にでも入れば、差別用語だのと騒ぎを起こされかねない用語でもある。しかし、その文章には、氏の「坑夫」たちへの深い尊敬と信頼が、その飾り気のない言葉使いにあふれている。
たとえば、この記事は次のような表現で結ばれている。
・・・私の脳裏をよぎるのは一緒になって一生懸命頑張った熟練の坑夫たちの顔です。地山の性状が急変しても技と工夫と頑張りで切り抜けた彼らから、何のための技・工夫なのか? なぜ頑張れたのか? を学び、しっかりと伝承してゆくことにこそトンネル技術の未来があると思う次第です。

1967年7月、青函トンネル工事見学会記念写真(北海道側吉岡坑口現場にて)
私は、トンネル施工自体に関わった経験はまったくない。ただ、学生時代、この8月に故人となった学友と見学会を企画して、当時、日本(あるいは世界)のトンネル界の歴史を飾る事業であった青函トンネル工事〔写真〕をはじめ、いくつかの事例の学びの体験はした。
その暗闇の地底にうがたれた一筋の穴をひたすら掘り進んでゆく作業は、世に技術職は多数あれと言えども、他に類例を見ない実に特異なものである。
そして、青空におおわれた明かりのもとでも、そうした特異性に匹敵する心髄ある試みは多々あると思う。要するに、最終的に帰されるのは、人間自身が創出する可能性である。