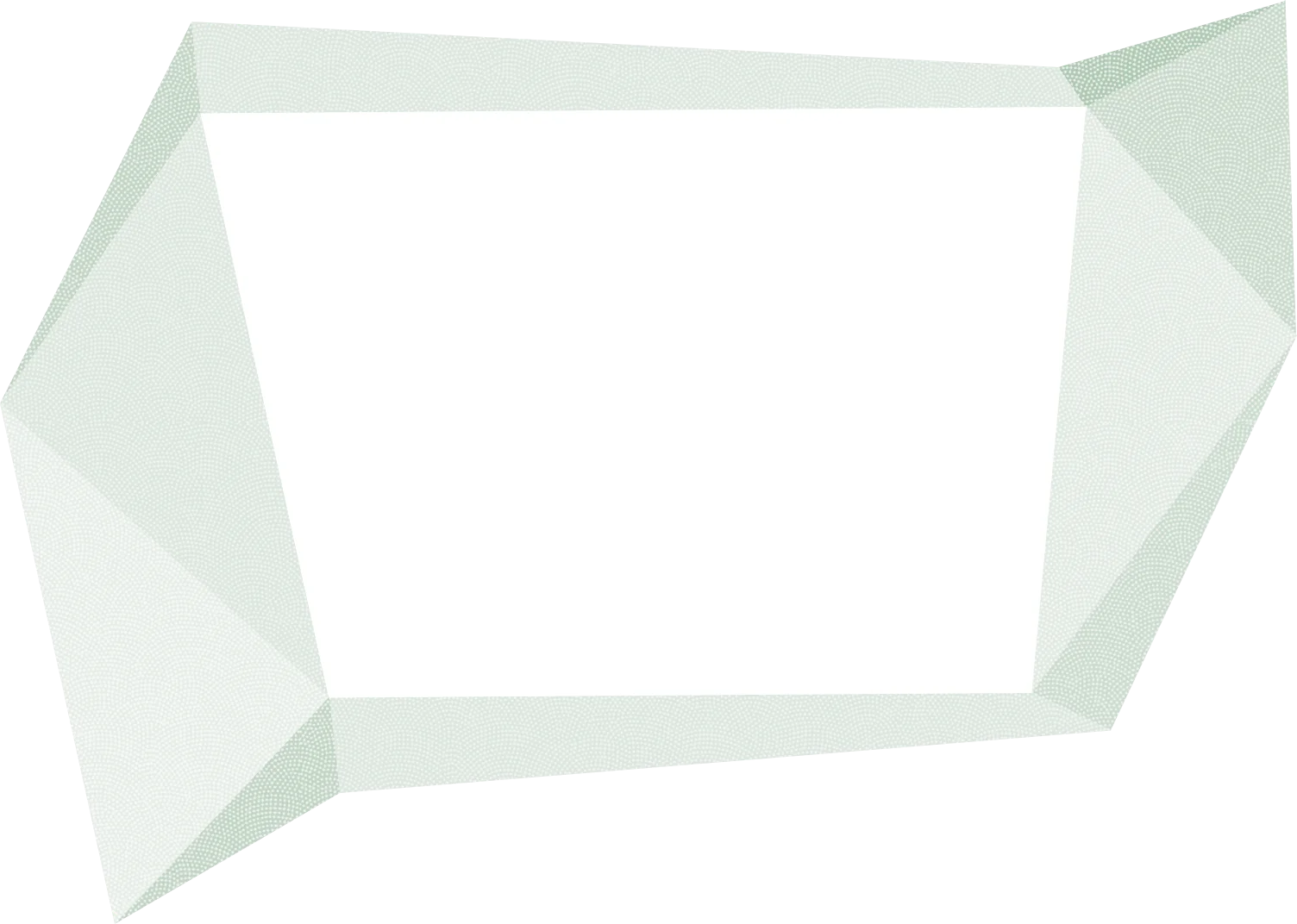恐竜の「ロングテール」
前号掲載の〈「超一流コンサルタント」に聞いた本サイト評」〉で、『両生歩き』と『フィラース』の二サイトについて、AI(そこではMSのCopilot)に聞いてみた回答を記事にした。そこで気付いたことがある。それは、そうしてAIがやってくれていることは、それを「宣伝」に使うのは外道なのかも知れないが、ともあれ、AIの回答は、けっこうの「よいしょ」もしてくれて体のいい権威付けとなり、ましてそれを記事にするのは、発行者にとっては、もうこれ以上の「宣伝」法はないのだ。
というのは、それは、ほかの誰でもないAIが述べていることであり、そんじゅそこらの「先生」のご託宣ではない。少なくとも、人間を超える能力を発揮してのその見解である。ゆえに、「宣伝」効果どころか、ある種のハクを得たような、妙な自負さえ持たせてくれる。
ただし、AIは時には嘘を言うようで、それはその世界で「ハルシネーション〔幻覚〕」と呼ばれ、いわばAIが自己矛盾に陥った時のことのようだ。つまり、そのあたりを勘違いしないように用心した上で、AIの効用とは、その要約なり網羅なりの力はそれこそ超人間的であり、それを使って自作の成果を評価させることは、言うなれば、この世のトップレベルの評定者のお墨付きを得るのも同然な効用とさえ言える。
つまりは、そうした超強力かつ汎用な道具が登場してきているということで、それがスマホを通じて誰もが手軽に利用できるとなれば、すごい常識が世界に広がるということにもなる。
何はともあれ、自分の成した産物さえあるならば、AIをそのように“私的”に、逆用できるということだ。
素人判断だが、ここに、AIに飲み込まれるのではなく、使いこなすひとつの手があるように思う。言うなれば、そうした自作の土台さえあるならば、それを足掛かりにして、その超偉い先生の虎の威をそのように手軽に借りることができるのだ。さらに誇大に言えば、自己創生のための秘めたる武器にさえ用いれると言える。その意味ではもはや、へたに大学など行く必要はないのだ。
そこで、こうしたAIの得意作業について、ついでながらに思うことがある。
今時、世に飛び交う情報の量はそれこそ半端ではなく、それにいちいち付き合っていれば、時間がいくらあっても追いつかない。そこで、ターゲットとした何らかの相手についての情報を、ひとまずAIに要約してもらってそのアウトラインをつかむことは、手順の上でも効率の上でも、実に妥当な方法だろう。博士クラスの論文でも、テーマに関する文献の網羅とそのアブストラクトはその導入部における必須プロセスである。
ここで上に述べた前号記事に戻ると、私の手掛ける二つのサイトのコンテンツにしても、もしそれを本にしていれば、おそらく2~3百冊にはなる分量がある。それを、そのように要領よくまとめてくれたのだから、幾らかでも関心を持った読者にしてみれば、そうしたAIの回答は、その取り合えずの相手に傾注するのも唾棄するのも、手っ取り早く役立つ案内にはなっているはずである。
加えて、私が取り組んできているような、やたらくどくどと辺縁な作業については、それが一般に「評論」されることなぞ、まずは起こらない。そこでそうした産物は、放置しておけば闇落ちしてゆくしかないのだが、そこでその恐ろしく狭き門を、AIのこの利便性を借りて何とかすり抜けようとの試みが、その記事であったとさえ言える。だからこそそれを、よい「宣伝」と見れているわけである。
何はともあれ、それをきっかけにして、より多くの人に実物のコンテンツに接してもらえれば、発行者としては、この上のない喜びなのである。
ところで、30年以上の昔、今日の巨大企業アマゾンがオンライン本屋としてそのネットビジネスを創業した時、無名の物書きたちがあたかも天の助けとそれを受け止めた。というのは、その当時「ロングテール」と呼んで上のイラストのような恐竜の「長いしっぽ」と自分たちを譬えて、その新興ビジネスのもたらす新規な効果に期待が寄せられたからである。
通常、本屋の店先に並ぶような本は、それこそ一握りの「売り物になる」著作に限られる。つまりその舞台側では、店先にも配本されずに切り捨てられている、おびただしい数の無名の書き手たち作品、つまり「長いしっぽ」=「ロングテール」がある。
アマゾンの始めたオンライン本屋は、実物の本を扱う店を必要としない情報だけの書店がゆえ、この「ロングテール」も扱うことができた。まさに「しっぽ」作家にとっては、「救世主」は大げさとしても、少なくとも彼らにとってのチャンスを開く、新たな流通ルートは開かれたのである。
デジタル情報自体は、数字や記号の無限な羅列であり、そこに貴賤も前評判の良し悪しもない。そしてその無味乾燥な数字や記号の羅列が、私たちに必要な姿となって現れるかどうかは、それらの数字や記号の特定の組み合わせが、検索によってマイクロエレクトリック的にヒットするかしないかだけである。実にフェアーな仕組みというべきであろう。
そこで、かつて「ロングテール」がそうであったように、今後の時代にあっては、AIによる検索と要約が合体した能力が、マイナーな論調や価値観や生き方を表したコンテンツにすら、世の関心の照明を当てることが可能となる時代になってきている。まさに、既成の「貴賤も評判も」抜きにして、無数の多様性がフラットかつイーブンに並列する時代が到来してきていると言えよう。しかもそれは、デジタル情報を媒介にしているがゆえに、距離も時間も無きに等しい世界においてである。
ここに、上記のようなAIの「逆用」である。それは、マイナーな作者による“ハク付け”期待も含めて、イーブンに働く新規な可能性の存在がゆえの活用法である。そこに、これからのAI時代における、その超人間的能力に並置している、人間を主とした、人間によるコンテンツの重要さが返り咲いてくる。
つまりそこでは、生の人間の創り出した情報がまず先にあり、それをAIが後追いして効率的に取り扱う。AIの創り出した情報を人間が追認するということではない。かつての紙の本屋の時代でも、まず本があっての本屋であり、古本屋さえあった。
ただそうは言っても、人間作かAI作か、その見分けがつかない問題がすでに生じ始めており、人間の側としても、まずは誰かの作品の借用のルール作りに始まり、人間ならではの質を創生する意気込みとその真贋が見分けられる目や環境は必要だろう。
ともあれ、時代は、従来の単語つまりキーワードベースの検索から、一定の意味内容をベースとしたAI検索の方向へと動いている。
言うなれば、権威を誇った旧制度もAIの駆使次第では容易に代行され、また、なまじっかの博識では出番もしだいに薄れる時代になってきている。
すなわち、人間にとって、情報の量ではなく質に核心が移る動向をはらんで、「第四次産業革命」が進行している。
さて、そこでなのだが、別掲の二記事(「サイト訪問統計分析レポート」、「10月『日平均訪問者数』)のように、この10月の私の二つのサイトへの訪問者数が各段に伸びている。こうした増加傾向には、どうやら、上記のAIの「宣伝」効果が、ひと役果たしているのは間違いない。