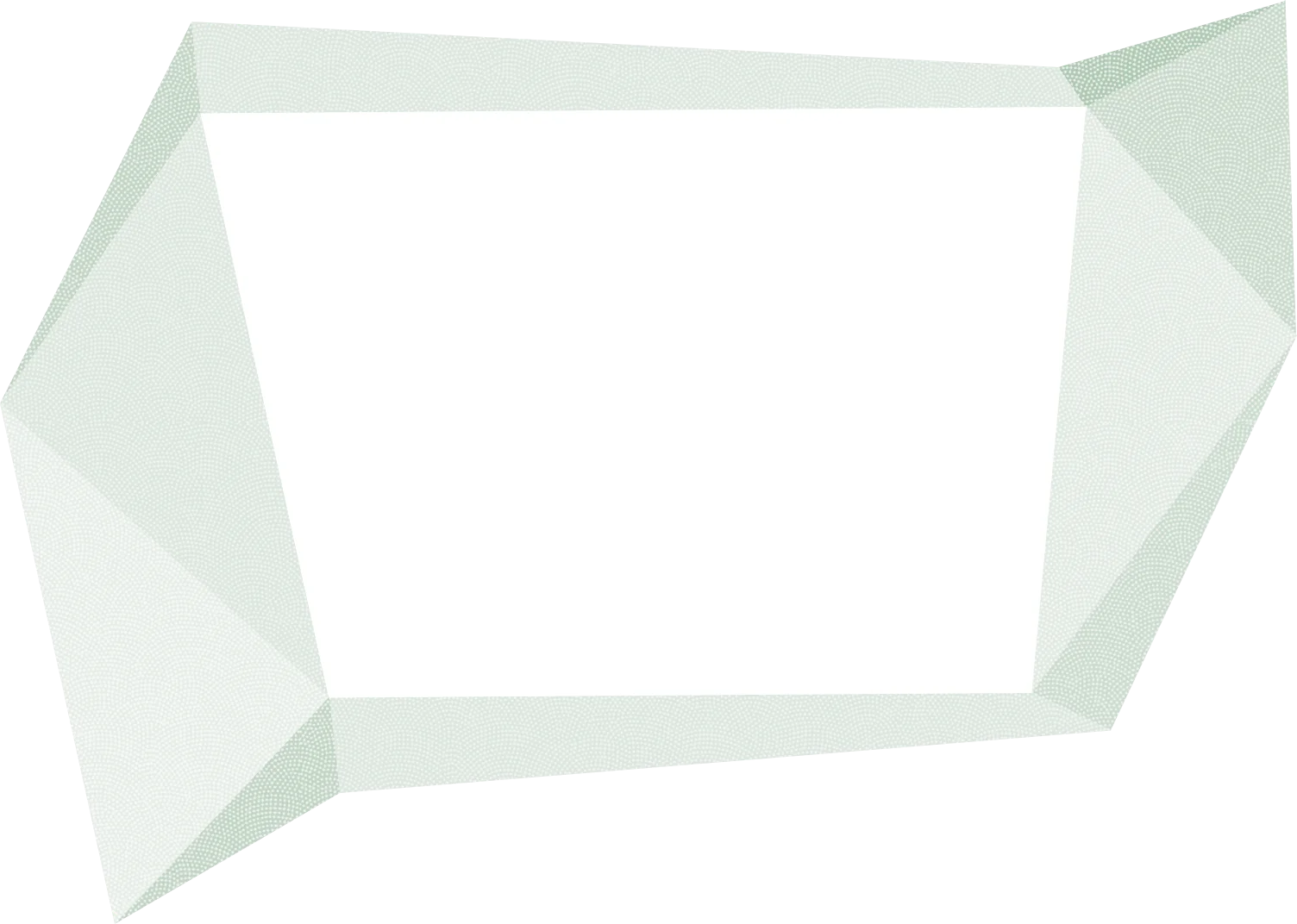今年5月半ばから5週間にわたった中央アジア諸国の旅は、日本をはじめとする島国では体験できない、陸路によっていくつもの国境を越え続けてゆく体験だった。

古都サマルカンドは、いまや“ウズベキスタンの京都”の趣きがある
むろん日本も国境を持つが、それは海上に引かれた制定上の線で、現実に、まして身近に目視できるものではない。
そこでたとえば、海外旅行の際などで実体験する国境は、あたかも、空港の複合ビルの一角にある、今では極めて自動化された扉付きゲートあたりがそれで、実際の国境と地理的には何の関係もない。加えてそれは、日頃通っている駅の改札ゲートと、形状的にはさほどの違いは見出せない似かよりであり、国境の存在にかかわる現実性は、ますます遠ざかるものとなる。
つまり、日本人にとって国境とは、現実の地理上の境界線というより、パスポート提示にはじまる越境手続きをもってしての、いかにもフォーマルなものとなっている。
そうした国境が、中央アジアのような大陸の国々にあっては、その線上には二重、三重のフェンスも延々と設けられていて、物理的にもはっきりと認知でき、まさに目前にありありと存在する、実体そのものの境界線である。
ただ地図で見ると、そうした地上の国境線も、その大部分は、大きな山脈とか大河とかがそれを成していて、日常生活上からは、遠く隔たった存在に違いない。
私は大陸国に暮らしたことがない——たとえオーストラリア居住が長いとしてもその大陸全体が一国である大きな「島国」——ので、そうした国境についての日常感覚がどんなものか、ちょっと実感がわきにくい。
それをこんどの旅行には、陸路越境を出来るだけ取り入れたことで、実際にかつじっくりと、それを体験することができた。
そうして今回、国境を合計7度にわたり陸路で通過したのだが、その中には、ひと晩に2度のこともあった。
そこで感じたことだが、まず、おおむねどの国境付近にも、とくに外来者には、緊迫した雰囲気が漂っていた。加えて、そもそもそんな場所は、たいてい、人びとの生活圏からは遠い、人里離れた辺地にあった。そして、国境を通り貫ける国際道路がある場合、その辺地にぽつんと国境管理の検問所がおかれていて、人間から、物品、車に至るまで、あらゆる通過物への一種ものものしい検査が行われているのが常だった。
つまり国境は、まさに陸地を区切る物理的境界そのものなのだ。日本の空港内ゲートのような形式的存在とは、名は同じでも、まったく別物である。
そうした地上の国境のなかには、ありきたりな貧相な川が国境を成している場合もあって、そのこっち側とあっち側とに、ことさらな違いが生じようもないようにさえ思われた。だが、実際にその境を越えてみると、人びとの顔立ちも変わっていたり、行き交う車が、トヨタ一色だったのがシボレーばかりに突如様変わりしたりして、なるほどと感心させられたりもした。
そこでちょっと歴史を調べたりしてみると、古くは藩王間の、そして近くは大国の介入による幾度もの争いがあって、現在のその線をもって、そうした永年の対立が、ともあれそう落ち着いているらしいことが判る。そしてそう安定に至っているからこそ、外国からの旅行者である私たちにも、その通過が許されている。
日本は島国で、上述のように、その国境線は海洋上にある。だが、過去にさかのぼると、たとえば江戸時代、その日本国土の中にも封建領土間の境があって、そこを通る街道上には、関所が設けられていた。
要するに、島国であろうと大陸国であろうと、そこに政治勢力上の領土が別々に存在している場合、互いに伝統や統治の違いがゆえに、自ずからその境界も生じることとなる。
今度旅した中央アジアの国々の場合、そうした歴史上の経緯が今にさえ投影され、あたかも生き物のようであるのがその国境で、それがゆえに、その国境周辺に漂う緊張の違いによっても、私たちのようなよそ者にさえ、そのうごめきが感じ取れる。
日本の江戸時代の場合、その島国内の争いの平定が優先され、外界とのやり取りを第二にするという鎖国政策が布かれていた。つまり、海洋が防壁となって、外敵の襲来を妨げてくれる地勢的有利さはあった。
これは今度の旅をきっかけに抱いた素人考えだが、その江戸時代、海外の各国では、ことに大陸国同士の場合、日本の戦国時代さながらに、相互の争いに明け暮れていた。そして、その後も続く大なり小なりの紛争や戦争によって、それぞれの国は、対立にまつわる処置への苦労や知恵を体得していた。
それが日本の場合、関ヶ原をもって戦国の世もひとまず落ち着き、国内のいざこざはあったろうが、それは対外的なものではない。そうした泰平のほぼ三世紀をへて江戸末期に至って、力を増した外国勢の圧力が周辺に迫り、遅ればせながら、世界を相手の外交的試練にさらされることとなった。
そうしたいわばこじ開けられた開国以来の日本の歩んだ道は、いまだに議論の分かれる、多難な経路をへることとなる。
これも私見だが、どうも明治維新以降の日本近代史は、そうしたローカルな、つまり純国史的観点で、独善的に修飾されがちなように思う。
さて時は移って今の時代、外国旅行をするに際しては、予約サイトや大使館サイトを通じて、たいがいの準備が居ながらにして出来てしまう。ましてパック旅行などを選べは、それはもう、コンサートのチケットを買うほどの簡便さである。それに、移動にしても航空便を利用すれば、その機から降り立ったらそこがもう、いきなり海外の目的地である。
こうして、航空機を利用し、オンラインで旅支度の整う時代にあっては、地上を移動して陸路で国境を越える体験は、それこそ、「シルクロード」や「奥の細道」の時代さながら、移り行く風土や国柄や人々の暮らしぶりの変化を目の当たりにできて、そこにつぶさで格別な旅情緒が味わえる。
それに、今回の中央アジアの国々のように、海上ではなく陸上に国境線が引かれれている諸国にあっては、現在の隣国同士間にもそれなりの緊張と和平が如実に尾を引いていて、それはことに島国の人々には、訪れてみて気付かされたことだが、その継続する緊迫度を想像することすら、なかなか容易なことではない。
今回、ことにアフガニスタンの国境で体験したような、その国境上での入国許可書類の発行の様子を目の当たりにして、その半日以上を要した緩慢な作業時間の流れをはじめ、その発行責務を果たす現地官吏の人柄をふくめた在り様などに接し、それはありありとした、そこに生きる人びとのあり様そのものであった。
まさに「一見は百聞に如かず」の諺通り、陸路による越境だからこそ味わえただろう、手探り、足探りな、体験があった。