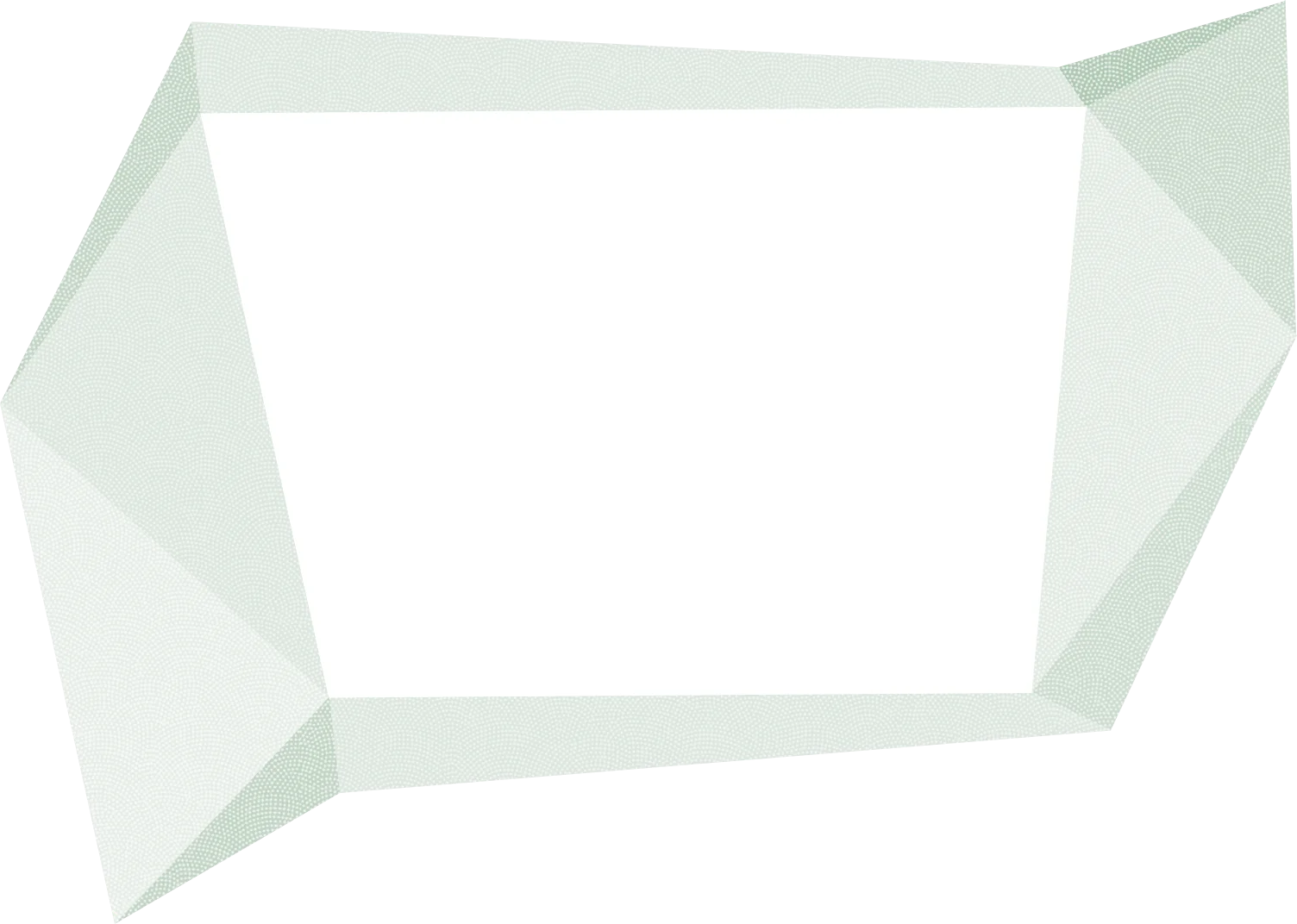居酒屋談35号そして本独想記32号に引き続いて、中央アジアの旅で体験した「不思議な遭遇」について考えている。
そしてその謎を解く鍵が、むしろ、旅をすること自体にあるのではないかと推測している。
そこで仮説を立てるのだが、旅をするのとは反対に、定住したり、国といった固定した枠内に安住したりすることが、人間にとっては、むしろ“不自然なこと”と断言するのは無理としても、大きく片寄ったものであるのではないだろうか。
そして、そうしたノーマッドな在り方が示唆することは、この定住とか国民とかとの、今日のほとんど全地球に行き渡った常態こそ、生命の本来の在り方に“背いている”とするのはこれまた行き過ぎとしても、大きく片側へと振れているものではないだろうか。
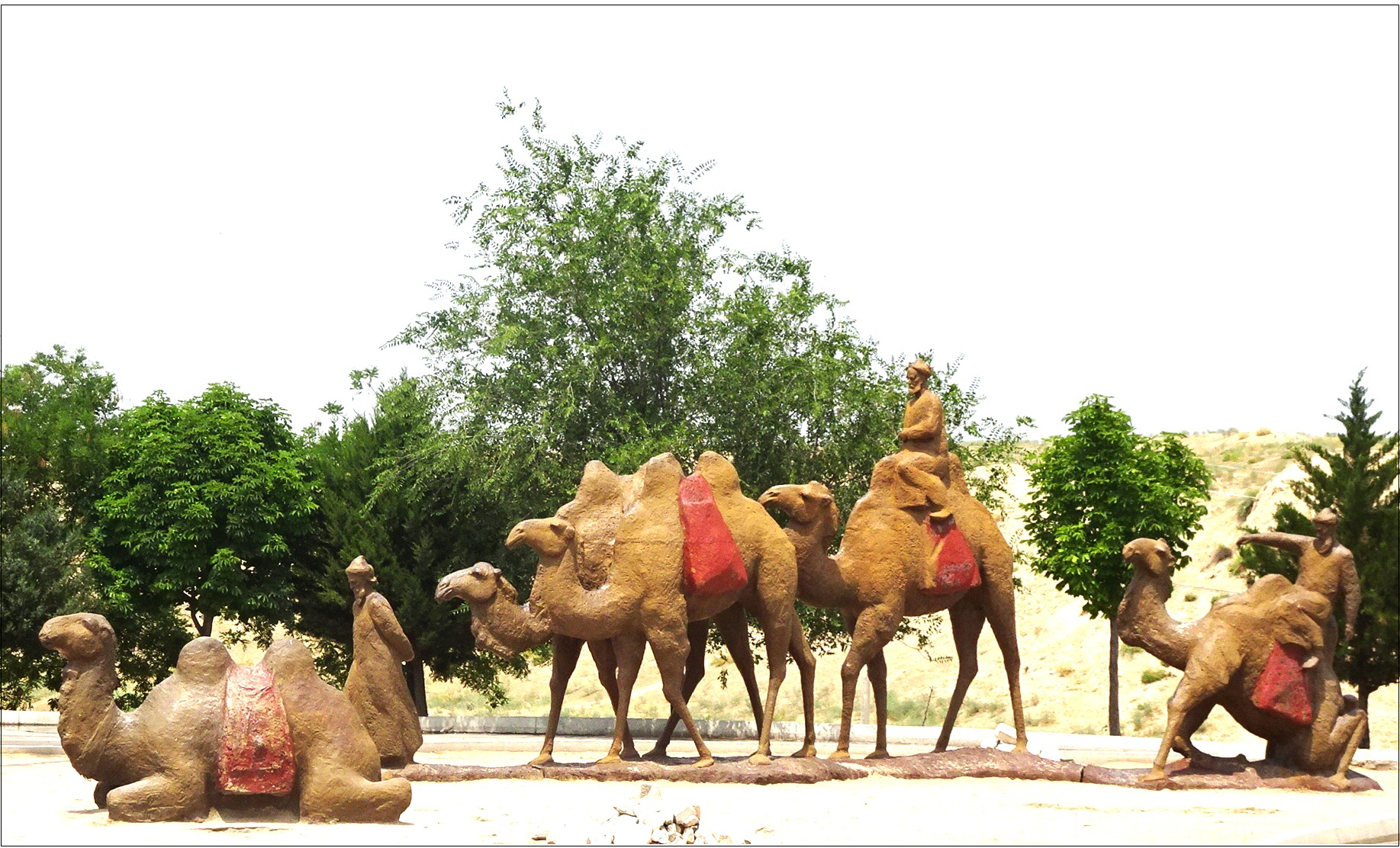
遠い過去には、旅を日常とする生業があった
そこで、こうしたノーマッドなし好を「旅心」と呼ぶとしよう。
そしてまずその「旅」なのだが、今日における、定住したり、定職に就いたり、特定の国の国民であったりするような現代の通常な暮らしにあって、そうした日常を破る〈一時的な逸脱行為〉を、私たちは「旅」と呼んでいる。
そういう「旅」は、日常性を破る非日常性と考えられるのが常で、そこに「旅」の意義や楽しみを見出している。
だが、それをひっくり返して、むしろ「旅」を日常性として考えてみたらどうだろうか。
そしてちょっと思いを巡らせてみれば、「人生は旅だ」という表現を、誰しも内心ではいかにも自然に受け止めているはずだ。
まして、そうした人生が死をもって終わらされることを、誰しも「旅立ち」と呼び、しかもそれを「永遠」のものと納得しているはずだ。
つまり、「旅」とは、言われるほどに、一時的なものでも非日常的なものでもなく、もっと本源的なところに根差した私たちの在り方なのではないだろうか。
『方丈記』ではないが、それこそ川面の「うたかた」のように、「無常」こそが常でさえあるのだ。
そもそも、今日のような定住した生き方が、誰しもの日常となってきたのは、人類の長い歴史が作り出してきた産物と言えるだろう。
すなわち、古代の人びとが農業を知り、集団をなして棲みつき、村ができ、やがてそれをまとめて国という勢力とし、さらにそこに余剰生産の蓄積を見出すこととなった。そして時代が移り、そうした富の蓄積が国を富ませ、近代産業をもたらし、さらにその生産性の向上のため、分業というそれぞれに固着した数限りない定職からなる組織的生産方式を編み出し、それが極めて緻密に組み上げられ高度化した形態が現代である。
そうした生産の能率化を支えたのが、人びとが定住し分業し定型化された生き方である。さらに、それがいよいよ現代へと至って、情報技術の究極的な発展の結果、もはや生産過程における人間のかかわりを限定化させる、機械自動生産すらが射程に入ってきている。
こうして人類は、生産に当てる時間を大きく削減し、そうして生まれた余剰の時間をどう有意義に用いるか、それが新たな課題となる時代を迎えつつある。
ちなみに、年金生活とは、近代のもたらした社会保障制度の産物であり、年金生活者には制度的にその余剰時間が保障されている。また今日では、若くして財をなした人たちは、そうした制度に頼るまでもなく、その余剰時間を満喫している。
ところで、本サイト『両生歩き』の副題「人生二周目、ポスト還暦」も、ほぼ二十年前、自分の還暦に際して、そうした流れを予感して付けたタイトルである。
このようにして人々は、その余剰な時間を所有するようになって、それをどう使うかが問われ、それに頭を使うようになってきている。
そこでしだいに着目されてきているアイデアが、これまでのような固定した生き方に新風をもたらす、ノーマッドな時間の過ごし方であり、そこにおのずから立ちのぼってくる「旅心」である。
つまり「旅心」とは、長い人類の歴史の発展の頂点に現れてきた心的傾向である。そして、これまでの生存のための固定的生き方に伴う義務や拘束から解放され、自由な時間の過ごし方を味わえるようになった現代人の、新たな心の持ちようを表している。いうなれば、新たな人生戦略である。
そしてその一方では、今日の科学技術の発達が、その最先端において、量子論という新世界を切り開いてきている。
それは、近代までの世界を先導してきた伝統科学の原理=要素還元論を見直し、その線的論理の限界を見せつけてきている。そしてその先に見出されてきている新たな科学たる知見が、「重なり合い」とか「量子テレポーテーション」という新概念を常識とする、これまでの伝統科学からすると“非常識”な、量子論の世界である。
そこにおいては、そうした「重なり合い」とか「量子テレポーテーション」をおこす現象が、《対》となった要素同士の“雲状”の関係において発生していることである。
そこで、時間や空間を超越して結び付き合うこの《対関係》が、いまや科学の最先端のテーマとなっており、現に、コンピュータの性能を飛躍的に高める、量子コンピュータの登場に、この性質が使われている。
ただそこでなのだが、現在の学的常識の範囲では、その《対関係》は、物質のミクロな世界での素粒子レベルの振る舞いとされている。生身な人間というマクロな世界は別というわけだ。
だがしかし、そうした振る舞いは、人間というマクロな世界でも起って当然なのではないか。なぜなら、そういう人間にしろ、そうした素粒子の集合体なのだから。
こうした議論はまだ解明途上の分野であるのだが、いまや、情報生命学とか、遺伝子生物学といった新分野の開拓により、突破口が開けられてきている。そしてそうした生命情報レベルでは、量子理論の適用も可能であり、人間の身体活動における微細な化学的働きの背後において、モノとコトとが区別できない、《生命情報の働き》が注目されてきている。
つまり、人間大レベルにおいても、人の感性や直観という領域を取り上げてみれば、この《生命情報の働き》が機能しているとは考えられる。すなわち、これは日常的には、人のもつ《感性》に属する問題として、その《感性》に敏感な人と人との間には、上記の「重なり合い」とか「量子テレポーテーション」に相当する、共感や交信も働いていると考えられる。ちなみに、恋人同士の愛の交換は、まさか、ドラマのための単なるフィクションなのではあるまい。
さて、そこで「旅心」に立ち返るのだが、「旅心」とは、人びとが自由な時間を味わい始めた時代における、こうした《感性》のもたらす要請にしたがって、まずは物理的な移動にはじまり、ひいてはメタな移動へと高揚してゆく、そうした心の働きとそれのもたらす移動行為である。
ゆえに、旅という地理的な選択をした結果のその特定な場所に、特定の人たちがつどって来ているということは、そうした人たちが、一種同類のこの《感性》を発揮してその旅をし、そこに何らかの類似した期待を託して集まって来ているということであろう。そこに、一見、偶然にも見えながら、あらかじめそう選ばれた、そこにしかありえない、共有する価値観が、少なくとも潜在するはずである。たとえ、まだ意識までされてはいなかったとしても。
すなわち、「旅心」の心髄とは、移動がもたらす、そのあたかも偶然的な結びつきという人的収れんを通じて、もっとも稀有な人的かつ価値的機会を獲得する、そのノウハウを意味している。言い換えれば、そういう飛躍をなしとげる秘訣とも言っていい。
かくして「旅心」とは、人間の歴史が築いてきた生存の定住性・固定性が生みだした繁忙がもたらす、機会や価値観の収縮を立て直そうとする働きである。そしてそれは、本来の、あるいは、忘れ去られていた生命の仕組み――すなわち無限な可能性を秘める生命情報の世界――への、《感性》を通じたよみがえり方と見ることが出来よう。
そうした、直観される可能性の気配をたどって、ある日、ある所につどったがゆえに、そうした人たちの間には、他では得られない共有や一致が成立する。そしてそれは、旧来的な常識には、良くても「不思議」としか見えず、悪くすればその稀有な意味すらも看過されがちな、そうしたフラジャイルながら奥深く息づいている《超絶品》なのである。
そして付け加えておけば、古い伝統に疎外されてきた人々、たとえば女性が、それだからこそ、そうしたよみがえってきている生命情報に、より敏感に反応しているのであろう。そこに、「男の沽券」なぞまるで風前の灯火とたとえてみても、相当なリスペクトと言ってよいだろう。
最後に、ここに述べたことは、ことにその《生命情報の働き》の議論を扱ってきている兄弟サイト『フィラース』において、その角度からの議論が同時進行している。本稿と合わせて、お読みいただきたい。