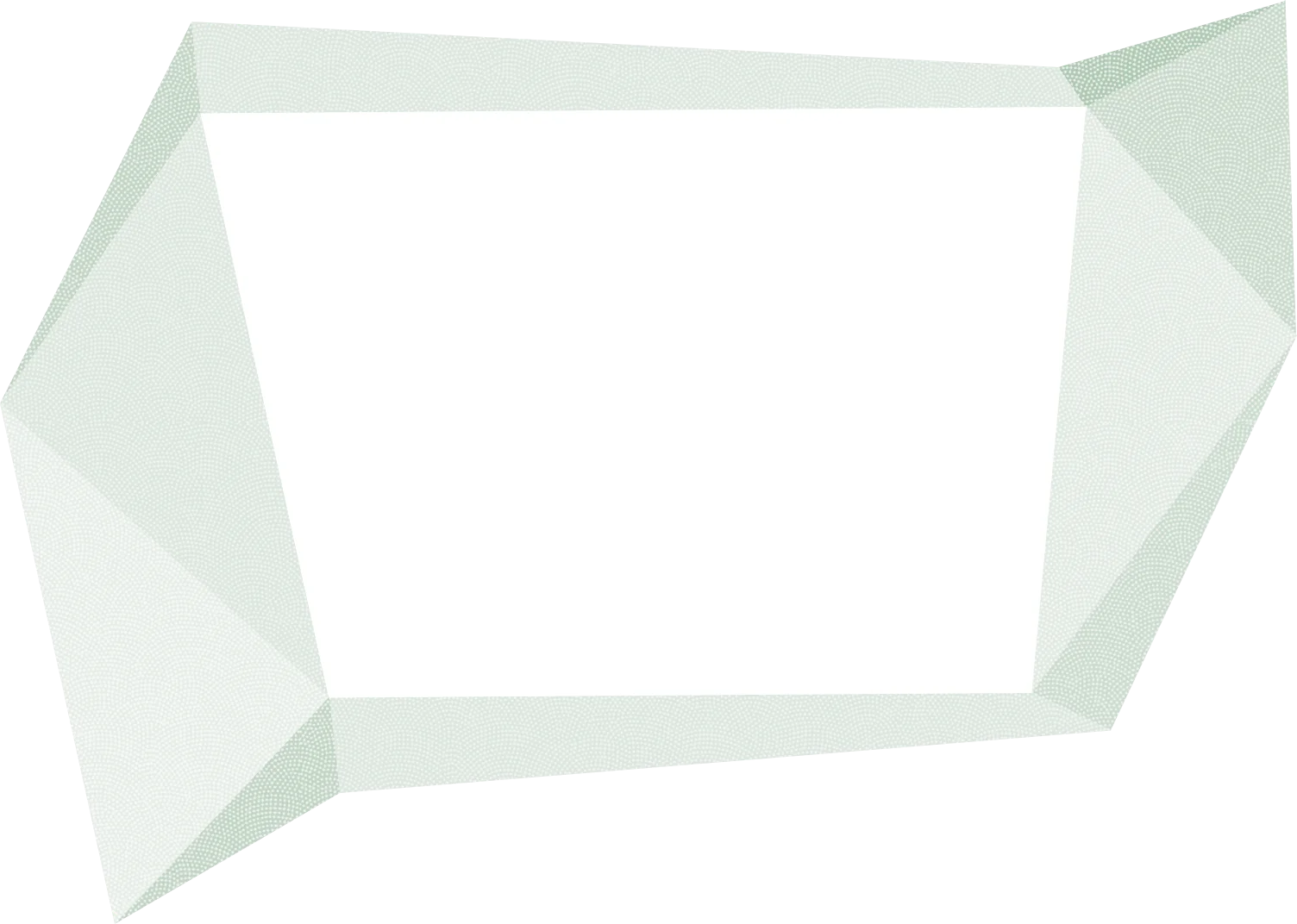どうやら「人生二周目」の20年間は、一周目の延長として、その「変形」としてしか考えられていなかった。それが、80歳を境とした「三周目」を目前にして、もはや根本的に「異質な」ステージとして捉えるべきでありそうだ。と言うのは、「二周目」のリタイア後の人生を支えた基盤は年金制度にあったのだが、それはズバリ言って、〈片手落ち〉な制度であるからだ。つまり「三周目」に入ってそれを〈両手揃えた〉ものとするには、年“金”ではなく、もはや金銭に頼らぬ、年“〈心〉”とでも呼ぶ次元にすべきなのだ。
人間、大別すれば、身体と精神という二つの根本的な構成要素からなる存在である。もちろんこの二要素は、複雑かつ精緻に入り組んでいて、その一要素のみを取り出すことは不可能だ。
そこで、一人の人間の長い生涯を、いくつかのステージに分けてみる。
まず、幼年期は他の動物にはない人類特有の被保護期で、その間、身・神の二面はまったく未発達で親による全面的保護、育成が不可欠である。それが未成年期では、その二面は共に大きく成長し、ことにその末に身体面はほぼ成人に近づく。そして成人期に入れば、その二面は完全に成長を遂げ、社会的には現役時代として、その完成した身・神の二能力をもって生産活動に献身し、その余剰生産部分は、社会制度を通じて高齢期を支える原資として金銭的に蓄積される。これが年金制度で、先進諸国の社会保障制度の一根幹をなす。
俯瞰されるこうした各人生ステージを遂げて、人は60歳に達して還暦を迎え、ともあれ「二周目」に入る。
ここで、現役期に蓄えられた原資が使われ始めるのだが、それは制度的方法として唯一お金を通してやり繰りされてきたもので、まさに資本主義的、つまり、文字通り「年金」システムであって、その金銭的大小が、退職後の人生を左右する決定的要素とされる。ちなみに、老後の人生の組み立ての相談に当たるのは、通常、いわゆるファイナンシャルプランナーと呼ばれるお金使用のプロが主役となる。そしてその金銭的土台形成の上に、医学だの余暇だの運動だの様々な分野の専門家がその使い道にアドバイスを与える。
さてそこでなのだが、上にそうした年金を中心とした老後の生活を〈片手落ち〉と断じた。
というのは、上記の各人生ステージの初期、未熟な幼年期を親の保護が不可欠であると述べたが、そこでは、親が得てくる金銭を通じての物的保護に留まらず、愛情とよばれる潤沢な非物的、言い換えれば心的投入がふんだんに行なわれていたはずである。
そこで、現役期をその間において、その前後に、幼年期と老年期があるわけなのだが、いずれも何らかの保護や介護を必要とする、身体的に未熟あるいは衰弱した時期として共通なものがある。
それが、老年期には、親子関係に代わって、社会制度による金銭的な支えとしての年金がある。
さて、ここまで述べてくると明らかだが、その年金には、幼年期にあったような心的投入は何ら考慮されていないことが判る。
あるいは、その金銭主体の制度がゆえに、老年期、ことに健康寿命期にある、高齢者の社会的働きの役割が想定されていないことも、合わせて明瞭となる。それこそ、「悠々自適」と称して、まるで無為に遊んで過ごせばよいだけの存在であるかのようにだ。
もちろん、現実問題として、現役期を中心軸に前後する二種の人生ステージの対称性を、そのように同質に並べてみること自体が不適切とする見方もあるだろう。
しかし、そうした老年期にいたってゆく、人生「二周目」、まして「三周目」を念頭におく置く時、自分のその人生ステージが、いかにもファイナンシャルプランナーの持ち場のみで扱われ、それで充分なのであろうか。だからこそ、大いに〈片手落ち〉と見れるのである。
ここで私の場合の体験を述べさせてもらうと、その「人生二周目」の開始を、食うための労働から解放された、待望の「自由人生」とし、それを文字通り宝物のように享受させてもらってきている。言うなれば、還暦までの長く苦しい実習期を積んだ後の、いよいよの本番実践期である。それをまるで余命のように扱うのは、社会的にも大いに無駄なことをしているかのごときだ。
そこで、現役期に燃え尽きずに、なんとか健康の片りんを保持してリタイアに漕ぎつけ、お金の役割はほどほどと受け止め、むしろその「宝物」をフルに体験するために不可欠の健康の維持を第一とした生活を送ってきている。
そこで次第に見出されてきている視界が、上記の〈片手落ち〉に終わらない老後の送り方であり、それこそ、現役期を対称軸に、幼年期に潤沢に受け取っていたはずの、心的な世界の貴重さであり、その活用である。
ゆえに、「人生三周目」への見取図には、この心的要素を、欠いてはならない必須要素として含めておきたいものとなってきている。
最後に、付け加えておきたい私見がある。それに別記事「のた打つ『三周目』」では、今の自分の日常で起こったその生な実情を述べている。それは、老年期に避けられない、いわゆる認知症状についてである。現行の医学的見地はさておき、それが認知症と呼ばれる病状として現れてくる人的因果関係には、ここでいう「心的要素」の欠如が大きく作用しているのではないかと思われることだ。そしてそれは、認知症患者自身の側の要因だけでなく、その周囲がそう見たり扱ってしまっている実態にも、その原因があるのではないかと思われることだ。ちなみに、私たちは、幼年期にある小児を、今日、老年期にある衰弱した老人を認知症とするような視点をもって見ていただろうか。ただただその小児たちは、まぶしいほどに、幼く愛らしい存在そのもののであったのではないだろうか。老人が認知症へと退行してゆく現象には、扱い上、あるは扱われ上の、ポジ・ネガの対比が影を落としているように思う。