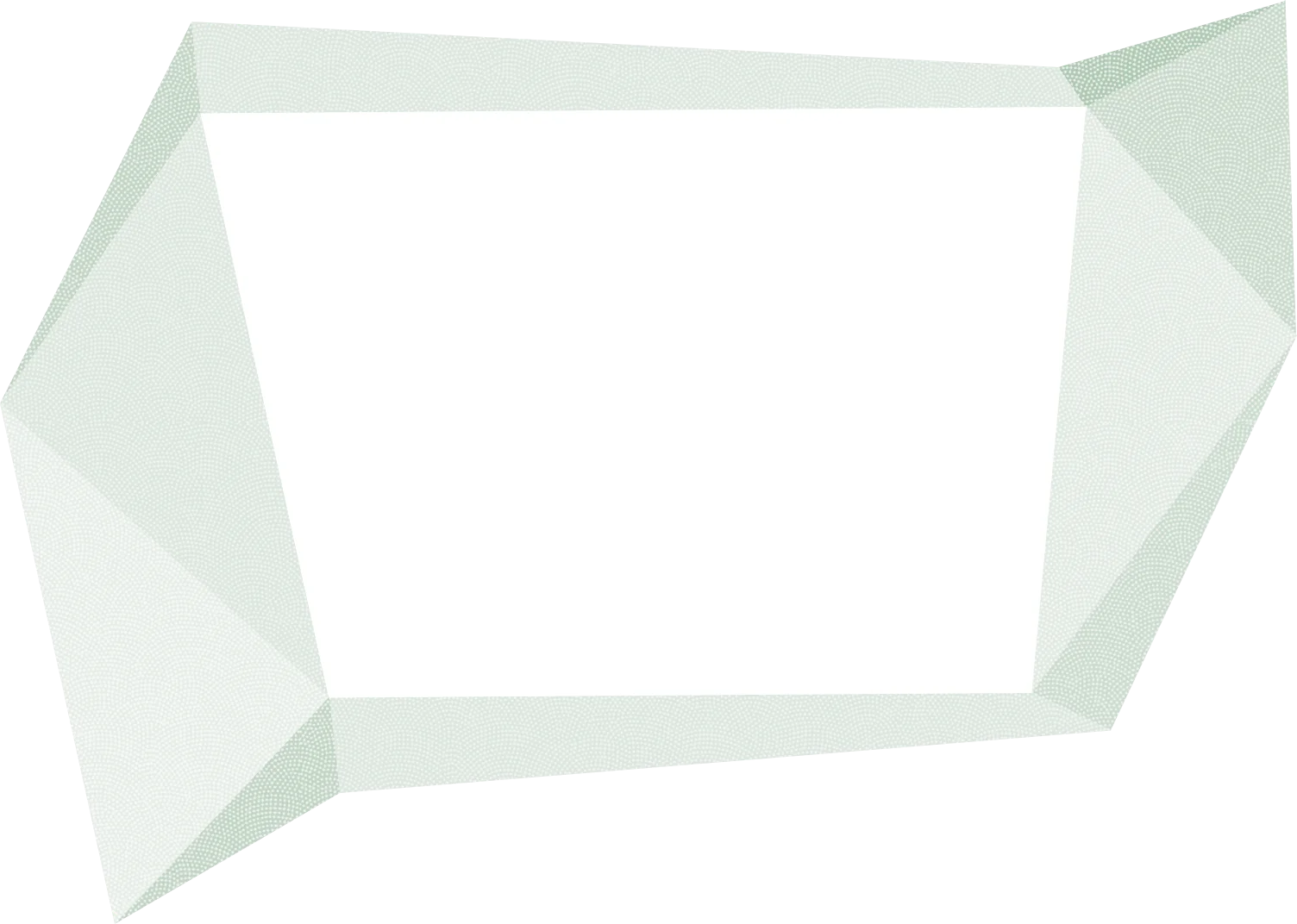今回の〈半分外人-日本人〉は、いまや沸きにわいている「訪日観光ブーム」への、ご多分に漏れず、苦言です。
まずはじめに、そうしたブームに火を付けた、「観光立国推進基本法」と命名されたその法律からみておきます。以下は、2007年1月1日施行のその法律の前文です。
観光は、国際平和と国民生活の安定を象徴するものであって、その持続的な発展は、恒久の平和と国際社会の相互理解の増進を念願し、健康で文化的な生活を享受しようとする我らの理想とするところである。また、観光は、地域経済の活性化、雇用の機会の増大等国民経済のあらゆる領域にわたりその発展に寄与するとともに、健康の増進、潤いのある豊かな生活環境の創造等を通じて国民生活の安定向上に貢献するものであることに加え、国際相互理解を増進するものである。
我らは、このような使命を有する観光が、今後、我が国において世界に例を見ない水準の少子高齢社会の到来と本格的な国際交流の進展が見込まれる中で、地域における創意工夫を生かした主体的な取組を尊重しつつ、地域の住民が誇りと愛着を持つことのできる活力に満ちた地域社会の実現を促進し、我が国固有の文化、歴史等に関する理解を深めるものとしてその意義を一層高めるとともに、豊かな国民生活の実現と国際社会における名誉ある地位の確立に極めて重要な役割を担っていくものと確信する。
(以下略)
実にまともな政策で、なかなか立派な前文です。
私は、ここにうたわれている国際平和まで視野入れた「観光立国」との使命には、完璧に賛同します。まさに、こういう「国際観光」こそ本当のものと、心底、願っています。そしてそれは、観光どころか、外交政策の柱とさえ言っていいものです。
ところがです。こうした気高い使命と現実の「観光立国」の姿とは、あまりにかけ離れています。
そこで私のこの苦言を露骨な言葉で表現すれば、その現状は、「国自体を売春しているに等しい」となります。
施行からもう18年。そんな現状は初期的な不具合と言い訳しようにも、十分すぎる時間がはや過ぎています。
こうした現実は、言われる「オーバーツーリズム」どころか、チープな事物を買いあさる、そんな訪日者への“へつらい”に堕していることを意味しています。
だからこそ、かつての貧民が自分たちの娘を涙ながらに売春業へと売り渡していた、そんな過去の醜い時代が連想され、上記のような表現となってしまいます。
しかも円安が、その傾きに拍車をかけています。
仮に、円安がなんとしても避けられない、かつ、積極的意味も含んだ施策だとするなら、ただ訪日客の量的面を目標としないで、それを質と絡み合わせる施策もあるはずです。
たとえば、名称はともあれ、可変的な「観光税」なり「滞在税」などを、しかも地方に任すのではなく国が先に立って国境上で徴収して、有効にそのレート安をバランスする手は打てるでしょう。
私自身、長く外国に暮らす人間として、歴史も文化も自然も異なる地に魅力を見出し、それなりのコストを費やしてでも、それを実体験し、血肉にしてきた者のひとりです。ゆえにこの苦言は、けっして、外国人差別に根差すものではありません。
上の前文がうたうように、世界中の人たちが、互いに訪れあい、知り合い、相互を理解することで、無知な摩擦や、ひいては戦争さえ起こしてしまう愚行を避けるためにも、個人レベルの相互訪問の実現ほど効果的な国策はないと信じています。
ところで、私は4月に一時帰国する予定でいるのですが、正直なところ、好きな山歩きも、有名地は避けて、辺鄙なところで楽しむしかないと思っています。加えて宿賃は、数年前と同じ条件で比べれば、もう倍ほどにもはね上がっています。それに我が人生、ようやくにして、たっぷりな時間が得られるようになり、それならではの悠長な滞在を楽しめるはずだったのですが、このウナギ登りの宿費下では、その念願してきた貴重な機会も、短く切り詰めざるをえません。
ふと思い立ち、懐かしい人や地をそぞろたずね、かつての思いを今一度反すうし、見直したい。そんな自然でつつましい願いが、単にコスパに釣られて押しかけてくる外来勢に押し切られてしまっては、肝心な国民の立つ瀬もなく、穏便な気持ちでいれられるはずもありません。
私は海外生活も長いのですが、いまだ、少なくとも半分は、日本人のままです。
そうした誰もが共有する自国らしさを、かくも売り飛ばさなければならない国へと、いつ成り下がってしまったのか。まさか、2007年ではないでしょう。