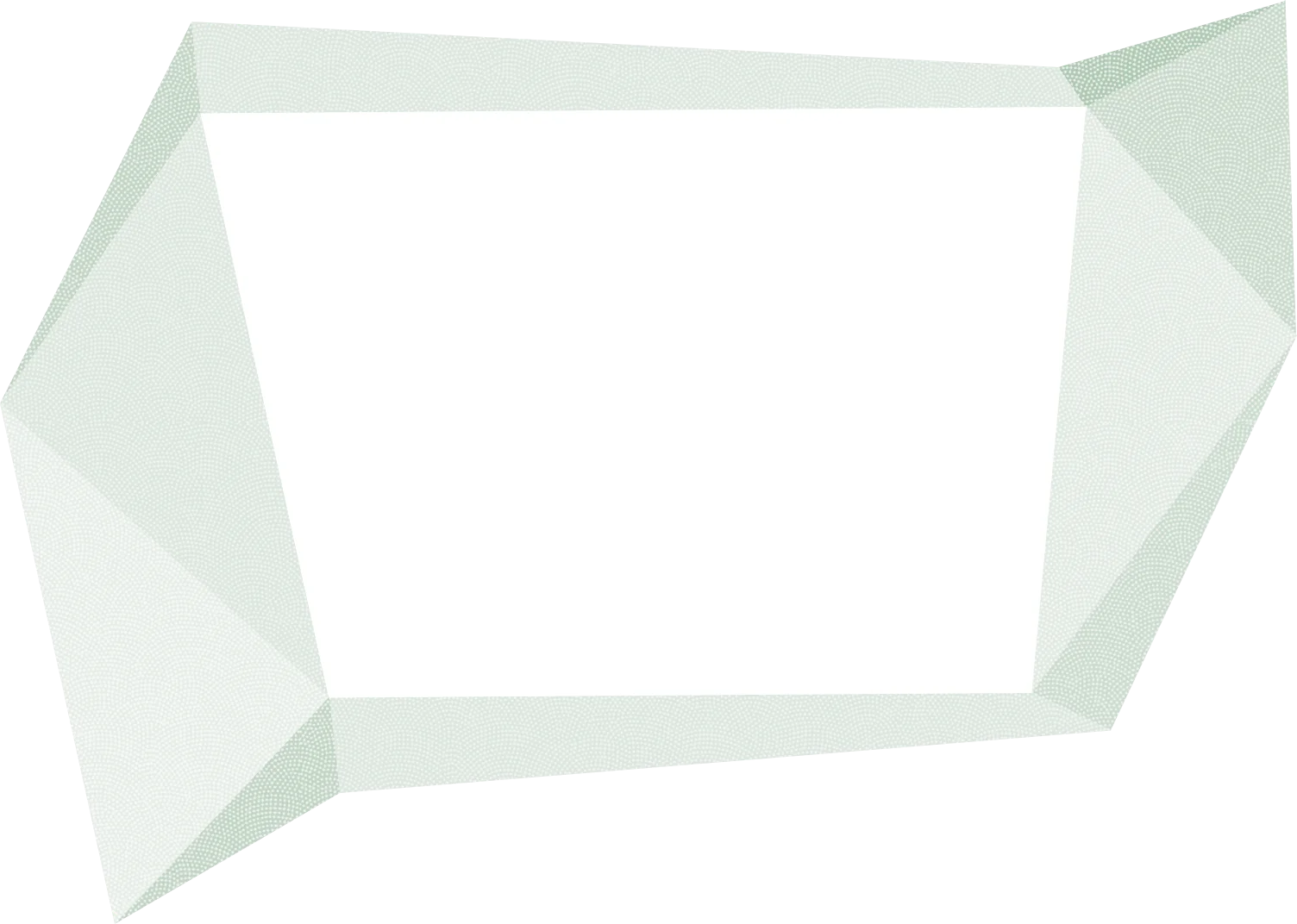先の記事「人生3周目は傘寿から」に書いたのだが、この79歳の一年間は、傘寿をもって始まる三周目の人生の準備期間となりそうで、その意味で、「三周目前夜」と呼べる。その少々長い「前夜」にあって、にわかに見え始めている視野がある。それは、社会的には、いよいよ登場した第四の産業革命と呼ばれるAIすなわち人工知能であり、他方、個人的には「健活」の中身と行方である。それを今号では、いつもの居酒屋談義を借りた「これには驚かされた」でそのAIの可能性に触れ、本稿では、自分の身心資源の問題として、この「健活」を考えてみたい。
まず、「健活」における「前夜」だが、後述もするが、どうもその「健活」の方向を探るに当たっては、人工知能の開発に沿うように見えてくる、“生のロボット”たる自分が、自分の生の知能をもちいて、自分の究極をシミュレーションしていることと言えそうなことだ。
そこでだが、いま、『脳・心・人口知能(増補版)』という本を電子版で読んでいる。甘利俊一という今日のAI技術の核心部をなす「深層学習」という数理的方法を世界に先がげて考案した先駆者の著になるものだ。2017年にその旧版が出版されたが、その後のAI技術の発展は急速で、本年4月に新たに3章を加えて、増補再出版されたものだ。
私がこの本にことに興味を抱くところは、その書名が示ように、いまや注目の分野の諸要点を網羅した内容をもって、その先進性の専門的解説——ことに「深層学習」とは 何なのか——と、それでいながら広い人間的視点——数理的手法に立ちながら——も合わせ持つという面である。またこれは私的な驚きなのだが、著者は89歳という私よりちょうど10歳年上なのだが、その年齢なのに、その文章は明晰で、曇りがない。むしろ曇りが無さ過ぎていて、いわば、ちょっと人間沙汰ではない著書であることだ。
まあ、何も私が心配するようなことではないのだが、こうした驚異的な進歩を遂げる人工知能が、それが進歩を遂げれば遂げるほどに高まる——聞けば、2045年ころまでに、人間の能力を越えるという——その能力である。
というのは、過去、コンピューターが登場し、やはり同じように驚異的な進歩をみせていたころ、私が目撃したのは、そうした技術的進歩が人間に及ぼす影響、ことに、あたかも人間がその新技術と競争しなければならないような社会環境、ことに労働環境であった。そこかつて人間が経験したことのない環境において、どれほど多くの人たちが病み、ひいては命すら奪われていったかということだ。
単なる老人の杞憂といえばその通りだが、一度あったことは二度、三度とある。こうした人工知能の発展が、やはり、かつて人類が経験したことのないものであるのは確かである。
そうした心配という点で、その焦点となるだろうところが、ならば、人工知能と人間の知能とは、同じ性質のものなのかというところだ。
つまり、今のAI技術なり、今後登場するだろうASI(超人工知能)と言われるものは、速度や容量といったレベルでは人間をはるかに凌駕するものであるとはしても、ならば、それが処理している能力は、果たして、人間が行っていることと同様のものなのか。
そこで著者は以下のように述べている。
心とは我々の駆動力である。心に付随して、喜怒哀楽、すなわち嬉しさ、怒り、悲しさ、そして楽しさがある。さらに、好奇心、意欲、責任感、嫉妬心、優越感など、心のカバーする領域は広い。
永い進化の過程を経て、心は形成された。人間は社会生活を送っている。このときに、仲間と理解し合う必要があり、心がこの役割を果たす。心を通じて仲間と共感し、仲間との一体感を得る。このような利点があるから、進化の過程で心が生まれたのであろう。
では意識とはなんだろう。意識も心の働きの一部である。第7章で、意識とは「自分がいま何をしようとしているのかを自分で知っていることである」と述べた。自分の心の動きを理解するのが意識である。喜怒哀楽や他の人との共感を意識できることも大切である。このような心の機能は他の動物にもある程度はあるだろう。動物にも情動がある。しかし、これを意識のレベルに上らせて自覚するのは人間だけだろう。人間は進化の過程で心の機能を高度に発展させた。今日の文明の源にはこれがある。(位置No. 2,809-2,820)
そんな時代がやってきているのであり、それに巻き込まれてゆく、この「前夜」を経ての人生「3周目」である。