
シドニーより羽田経由で直行した朝の松山上空 .
愛媛県宇和島のミカン農園で、希望した「山」と呼ばれる収穫作業ではないのだが、「工場」と呼ばれるミカン加工場での労働をしている。片やの人手不足と他方の旅趣向を結び付ける案内サイト「旅ワーク」によるもので、一月の雪山行きへの体慣らしのつもりで応募した。
学生時代のアルバイト以来の単純肉体作業で、文字通りひさびさな、また場違いなような異体験であるのだが、そんな追憶では終わらない、遠い道のりをぐるっと一巡りして帰ってきたかのような感慨がある。
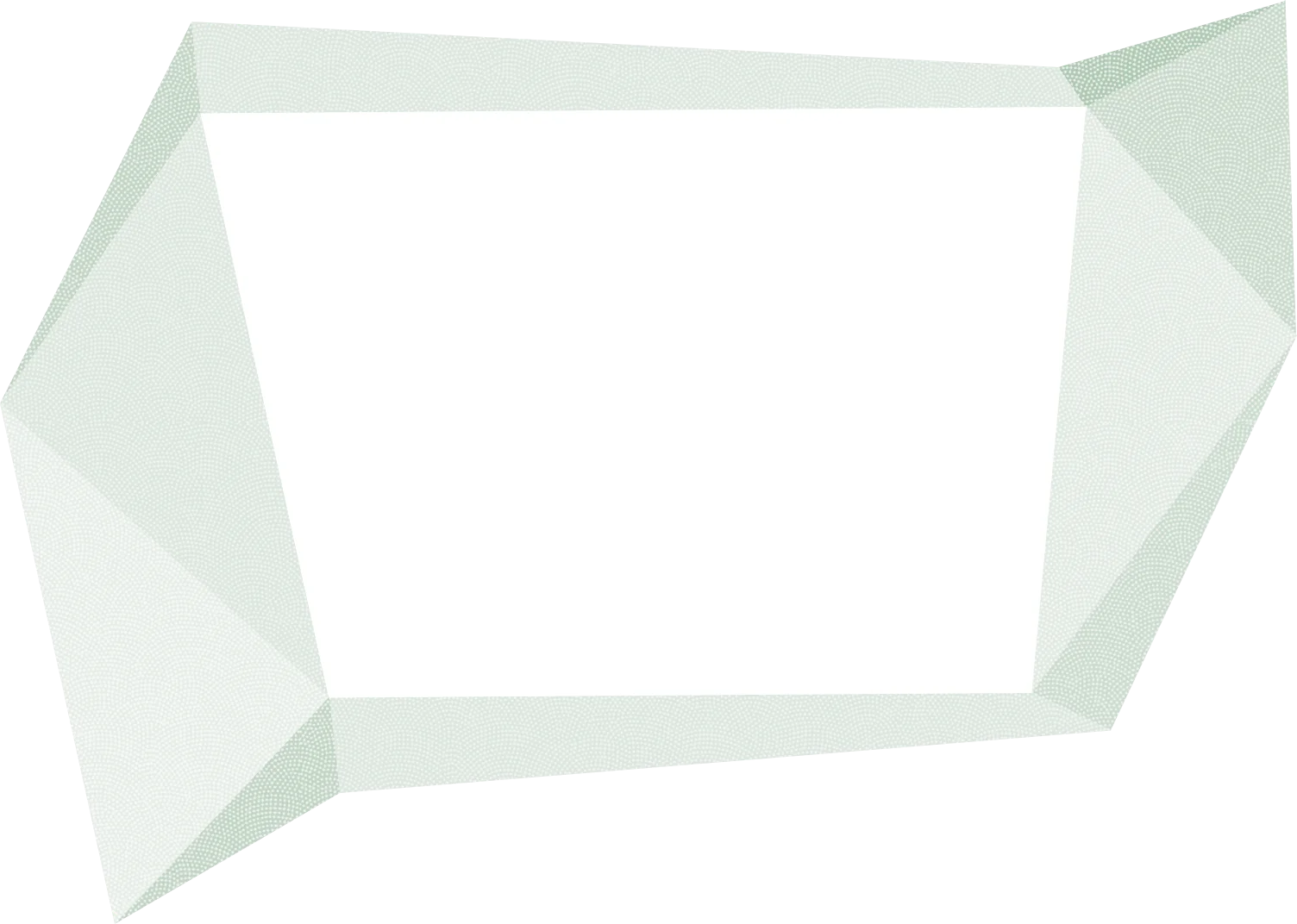
想えば遠くまで来たもんだ

シドニーより羽田経由で直行した朝の松山上空 .
愛媛県宇和島のミカン農園で、希望した「山」と呼ばれる収穫作業ではないのだが、「工場」と呼ばれるミカン加工場での労働をしている。片やの人手不足と他方の旅趣向を結び付ける案内サイト「旅ワーク」によるもので、一月の雪山行きへの体慣らしのつもりで応募した。
学生時代のアルバイト以来の単純肉体作業で、文字通りひさびさな、また場違いなような異体験であるのだが、そんな追憶では終わらない、遠い道のりをぐるっと一巡りして帰ってきたかのような感慨がある。
二重国籍を認めない日本

二重国籍を認めない日本を報じる最近の記事
新聞報道で、二重国籍を否定する日本政府を訴えた裁判が、相次いて敗訴していることを知った。それはたとえば、仕事の必要上、外国での永住ビザ滞在から国籍をその国に変更した人が、その時点で日本国籍を強制的に失うとしている国籍法を違憲とした訴えである。
私の知人にも、外国籍を取りながら、事実上の二重国籍としている人がいる。それに、世界の主要7か国(G7)で、二重国籍を認めていないのは日本だけである。
非ノーマッド志向
土木技術者の生き方 : 海浜公園の建設のケース
当サイトでは、2023年11月7日号に〈「坑夫」の「工夫」〉とのタイトルの記事を掲載した。引退したトンネル技術者が、その専門世界に注いだの自生涯を集約した専門誌への投稿記事を紹介したものである。
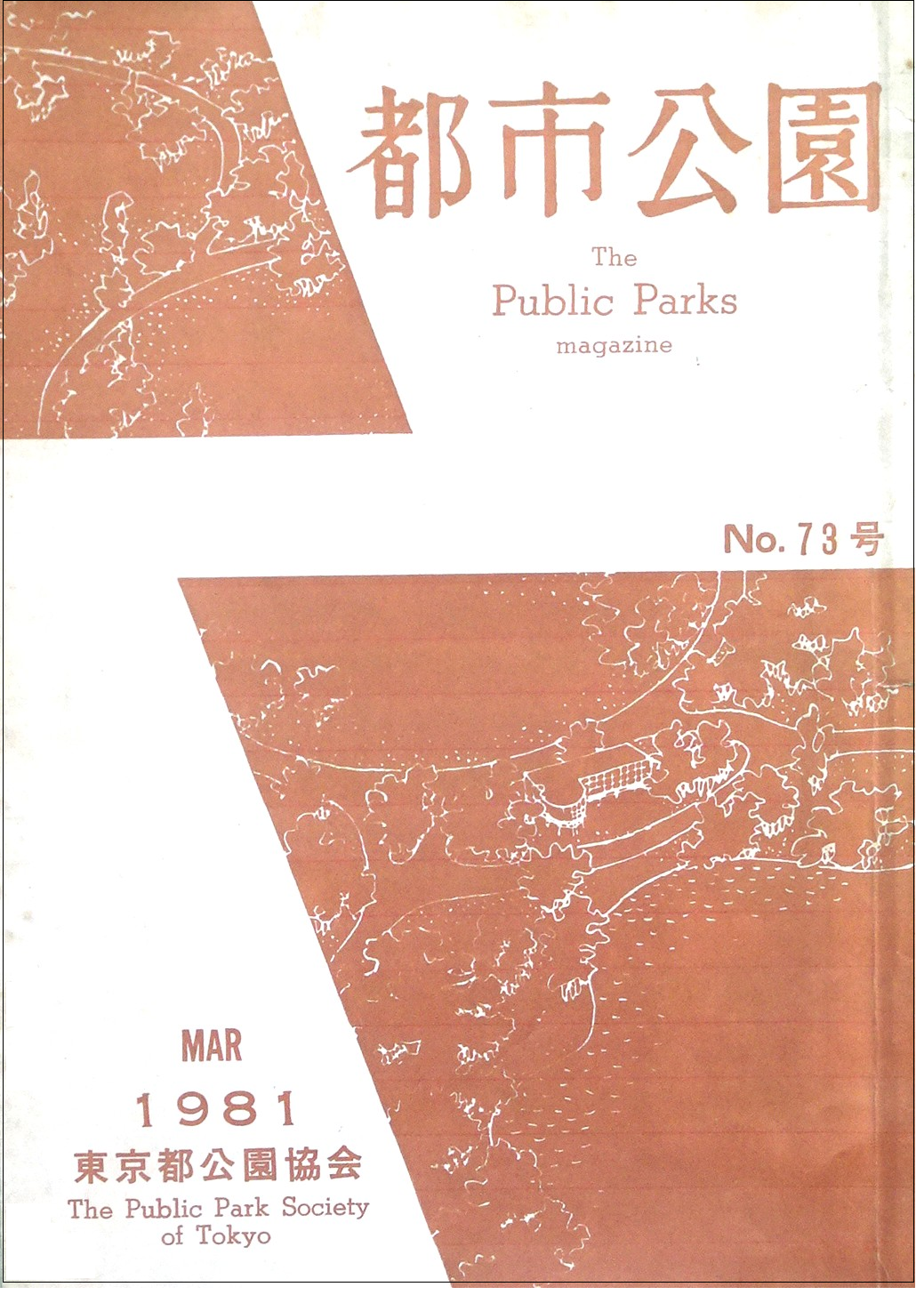 今回は、同じ土木技術の世界であるのだが、都市での公園建設を専門とする技師の手になる、これも専門誌(右写真)中の論文記事の紹介である(二名の執筆者のうちの一名より当記事は寄贈された)。そしてこの論文は、その技師の生涯にわたる仕事を集約したものというより、大学を出たのちの十年ほどの、いわば「新進」時代のひとつの取り組みを著したものである。そのためか、この論文には、学研による研究記録のようなスタイルと趣きがある。
今回は、同じ土木技術の世界であるのだが、都市での公園建設を専門とする技師の手になる、これも専門誌(右写真)中の論文記事の紹介である(二名の執筆者のうちの一名より当記事は寄贈された)。そしてこの論文は、その技師の生涯にわたる仕事を集約したものというより、大学を出たのちの十年ほどの、いわば「新進」時代のひとつの取り組みを著したものである。そのためか、この論文には、学研による研究記録のようなスタイルと趣きがある。
なお、当サイトでは他にも「土木工学、半世紀も経れば」において、近年の土木技術界の話題を取り上げている。
大井ふ頭中央海浜公園親水護岸等設計
陸路で越える国境線
今年5月半ばから5週間にわたった中央アジア諸国の旅は、日本をはじめとする島国では体験できない、陸路によっていくつもの国境を越え続けてゆく体験だった。

古都サマルカンドは、いまや“ウズベキスタンの京都”の趣きがある
英文は邦文の2倍
集計データが語る読者コントラスト
残雪の山歩きで見えてきたもの
今回の二年振りの帰国による日本での山歩きは、ハードルをちょっと上げ過ぎたかと危惧される、正直なところ、恐るおそるな試みでした。エベレスト登頂体験を持つ若く熟練した山岳ガイドが同行してくれているとはいえ、自分の身は自分で運び上げなければ登山にはなりません。体のあちこちの不具合はもちろん、78という年齢ならばなおさら、よせばよい愚行にもおちいりかねない不安を交えたチャレンジでありました。

「親ガチャ」そして「国ガチャ」も
変遷するゲームの“遊び方”

ズラリならんだ「ガチャ」ゲーム
これは、最初からそういう考えがあったという話ではないのですが、今になってよくよく考えてみれば、そういうことだったのかもと思えてきていることがあります。
それは、「親ガチャ」という言葉があり、その「乗り越え」という行動があるように、「国ガチャ」という言葉があったとしたらどうだろうということです。そして、自分が長年にわたって取り組んできたことが、たとえ暗黙にではあったにせよ、この「国ガチャ」を乗り越える行動であったのかもしれないという思いです。 詳細記事
二人の台湾人作家
いずれも日本語で作品発表
先に「二国を股にかけるということ」という題名で、温又柔(おん・ゆうじゅう)という台湾人作家について触れ、言語的アイデンティティに関連して、私自身の体験――「恥」か「強み」か――をかきました。それが機会となってその後、李琴峰(り・ことみ)というもう一人のやはり台湾人作家を知ることとなりました。この二人の台湾人作家は、どちらも日本語による小説を書いていて、日本語という自分の母国語ではない外国語によるそこまでもの達成の事例となっています。そこで、その足元にもおよばない私の外国語習得能力の「恥」を改めて噛みしめつつ、二人の日本語はどれほどのものかとの好奇心も手伝って、二人の作品を読もうと思い立ちました。 詳細記事
「漱石論」の“焼き直し”だとしても
二つの視点の融合の時
前回に予告しました漱石論についてですが、注文した本『漱石「文学」の黎明』(神田祥子著)が到着し、さっそく読み始めています。
今のところ、まだその「はじめに」に目を通した程度なのですが、まずそこで、思わぬ発見というか、気付きというか、ともあれ、意外な〈遭遇感覚〉を体験しています。 詳細記事