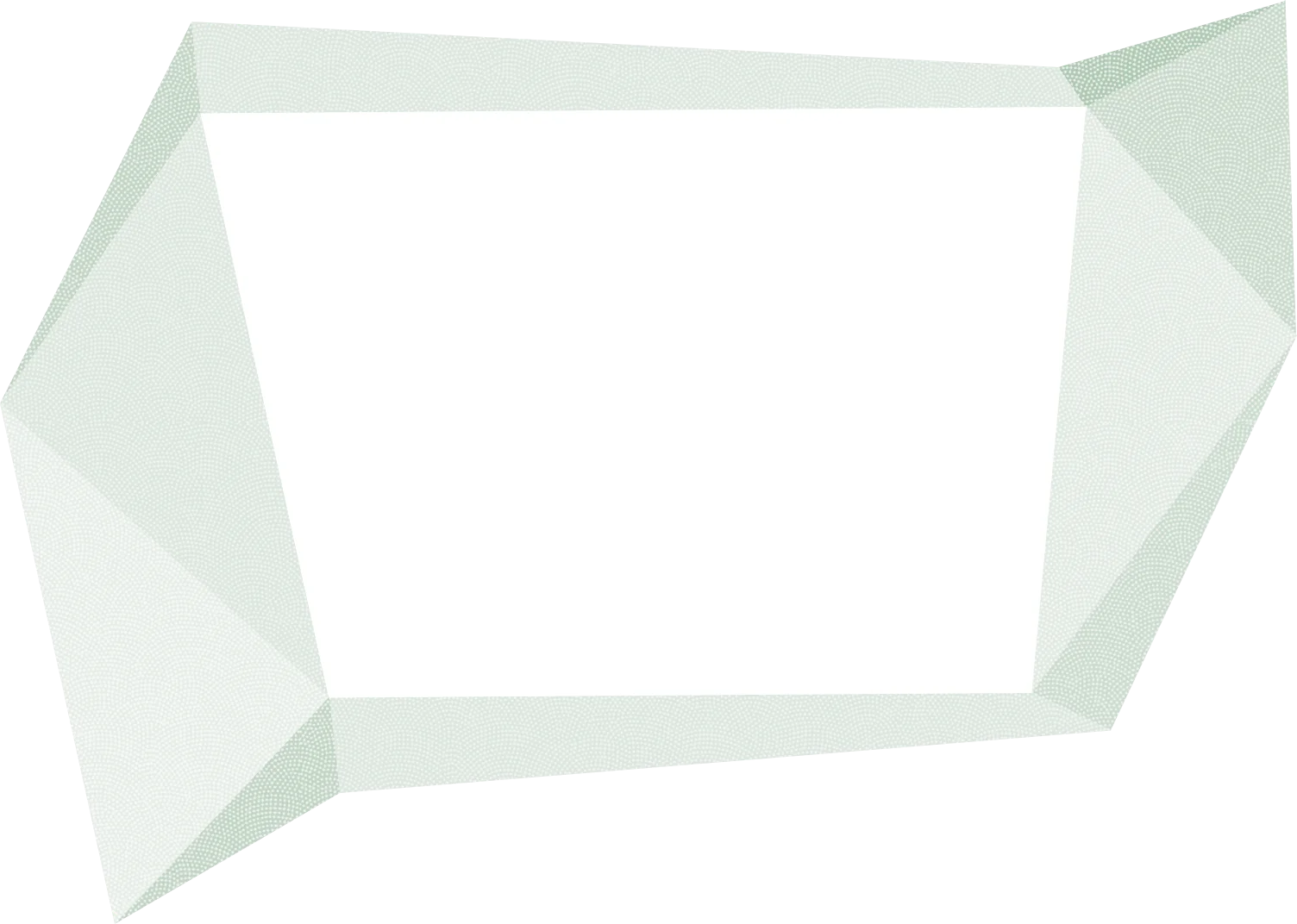先に「二国を股にかけるということ」という題名で、温又柔(おん・ゆうじゅう)という台湾人作家について触れ、言語的アイデンティティに関連して、私自身の体験――「恥」か「強み」か――をかきました。それが機会となってその後、李琴峰(り・ことみ)というもう一人のやはり台湾人作家を知ることとなりました。この二人の台湾人作家は、どちらも日本語による小説を書いていて、日本語という自分の母国語ではない外国語によるそこまでもの達成の事例となっています。そこで、その足元にもおよばない私の外国語習得能力の「恥」を改めて噛みしめつつ、二人の日本語はどれほどのものかとの好奇心も手伝って、二人の作品を読もうと思い立ちました。
そうして、それぞれの代表作、温又柔著『真ん中の子どもたち』と李琴峰著『彼岸花が咲く島』を、敬服の念をこめて読ませてもらいました。ちなみに、どちらも日本の文壇で注目され、前者は芥川賞候補作(2017年上半期)、後者は芥川賞受賞作(2021年上半期)に選ばれています。
この二著作は、そのテーマはそれぞれ、前者が、自分にかかわる言語、ことに、日本語、台湾語、中国語という三言語にまつわるアイデンティティ問題を扱い、後者が、これは純粋な創作としのフィクションとなっています。そして後者は、芥川賞を受賞しているように、作品としての完成度は高く、いわゆる文芸上の価値はなかなかのものと受け止められました。
こうした二作品の比較という限りでは、私は、言語にまつわるアイデンティティの複雑さを著した『真ん中の子どもたち』は、真実味という角度で、今日に実際に生きる人間の在りようを取り上げており、『彼岸花が咲く島』の読み物として出来の良さに比べ、時代の問題を提起していると読みました。ことに、台湾、中国、日本という、東アジアの近代史における侵略戦争、植民地化、独立、そして今日ますます深刻となっている台中関係といった歴史的脈絡の中に置かれた人々のアイデンティティ問題として、今日の世界のリアリティーの一角を描き出しています。
こうした台湾を母国とする二人物の著作に接して思わされることは、その作品様式上の違い――片やドキュメンタリー風、片やフィクション物語――はあるものの、異なった国にまたがる出自の現実を背負った人間たちに植え付けられている、存在の〈複雑性〉が見られることです。そしてこの〈複雑性〉とは、私のような、日本生まれと育ちという単一性に対する〈複雑性〉ということで、私のいう「二股かけ」にしても、そうした単一性に基づくほどの「二股さ」にすぎません。
言い換えれば、そもそも自分の使う言葉に関し、コンプレックスや根なし草感を伴うことがあったとするならば、私の場合、せいぜい日本国内での転居に伴う方言上の違いがもたらす緊張程度です。ゆえに、そうした言葉の違いに由来する人生行路上へのインパクトもその程度なものにとどまり、したがって、私の生業上への方向付けも、言葉上の敏感さは必須に違いない、小説家業へと導くほどのものにはならなかったことです。
むしろ私の場合、「二股かけ」とか「半分外人-日本人」とかと言った自己選択結果は、言語にまつわるアイデンティティの問題というより、移動がもたらす疑問の種として働いてきているようで、それが、終極的には、兄弟サイトの『フィラース』に述べているような「非科学-科学」といった方向へと向かっています。
どうやら、私の関心を文学より科学へ向かわせたのも、こうした「程度」の違いのようです。
【〈半分外人-日本人〉バックナンバー】