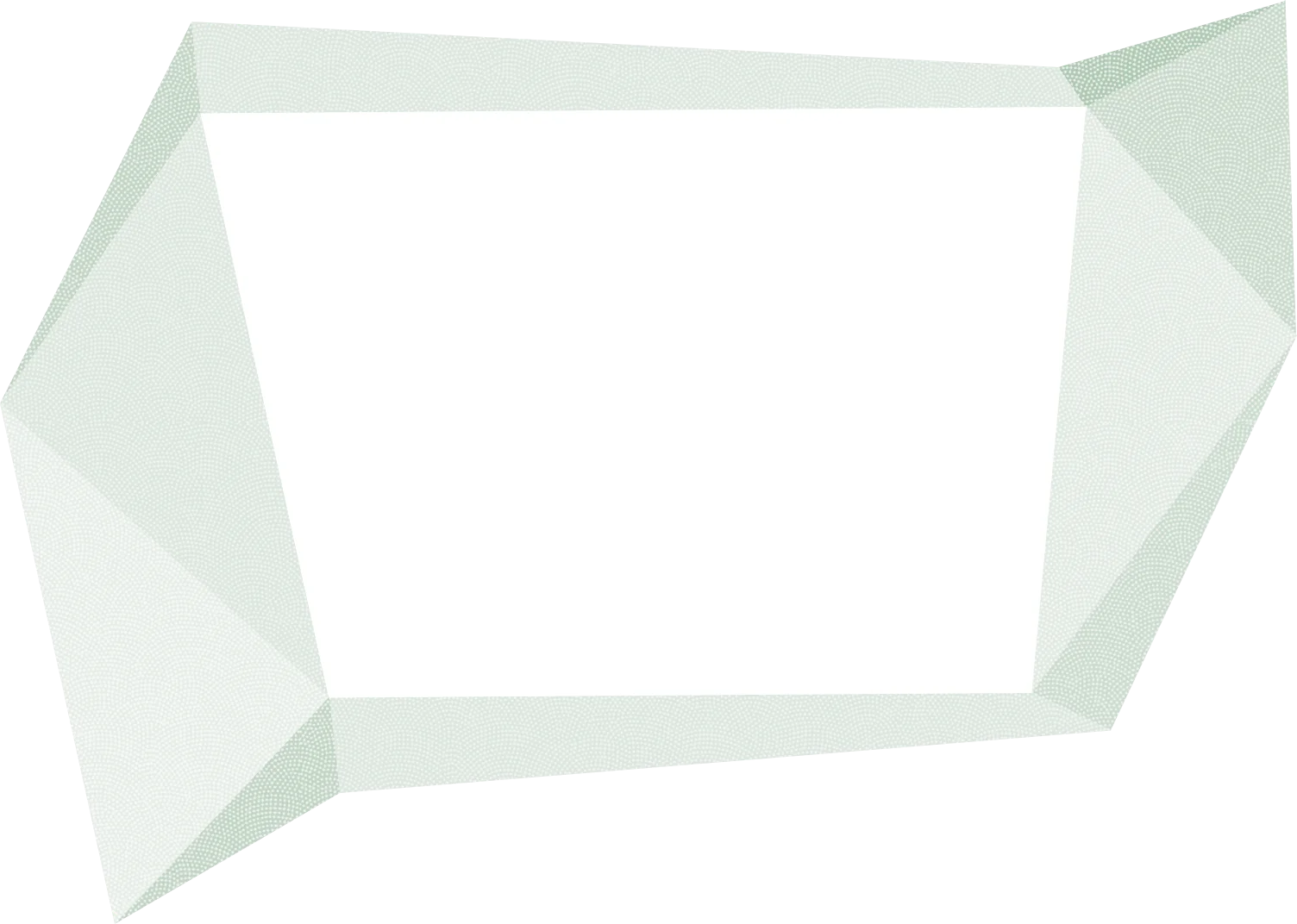雑誌『世界』で、昨年4月から始まった「日本語の中の何処かへ」と題する連載エッセイがある。著者は、温又柔(おん・ゆうじゅう)という1980年台湾生まれで、幼少時に来日、東京で育った作家である。
その温又柔は、連載初回を、まず引用で始めている。
というわけで、もし私のことを本当に傷つけたいのなら、私のことばの悪口をいってください。民族的アイデンティティとは、言語的アイデンティティのふたご――私とは、私のことば、なのだ。私のことばに自信がもてるようになるまでは、私は自分に自信をもつことができない。
(グロリア・アンサルドゥーア)〔注記〕
そして温又柔は、このアンサルドゥーアによるちょっとした「戦線布告」ともいえる以下の「宣言」を、「心底私は勇気づけられたのだった」と告白する。
私はもう、存在を恥だと感じさせられるのをやめる。私は自分の声をもつ。
〔注記〕グロリア・アンサルドゥーアは、メキシコ系アメリカ人のフェミニズム研究者。
私は、以上の二重の引用を通して、明らかに立ち位置は異なりながら、二国を股にかけることによって同様な恥や緊張を抱くこととなった、自分と重ね合わせている。
まずこの「立ち位置の異なり」だが、少なくとも温又柔にとって、日本という異国に住むこととなったのは、自分の選択ではない。だが私にとってそれは、はっきりとした自分の選択だった。
そういう二者なのだが、自分が使おうと決断していることばについて、恥を感じているというのは私も同じである。たとえそれが母国語であれ、それを表現の手段として使う「私のことば」と決めたとしてもだ。
つまりその「同じ」とは、「私のことば」との決心にまつわるひとつの通念を通してである。温の場合、母国語でなく外国語である日本語としたことだ。他方、私の場合、長年の外国暮らしなのに、少なくとも相応なバイリンガルでないことである。かくして両者、そうした「通念」による暗黙のプレッシャーと、「同じ」く、対峙することとなった。(この「通念」が、日本語で「空気」と解釈されるのは特殊である。だがこれは、その「空気」たるものに似てはいるが同じではない。要するに、多数見解である。)
そこでなのだが、彼女が、「私は決めた。自分の半端さを嘆くのはもうやめよう。これからは、ナニジンとみなされようが、もう動揺しない。/私も、私のことばで生きるだけだ」と、自己宣言している。
そしてこの連載初回を、以下のように述べて終えている。
今も私は、日本人の多くがもたずに済むうしろめたさを持て余しながら、日本人の多くはただの一度も失わずにいられる自信を回復する必要にも時々迫られて、私のことば〔縦書き原本は下線でなく傍点〕を書く日々を送っている。
そして、日本語とそんな関係を築いた台湾人は、決して私が初めてではないのだとも知っている。
たとえば呉濁流(ごだくりゅう)。1980年生まれの私よりも、ちょうど八〇歳年長の作家である。私が、自分にとって曾祖父の代にあたる台湾の作家が「アジアの孤児」と題した小説を日本語で書いていたと最初に知ったのは、私が私のことばに自信をもとうと奮闘した時期と重なる。
さて、以上のような少々長い導入を述べて、私がここに言いたいことは、じつは、彼女と私の間の同異ではない。そんなことなど、並べてみても、「人それぞれ」の話だ。
そうではなく、私のポイントとは、それが母国語だろうが外国語だろうが選ばれた「私のことば」に託す、自分のアイデンティティと呼ばれる、長くそれをつちかった土壌がその人にもたらす意味の発見とその扱いである。
ここでは、両者ともに、決心された「私のことば」は日本語なのだが、ポイントはむしろ、その両者が二国を股にかけることで共に抱いている、上記のような「通念」上のものにとどまらない、恥や緊張の感覚である。これこそ私の自論、自分という実験台を通しての観察者視点である。
言い換えれば、一度、二国にまたがる生活を、自己選択であろうがなかろうが体験することになった者が、その違いに身をさらしながら、説明に苦労する困惑を生きなければならないという、その環境がその人に与えている問いかけである。
その二国を股にかけることで体験させられ、あるいはしてしまう、困惑をどう表現するのか、それ自体が重要である。
そこには、たとえば、生まれ育った故郷を後にし大都会に出てきた際のような青春時代の原体験を振り出しに、その後成人してからの、今度は人生として選択することとなるような、〈越境〉のもたらすものがある。
ことに、故郷との帰一感を重視したり維持しえている人には当たり前――それこそ「空気」――と受け止められがちな、生まれだの性別だのといった、人にまつわる“所定性”についていろいろ取り沙汰されることは、その同類“所定性”に発する話であって、そうした〈越境〉がもたらす緊張との間には大きな開きがある。
そこで感じてしまうそうした困惑こそ、二国を股にかけることとなった者の、時には「恥」であり、時には「強み」である。そして温又柔は、その「恥」を、グロリア・アンサルドゥーアの宣言に勇気づけられ、〈自分の故郷〉だと発見した。
そのアンサルドゥーアにしても、女性であるという“所定性”によって、フェミニストととなり、くわえて、メキシコ系であることでそこに民族性を発見して、あらたなフェミニスト論を展開している。
言い換えれば、もはや今日、各国が均質な人々で形成できたという、かつてのような〈移動の困難性〉がもたらす特徴がいろどった時代ではなくなっている。いうなれば、いまや〈越境〉の時代なのだ。
そういう時代にあって、私の場合、本稿が日本語で書かれているように、ナニゴに託すかは、それだけの長居をもっても選択問題にはならなかった。ちなみに、そういう外国語の問題が、いまやIT装置の発達をもって“決定的に”技術上の問題と化しつつあることは、技術に乗らぬことば以前の「土壌」の問題を、いっそう浮上させることとなるはずだ。
つまり、温又柔のタイトルのごとく「日本語の中の何処かへ」と、そこで自分がナニジンであるかをめぐり、あらためて「民族的アイデンティティ」と呼ぶしかないものが、あるのかないのかも含め、俎上に上ってくる。