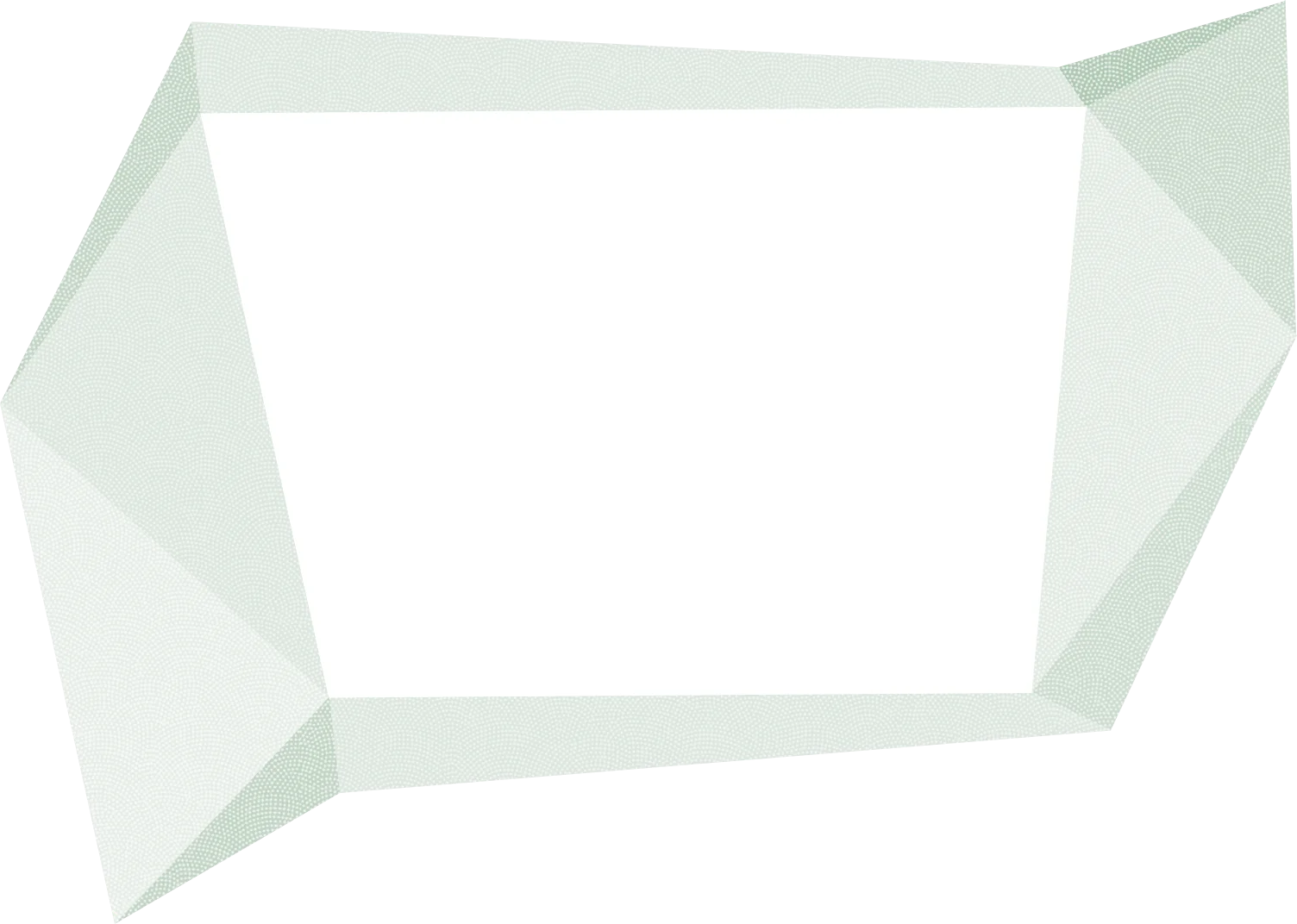人間、自分一人で、あれもこれもの役割を受け持てるわけではありません。社会の中で、人それぞれに、自ら選らんで、あるいは行き掛り上で、とある部分を引き受けています。前回ではそうした役割を、経済学の角度から、「分業」について振り返ってみました。
今回はそうした役割分担を、「分ける」視点からではなく、むしろ反対に、「包括する」二つの視点から見てみます。一つは、生物学的目線で、そして他は、一般に「人の道」と呼ばれる目線です。
まず、「人の道」との目線から先に述べてゆきますと、この視野はいわゆる学問的なものではなく、その用語自体が明瞭な定義を備えているという性格のものではありません。むしろ、私たちの生活の長い流れのなかで、時代にもまれ磨かれて、しだいに出来上がってきた規範です(法律用語でいえば習慣法にあたり、成文法に対置するものです)。ゆえに、どこか道徳的でもありますし、どこか情理的でもあります。ただし、それを「人道」とつづめてしまうと翻訳語臭くなって意味が横ずれしてしまいます。
ともあれ、この「人の道」には学術用語のような冷たさはなく、いかにも角が取れていて温もりがあり、輪郭のあいまいな難点はありながら、それが示唆する内容は、決して軽々しいものではありません。
こうした「人の道」と呼ばれる規範に含まれる役割分担は、しかし、それを理解したり身に着けたりするには、それなりの時間や経験を要します。それに、教えを請おうとしても、そもそも、教わって修得できるというものでもありません。
私なぞ、若い時分には、そうした筋合いの話が、とにかく好きではありませんでした。なにせ説教臭くてうっとおしく、時勢とも距離があり、それに、直感的に響いてくる鮮度もありませんでした。加えて、それを匂わす年長の人たちがどこか胡散臭く見え、敬ってみようにも接点の取りようがありませんでした。そこで、だいたい十歳も離れた人たちともなれば、もう人間の部類にさえ含めないといった、大したへそ曲がり振りを地で行っていました。
そうでしたので、自分が歩もうとする行方というものも、自分で触知できる身近なものへの関心や取り組みという目先に終始するもので、性癖としては、理科工作的な分野への面白味を第一とするものでした。そうした意味で、「人の道」というような社会的関心はもっぱら希薄で、手先の器用さも手伝って、「物の世界」への興味本位の接点が主体となっていました。
そのようにして、やがて迎えた進学にあたっては、理工系の方向はもはや自明となっていて、大学も迷わずそうした学部を選び、4年後には――大学紛争時代という混迷のうちに――そこを後にすることとなりました。
かくして、前回見た「分業」という観点では、現代産業社会の求める明瞭な専門性の第一歩を身に付けることとなったのですが、人的な体験という面では、明らかに免疫状態のままに、社会に文字通り“巣立ち”することとなりました。ゆえに、そうした私は、この就職をもって、「人の世界」に、初めて接することとなったわけです。そもそも、近代社会での高等教育課程とは、成人ぎりぎりまでもの、そういう分離を前提とした制度でもあります。
こうして、いわゆる「社会人」となることで体験してゆくことが、この「人の道」を自分なりに発見、会得する経緯となるのですが、その葛藤を中心とした過程を詳述することは本稿の目的ではありません〔そうした体験詳細としては、自伝的には「相互邂逅」、人生ガイドブック風には「自‘遊’への旅」などがあります〕。
むしろ、このようにして、いわば「純粋培養」された若造が、社会という多様な価値観が渦巻く、知るはずもない「世間」という既存世界に参入することとなったという経緯が重要です。ある意味では、そうした“兵隊訓練”と“実戦部隊配属”ということです。またそうであるがゆえに、その後の日々の在りようとしては、過敏な反応を伴う、ぎくしゃくした発展を持つこととなりました。
そのようにして、一種の溝を内蔵したまま「人の世界」と遭遇した結果、意固地な反発を盾に、周囲への溶け込みの悪い、かたくなな殻をかぶった姿勢を持つにいたります。そこでなのですが、やがてそうした居心地の悪さが反面教師となるように、両端から不等号によって挟まれるようにして、むげには否定しえない「人の道」とされるものを、しだいしだいに発見する独自の契機にはなって行ったのでした。
むろん、こうした認識は私的なもので、その一々を一般化できるものではありません。ただ、個々の詳細は異なれ、誰もが担う共通部分や要素はあって、互いに重なり合った過程をつうじた共有の成果を形成していることに間違いはありません。したがって、それは理念的でも体系立った学習課程――つまり「成文法」――でもなく、むしろ、時間が紡ぐ多様で具体的な体験の蓄積――つまり「習慣法」――です。そうであるだけに、人が若造であるうちは、そういうおのれは、いまだ未成な欠陥のかたまりそのものなのです。
私が若かりし頃に固執した年長者への反発も、先に生きている者がそれだけで強みとなる、そんな一見アンフェア―な仕組みへの自然な反応でもありました。
こうして、一定の長さの習熟期を過ごしたのですが、私はそれを、伝統の教える還暦という節目をもって、「人生一周目」と呼んでいます。つまりそれは、「二周目」の人生ための準備期間であったという含みでもあります。
では次に、第二の役割分担ですが、それは生物的なものです。すなわち、この地球上におけるぼう大な体系をなす生態系において、そのほんの細部を分担する〈部分と全体〉という関係にある片方です。
ただし、これを上述のような人為的「分担」と並列して捉えるのは無理があります。というのは、それが生態系といういまだに謎の多い巨大システムにおける「分担」であるにとどまらず、「自分」という人の個的存在においては、生命という自己創生機能をもってその自らの意識が立ち上ってくるという、そうした深淵な仕組みに関わるものであるからです。つまり、明瞭にここにある個自身は、そうでありながらその基盤にはいまだ多くの未解明部分を残しており、それでもそれに全的に依拠せずにはありえないという存在でもあるからです。つまりは、なんだか解らないものの上に立っているこの「私」というわけです。
それに、「奢り高ぶる人間」とは度々指摘されてきていることですが、たしかに人間が生態系の頂点に位置していると表現は可能としても、だからと言って、その生態系全体を支配君臨できない、あるいはすべきものではないことは、近年の異常気候の深刻化を見ても示唆的です。これはどこか政治に似ています。
そこでここでいう「役割分担」と言うものは、持って生まれた、もはや自分ではどうしようもなくそこに拠って立つしかない自らの独特性という「役割」であり、別な言い方では「個性」です。
そういう意味では、全体と結びついた相互関係を抜きにしては語れない、〈部分と全体〉、あるいは、〈自己と環境〉の問題です。
ここには、集団をなす人間が、自然界の中で、その一部をなして、無数の生物多様性の中の一種として存在している生物的「役割分担」があります。くわえて、人間個々人として見れば、その役割部分はさらに微細で、それを個々に取り上げてなぞしてられないほどに微々たる人的「役割分担」があります。
そこでですが、この微々たる後者にとって、その自己たるものは、生態系および生物体系内の「役割分担」には、生命の仕組みとして、それに敬虔に従うしかないものです。それはことに、既述の経済的な「分業」と並べてみるにつけ、二者の在りようは本質的に異なっているにも拘わらず、その「部分と全体」という形象的類似性をもって、あたかも同類であるかに扱われる傾向があります。
ちなみにその典型が、生物体系内の顕著な「役割分担」である雌雄あるいは男女の違いが、明白に、経済上の扱いの差の根拠にされていることです。そればかりか、男女以外にも、人種や、地域の違いといった集団上の差異をもって、経済上の待遇の差や支配すらの根拠ともされていることです。
そしてさらには、「分業」と「役割分担」の混合を根拠に、その細分をピラミッド状に組み上げた構造が、あたかも当然許容される存在として支配力を定着させ、自然界の中でさえ、その君臨支配が当然視されていることです。言い換えれば、その後ろ建てとなっている、経済合理性や政治力学といった実務論理について、その見直しが必要となっているということでもあります。
こうして、「役割分担」の根拠としてあげられる、「分業」とは本質的に区別されるところの、「人の道」と「生物体系」の二つは、「分業」の根拠となってきた科学的分析とは出どころの本質的に異なる、〈部分と全体〉が相互に織りなす、〈部分であって全体である〉――こうした一見論理矛盾したかの認識は、西田哲学の「矛盾的自己同一」との考えにも見られる――とも表現しうる、そうした《一体関係》を成している中での、政経上の実務論とは次元を異とする、「役割分担」であることが判ります。
そこで、人生の〈「二周目」から「一周目」を振り返る〉本テーマに立ち返れば、「役割分担」という人間にまつわる実に奥深く豊かな在り方が、時の勢力によって、いかに歪めて利用されているかという視野に行き着きます。
ところで、こうした到達を別の角度から考察する「科学的概念のもつ限界性」について、別の機会で論じてきています。参考までにご案内いたします。