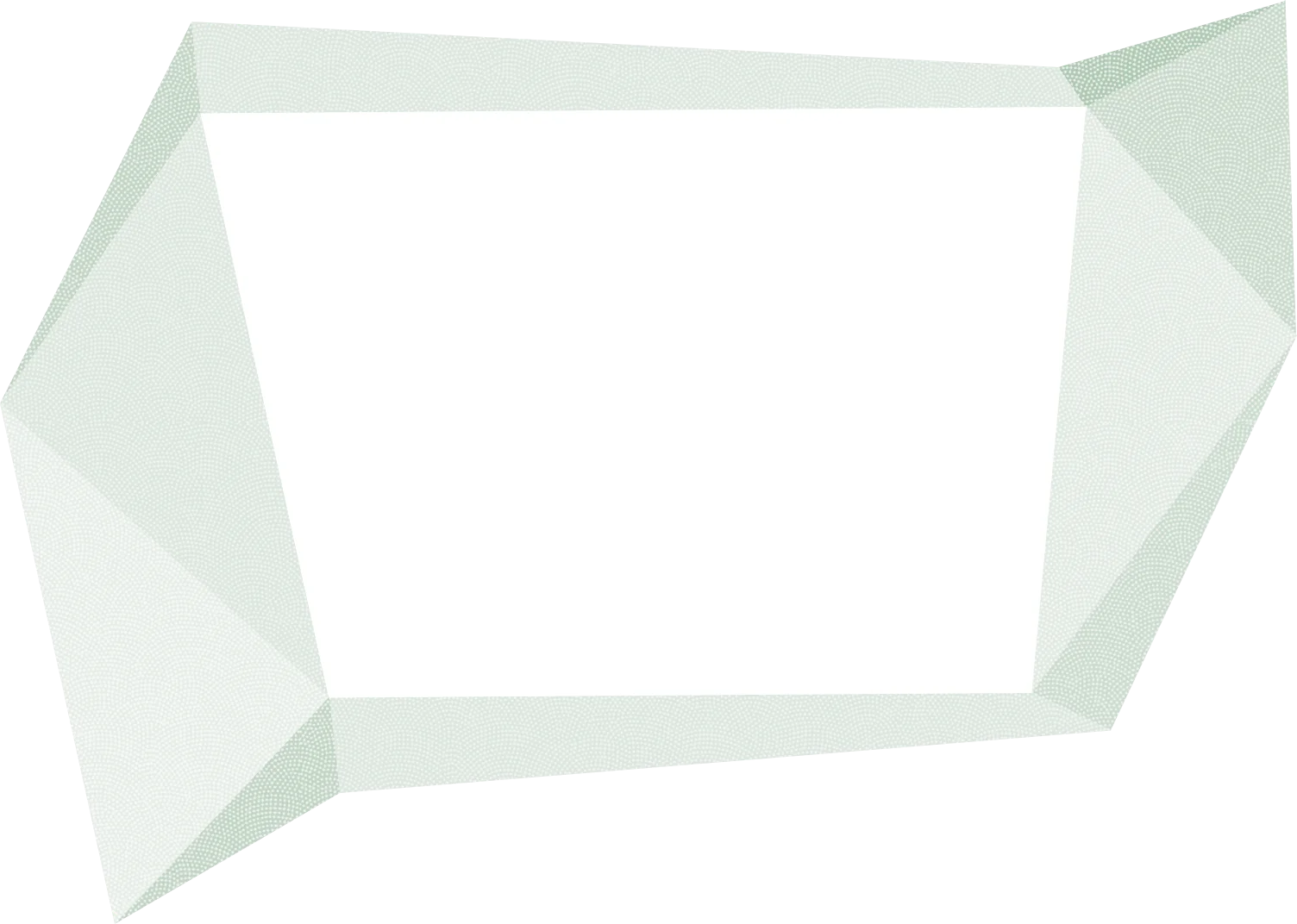兄弟サイトの『フィラース』に、先月亡くなった松岡正剛さんの逝去について、私は、そこにひとつの見落としがあったと見る立場での見解を書いています。
ただその見方について、それがあの松岡さんについてだっただけに、少なからずはばかれるところがあります。
その出どころは、一方での、実質的な絶筆書と思われる対談録『初めて語られた 科学と生命と言語の秘密』の随所にみられる、尽きぬ進歩を遂げる生命情報科学の今後を見通す、彼の慧眼です。
しかしその他方、いわゆるライフワークとの面では、人が成すその有限行為にあって、いつかは遭遇せねばならない生命的限界という深淵です。
こうした無限と有限のはざまにおいて、《自分の死の設計》という点で、まかり間違えば醜い事態も生じかねないその最後の土壇場に備え、たとえば、あえての弱点を残しておくことでコントロールされた命取りを用意し、間違いなくそこに自分を持ち込んでゆくといった、〈出さねばならない現実解〉との観点がありうることです。
この《自分の死の設計》に関し、これも彼の実質上の絶筆に相当する見解と思われる、本年3月7日付『千夜千冊』の「脳と腸」に残された以下の表現があります。
「ぼくはこの恩沢に富む突沸にかまけすぎてきたわけである。それをいいことにジンセー晩期の歪曲の何たるかを惧れずタバコをずっと喫いまくってきたわけだ。内臓感覚によるバイオフィードバックをないがしろにしてきたわけだ。傘寿が惨寿になっても仕方なかったのである。」
すなわち、上記の「はばかられる」とは、この彼にしてはいかにも実直な――読み方によっては“自嘲的”な――表現に託された、その真意をどう受け止めるかについてです。
つまり、自分の生体資源の限界を、不用意な成り行きに任せず、かつ、その「恩沢に富む突沸」を最大化する方途として、愛煙による「惨寿」という、いかにも典型的な悪癖による結末が、あえて――もしや、やむなく――選ばれていたのではないかと、上記の見解のように見てしまえることです。
むろん、名だたる医師のもとで闘病もしていたでしょうから、その診立てには従ったでしょう。そうであるからこその、この慎重な表現でもあったと受け止められます。
そういう多義な脈絡で、一連の実質的絶筆表現に隠された意味は、ひとつしか選べない「ジンセー」からの旅立ち方として、捉えにくくはあるのですが、一種の「悪がり」という現実的装いだったと雑ぱくに見なしてしまっているのが上記の兄弟サイトでの見解です。
そこでなのですが、ここにはまた、「恩沢に富む突沸」と「限りある生体資源」のなす高次方程式を解かねばならない、そのような《のっぴきならなさ》という生命的条件があります。そしてそれを少々強引にも一般化すると、《のっぴきならなさ》という、誰もがその人生において不可避かつ当たり前に引き受けている、〈普遍条件〉と〈蓋然解〉があるようにも思えます。
そこで、その彼とわずか二歳差ながら、なんとか「命取り」の延期をたどりつつある私には、《自分の死の設計》において、微妙な接線上ではありますが、「悪がり」を装うどころか、まだ呑気にも、自分という生命に到来するだろう、ある種の成り行きに最後まで任せていたいところがあります。
だからこその、本独想記の前回の「大いなる『見込み違い』」であり、松岡さんが言う「バイオフィードバック」、私の言う「自分の〈内なる声〉」への傾注です。
果たしてこの傾きは、正解なのか愚解なのか。
ともあれ、以上は私の〈牽強付会〉レベルの短見なのですが、それにしても、臨終の瀬戸際にあって、最後の「千千」においてその編集思想は、「せっかくだからこの不埒な『極み』の感覚を観照してみようとも思う」と記されています。