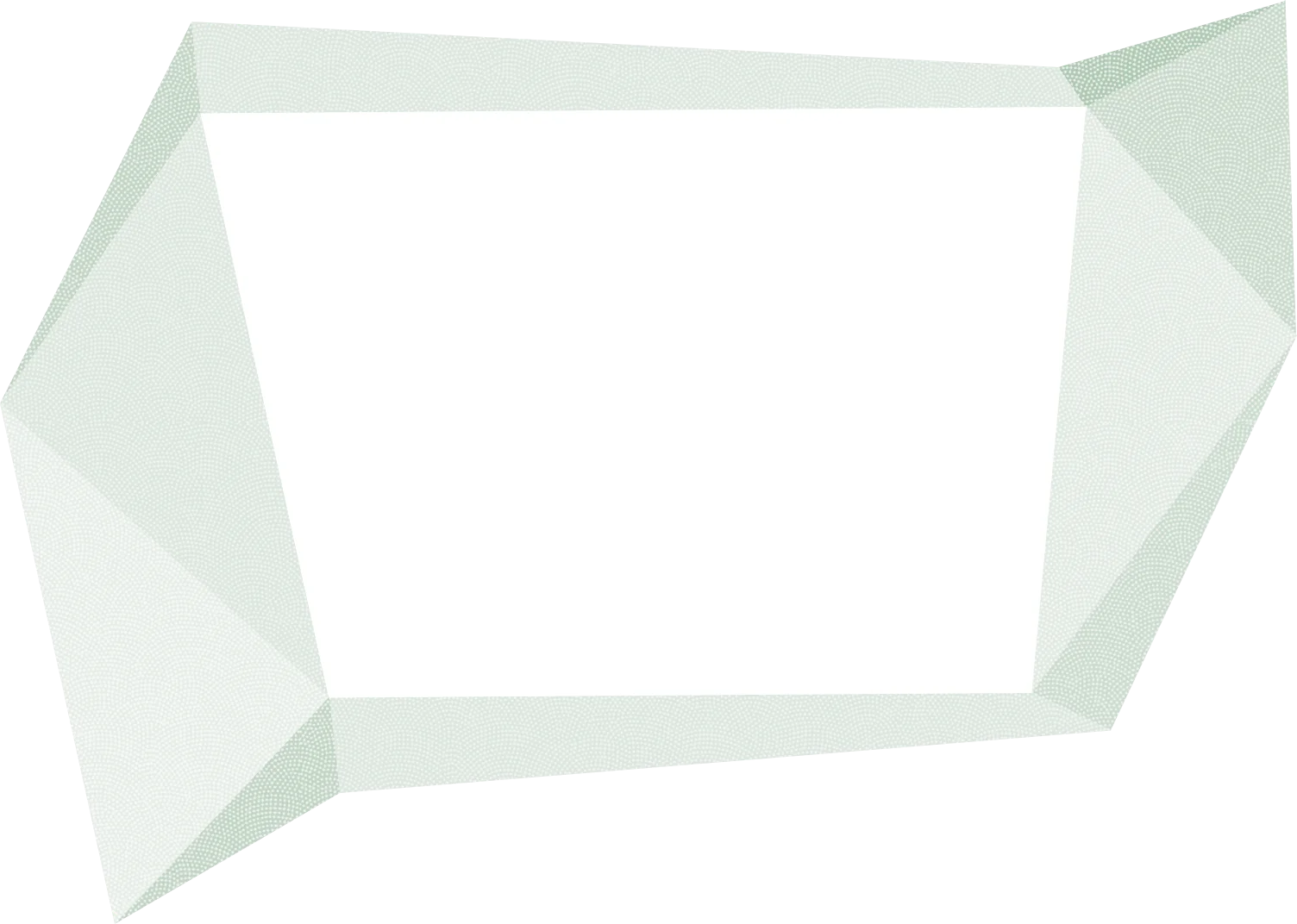運動の後、芝生の上に座して、こう思った。
 私は、どういうわけか自分の意識をこう持ってここにいて、その〈眼鏡〉をとおして外界を眺めている。自分でも、また誰からも、意識のそういう在り方の理由もその目的も、説明はおろかその問いさえ聞くことは極めてまれだ。意識はただ、気付いた時にはそう存在していて、それを今まで長々と引きずってきている。
私は、どういうわけか自分の意識をこう持ってここにいて、その〈眼鏡〉をとおして外界を眺めている。自分でも、また誰からも、意識のそういう在り方の理由もその目的も、説明はおろかその問いさえ聞くことは極めてまれだ。意識はただ、気付いた時にはそう存在していて、それを今まで長々と引きずってきている。
間違いなく、昔は、我を張ることを、そうとも気付かぬほどに当たり前としていて、「自分、自分」と、おのれを中心にすえた同心円を保持するのに汲々としていた。
その頑固な自分中心の考え方の最たるものが、自分が出会った大切な人との結婚であったはずなのに、愚かにもその「自分の沽券」を張り続けたために、相手にあいそを尽かされ、離婚に行き着いたことだ。
むろん、すべて良かれと信じてやったことではあったが、そのどこまでもついて回る自己意識という曲者に乗っ取られて、日々のせっかくの体験にも拘わらず、そのメガネ越しでしか目に入らなかった。
そうしてそれが、今日に至るまで七十数年も続いたというのだから、おそろしいほどの人生の浪費に違いない。それとも、そんなことは誰にも似たり寄ったりの話で、「皆で渡れば怖くない」の類の話であるのだろうか。
まあ、いまに至ってみれば、そんな話はどうでもよい。要は、そうした足跡を疑うことなく残してきたという事実だ。
ただそこでひとつの救いは、遅きであったとはいえ、まだ余命のあるうちにその浪費に気付けたことだ。しかもその余命も、平均といった間尺で見れば、この年齢にしては珍しいと医者からも言われる、そこそこな健康を伴っていることだ。
以上の思いは、先日、日課としている運動を終え、事後のストレッチを済ませ、芝の上に座していた時に抱いたことである。そこで、その突然に訪れた体験の経緯を記録しておけば、以下のようになる。
快晴も幸いして、気分も自然も爽快この上なく、大きく傾いた夕日をみつめながら、深い呼吸に気持ちをゆだねていた。
そのきっかけは、そうした爽快感がどうして得られているのかとの思いが、ふと頭をかすめたことだった。というのは、これまでとはどこか違いがあるような気がしていたからだった。
以前はそんな時、そうした運動を行う身体に対して、自分があたかも主であるかのごとき、ある種の支配服従関係のような奢った意識が常に存在していた。それが今は、えらく違っていた。
それには、最近の身体科学上の情報を得ていたせいもあったと思うのだが、運動をもたらす筋肉の働きというものが、何と脳の働きにも近いというものだった。そんな予備知識も手伝って、運動の最中でも、従来のような自分の意識の側のそれでなく、自分の身体の側から発せられている声といったものを、なにやら素直に感じられるようになっていた。つまり、「バイオフィードバック」と呼ばれる、身体感覚が物語る世界に触れられるようになっていた。
そして、そうした運動体験とともに、そう芝上に座して目に入ってくる、あたりに広がっている光景が、いまや、眼鏡越しどころか、身体とつながりあった境目のない世界と感じられ、かってのような、何かに対して「よう頑張った」とする勝利者めいた意識とは、大いに異なる世界に入り込んでいた。
あるいはそれは、登山の際、あえぎあえぎ足を運んで山頂に立った、あの、大自然に迎え入れられているかの感動にも似ていた。
もちろんその発見は、その直前の一時間ほどの走りがもたらした、身体と自意識との間のキャッチボールがあってがゆえのものだ。もしそれもなく、ひと時の散歩の際での思いであったなら、そんな爽快感さえ、ただ、気分のリラックス効果のひとつと納得されていただけであろう。
ところがその時、にわかに立ち登ってきたのが、一種の《窓》の感覚である。それは、上述の〈眼鏡〉の感覚とはまったく異なった、もっと大らかでありのままな視界だった。
そして、そういう視界を得ているその自分とは、それこそ、その《窓》の向こうの風景を映している一台の映写機との感覚で、そこでは従来のような、しゃしゃり出てくる自己意識の介入は消え去っていた。
したがってその自分とは、そういう映写をおこなう一種の《観測装置》に過ぎなく、これまでの沽券に駆られた「主」めいた思い込みとは大違いだった。
そこで、そんな存在でしかない、そしてそれほどな存在でもあるその自分とは、考えてみれば、この地球の大自然がもたらしてきた生命発生とその進化現象の最末端の果てに、偶然のようにも灯っている、ほのかな点火現象ほどのことなのではないのか、という思いだった。
それはつまるところ、これまでの「自意識」も「我を張った自分」も、そうした《観測装置》の内部で生じている、いわば“乱反射現象”が作り出した幻影にすぎないのではないか、との考えにも行き着く。
さらに突き詰めれば、身体内でガン細胞が不穏な増殖をするように、脳内において、生体情報が“乱増幅”を繰り返した結果の虚像とも喩えられた。
これはとどのつまり、長年にわたって私の内部を占めてきたそうした「我」は、間違いなく存在してきたとはいえ、それは、地球環境が数十億年をも要して発生させてきた生命現象の末端にもたらされた、生体情報のランダムな〈短絡〉現象が成している、しいて言えば、〈虚像投影〉としての存在ではないかとすら思えるものだった。
そうして、現に私がしてきたように、長年にわたって「ひとりよがり」を成してきたその結末でようやくにして達した、その我を張る意識が身体という《内在自然》との対話に目覚め、その総和的な一体性に気付く《観測性能》であった、との感慨であった。
そこでこの《観測性能》を、今日世界のひとつのメッセージとして引き出せば、
人類は、「自意識」のもたらすトラップにいまだに捉えら続けており、「バイオフィードバック」という“民の声”に、耳をふさぎ続けている“専制君主”たる存在ではないか。
終わることなく繰り返される戦争行為を見るだけでも、それは明らかである。
との表現となる。
ともあれ、芝上に座し、やわらかな夕日を浴びながら、以上のようなアイデアの湧き上がりを体験していたのであった。