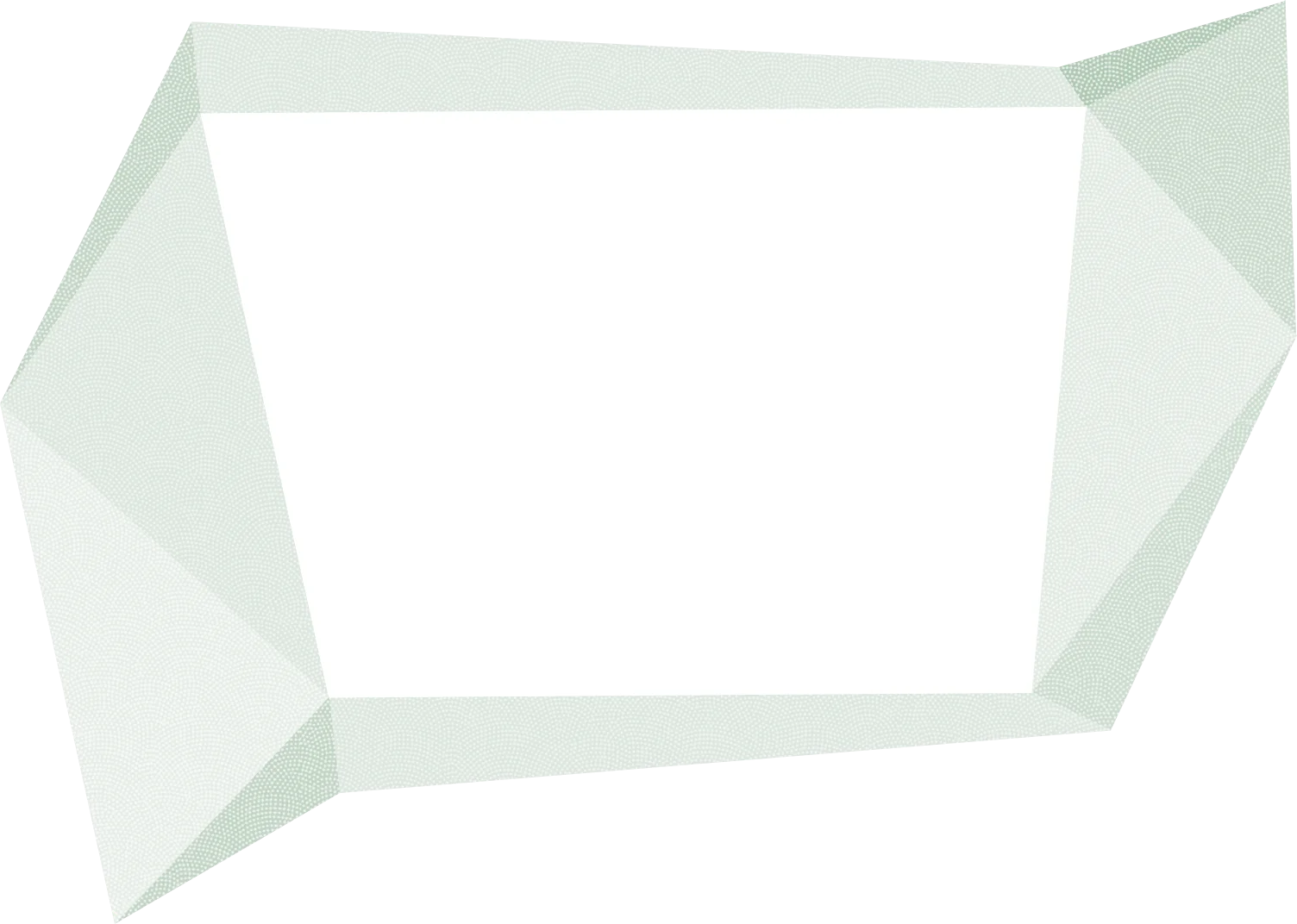ここに興味深い集計データがある。今年3月7日付の《「人生二周目」独想記》第27号に、「戦争しない国はどこ」と題した記事を掲載した。この記事は、英訳もしてバイリンガルになっているのだが、この6月中のアクセス数集計をしていて、その邦文と英文との間に、127対288との、2倍強の違いのあることが判った。
まず、その記事の内容を要約しておくと以下のようになる。
今や世界の主要国が独裁傾向を示しつつあり、それに従い、世界がいかにも〈戦争頼み〉の危険な時代へと移りつつある。それが、民主主義に制限あるいは皆無同然の全体主義国家のみならず、米国のような民主主義のモデルと称されるような国によっても、その〈戦争頼み〉の傾向が顕著となっている。その民主主義の旗手のはずの米国にそうした独裁志向のリーダーが生まれた経緯に、選挙の自由投票制による結果があり、国民の過半数に満たない過小支持率の政権でも、国の権力を総取りして世界を牛耳ることが、独裁志向リーダーの国家戦略となっている。一方、世界の投票制度に目を転じてみると、投票が自由つまり任意ではなく《義務制》となっている国もある。その一例がオーストラリアで、今年の選挙でも、全有権者の実に93パーセントが票を投じている。こうして文字通り総国民の意志が問われるのその選挙戦では、異色な独裁傾向者が勝利を獲得するには、その政策が、男女老若そして全移民人種にわたる、総国民の過半数を納得させるに足るものであることが必須となる。それは、自由投票によるおおむね60パーセント前後の投票者数を土台に、造られた脅威と誇りにあおられて決起した“過半数”ではない。
私は、そのオーストラリアに住んで40年、来月には79歳となる〈半分外人-日本人〉であり、そうした全員参加の選挙制度の実相を目の当たりにしてきた。ただその当初、この義務(棄権には科料される強制)という聞こえの悪い制度に、異様感を抱かなかったわけではない。
それがこの国に長居して、人びとや政治の日常を身近に目撃するにつけ、この義務/強制が定着した効果とは、その耳障りの悪さとは逆比例して、政治家と国民との間の距離感を縮め、いい意味のポピュリズムが根付いていて、独裁者といった特権者に自分の期待を託すには疎遠な政治風土となっているのは確かだと受け止めている。
私見を述べれば、それでも競い合いや勝ち負けに意義を燃やす人たちは、スポーツにその場を見出している。オージーのスポーツ好きは並ではなく、街々にスポーツ諸施設も行き届いており、オーストラリアが人口当りの五輪メダル獲得数でのチャンピオンであるのもうなずける。
したがって、異才を自認するハイパフォーマーは、そんな自国に物足らなさを感じ、英国だの米国へと渡って、個的満足を達成しようとする。逸材が居付かない環境とはいえようが、それでも、そうした人材を生んだ母国との事実は揺るがない。
私の先の記事が、英文では邦文の2倍の読者を得ているのは、その国別内訳は不明だが、こうした内容から、オージー読者が多数であるのは間違いないだろう。
そこで極端なことを言うようだが、いまや問題は、個人の満足ではなく人類の問題である。すなわち、戦争という見も知らずの人と人との殺し合いか、平和という個的達成感は薄いながら皆がそろって平安であることの、一体、どちらを現実に望むかだ。そうした人間世界の肝心さの問題だ。そもそも、独裁に譲れる問題と、主旨が違う。
自由/任意投票制は、その聞こえの良さとは裏腹に、そうした肝心さにむしろ背を向けがちである。他方、義務/強制投票制は、その肝心さを外さない選挙制度だと思う。
この聞こえのよい制度が決定的な惨劇を生む前に、独裁依頼の悪夢から目を醒ましたいものだ。
むろんことの本源は制度にあるのではない。すなわち、事実上の義務/強制投票の実施に等しい、投票率の大きな上昇があれば、この問題への解答はおのずから導かれよう。
追記となるが、上記のバイリンガル記事へのアクセスは、邦文、英文ともに、この6月に急に高進し、ああかも世界の情勢に反映しているかのようである。ことに英訳記事は、それまで日に1アクセス程度の微々たるものだったが、月に300ほどへと著しい増加に転じている。