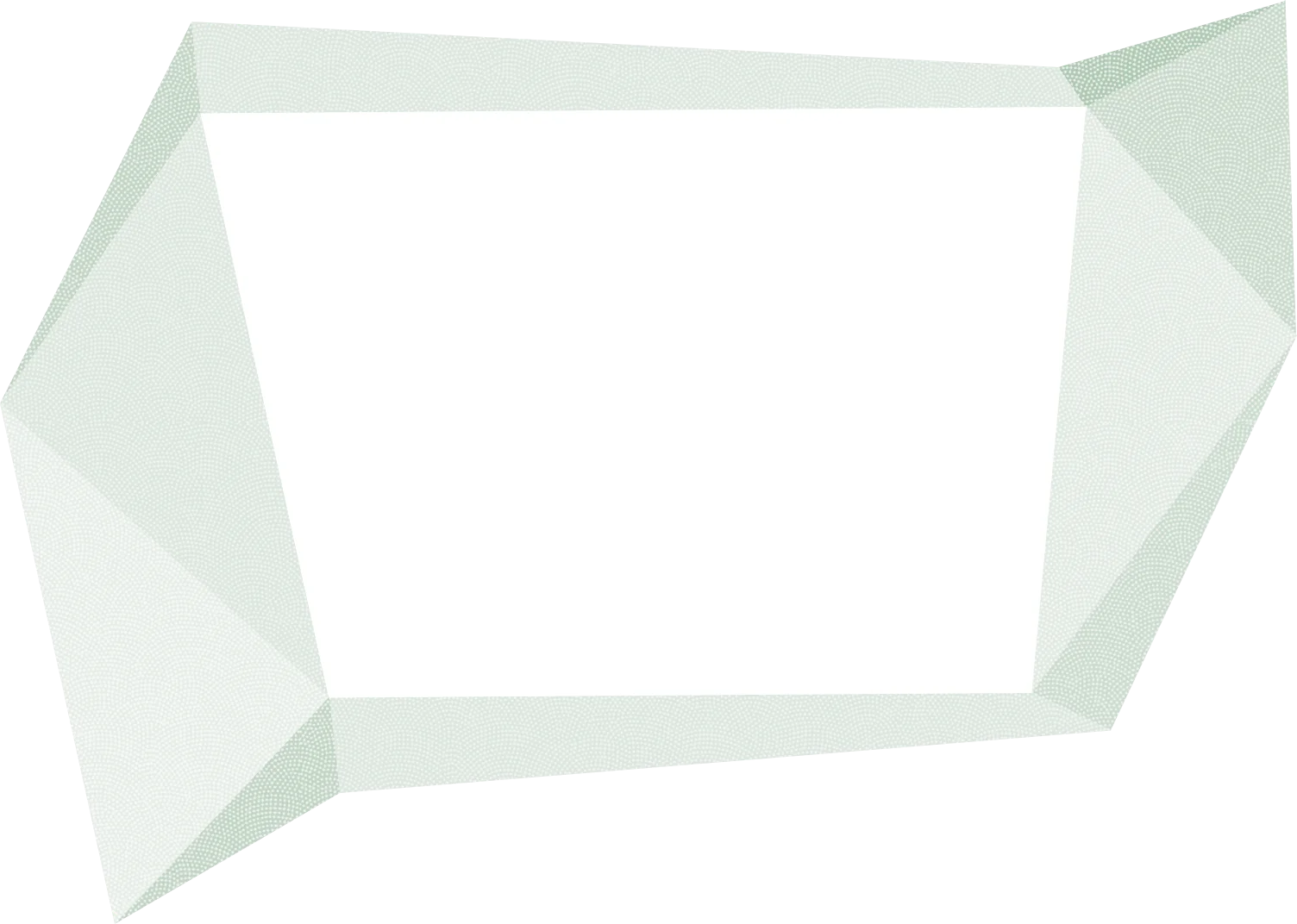前号の「〈続〉 残雪の山歩きで見えてきたもの」では、奥秩父での山行体験が発展して、なにやら、量子理論の自分解釈版になりそうな記事となった。それが、兄弟サイトの『フィラース』に掲載中の「MaHaと僕のシェアーライフ」の「2.03 「並行宇宙」論と共に」ではさらに発展して、ことに、量子理論の「並行宇宙」論の私版を述べることとなった。
そう述べながら、これはもしかすると、今日風「夢」ではないのだろうかとの思いも頭をよぎる。
そこで、それがもし「夢」であるとするなら、そのドキュメンタリー映画中での宮崎駿の告白、「人間の夢とはことごとく、呪われた夢なんです」が、再度、想い起されてくる。
宮崎にとって、彼の表現手段は、あえて言うまでもなく、アニメである。
この動くマンガという、日本に発した表現上のポピュリズムは――私がネパールで、大揺れするバスの中で偶然に隣り合わせた(日本好きの母親が名付けたという)「タロウ」という名のオランダ青年が日本アニメの熱心な愛好家であったことでも体験したように――、いまや世界の若い世代におけるひとつの文化潮流すら成し始めている。
他方、私にとっての表現手段は、ここに書いているように、つたない文章である。
これは、宮崎アニメのように、インパクトのあるポピュリズム性はもちえない。ただ、なんとかその弱点を補おうとして、今ならではのインターネット技術を駆使し、瞬時の伝搬力を備えた取っ付きやすい手法も取り入れている。
そうしたねらいを込めて、たとえば上記の「MaHaと僕のシェアーライフ」では、文章上のマンガよろしく、口語調のスタイルをとっている。ただ、いかんせん、その内容が、量子理論の「並行宇宙」論などと、おそろしくがちがちのものとなるに及んでは、せっかくのそのスタイルも効果を発揮しそうもない。それに、絵が示す、一目に込められる情報性にはとてもじゃないがかなわない。それこそ、「百聞は一見にしかず」である。
そのへんのギャップを埋めようとして、私はよく、図表も使う。おそらくこれは、自分が理工系の学生時代を過ごしたためか、そのあたりの初期環境からくる慣れが影響しているのかも知れない。しかしその図表も、もとはと言えば、数学上の表現から来ているものだ。だからそれに本格的にならえば、いっそう理解困難となるし、そもそも私は、そうした高度な数学には歯が立たない。ただ、ものごとの関係を視覚的に表すことは時には有効で、言葉にして表現する回りくどさを避けるために、その力を拝借している。
さらに、ことに量子論にいたる先端の科学技術が、高度数学による数理手法にのっとっているため、その真の理解のためには、その世界に頭を突っ込む必要がある。ただし、それはもう、超専門的な分野であって、私のようなアマチュアのレベルでは、そのほんの基本的な考えに触れる程度がやっとである。そんなこんなで、専門性という意味では「痛し痒し」の立場しかとれない。
ただ、そうした進化する専門領域の一方で、私が重視する方面として、極めて一般的なのだが、それだけに、現代へといたる社会経済制度がもたらしてきた現実上の特性がある。
それというのは、私が「生活者」と呼ぶ観点を繰り返してきているように、市場経済、ことに労働力の売買という人間の商品化がもたらす、ただの制度的影響では終わらない人的形成上の問題である。
これはまず、社会を持つ者と持たざる者とに分けるように、社会に一様な傾向をもたらすものではなく、さまざまな分断を形成して、その認識に顕著な対比をもたらす。
加えて、その制度的影響の結果が個人の特性の上に影をおとし、その個人差がゆえに私的問題として片づけられる。
だがそうでありながら、現代の市場経済制度にあっては、その人が使用者でない限り、他の大半の人びとはその生存の維持のために、自らを商品として売りに出さねば生きて行けない。
私はこの問題を経済制度上のそれとしてではなく、その制度の歴史的定着による、人間に根付いてきた世界観の問題と見る。すなわち、人間を商品として格付け、値段づける、人間が生命でありながらモノとしてあつかわれる認識体系の問題である。
このある意味で人間世界の大懸案――それこそ階級対立という宿痾――とされてきた問題を、私は、今日までに量子物理学が見出してきた、人間の世界認識を根底から覆す発見と結び付けて、経済制度的かつ量子論的な二重の問題として捉えたいと考えている。
つまり、量子論の最新の到達である、「並行宇宙」という見方は、こうした二重の問題を、人間の世界観を根底から改める働きをもって、一括して解決できる可能性を秘めていると見る。
これを、厳密な量子理論とはそれだけの距離をあえて持たせた自分解釈上の「並行宇宙」論として、すでに人間は、この地球上にそうした「並行世界」を形成してきており、そうした世界を是認する世界観上のバックグラウンドとして、従来の物理学の世界を築いてきたと見る。
言い換えれば、私は、この「並行宇宙」論にはじまる今後の量子論に基づけば、人類は、市場経済に頼らずとも、それよりいっそう豊かで、かつ、平等かつ多様性のある社会を現実に築きうると、少なくない希望的観測を含め、見ている。
すなわち、「生活者」である私たちにとって、この「並行宇宙」論によるもう一つの世界として、その長年のくびきを取り払われて生きることがことが現実に可能となるという考えである。むろん、それまでの道はまだ長いだろうが、そこへと向かう、確実なステップは、年々、きざまれていると見ている。
さて、この「夢」がまたしても「呪われた夢」となるのかどうか。宮崎駿はそれでも映画を作りたいと言う。
松尾芭蕉ではないが、「旅に病んで、夢は枯野をかけめぐる」である。