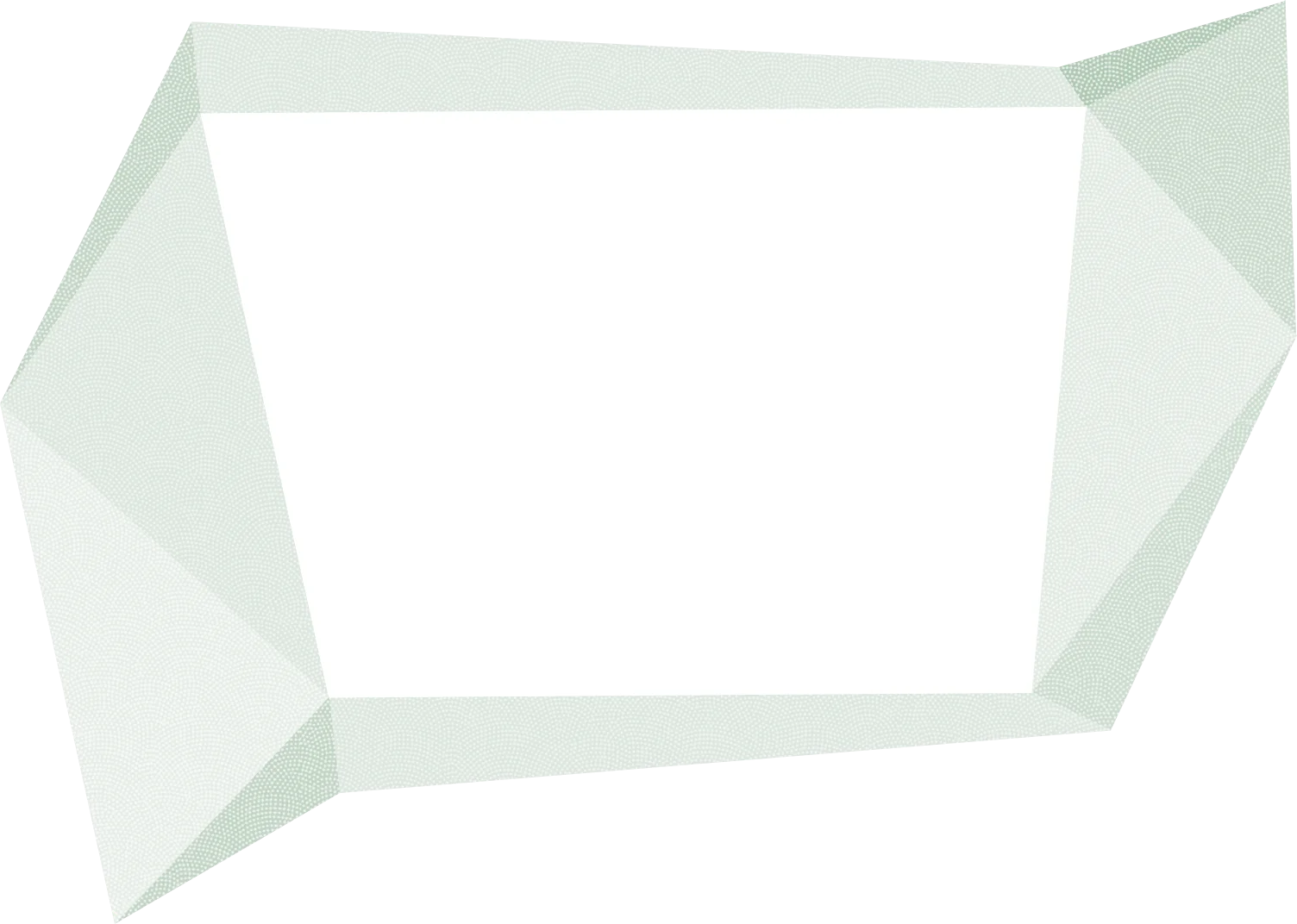今回の二年振りの帰国による日本での山歩きは、ハードルをちょっと上げ過ぎたかと危惧される、正直なところ、恐るおそるな試みでした。エベレスト登頂体験を持つ若く熟練した山岳ガイドが同行してくれているとはいえ、自分の身は自分で運び上げなければ登山にはなりません。体のあちこちの不具合はもちろん、78という年齢ならばなおさら、よせばよい愚行にもおちいりかねない不安を交えたチャレンジでありました。

その山行を結論から述べれば、なんとも表現が難しいのですが、ひと皮むけたとか、一段ステージを上げたとかと言えるかの、まったく新たな認識次元への到達でした。
それはまた、自信を取り戻したと言えなくもないのですが、そうした過去を尺度としたその残存具合というより、むしろ、これまでに体験したことのない、新規な自己安息の境地です。
ひらたく言えば「捨てたもんじゃない」と希望を抱ける、あるいは少々ややこしくには、「老いた経験知に若き行動知が作用して発芽する、〈老若共闘〉が名実ともに実現した」、そういう新次元な領域への至り着きでした。
それは直接的には、もちろん登山体験に根差してはいるのですが、そうした特異体験によるとは限られない、もっと広い人間社会での各分野へとも通じる、新たな可能性の発見でした。

飛行機雲を引きつつ、頻繁に上空を行く旅客機。
そうした今度の山歩きの現地は、残雪にはばまれて予定の一部の消化に終ったのですが、東西に横たわる標高2千メートルを越える、春もまだ浅い、奥秩父連山をゆく縦走路です。
しかもそこは、昼間の登山の際中や夜のテント泊中の我々の頭上を、飛行機雲を引いたりそのジェット機音を闇に響かせたりして、頻繁に旅客航空機が東西に行き交う、まさに日本の幹線航空路を頭上に冠した山歩きでした。
そして、そのようにして地上と上空で織りなされる二様の人間模様は、片や雪中での徒歩行や野外泊の、他は、快適性と機能性の粋をきわめた高空での高速移動という、人間が選ぶまるで異質な行いです。そこでその違いが示唆するものは、まさに天地に広がって展開されている人間たちの営みにおける、〈野性回帰と洗練追求〉という、象徴的コントラストです。
それに私はそもそも、この一時帰国という、赤道をまたぐ南北半球間の飛行移動をもってそこに来てきているものです。そしてこれまでの、幾度ものその上空移動体験が異国間の地上体験をもたらし、それが本シリーズのテーマでもある、〈半分外人-日本人〉という感慨を生んできています。その意味で、この上空・地上といったコントラストはさまざまにミックスし合って、私の人生への特有効果を生んできています。

滑落防止のため、木にザイルを回し、私の危険個所通過を確保するガイドのS君。
そうしたコントラストという観点ではまた、片や78歳という老境に達した者と、39歳というまさに人生佳境にある二者があい携わって、残雪に苦労させられながらも共に山中を踏破してゆく老若の協働が、そこに追求、展開されてもいるものです。
そしてそのようにして苦楽を共にする二者にとって、その数日にわたる共同行動は間違いなく、互いの胸中の交流を果たすに十分すぎるほどの、時間と機会を提供する体験であったことです。
そこでですが、そうして見出された新たな感慨について触れておけば、健康がもたらすものに長寿があるとするなら、それは、長生きをもって古い価値観をより長く誇示し続けることに意義があるのではないでしょう。むしろ、次々と絶えることなく生み出されてくる新たな生命がもたらす新たな価値観に、それだけ長くにわたって接し、理解する、その機会を広げているということにあるはずです。
ゆえにそうした価値観とは、最初からきまったものが存在しているものではなく、新たな環境につちかわれて、新たな生命が作り出してくるものと言えます。
ところでこの山行は、その初日、埼玉県側の三峰口駅の駐車場に車を乗り捨て、地元のバスで川又まで入り、その先の国道脇の登山口より取り付くものです。そしてほぼ南方向に高低差1,500メートルを登りつめ、雁坂峠で山稜に達した後、水晶山(2,158m)、古礼山(2,112m)、燕山(2,004m)を小縦走し、雁峠より山梨県側の新地平に下ったものです。

この縦走路上で度々私たちを歓喜させてくれた富士の雄姿(古礼山々頂上より)
そうしたこの4日間での山中活動では、まるでそれに合わせてくれているかのような快晴の日が続き、その巡り合わせの良さに、心底、感謝したい気持ちでした。そして4日目になってようやく、全天が雲で覆われはじめて風も強まってきました。そこで、まだ食料や意欲上の余裕は残すもののそこを最終日に行程を切り上げ、小雨の降り始める中を山梨側へと下山しました。

このくらいの雪はまだ浅いほう。
当初の計画では、東京都の最高峰、雲取山(2,017m)に至る縦走を考えてはいましたが、それは無雪期のコースタイムをベースとしたものです。それが実際では、残雪が足首から膝ほどまで――吹き溜まりでは太ももまでも――の深さで私たちの進行をはばみます。また、野生動物の足跡以外にはまったく踏み跡がないバージンな雪面のため、ルートファインディングになかなか神経を使わされました。おかげで、それぞれの区間に要した実時間は、地図が示す各標準タイムにくらべ、その3倍から4倍を要する難儀さとなりました。
そのようして、私たちに許された全行程を終えて無事、下山したのですが、その下界で出くわしたものは、越えてきた山々の真下をくりぬいたトンネルの出入り口でした。
そうして下山を終えた私たちには、まずは、乗り捨ててきた車を回収せねばなりません。そのため、山梨、東京そして埼玉と、地域全体を延々と遠回りしてそこに戻る必要がありました。しかし、昔のことならともかく、今日にあってもそうするのは考えものでした。そこで今や可能となっている最短距離の帰路をとることとし、このトンネルを抜ける車のヒッチハイクを試みたもののあいにく捕まらず、やや出費はかさむものの、地元のタクシーを呼んで、はるばる越えてきた山々の反対側へと戻ることとしたのでした。
このように、この絶妙の山歩き体験――恐らく私にその再度のチャンスはないだろう――を与えてくれたこの地は、空には東西の幹線空路が走り、地上では、かつて秩父と甲斐を結んだ「秩父往還」の難所の峠越えが、今では南北6.6キロの長さの雁坂トンネルによって文字通り最短、水平に結ばれていて、まさに現代技術の粋として、そうした地理的条件を縦横にかつ立体的に克服し、私たちにその利便の使用を誘いかけていました。
かくして、私たちの徒歩行という古めかしくも生身な身体活動は、この天地にわたる現代技術のもたらす機能的交通体系の効用とあいまって新旧両界体験となり、まるでタイムスリップとの解釈すらも可能な、異次元な発想へとも高揚させてくれたのでした。
こうして3泊4日を要したこの山行は、時代的にも地理的にも技術的にも交錯した、特異な体験を味合わせてくれたばかりでなく、そこでそう行動した人間たちに生じさせる効果として、老若の交流と共闘が実現するという、マルチ次元な成果をもたらしてくれたのでありました。
それはことに、不安のうちこの山行に挑んだ私にとっては、年齢という固定観念にいまにも縛られそうであった場からの脱出劇がもたらしてくれた脱皮感と、その果実としての新たな可能性が見え始めるという達成感に彩られて、未来的な視野を開いてくれる、老境ながらの実に貴重な体験となったのでした。

早春の朝を迎えた雁坂小屋
【ご 案 内】
当山行記中の山岳ガイドにご関心がおありの際は、山登りガイド、講演、技術指導などなんなりと、下記の本人まで連絡をください。
市川高詩 通称「シカオ」
連絡先:070-8304-0449
ウェブサイト:高詩 シカ男 / 七大陸最高峰を目指す(@takashikao)
彼は、世界一周の自転車旅行を通じて、世界7大陸の全最高峰の登頂をめざしています。すでに6峰は登頂に成功し、残すは、南極大陸の最高峰(ヴィンソン・マシフ、4892m)のみです。今は秩父の武甲山の麓に居住し、横瀬町の観光課の職員を務めながら、最後のターゲットの達成を準備しています。
〈続き記事〉