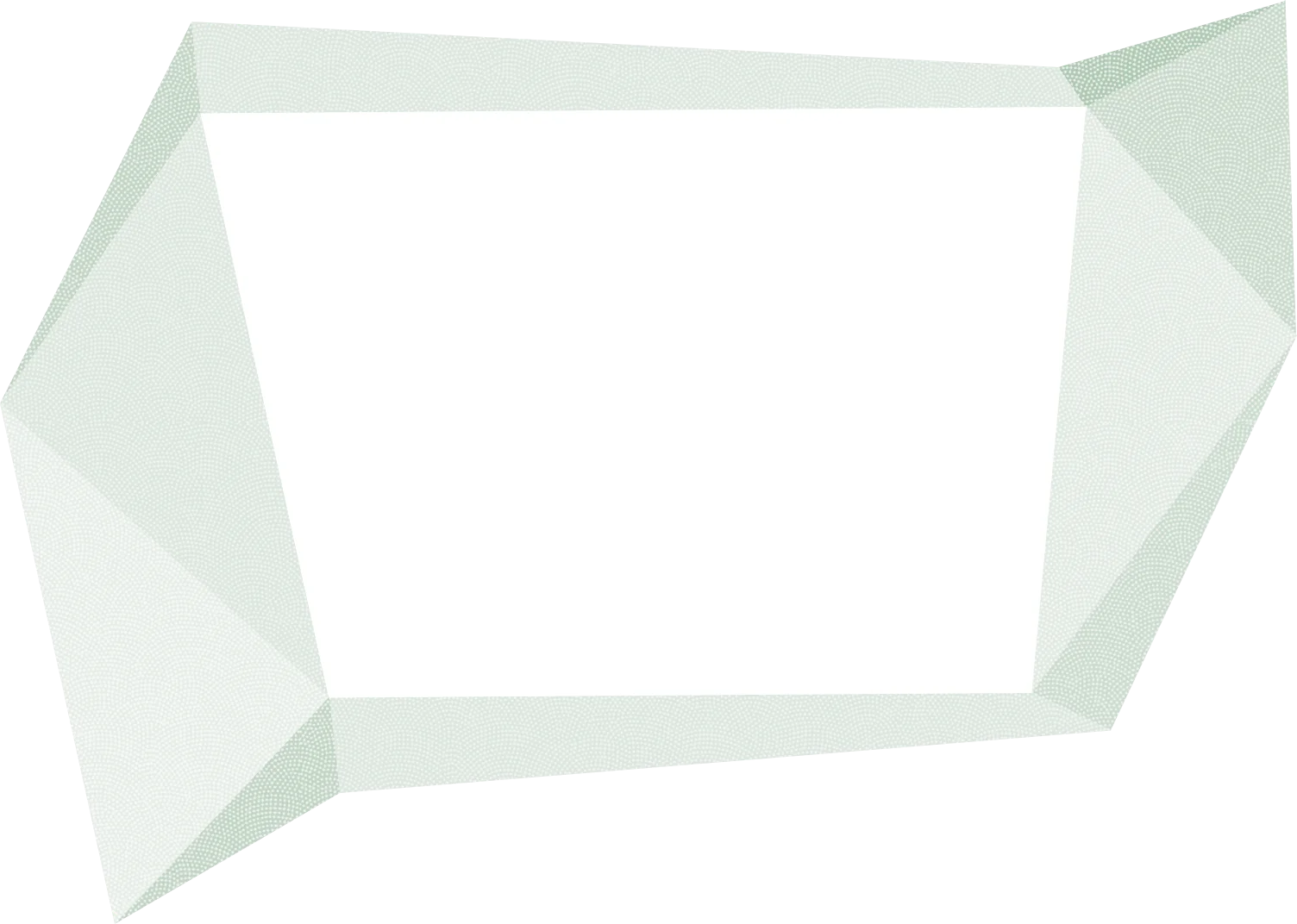前号では、「『AI時代』にあらがう」などと題して、「古き左巻きのツイート」を書きました。
左だろうと右だろうと、生存せねば意味がない以上、世界ではその純粋「左傾」国家は独自の変節をとげ、いまやその名残りを冠した独裁国家となるに至って、威勢のよい鼻息をふりまいています。
むろん、その「独裁」には到底なじめるものではなく、いい年となった「古き左巻き」たる孤人は、この怒涛の「AI時代」のサーフィンを試みようとしています。
そんな日々、次第にそのAIたるものの輪郭が判ってくるにつれて、1980年代半ば、PhDにとっかかったばかりの頃を思い浮かべています。いわゆるPC時代の始まりの時期です。
そのPhD作業の「木を見てはいるが森がみえない」苦悶の中で、指導講師がサバティカルで姿を消す間、私は思いついた興味本位の脱線をはかり、「自動論文作成プログラム」なんぞといったものの作成に熱を上げました。
当時、世に出たばかりのアップルが、素人にもプログラムができる「ハイパーカード」といったアプリも出しており、それを使って、曲がりなりにもこの自前プログラムを作りあげたわけでした。おかげで、その後のPhD論文の作成ははかどり、引用文献数の多さも得点となって、無事、学位の取得はうまく行きました。
そうした脱線も含む作業の中で発見したことは、PhD論文の要所は、「問題設定の枠組み」と呼ばれる仮説の存在が重要であることで、論文の中身は、それの立証がなるかならないかの論述作業にすぎないことです。私のそのトイようなプログラムは、その論述作業部分を自動化したものでした。ただ、その作業過程では、自力の文献探索の結果を仮想カードに落とし込まねばならず、あいかわらず、肉体作業で無数の文献にあたり、その結果の入力作業はマニュアルでする必要がありました。
今日、AIがこなす能力は、この論文の論述作業の自動化はもとより、文献探索まで立ちどころにやってくれます。しかも、その探索の範囲は、それこそ世界中の文献を網羅したものです。いうなれば、もはやAIは、PhD学位を売り物とする大学の商売を台無しにするのも同然で、いわゆる博学といわれる人的存在は、いとも容易にAIに取って代わられてしまうでしょう。つまり、お偉い教授方は、生涯積み上げてきたその知的蓄積の価値や規模をめぐって、その面でAIと勝負せねばらないということです。
ただ、相変わらず残っているのは、AIは最初、質問を与えないでは動き出してくれないように、「問題設定の枠組み」の役割の重要さです。つまり、AIの能力の発揮の度合いは、いったん質問として与えられるその内容いかんということです。
AIは、その質問は自分では出さず、それほどの能力を持ちながらも、「疑問」は抱かない存在です、いまのところ。
私は、AIを動かしているアルゴリズムの内容については完璧に門外漢です。数理的論理構造のあれこれとは理解していますが、そんな抽象的理解程度です。
そうした理解の限りですが、この「疑問」という働きについて、AIが、つまり、数理的論理構造がそれをもてるのかどうかについては、大いにこれも「疑問」です。
つまり、「疑問」とは、生きた人間が見出す、自分の感じることとそれが現実に在ることとの食い違いに発するものです。
つまり、その「感じる」という働きがその原点に存在しています。
AIは、この「感じる」ことができるのかどうか。むろん、人間が「感じる」という時、それは、物理感覚的な感触だけでなく、情理的な感触も含んでの「感じる」です。
AIは、その物理的な入力はしえても、情理的な入力については、そもそも、その情理たるものがアルゴリズム化されるものかどうか。
よく、AIは「心」を持っているかと話題となりますが、私の考える「心」というものは、アルゴリズムという測定可能数量から成り立つシステムの圏外の、それこそ、生命の謎にも関係している、命ある分野に発すると考えています(詳しくは兄弟サイト『フィラース 』の諸記事参照)。
以上のような観点から、私は、まだまだ、この情理や心の分野における人間の役割は揺るがないとの認識をもって、AIがもたらしているその“超”博学な知力には「あらがう」ことなく、その他方、人間としての「疑問」を大いに駆使してゆこうと思うものです。