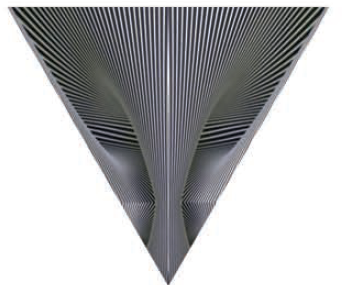なあ、これはMATSUの持論――「《し》は通過点」――にもからむ話だが、それをちょっと別の角度からアプローチしたい。と言うのは、いま俺がここに来て残念に思っていることのひとつ――これはその内でもことに大事なこと――だが、いわゆる晩年にさしかかった自分が、あるバランスある視野を持てず、無念なことに――まあ常識的でもあるんだが――、老境と終末の感覚にとらわれたまま、ここに来てしまったことだ。
その説明のために、ちょっと回り道を許してもらいたいのだが、これは誰しもそうだったと思うが、若いころにはよく、いわゆる《理想と現実》のジレンマに悩まされたもんだ。そしてその悩みは年齢を加えるにつれ、人生経験によろしくもまれて鍛錬され、《観念と因果律》の対立にも至った。そしてさらに、それを人間社会の制度や概念上の対立項として集約すれば、《宗教と科学》とさえ規定しうる人間社会の最大の詰問にまで発展してきた。そうした、結局、解決にはほど遠い地球的問題を置きっ放しにしてきた、などとほざけば誇大癖すぎるが、せめて、俺の「残し忘れてきた遺言」くらいの気分は持っている。 詳細記事 →
シンボルあるいは象徴を、この章に論じられているほどに受け止めることは、正直なところ「考え過ぎ」とか「こじ付け」ではないか、と思わせるところがあります。しかし、例えば英語には「numerology」(数秘学)といった用語があるように、数字占いの意味付けとなる数字の謎をさぐる研究分野があります。言ってみれば、数学だって、そうした関心を出発点としてきた経緯があるのでしょう。だが現在では、それは科学扱いはされてはいません。本書を含む二部作のテーマである「エソテリック」も、科学界からは、せいぜい「疑似科学」としか扱われていない分野です。
しかし、もし科学を、科学となしえるために不確かな部分を切り落とした骨格のみだと見なすなら、その血や肉についての考察は、すくなくとも可能性として、科学の未開拓分野を含む、将来的なエリアと言えなくもないでしょう。
個人的関心ですが、そうした「考え過ぎ」と「深慮」間を往復させられる運動が、本書を訳読している面白味です。 詳細記事 →
| == 本書の《もくじ》へ 「もくじ」の中の《本章》へ == |
聖なるシンボル(その1)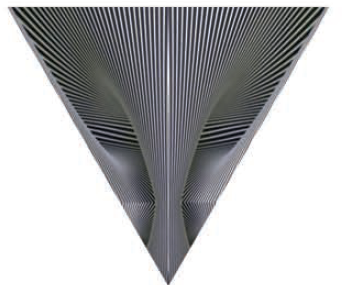
「地球上のすべての現象は象徴的であり、各シンボルは開かれた門で、魂の準備が整っていれば、世界の内部へと入ることができる。そこは、あなたも私も、昼も夜も、すべてが一体である。」 ――ヘルマン・ヘッセ(ドイツ人作家)
聖なるシンボルは、宇宙の言語である。それには、実際に我々が誰であり、人類や細胞分裂や多くのイメージの根底にある幾何学が何であるのか、その謎を解く力がある。その隠された意味は、各時代を通して、画像、神話、民間伝承、そしてシンボルを使用した神秘主義者によって明らかにされてきた。幾何学の母型と印は、完璧に完全で、不変で、時間を越えた現実性をもって、「神の心」から直接に表出してきている。宇宙は振動であり、これらの聖なるシンボルの原則はすべて、振動である波形現象に直接対応している。科学は宇宙が振動であることに同意している。聖なる幾何学とシンボルは、視覚、時間、宇宙次元での振動として見ることができる。 詳細記事 →