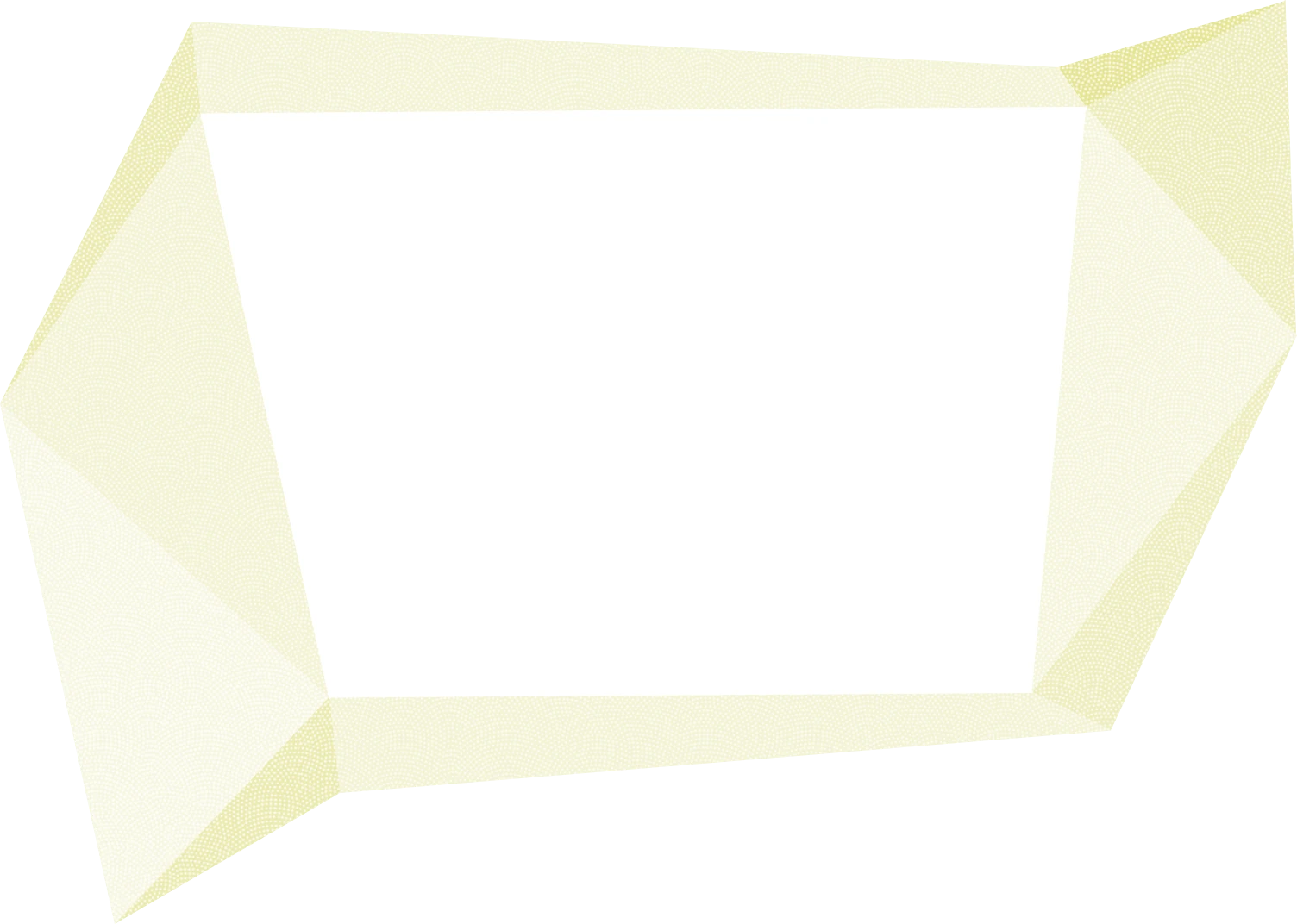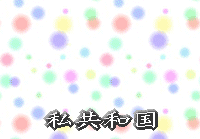5月22日〈木〉
昨日は、ビシュケシュを出て、キリギスの最大の湖、イシククル湖に向かった。予定していたバスは使えず、宿の主人の紹介で、安くタクシーが雇えた。所定なら5~6時間のドライブなのだが、道中のあちこちで道路工事が行われていて、時間を食わされた。おかげで8時間近くも要して、湖の東端の町、カラコルに到着。さすがに疲れて民泊宿に着いた。
このイシククル湖は琵琶湖の9倍の広さを持ち、東西に180キロ、南北では最大70キロの規模。水面標高は1,607メートル。それを、東西に陸路で縦断したのだから、時間を要するのももっとも。
なおこの湖、ソ連時代には魚雷兵器の試験場があったため、外国人の立ち入りはできず、世界からは閉ざされた幻の湖だった。
このカラコルという町は、天山山脈の巨大な盆地に水をたたえたようなこのイシククル湖の東端に位置し、見たところまだその端緒に着いたばかりのようだが、登山とスキーのメッカのような町だ。ちなみに、天山山脈の最高峰ポベダ山(7,439m)登山にはこの町が基地となる。
湖の南側には、天山山脈の万年雪をいただいた7000メートル級の峰々が、見渡す限りに波を打つように連なっている。
地理的位置関係を言えば、先のアルマティ市の南側の山脈が、このイシククル湖の北側に横たわっていて、そしてこの湖の南側の天山山脈の主脈を越えた向こうが西域中国および北インドとなる。あの三蔵法師はこの湖を経てインドに向かったという。
-
ご存じ、三蔵法師こと玄奘は、仏教の原典に基づいて研究しようと志し、独力で629年に長安を出発し、艱難辛苦しつつ新疆ウイグル自治区の天山北路―トルクメニスタン―アフガニスタンからインドに入り、ナーランダー寺院(那爛陀寺)でシーラバドラ(戒賢)に師事して学び、インド各地の仏跡を訪ね、仏像・仏舎利のほか梵本657部を携え、645年に長安へ帰った。
私たちが目にしているこの光景を、1,300年前、三蔵法師も見ていたのかと思うと、勝手ながら、因縁のようなものを思う。
この町に三泊して、付近の山々のトレッキングに挑む予定にしていたのだが、宿のインターネットが故障中で使えず、ブログ作業がでず、それに宿主の態度も横柄。やむなく、この宿には二泊に短縮することに。
そこで貴重な一日、地元のバスで山懐まで入り、せめてもの山の味をかじる。峡谷には、氷河に発する薄い白乳色の水がとうとうと流れ、谷間には温泉が湧き出ており、数件の貧相な温泉宿がある。ところが、温泉につかるのは水着必着で味もそっけもない。日本なら抜け目なく結構な温泉地帯になっているだろうに。

町の背後にそびえる天山山脈の一部のカラコル山(5,216m)
5月23日〈金〉
カラコルの宿を朝8時過ぎに出て、次の宿泊地カジサイに向かう。その途上、乗るバスの出発場を確認のため、インフォメーションセンターに行く。そこで出会った地元の婦人が親切に、自分の車でバス発着所まで送ってくれる。
このカジサイという小さな町は、イシククル湖の中ほどの南岸すなわち天山山脈側にあって、太古より氷河によって押し出されてきた厖大なモレーン丘の縁に位置している。町の前は湖のビーチとなっていて、夏には海水浴場になるようだがまだシーズンではない。
ビーチに出て透明な湖水をすくうと、ほんのり塩味がする。というのは、同湖は流入する川は数えきれないが、流出する川がなく、湖面のバランスは、蒸発によって保たれているからである。あと何万年、何億年もすれば、人間による汚染が起こらないとすれば、立派な塩湖に成長しているだろう。

背後の万年雪をいただくのが天山山脈、手前の褐色の丘が氷河モレーン。
5月24日〈土〉
朝、カジサイを立って、再びビシュケシュへ向かう。
昨夜の雨が上がり、空気中の塵が洗い落されて遠望がきく。背後の天山山脈が雲間に姿を現す。

雨上がりの雲間に姿をあらわした天山山脈

丘の上に何やら看板がある。よく見るとソビエト時代の名残り、レーニン像。
バス停で待っていると、通りかかったトヨタ、エステマが止まり行き先を聞いてくる。いわゆる乗合タクシーだ。交渉の結果2,000ソム(3,500円)でOK。距離は300キロをはるかに越え、行き先のゲストハウス門前までの料金なら格安。
タクシーは乗り合いなので、途中、いくつかの村に立ちより、人だの荷物だのをピンポイントで拾いに行く。住民の必要に臨機応変に応えるスマホを駆使したビジネスで、辺ぴな村のおばさんがスマホ片手に荷物をかかえて乗り込んでくる。全部の料金を合わせれば、運転手の収入は、我々の払った料金の数倍になるだろう。

対岸は、雲か雪山か見分けがつかないのだが、アルマティ市の背後に位置していた4,000メートル級アラタウ山脈の反対側からの姿。
途中に立ち寄った小高い山麓の村からは、イシククル湖の対岸の山脈が見渡せた(写真上)。
タクシーの車窓から見える風景は、見渡す限りの荒野の向こうに、すそ野の引く扇状地を形成した背後に、高々とそびえ立つ天山山脈のうねる山並みが行けども行けども続いている。標高1,000メートルほどの高原の向こうに、雲以外に何も遮るものがなく、6~7,000メートル級の峰々が天を突くように波打っている。こんな雄大な景色に毎日接していれば、こまごましたことなぞ気にしない気性が育っても無理はない。
到着したゲストハウスのあるビシュケシュ東北地区は、大きなモスクもあって、イスラム風俗が目に付く。時もちょうど昼時で、あたりにはコーランの祈りの声が響いていた。
5月25日〈日〉
 ビシュケシュにて、ゆったり日。午後、市内のバザールにて買い物。と言っても、当面の食品だけなのだが、そこで面白いことが起こった。露店で野菜を売っている兄妹からトマトをキュウリを買おうとしたのだが、細かい札がない。そこで、おつり分でイチゴを買おうとした。すると、イチゴはプレゼントだといって、1キロにもなるだろう量を袋に入れて私たちに手渡してくれる。それどころか、トマトとキュウリをさらに一個ずつ加えて、それもプレゼントだという。どうしてそんなに気前がいいのか、訳が分からない。ちなみに、我々が何人かと聞かれたのはすべてが終わった後のこと。したがってこのプレゼントは、我々が日本人であったからということではない(写真右)。
ビシュケシュにて、ゆったり日。午後、市内のバザールにて買い物。と言っても、当面の食品だけなのだが、そこで面白いことが起こった。露店で野菜を売っている兄妹からトマトをキュウリを買おうとしたのだが、細かい札がない。そこで、おつり分でイチゴを買おうとした。すると、イチゴはプレゼントだといって、1キロにもなるだろう量を袋に入れて私たちに手渡してくれる。それどころか、トマトとキュウリをさらに一個ずつ加えて、それもプレゼントだという。どうしてそんなに気前がいいのか、訳が分からない。ちなみに、我々が何人かと聞かれたのはすべてが終わった後のこと。したがってこのプレゼントは、我々が日本人であったからということではない(写真右)。
ともあれ、売り切る事情はあったのだろうが、こちら側としては、大歓迎のハプニングだった。ところでこのイチゴ、小粒なのだがとても甘かった。
今日はこれから、宿を出て、夜行バスの乗り場に向かう。10時間はかかる長旅だ。明日朝には、ウズベキスタンのタシケントに着く。
5月26日〈月〉
昼間は、宿の庭のあずまやでゆったり過ごし、午後、7時発のタシケント行きの夜行バスに乗るため、ターミナルへ。
このバスは、二度の国境越えをする面倒な便で、距離650㎞を正味時間では8時間ほどで行くのだが、国境越え審査を含めて合計すると、何時間になるか予想が付かない。先に逆コースで来た人の話では、一つの国境越えで4時間もバスを待ったという。
ところで、当ビシュケシュ市街は、古い型の車やトラックが数多く走っていて、排気ガス規制が無いも同然。周囲にはこれほどの広大な大地に囲まれていながら、環境対策はかえって甘い。おかげでノドをやられて、咳とタンがしつこい。そのため、風邪をひいたような症状で、体調がすぐれない。それでこの長旅に耐えられるが懸念となった出発だった。
最初のキリギスからカザフスタンの国境は最短時間で通過できた。ところが案の定、二度目のカザフスタンからウズベキスタンの国境は、国境の両側に、長い車の列が見られ、その最後尾についた我々のバスがやってきそうもない。こそで、乗り合わせた4人で、国境からタシケントの市内までタクシー(一種のウーバー)でゆくことにした。幸い、ウズベキスタンの物価は驚くほどに安い。この20キロほどのドライブが40,000ソム(約400円)というから驚き。市内到着後に飲んだ朝一のコーヒーが、一杯25,000ソム(約250円)だったので、なにやら、物価のバランスがおかしい。
5月27日〈火〉

壁に飾られていたタペストリーとドライフラワー
こういう次第で、えらく疲れはしたが、さいわい大した支障も起こらず、昼前、無事にタシケント中央駅に近いゲストハウスに到着した。
自宅を改装した民泊で、相変わらず言葉はよく通じないが、なかなかセンスのある宿。宿の女主人が親切。
換金のため銀行を探したが、スーパーの一角のATM機器でそれができるという。米ドル札を差し込むと、相当の現地通貨が出てくる。身分証明もいらぬ容易さに、あっけにとられる。
5月28日〈水〉

タシケント駅に飾られた陶製の壁画
ウズベキスタンの首都タシケントは、けっこう近代化された都市で、道路も広く、大気汚染もさほどは感じられない。地下鉄も整備されていて、各駅のつくりが、名物の陶器をあしらった美的なもの。日本の宣伝だらけの地下鉄に比べ、それほども混まず、片道数十円の乗車賃で、これが運営されている。
その地下鉄にのって、東洋一というバザールへ。もう広すぎてとてもじゃないがまわり切れない。途中、休憩をしようと庭園の木陰に入ったのだが、そこは地元陶芸品の展示販売館。日本の陶器とは大いに趣を異にする 作品におもわず見入った。
5月29日〈木〉
今日は全日の移動日で、まずタシケントからサマルカンドまで3時間半の鉄道の旅。日本の在来線の感じで、家族連れやら商用客やら、現地の庶民にまじっての旅。客車の通路を、乗客の幼児たちが社内販売員の足元を駆けずりまわる。通路を隔てた隣のおばあちゃん、そんな子供たちをとうせんぼして笑顔。誰も子供たちが迷惑だなんて言わない。
サマルカンド駅に到着後、その足で乗り合いタクシーを使い、タジキスタンとの国境へ。越境手続きの後、山間の町パンジャケントへ。
この国境、小国同士のためなのか、これまでで一番簡素なもので、手続きも物々しさがなく、なんとものどか。日本の県境が国境となったら、こんな感じなのかも。
5月30日〈金〉
この山間の町パンジャケントは、乾燥地帯と山岳地形とが一体となった、日本にはちょっと類例の見られない地方小都市である。加えて、イスラム文化色の濃い、保守的な雰囲気を漂わせ、なんとも古式ゆかしい田舎町。

はげ山同然の山体に、亀裂のように深く峡谷がえぐられている
それだけに自然資源は豊富で、町の産業は観光ビジネスに頼っている。マンション工事もあちこちに見られ、経済は順調のようだ。
そんな町に投宿しながら、そうした観光に関心のうすい当方、長旅の後の休養と決め込んだ。
この中央アジアという、まるで肉食中心の世界で、魚料理から遠ざかって久しい。そこに、町外れの大きな川の岸に川魚料理店があると聞いていさんで出かけた。
 その川魚とは、マリンカと呼ばれるマスに似た魚で、肌がつるつるとしていて鮎のようでもある。サイズは10から30センチほどといろいろ。それをいったんグリルし、そこにポテト、トマト、オレンジを加えニンニクの利いたオイルで料理してある。泥くささを抜くため、清水でしばらく泳がせてあるともいう。久々の魚との当方の弱みを減点しても、じつに美味である。デザートにチェリーが山盛り。ただし値段はちょっと高い(ビール1本入れて2人分で2,700円ほど)。
その川魚とは、マリンカと呼ばれるマスに似た魚で、肌がつるつるとしていて鮎のようでもある。サイズは10から30センチほどといろいろ。それをいったんグリルし、そこにポテト、トマト、オレンジを加えニンニクの利いたオイルで料理してある。泥くささを抜くため、清水でしばらく泳がせてあるともいう。久々の魚との当方の弱みを減点しても、じつに美味である。デザートにチェリーが山盛り。ただし値段はちょっと高い(ビール1本入れて2人分で2,700円ほど)。
木立に囲まれた広々とした苑内に、ガゼボが点々と配置されていて、その一つひとつが、いわば解放された個室である。なんともくつろいだ気分となって、そこで昼寝したくなる。
5月31日〈土〉
この町パンジャケントは、背後の丘陵地に古代パンジャケントの遺跡を残しており、世界遺産に指定されている。その頂上からのパノラマは素晴らしく、周囲の山々を一望できる。


古代遺跡のはるか後方に、ファン山脈の峰々がそびえる
6月1日〈日〉
今日は、パンジャケントから、タジキスタンの首都ドゥシャンベまで、450キロのドライブの旅。合乗りのタクシーを手配、地元の老御夫婦との4人で、天山山脈の支脈、サン山脈を越える移動。
天気も申し分なく、私は子供のように、車窓に展開される山岳風景に目を奪われた。行く国道は、ザラフシャン川をさかのぼりって東へ向かい、200キロほど行ったところで南折し、その支流を詰める。ハイライトは延長5キロの峠越えのトンネル。その長いトンネルを抜けると視界が一気に開け、車を止めてもらって雄大な景色に見とれる(写真)。

中央右手の高峰が、サン山脈最高峰のテムタルガ山(5489m)。
このザラフシャン川をさかのぼる車の旅は、パキスタンのカラコルム山脈のフンザ渓谷をゆく旅に似たところがある。距離にしても同じくらい。ただ、フンザ渓谷の場合、両岸に迫る山々が7~8000メートル級で、その高度上の圧倒さには見劣りがある。
いよいよ、アフガニスタン入り。ともあれ、なにが起こってもおかしくない場への移動に、緊張満々の日となる。

荒涼とした“国”外れ。はるか向こう側がアフガニスタン
朝6時、ドゥシャンベの乗合いタクシーのターミナルで、昨日街で合流した別の日本人2人と合流、くわえて2時間半後、国境の関門で、さらに日本人4人のグループと合流、にわか仕立てながら、総勢8人のアフガニスタン訪問団となって、タジキスタン・アフガニスタン国境を越えることとなった。
我々以外の6人は、いずれも旅慣れた30代から50代の人たちで、難関アフガニスタン入りを計画していることを事前に互いに知り合い、現地集合となったもの。
9時、越境手続きが始まり、結果的には、丸一日を要したアフガン入りとなった。
幅1キロはあるだろう、大きな川が国境となっており、その手前のタジキ側での出国はさほど問題はなく、その後、往復する車にそれぞれ乗り込んで橋を渡り、アルガン側の検問に到着した。
さあ、これからが、ほぼ午後4時にすべてが終了するまで、7時間余りを要する延々たる手続きの始まりとなった。
その詳細をいちいち述べないが、見渡す限りに広がった乾ききった荒野に建つ数件の建物のうち、主手続きをする事務所の前の大きく枝を広げた松の木の木陰で、地面に敷かれた6畳ほどの絨毯の上で、一行8人は、まるで効率性など無視した、遅々と進められる越境地発行の入国ビザを得る手続きを待つこととなった。
すべてが完了して自分のパスポート上に張られたビザ証を見ると、もう十数年前に使われていたものと用紙も様式も字体も瓜二つなシールだった。それを印刷するプリンターも同様に古さのもので、要するに、同国外務省の国境管理上のシステムは、先進国の十数年前のものを踏襲して動いていた。
その事務所でビザの発行を担当しているのは、三十代後半の二人の官吏で、一枚のシールを完成させるために、少なくとも各30分は要して、それを行っていた。また、そこまでに行くにも、所定費用を払ったという証明書を現地銀行から得るため、最寄りの町までタクシーで往復し換金、支払い、加えてその間、所定の煩雑な文書記入せねばならない。今なら多くの国では、すべてがオンラインですませる。想えば昔、国によってはわざわざ大使館まで出かけてビザを得ねばならないことなどは常識でもあった。それを、このようやくにして平和をとりもどした貧しい国は、訪れてくる外国人のため、国境でのビザ発行までして、懸命に歓迎しようとしている。ちなみに、この現地ビザ発行を許しているのは、主には途上国のみのようで、そこに先進国は含まれていない。日本はどうも例外のようだ。だとすると、この日本人への特別扱いは、何を意味するのだろうか。私見だが、少なくとも故中村哲さんのお陰であることは間違いないと思う。
興味深かったのは、私たちのビザ発行は最後となって、それを最後にこの日のビザ発行事務は閉じられた。その発行作業が完了した時、一人の官吏は私たちに、今日の宿泊地クンドゥズまで自分の車で送ってくれるという。それからタクシーを呼んでこの町までゆくのもまたひと手間かかる作業である。そこにこのオファーは実にありがたい(なお、そこでのお金の遣り取りついて、こうした場面ではそれをするのが私たちのポリシーである)。
そこでなのだが、この官吏は、目のきれいな好感のもてる人物で、育ちもいい人らしく、英語ができ、車中では、携帯で写真を見せながら、自分が3人の子の親であるなど、親しみのもてる会話を交わした。その中で、彼は日本で自分と同様の仕事をしている人の給料はいくらかという。しかも、自分のそれは、月150米ドルだと白状しながら。
これは私の持った印象だが、日本に「おもてなし」という来訪者への配慮があるように、どうやらこのアフガニスタンという国にもそれがあるようだ。それが、大国のエゴにもまれもまれて、これから見てゆくのだが、この貧しい現状となっている。
クンドゥーズ市は 大きな盆地の中にある。 この盆地には南から クンドゥーズ川 、東から ハーナーバード川 が流れてきて、 砂漠 の中に広大な オアシス を形成している。
6月4日〈水〉
クンドゥズからアフガニスタン首都のカブールまで約300キロ、計画では6時間の移動の日。ところが実際は大違いとなった。
まず、昨日発行されたビザに政府のスタンプを得るため、まだ設置されて2か月という街外れの新築のオフィスを訪れる。役職名はわからないのだが、日本なら外務省地方事務所長といったところか。立派な執務室に通され、彼のサイン付きのスタンプをもらう。その際、たかが旅行者に過ぎない人たちにそのように直接会い、お茶や茶菓子も出され、ここで交わされた会話も打ち解けたものとなった。彼が余りに若いので年齢を訪ねるとまだ20歳代だという。見るからに賢そうな人物で、新たな政府の一翼を担う意気込みや人材配置を感じさせられたひと時だった。これは勝手な想像だが、日本の明治維新の頃、やってきた外国人の抱いた印象も、こんなものであったのではないかと思った。
その後、乗合いタクシーで昼12時に出て、カブールに到着したのは午後10時、所要時間は10時間。ネパールでもそうだったが、インフラ整備のすすんでいない途上国の悪い道路事情の下では、よくある大誤算。
乗った乗合いタクシーはトヨタのカローラ。それに大人4人と運転手が乗り込んでの10時間はきつかった。
ただ、乗り合わせた二人のうち、私の隣のアフガン男性は、なかなか隣人にも気遣っている 様子で、スマホの翻訳を使って話しかけてくる。その現地語からの邦訳は時に意味がつかめぬものだったが、そのなかでナカムラとの日本名がある訳があった。確かめると殺された中村医師のことで、彼はそれをわざわざ告げようとしていた。

トンネルの標高は3,363メートル。背後の山稜は4000メートルに近い。入口のアーチの文字には、「アラー以外に神は存在せず、モハメットはアラーの使徒である」と読める。
この道中には、標高3千メートルを越えるのサラン峠越えがある。そして峠には延長2,600メートルのトンネル(1960年代にソ連の援助で建設)があるのだが、内部は狭く二車線がギリギリ、しかも大型トラックの排気ガスやほこりでほとんど視界が効かない。
ともあれ、このアフガンの運転手の運転はほとんど神わざ。平地の比較的整備された箇所では、上下二通の道路は事実上3車線で、センターラインをまたく真ん中の車線は両側からの追い越し車線。そこを最高では130キロの速度で追い越しを掛け、正面衝突寸前のタイミングで対向車をかわす。それが山道にかかると、ほとんどがセミトレーラの大型トラックが、のろのろと登っているため、小型車はその車間をぬって追い越しを掛ける。遅いトラックを追い越しているトラックにさらに追い越しをかけ、対向車が来ると反対車線の向こう側の路肩までを走る。ともかくハラハラのしっ放しである。
このサラン峠を越える交通量は、それこそハンパではない。国の南北を分ける山脈を横断する幹線道路で、登りも下りも、列をなす大型トラックは、視界の限りにつづいている。そこにバンクや故障したトラックが道をふさぐと、その長蛇の車列はとまったままとなっている。
6月5日〈木〉
到着したカブールは、道中の暑さからそれを覚悟をしていたものの以外に涼しい。それもそのはず、カブールの標高は1,791メートルで、いわば高原都市。
その初めて訪問のカブールで、想わぬ出会いを得ることができた。Tの職場での同僚であるアフガン出身青年が、その家族を紹介してくれたからだ。
今日、初対面かつ外国人の私たちを自宅にまで招いてくれて、手厚い昼食までも振舞ってもらえた。そして、それぞれの家族メンバーのあらまし紹介に始まった、互いに打ち解けた歓談から、今後当地を訪れた際にはホテルなど使わず是非とも自宅に泊まって欲しいなどとの歓待にいたるまで、まるで、旧知の友人ができたかの関係が作られたも同然の発展となった。
かくして、一般に報道される情勢とは裏腹に、現地の人々の生活の実際の在りようを、そのふところに飛び込め、それを目の当たりにすることがでた。これこそ、世に言うキケンなぞを顧みずにやってきた甲斐というもので、まさしく「一見は百聞にしかず」そのもので、旅とはそもそも、こういうものなんだと思う。
その歓談の中で私は、私がこの旅行の一つのテーマとしている、外から見た日本の実像についての声を聞くことを試みてみた。すると、家族の一人でTの職場の同僚の伯父(下写真右)が「日本は世界で一番の文明国である」と言う。そこでその理由を尋ねてみた。その返答は、「日本ほど、その環境の悪化を克服してきた国はなく世界のモデルである」と、環境保全関係を職務としている彼は言った。

Tの友人の兄(中央)と伯父二人。女性たちも紹介されたが来客の場には姿をみせないのが習慣。
6月6日〈金〉
カブールよりマザリシャリフへの移動日。一昨日よりさらに長い移動に加え、その半分以上が、一昨日の逆向きの移動。
一昨日は、乗合いタクシーに4人の合い乗りで、窮屈でまるで拷問。
そこで今日は、乗合いタクシーながら、乗客は我々二人のみとして、料金は割高になるものの(約1万円)、その道を選んだ。
その道中、路上の関門で、往路より多い、数回のチェックを受けた。パスポートの写真を撮って記録している。その際、ほとんどで、まずは中国人かと聞かれるのが多いのだが、我々が日本人が知ると、とたんに態度を和らげて親しみらしきものを表わす。これは大げさでも手前味噌でもなく、実際の体験である。
この移動、苦痛は改善されたものの所要は11時間。埃まみれでくたびれ果てて宿に到着した。