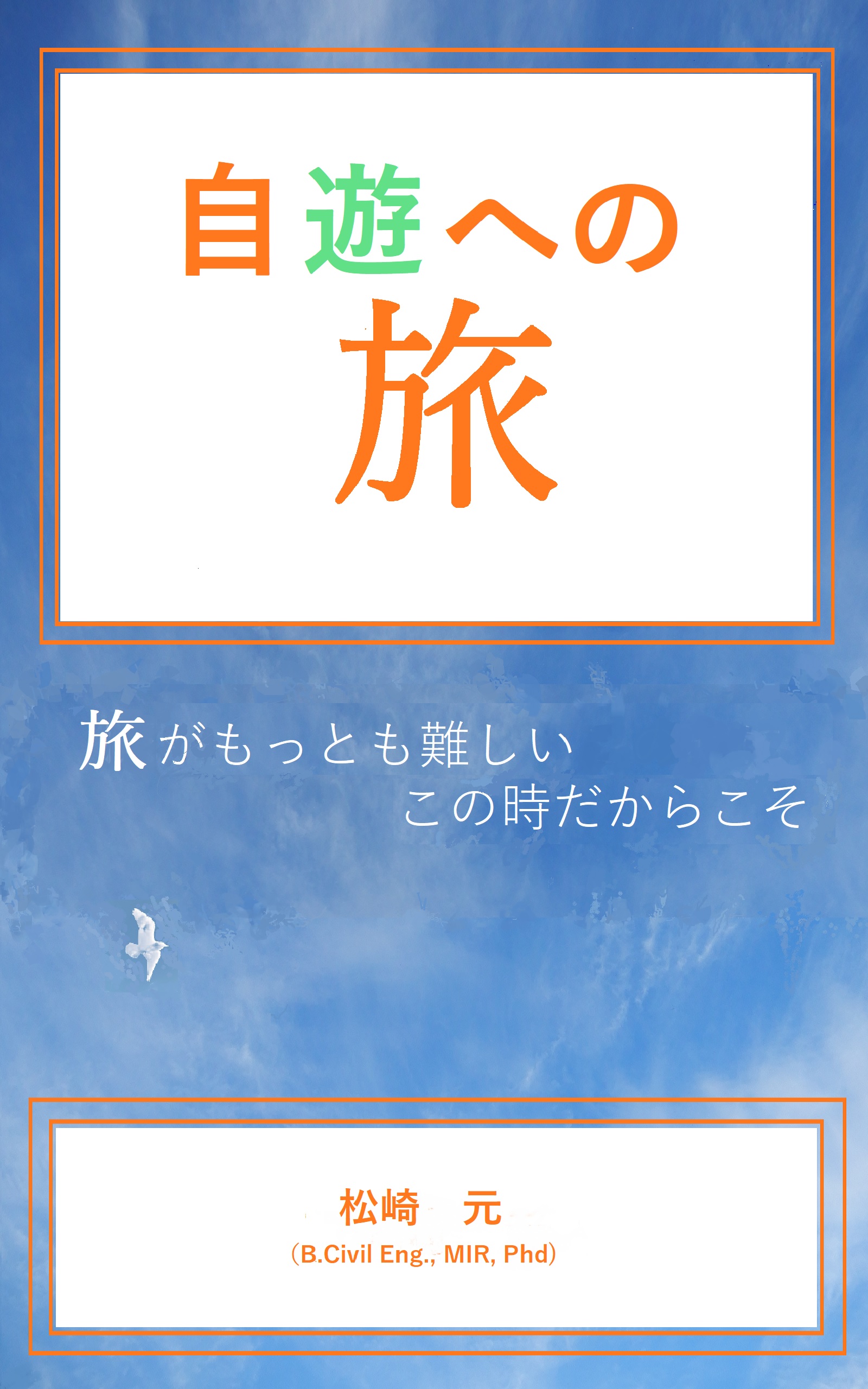
=========
こんな、旅立ちにもっともふさわしくない時に、旅の本を出しました。なぜなら、まったく見通しの立たない閉塞状況だからこそ、扉を開く、旅を必要としているからです。そしてこの旅とは、航空機などに頼らずとも、明日にでも飛び立てる旅です。「ホォー」とでも思われたなら、さあ、ページを開いてみてください。
==============
もくじ
(英訳版)
(各見出しは、その本文へとリンクされています)
|
|
|
はじめに
私はいま、この本をもって、旅への「いざない書」にしようとしています。
ただし本書は、いわゆる旅のガイドブックではなく、もっと違った旅へといざなおうとするものです。
ただ、そうとは言っても、いまや世界はコロナ・パンデミックの渦中にあり、沈静の兆しもなく、まだまだ、先行きの見通せない五里霧中にあります。
そのコロナ禍が、一過的な感染現象で終わるとは、もはや誰にも考えられない展望です。しかも、それがこの先、いったいどのような「常態」をもたらすものなのか、その実相もいまだ不確実です。
そのような時、「旅」なぞと言っても、特例的な再開は別として、短・中期的な見通しとして、コロナ以前のような日常的な旅行熱が、再び大潮流に復活してくるとはとても考えられません。
世界には、すでに数千機の航空機が、地上にただ駐機あるいは引退のうき目にさらされています。こうして立ち消えた膨大な輸送能力、あるいは航空需要が、数年のうちに再現してくるというのも、きわめて望み薄な期待でしょう。
さて、そこなのですが、確かに、世界の旅行産業レベルの実態で見た場合、コロナ禍インパクトはまさに壊滅的で、少なくない事業者の廃業や転業が強いられています。むろん、旅行者側にしても、当面は海外旅行は見合わせ、目的地を近場に代替して時をしのいでいるのが実情です。
だがしかしです。そこが考えどころなのですが、この歴史的な変動期は、それこそ、その「旅」について、あらためて捉え直すには、またとない好機であるのも確かです。そもそも「旅」とは、飛行機が飛ばないからといって立ち消えになってしまう性格のものなどではありません。
逆説などとややこしいことを言う積もりはありませんが、こうした大きな変動状況は、逆に、誰にとっても、安直に選べるものではないが、じっくりと検討し、しっかりと準備を整えた取り組みとして、本来の「旅」に立ち帰るには、むしろ適した状況ではないかと思われます。
ことに私は、この「コロナ閉塞」に遭遇して、せっかく描いてきた自分の旅行計画を台無しにされた、多くの若い世代の人たちを念頭に、それを考えています。
あきらめることなかれ。「旅」とは、これくらいの事で雲散霧消されるものなどでは決してありません。
私はすでに70歳を越え、自分なりの「旅」を行ってきた人間です。しかし、その「旅」が、これまでのような旅行熱に浮かされたかのような、それこそ流行り病同然のものであったのかどうかと自問すれば、それは明快に「否」です。
それに私は、自分の「旅」が完遂したとも、まだ考えていません。後述するように、さらなる次元の「旅」を追求中でもあります。
それにそもそも、人生とは永遠の過客です。
今日の実情は、コロナのお陰で、時間がむしろ豊かに復活した感があり、いわんや、あせった判断によって片付く類の問題に遭遇しているのでもありません。
本書で私が採り上げようとしている「旅」とは、タイトルに掲げてありますように、「自‘遊’」を求める「旅」です。
そこでまず、この「自‘遊’」との語を説明しておきます。
ただし私は、この語そのものに、さほどの重きを置いているわけではありません。むしろその語自体より、その語をもって示唆し、代言しようとしている内実こそが重要で、したがって、それをじっくりと述べてみようとしたいがための本書です。
そのようなタイトルであるこの「自‘遊’」については、「じゆう」と読んでいただきます。そしてその読みの通り、その語感は「自由」に通じるものです。
ただし、この「自由」との語には一般に、すでにありとあらゆる状況とその脈絡により、多様な意味や使用目的が含まされており、そういう意味では“不自由”な「自由」です。
そこで、そうした脈略には一線を画し、私たちの一人ひとりが、自分なりに、のびのびと「じゆう」に鳥のごとく空を翔ぶ、そうした《あらゆる拘束を取り払った》イメージを込めてこの語を造語し、そういう意味をこの語、「自‘遊’」に託しています。
「遊」については、もちろん「遊ぶ」の「ゆう」ですが、この「遊び」が、日本人にはなかなかできない。つい、そうならないよう戒めてしまう。だからこそ、このなんとも切ない習性からも「自由」となるよう、その対極の在り方を志してみようとするものです。
さて、ここでそういう「自‘遊’」を述べる本書のコンテンツについて概観しておきます。
いま、私は、「あらゆる拘束を取り払う」と表現しましたが、そのあらゆる拘束とは、以下のように、私たちの暮らしとは切ってもきれなく、もろもろの場面において執拗に作用している見えにくい宿敵のことです。
そうした「拘束」について、それをいくつかの切り口において見定め、それらから、賢明かつしたたかに、自分自身を解き放って行こうという意味での「旅」を語ろうというものです。
最初に取り上げる「拘束」とは、何よりもの大敵、すなわち、「食ってゆくための」それです。これは、「生存条件」としてそれを捉えれば、ほとんどあらゆるものがそれに含まれるものでしょう。しかしここでは、それを「収入を得るための必要」として、現行の経済システムとの関連で考えます。
第二の拘束とは、第一の経済的、物的なそれと関連し、政治的拘束です。「自由」との用語も、その多くがこの脈絡で用いられています。だが、そうした、多くは見せかけの言葉に、自らを浮き足立たされてはなりません。冷静に自分自身に立ち帰って考え、どういう「自由」が必要なのか、そこに焦点を当てましょう。
第三の拘束とは、学問上のもので、現代の「骨のある」世界観の大半は、この認識において成り立っています。ただ、「学問」と聞けば、日常の暮らしの上では直接の関心事ではないでしょう。ところがそれは、教育において、大きな支配力を振り回しています。そして、その教育を通じて、人為的、組織的に私たちにたたきこまれた枠組みのなす拘束は、実は、これがまた根が深い。
第四の拘束とは、自分の身体という有限性です。誰しも疲労や病気には勝てませんし、さらには、いつかはあの世へとも旅立って行かねばなりません。だからこそ健康が希求されるのですが、私たちにとってそれは、他の何よりも「身近な」拘束になってしまっています。この人生上の《元手》であるはずのものが、往々にして《消耗品》扱いされてしまう裏腹関係が、なかなかうまく舵とれないのです。
第五のそれは、身体上のそれとは別次元ながら、やはり同じく、資源でありつつも障害にもなりがちな、精神的、心理的なそれです。この拘束は、第三の教育上のものとも絡まって、第六の思考上のそれへとも連なります。
第六の拘束は、本書でいう「旅」の地図となるべき、思考上、あるいは思想上のそれで、ある意味では宗教とか信仰上のものとも絡みます。したがって、多くの拘束は、無意識のうちにこの領域に関連し、時には、自作自演の拘束へとも発展します。
第七では、こうした諸拘束を総合し、ことにそれを、個として見る視界と、集団として見る視界の両面からまとめてみます。
以上のよう、その多くはなかなか見えにくいさまざまな拘束を、なんとか乗り越える知恵、そしてその実践プロセスを、本書では「旅」と呼びます。
つまり、本書でいう「旅」とは、生きて行く人生航路そのもののことです。
だからこそ、それは、たとえ百年に一度の災厄に遭遇している場合であっても、それがゆえに断念したり、何かに代替できる筋合いのものなどではないはずです。
むしろ、それならそれとして、そうした格別の困難にいっそう適した特別な対処をもって、腰を据えて取り組まれなければならないことのはずです。
ゆめゆめ、コロナ禍を理由として、「旅」への構想を捨ててはならない、ということです。
そうして、むしろコロナを機会に、拘束というマイナスをプラスに変換し、それを合算、あるいは掛け合わせた時、それはまさに「空を舞う鳥」とたとえるべき、雄大な「旅」となってゆくはずです。
であるがゆえに、本書を『「自‘遊’」への旅』とタイトルを付け、その「いざない書」とするものです。
ところで、私は本書の出版を、冒頭で触れたように、「アマゾン社」が提供しているオンライン出版システムを用いる予定を変更し、自力による出版に切り替えました。
この我流出版法は、コロナ禍の真最中の、それこそ「まったく動きの取れない」状況の中での“苦肉の策”でありながら、ある意味で“正道”への回帰ではないか、と考えています。というのは、とかく敷居も高く、(たとえアマゾン方式だろうと)既成の流儀にも倣わねばならない従来の方式より、そうした枠組みに拘束されずに済む自流の方式へと立ち還り、徒手空拳の者同士のコミュニケーションには、かえって最適なものを築けたのではないかと考えられるからです。
私も――オーバー70ながら――このコロナ禍を好機と考え、本書の出版という新たな「旅」にチャレンジしたのですが、それがこのような“平民的”出版に帰ってくることができ、思わぬ成果を見出せたと嬉しく思っています。
かくして、本書の出版は、表紙のデザインも含め、文字通り誰の手も借りない、自分式の仕事でした。そうして、いまやこういう方式が求められている、そんな時代だと実感している次第です。
1 食ってゆくジレンマ
生存手段確保の鉄則
思い浮かべるのですが、私が、自力での生活を始めたばかりの20代初め、その最大の課題は、何といっても、やや象徴的に言えば、「どうやって食ってゆくか」――より正確には、金のための妥協と自分の本心とのギャップをどう乗り越えるか――との難題でした。
1970年代初頭のその当時、日本経済は好調で、学業を終え就職すること自体には、選り好みがことさらに強くない限り、困難はまずありませんでした。むしろ私の困難は、そうして得た最初の仕事を、わずか半年で辞めた後からのことでした。
仕事を辞める決心をしたその日のことが思い出されます。その朝、ラッシュアワーで混み合う新宿駅で、どうしても仕事場へ向かう電車に乗ることができず、反対向きの電車に乗って、山梨県の山へと向かいました。そしてその電車に乗る前、ホームの公衆電話から親友に電話し、「これから数日間姿を隠す。ちょっと騒ぎになるだろうけど、心配はいらぬ。後をよろしく」と告げて。
今から50年前、当時の社会常識では、一度就職した仕事は一生涯にわたり勤め上げるのは当たり前というものでした。従って、途中で仕事を辞めたり転職することなどは馬鹿な行為で、経歴を傷付け、もちろん収入上の不利ももたらし、社会人として、してはならない行為の典型でした。
ところが私は、そうして半年で仕事を辞めて表街道から脱落し、“裏街道”を迷い始めたのでした。
そうして、一旦乗った安定軌道から自ら脱落するという社会的自損行為を行い、心理的には実に暗澹たる状態へと追い込まれました。もちろん、自分には自分の考えがあったとしても、収入のために自分の労働を売ることが欠かせない以上、「自意識と現実の二重性」に板挟みになる、存在してゆくためのジレンマの大壁を眼前にしていたのでした。
そうした行動には、当時の若者の多くを捉えていた左傾思想が影響していたところはあります。しかし、この「食ってゆく鉄則」に、右も左もありません。
そのようにして、生活のため止む無く始めたその後の仕事は、当時は非合法のヤミの派遣労働で、今にして思えば、技術系とは言え、フリーターの元祖のような働き口でした。
私は、こうした生存手段確保のための拘束の問題を、自ら道を外すという異端なルートを通じて体験し始めたわけでした。当然のごとく、その後は、社会の“裏側”を行く道で、ある意味ではそこでしか見れない光景が見れたわけでした。しかし、たとえ脱落せずに正規のルートに乗っていたとしても、裏表の違いはあるにせよ、同一社会の別なタイプのジレンマを体験していたに違いはないでしょう。
今日では、長年の日本経済の停滞と、まして今度のコロナ禍の衝撃により、その鉄則によるジレンマの度はいっそう過酷かつ、まるで底なし沼同然となっています。
このように、この「食い扶持を稼ぐ必要がためのジレンマ」は、時代の違いを越えた根本的問題であって、世相を反映した特色を帯びつつも、個人の努力ではいかんともし難い、経済システムが故の拘束です。
したがって、ユートピア社会でもこの地球上に実現しない限り、それからの解放はありえません。
そこでですが、確かにそうであはありますが、相対的な努力にせよ、そうした板挟みの状態の枠内での「移動」は可能です。
そのために、何のために働くのかを明確にし、それを効果的、効率的に達成するように工夫することはできます。この一歩は重要です。
なぜなら、この「移動」は、もちろんその枠内での限られた動きなのですが、社会にはすき間や意外に楽しい裏場もあります。明確にした目的を見定めながら、日々、わずかでも自分の時間をひねり出し、自分ならではの場を作って行く作戦は可能です。
そして、そうした日々を送るうちに、また、別の展望が見えてきますし、思わぬ運や出会いもめぐってきます。
大事なことは、そうして自分の生存の足場をなんとか固めつつ、ぶれないで、本当にやりたいことの準備を積み重ねてゆくことです。もちろん、本人にとっては、その自信が持てず、不安にさらされ続けるのですが、残念ながら、それを楽にしてくれる妙薬はありません。
人生は長いです。いろんなことがあります。時代も少しずつではありますが変化もしてゆきます。そして、ピンチも来ますが、きっと、チャンスがやってきます。
終わりのない「旅」
こうしたジレンマ問題を、私は20代以来、《生存の二重性》として受け止めてきています。それにこの問題は、何も現代に始まったことではありません。おそらく、人間社会の歴史が始まって以来、何らかの形で、誰をも捕らえて離さない問題です。世界中の書物からめぼしいものをひも解いてみれば、その多くに、これに関わる詳細が述べられています。
ともあれ、どうせ離脱が不可能なら、いろいろな種類があるその「板挟み問題」のうちから、選ぶ基準をいろいろに変えながら、ジレンマに少しでもの明るみを見つけようとするのは人情です。
そうして私は、20代末、ひょんなことから労働組合の仕事に出くわし、その「経済的搾取の改善」と「金稼ぎ」の両立が図れるかもしれないと、それを職業として始めたのでした。そして数年後には、組織内の組合員が過労自殺未遂をする事件に遭遇、試行錯誤を経ながら、4年後、過労自殺行為に日本最初の労災認定を獲得する成果を導けたのでした。
しかし、そうした成果とて、いわゆる「後追い」――つまり起こってしまった被災への後からの金銭上の補償の獲得――にすぎず、重度障害者となった本人の体も境遇も、もとには戻りませんでした。そこで、それをきっかけに、労働問題をもっと広い視野で、ことに国際的に学びたいと、もはや中年ながらの留学の道を決心することとなりました。
そのようにして、生活の場は国外に広がりましたが、それから数十年して現在に至っても、自分の一部で金稼ぎを行い、他の一部を自分の本望に費やする、そうした「二重の生活」は続いています。それどころか、その「二重生活」を強いるシステムは、手を変え品を変え、いっそう巧みに人々への拘束の度を深めており、時にはそのジャングルの中で自分の位置さえ分からなくなります。
つまり、私が自分のこれまでの人生で学んだ限りでの結論では、この拘束は、人間社会に、「雇用と賃金」という生存方式が行き渡っている以上、自分が雇用主にでもならない限り、この世界からは無くなりません。また、自分が自分の雇用主になったからといって、それがゴールであるわけでもありません。あるいは、才能に恵まれ、自分の本望を思うままに発揮できる人もいるでしょう。
このあたりに、世界のトップを目指したり、有名人になることを夢に見たりする必要の出どころがあるのでしょう。そうした行動がこの二重性問題の解決になっているとは私には思えませんが、それはそれとして、他方の大多数の普通の人たちは、その拘束に死ぬまで付き合わされることに違いありません。
むろん、その付き合い方は千差万別で、そこに人生の多様性も機微も深みもあるわけです。そして問題もこのあたりまでくると、その二重性のジレンマ問題の場は、もう少し突っ込んだ考察の域に入ってゆきます。
そこで、この先の議論のバトンは次の章に引き継ぐこととなりますが、ここで加味されてくる、新たな要素があります。
つまり、私が「中年留学」の決心をしたように、いわば、問題の設定の地理的条件を変えてみるとの道がそれです。
よく言われるように「ところ変われば品変わる」で、人がある国で生まれ育って、そこで体験したことは、ひょっとすると、その国特有の問題であるかもしれない。ここに、地理的移動という新たな課題が登場してきます。
こうしてまさしく本書のテーマである「旅」の段階へと入ってゆくこととなります。
予想外のチャンスをつかむ
ただし、次の章に移る前に、是非、採り上げておきたいある視点があります。
それは、この20年ほどで、日本の「生存手段確保の鉄則」は、尻上がりに厳しくになってきている、つまり生活水準が低下してきていることに関連しています。そして、それに付随して、「旅」にまつわる環境も、動くことすらがリスクになってきている感があります。
たとえば、私の若い友人に、学業を終えた後、希望をもって社会に出たのに、行けどもゆけども、いわゆる「フリーター」の経歴しか得られず、ついには日本社会に幻滅し、夢を抱いてオーストラリアにやってきた人がいます。ワーホリとして懸命にあらゆる努力を惜しまずに可能な期間を頑張りました。だが、彼の場合、夢かなわず、どういう現実が彼を待っているのかは百も承知ながら、やむなく日本に帰ってゆきました。
すなわち、日本は言わずもがな、たとえ外に出ても、「生存手段確保の鉄則」がますます重く厳しくなってきていることに変わりはありません。
そういう状況ですから、容易なことでは、自分を食わしながら海外渡航費用までをも貯めることができない。またそればかりか、なんとかやりくりして海外に出たとしても、その海外でのチャンスも極めて細っています。
要するに、そうした「旅」に飛び立ちたいのは山々でも、そのハードルは、次第に高く厳しくさえなってきているのが近年の実情です。
そうした中で、最近、たとえば日本の看護師さんたちが、オーストラリアへ、ワーホリとか専門学校への留学として、私の周囲だけでも数人はやってきています。その中には、ナースの国際資格を目指す人や、あるいは、たまたま出くわしたこのコロナ騒ぎで、その専門を生かしてオーストラリアの緊急医療チームに加われ、新たな自分の生きる場を見出している人もいます。彼女の場合、それまでに準備していた英語能力やオーストラリアでの高齢者介護施設でのパート勤務体験が、突如発生したコロナ禍の事態と、偶然に噛み合ったわけです。
こうしたケースは、通常は「運」と説明されることでしょう。しかしながら、それだけに終わらせるには、いまひとつ飲み込みきれない事柄でもあります。というのは、どうも、運とも、偶然とも、あるいは経験的直観とも説明は可能ながら、それを越える、一連のなんとも特異な、チャンスを開拓する能力とでもいったエリアがあります。
従来の常識では一概には説明のつかないこうした分野が、私たちの生活にまつわって確かに存在しています。
そうした分野は、俗に「ニューサイエンス」と分類されたりもする領域では、それは「セランティビティー」と呼ばれる、この世界のもつ偶有性をキャッチする能力の発揮とも見られます。あるいは、「シンクロニシティ」とも呼ばれたりもして、自然現象が呼応し合う新規な認識のひとつとされたりもしています。
ともあれそれは、私たちが真剣にかつ繊細に物事と取り組もうとする際、どうしても意識せざるをえない分野です。
これについては、ここでの採り上げは以上にとどめ、あらためて後述(第3章)することといたします。
それに加え、今、コロナで世界は大騒動です。その影響で、その感染発生以前に、なんとか海外に出られていた人たちも、止む無く帰国を余儀なくされたり、外国で動きがとれなくなって釘付け状態になっていたりと、これまでの予測を越えた事態も発生しています。そこで、このコロナウイルスにまつわって、いったい何が起こっているのだ、ということともなります。
そこでですが、たとえ何事に出くわすとしても、そうしたドラマチックな展開可能性が人生であり、「旅」でもあります。
乱暴に聞こえるかも知れませんが、こうした時期だからこそ、従来の枠組みに捕らわれない、何らかの「勘」とも「透視力」とも言われる何かを働かせ、そうした不可知な「旅」への手掛かりをつかむ下準備をすることはできます。
そういう観点では、そうした一種の賭けを張りつつも、合わせてイザというコンティンジェンシー〔偶発性〕に備えている、それが人生と言えるのかも知れません。むろん、そこに保障はありませんし、反対に、石橋を叩いて渡る、あるいは叩いても橋なぞ渡らぬ道もあります。いずれにせよ、自分の選択は自分の手に内にあります。
そうであるがゆえに、自分を内面、外面にフル動員して感知力を磨き、周到な準備を時を惜しまず行い、一歩一歩と、それこそ、「百年に一度のチャンス」をつかんでしまう、そうしたケースがあるのも確かです。
一方、話は転じますが、昨年(2019年)12月、アフガニスタンで人道支援に取り組んできた医師、中村哲さんが銃撃されて亡くなりました。彼は私より一カ月ほど若いだけの同世代でした。
私は、彼の生き方も、そうした、まれどころか、あまりに特異な偶然を使命として受け止めた、重たい偶有性を自ら体現した最たる生き方だったのではないかと思っています。それはたとえそのような死を迎えるに至ったとしても、それで彼の生きた道の意味が何らも薄れたわけではありません。
人生とはそういう悲劇的事態をも含んで、究極的には予測すらも寄り付けない、まさしく「冒険」的こころみです。
それを自分の人生に取り入れるかどうか、もちろん、本人自身にかかっています。
2 政治・思想上の違い
オーストラリアへ中年留学
1984年秋、私は日本を後にして、オーストラリアにわたりました。
労働組合での仕事に大きな一区切りがつき、国際的な視野で、労働運動というものを学び直してみたかったからです。
ただ、自分の年齢はもう38にもなっており、いまさら留学生というのも“おっぱずかしく”、しかも肝心な英語はさっぱりという危なっかしさでした。
そういう中年留学とは、それなりに社会経験も積んだはずのいい大人が、いきなり小学生同然に“変態”するにも等しい、生活環境はもちろん、生活能力さえも退化したかの、大きなギャップの中に自分自身を置いてみることでした。
そして、自ら選んだその境遇は、まるで素っ裸も同然でした。日本にいた時のように、慣れ親しんだ慣習や、周りを巻き込んでなんとか事をなすといった術がまるで使えない、あるいは、自分の持つ現実的判断力――こんな能力が自分にあったのかと自分でも驚かされることとなる――が、厳密かつ正確に問われ実行されねばならぬ日々の開始でした。
したがって、日本時代に影響されていたような評判や地位などは、使いたくてもそれらを振り捨ててそこに来ているのであり、そうした上辺に惑わされない力量の試される日々でもありました。
そのようにして突入した異国生活を通し、しだいに発見できて行ったことは、留学という地理的《移動》がもたらした視野の違いでした。それは言うなれば、日豪という二つの眼で世界を見る、複眼視野――人間はこれがゆえに立体像がえられる――の獲得でした。
それと、それこそ「目からウロコ」とでも言える体験だったのは、あるわけがないと自分の常識では埒外〔らちがい〕にしていたこと――政府から自分への奨学金支給――が舞い降りてきたことでした。それこそそれは、先述の「セランティビティー」が自分に実際に起こったかのような、まったくの想定外の事態の可能性を考え始める契機を作ってくれたのでした。
そのように、実行しなかったら想像すらもできなかった諸々な体験をし、日豪という二つの世界に棲息するという意味を込めてそれを《両生生活》と名付け、それによる体験的学習を《両生学》と呼ぶこととしたのでした。(なお、この「両生学」については、後で改めて述べます。)
かくして、当初は最長でも3年と考えていた留学期間がしだいに伸びて、最後には永住するまでの長きに至ったのでした。
選べるものと選べないもの
オーストラリアでの生活は、それ自体からして私にとっての大きな選択だったのですが、その結果、オーストラリアに永住を決めその法的権利はえたものの、国籍まで選択するつもりはありませんでした。
というのは、国際的生活のための便宜からオーストラリア居住を選びはしたものの、国籍は、人間として所与の、つまり選択外の事項として、動かさないとしたのでした。
この国籍についての私の一見古風な考えは、それを「国」ではなく「地球」や「自然」とでも置き換えてみれば、規模は違うものの質において同列のものであることが解ります。つまり、それが自分の生命の拠って立つ根源であり、その変更は自分をまったく別の生命に置き換えることに等しいことと考えられるからで、そうした自然所与条件に「国」までを含めたわけでした。
同様に、人間の出生や育ちや血縁、遺伝なども、自分の選択外の問題として、自分の意志とは無関係に、それこそ、それに気付いた時には、すでに決定済みの事項です。
ここに私は、留学つまり海外への《移動》という選択を行った結果、選択した外国居住と、選択できない所与生存条件といった、自身にまつわる二重性に遭遇していたのでした。
この「選択可能・不可能」の二重性は、「可能」な側の事項は、いわば私の意志や思考が関与できる世界であり、それこそ、そこに「自由」を見出しうる領域です。
その他方、「不可能」な側の事項は、私の存在の根源条件であり、いうなれば、私のインフラストラクチャー〔下部構造〕の部分です。これを欠いて、前者の「自由」の行使も身体の私もありえません。
また先に述べた「食ってゆく板挟み」にまつわる「生存の二重性」についても、それを「理念と現実」といった対立と捉えれば、優先せざるをえなく、食って支える現実の自分の身体もやはり、身体というインフラとしての自分に相当するわけです。
労働組合時代の私は、「食うための」二重性の根源を資本主義という経済システムが原因と考えていました。それが、留学体験を通して、それまでの理念一辺倒な二重性把握から、生命体としての自分の存在を支えるインフラとの二重性の把握へと変化していたわけでした。
ところで、現世界の私たちの問題は、その生命のインフラであるもののほぼすべてが、それこそ「食うための拘束」との交換――つまりその拘束で得た金を払って買うこと――でしか得られないことです。それに、清浄な空気や水も、かつては無条件つまり「ただ」のものでしたが、それも、環境悪化によって段々と、お金を払わなければ得られないものへと変貌してきています。
この「生命のインフラ」とはつまり、自分の周囲のエコロジー環境のことで、これに関しては、追って第4章の「インフラとしての健康」でさらに採り上げます。
デュアリズム(二元主義)
私がオーストラリアに留学して発見した最大の学問上の収穫は、二元主義とかやや特殊に二大政党主義とかと訳される「デュアリズム」と呼ばれる政治理念の存在でした。
私はこの政治学用語を、現実社会を説明する概念として出会ったのですが、それはことにオーストラリアの政治経済的環境にあってはまさに「リアル」で、社会を構成する二つの基本要素が、労働者階級と資本家階級の二者によっているというものでした。
私はこの言葉に出会って、これがオーストラリアにやってきた成果だと大満足しました。というのは、日本時代、労働組合運動にかかわっていて、日本の社会では、労働運動どころか労働者という人たちまでがどこか日陰の身で、正当な社会的存在の場が与えられていないとのフラストレーションに常に捕らわれていたからでした(例えば私の母親なぞは、私が労働組合で働いていることを親戚らに隠し通していました)。まして日本の通念では、「労働者」は日本の社会には実在せず、せいぜいそれは左翼思想用語上のもので、実在するのは、「勤労者」とか「会社員」というものでした。
ところが、オーストラリアでは、そうした資本家と労働者という二者が、法的にも学問的にも、まして日常生活的にも、社会の二大構成要素としてれっきとして定着していたのでした。
それだからこそ、オーストラリアの社会は、両者を代表する二大政党制によって統治され、「自由国民連合」と「労働党」と言う二政党によって、数年ごとの政権交代も現実に起こり、その度に社会に吹く風向きまでもが変わっていたのでした。
後でも述べるように、オーストラリアの社会保障制度が、世界でもトップクラスを誇っているのも、こうして政権交代した労働党政府によって、日本ではとかく後回しや値引いてしか扱われぬ「労働者」の声が政治に反映される、一世紀以上にわたる経緯を経てきたからです。むろんその背景には、そうした反映が、経済成長にも結びついてきたからという現実的成功も重要です。交代する政府によって、労資両者の側からの後押しとチェックのバランスがそのように果たされてきたからでした。
また、こうして立場が互いに逆の政党が交代して政府を運営するため、政権党の腐敗や隠蔽は次政権によって容易にあばかれます。また、官僚も、どちらか一方に癒着や忖度していては、政府の交代の度に自らの偏りがバレてしまって自滅的です。かくして、むろん相対的ながら、より公平で民主的な制度が築かれる基盤がつちかわれてきています。
政治的恩恵の享受
私も、永住するようになって実際に、そうした法や制度上の恩恵を直接に身に感じてきています。
すなわち、「日本国籍のオーストラリア永住者」として、実際に両国を股にかけた生活をしてきました。それは、言ってみれば、生活条件上の「いいとこ取り」をするようなものです。また、もう少し視点を広げれば、政治的恩恵やリスクを分散した生き方を選べる選択肢を得てきたとも言えます。
自分の出生国に自らが封印されていた時代は、こうした国の違いによる利益やリスク分散の獲得はありえません。
つまり、地理的あるいは法制的により広い――決定的には国境を越える――範囲での《移動》を実行することにより、人生のよって立つ基盤がそれだけ広がりうるわけです。
それこそ「デュアリズム」たる二元主義を、政権交代という一国内二元性のみならず、居住国を交代するとの国際的二元性として得ることであって、一人の全人生レベルにわたって、その人生の選択の幅や恩恵や、いたっては世界観をすらをも広げることにつながるわけです。
ちなみに、私の知人には、二元主義どころか、数国での永住権の獲得を達成して、いわば人生の多元主義化を実行している人さえいます。
すなわち、いまや私たちの人生の「旅」は、それを国境にさえ拘束されないオープンエンドな場で実行することにより、その達成度合いに応じて、その最終的な見返りを射程に入れることが可能となるのです。
言うなれば、自らの保身しか考えない政治家や官僚にかすめとられた虚偽の「国」なぞはさっさと見限って、誰もが国の間の移動を本気で始めればよいのです。
「移民」という言葉が、国や政治家がその国の窮乏者を輸出することを意味した時代はもはや過去のものです。いまや、意欲あふれる優れた国民が率先して、自らを輸出して行く時代なのです。
コロナ後への視界
話を日本の日常にもどせば、この(2020年)9月になって始まった日本経済新聞の連載記事に、コロナ・パンデミックを契機に明らかとなった、世界の歴史的変化を「パクスなき世界」とタイトルした特集があります。その連載の各見出しや要点を挙げて見ると以下の通りです。
【連載「パクス〔注〕なき世界」】
〔注〕この「パクス」とは平和のことで、たとえば戦後の世界が「パクスアメリカーナ」と呼ばれたように、米国の世界覇権下の平和のこと。
(1)成長の女神 どこへ コロナで消えた「平和と秩序」
これまでの世界の平和をリードしてきた世界覇権国に衰退と、見え始めた様々な国家間紛争。
(2)競うのは主義でなく賢さもはや世界をひとくくりにできる理念は用済みと化し、むしろ、各国ごとの知恵をしぼった賢さが光りはじめている。
(3)再生迫られる民主主義自由か、安全か。あなたは自ら選択する重みに耐えられますか。
(4)ふるいにかけられる官民あなたの会社の存在意義は? その利益、社会に役立ちますか。
(5)自分の価値を自問する組織頼みから個の時代へ。この危機の時代に、あなたは何を頼みにして生きていきますか。
(6)人口集中から知の集積へあなたは大都市で生活したいですか。新たな都市像えがけますか。
この連載記事で言われている「ポスト・コロナ期」は、それまでの時期とは、大きく前提を異にすることが想定されています。すなわち、国内外政治、経済機構、社会体制、そして知的文化のそれぞれの面での変化です。ことに、個人の組織に対する位置がより重要視される要素が見られます。つまり、経済専門紙レベルでも、そうした変化を射程に入れ始めているのです。
また同記事の中で、三菱ケミカルHDの小林喜光会長はこう述べています。
日本は過去の成功体験にとらわれたまま30年来てしまった。アナログな世界、集団主義、皆が同じ方向をみるなかでの効率化の追求。そんなことを慣性の法則で続けていては奈落の底に沈む。目を覚ますには緊張感をもたらす天敵のような存在が必要だと考えてきたが、まさに新型コロナウイルスはその役割を果たしつつある。
コロナ禍が百年に一度のパンデミックであるとするなら、こうして予想される「推移」や「変化」も、その規模のものであるはずです。
そうして流動し始めた世界に対応して、私たち自身も、もはや旧来の旅行需要の「蒸発」などに拘束されず、新たな流れに沿った展望をもった「移動」や「旅」が必要とされ、潜在的ながら、それはすでに志されています。
ただし、こうした日経の記事が基盤とするのは、当然ながらビジネス上の観点です。先に「食ってゆくための鉄則」として述べたように、こうしたビジネス上の新たな動向は、その鉄則が持ち始めた新たなモードにすぎません。むろん、それを活用して、自分の必要を確保してゆくことは可能ですが、そうした新モードと、自分の本意や作戦とを混同してはなりません。
国という単位の相対化
上述のように、もはや国境は、国民をつなぎとめておくには、だんだん、無力になりはじめています。
ことに近年は、そうしたボーダーレス化の一方で、それに逆行しているかのように、差別意識の強い民族主義傾斜の動向が顕著となってきています。それはだからと言って、国家への帰属意識――中国は別格にして――が強まっているからではありません。むしろ、頼るべきものがもはや国ではなくなり、より小さな単位に分解していっているからです。
21世紀の最初の20年間では、そうした世界の傾向がおこりつつも、しかし、法的、制度的な枠組みはいまだ国別の体制は維持されています。その意味では食い違いがあります。
つまり、人の動きは急速にボーダーレスになっている一方、国ごとの制度は、それにはるかに遅れて過去を引きずっているといったズレが生じているわけです。
ここに、世界を流動する人々の間に、国家間の制度の違いを意図して目指すケースも増えてきています。やや極端な例ですが、世界の先進国を悩ます難民問題がこれに当たるでしょう。すでに述べたように、永住権の獲得をねらったワーキングホリデー取得者や留学生、あるいは、ことに女性で国際結婚をひそかな目的とする渡航者も少なくありません。
そのように存在している現実的にはけっして無視できない、社会保障制度や賃金水準の違いなどにもとづく生活条件上の格差について、もう少し詳しく見て見ましょう。
私が、オーストラリアへの「中年留学」当初は、それこそ、目先の2、3年のやりくりすらが心配であった程で、何年も後の結果なぞ、考えようにも見通しすら難しいというのが実情でした。そういう意味ではまるで綱渡りで、年ごとどころか、大学の学期ごとの推移に運命が託されているのも同然でした。ですから、率直に言って、10年とか20年後の結果をその初めから狙っていたわけでは決してありませんでした。
しかし、結果的にそうした時期に達してみると、国家間の移動を通じて、その前と後における、たとえば、同じ労働への報酬が、そうとうに異なってくる現象を目の当たりに体験することとなります。
早い話が、2020年現在で見ると、オーストラリアの法定最低賃金は19.84豪ドル、日本円にして1,500円前後です。日本のそれは、全国平均で902円です。およそ70パーセントの違いです。物価水準の差はあるとはいえ、一時的な滞在者であっても、この差の影響は受けます。
またそれが、永住権を得て社会保障の対象となれば高水準の失業補償も得られ、高齢になり年金生活に入った後では、その公的年金支給レベルの差も挙げられます。
こうした国の違いによる経済条件をはじめとした様々な格差、これを「旅」の第一の目的にするかどうは人によります。現に、賃金格差を計算に入れた国際出稼ぎ労働は、まさしく、そのための国の間の移動です。
それはともあれ、いったん「旅」を用意周到に考え始めれば、渡航先のビザ条件の調査をはじめ、各種の違いをよく飲み込んだうえで、行動を始めることとなります。したがって、こうした国家間格差がいやでも視界に入ってくるのは避けられません。
むろん、こうした差の背景には、上述のように、それをもたらすだけの政治的、制度的違いがあるからこそです。そして、もしあなたが、二つの国の永住権を持っていたとすれば、上記のように、その「生存のための鉄則」の様相も変化し、恩恵にしろリスクにしろ、分散する生き方ができるようになります。
このようにして、本書に言う「旅」の予想される結果は、あなたと国との関係が、唯一無二で、選択外あるいは事実上の強制であるものが、相対的なものにスライドするという違いです。
先述のように、私は個人的には、「自分の国」を選び変えてはいない、古風な変種です。そこにはこの「自分の」というところに何を含ませるかによるわけですが、むしろそこに、その二重性の両側の追求という次の次元の醍醐味も現れてきます。それに、ビジネス界では、この「自分の」は明快に、「自己利益最大化」であり、旺盛に追求されているわけです。
今後、国境の存在は、ますます薄れてゆく、あるいは、ケースバイケースの選択の問題となって、諸々の移動条件のただの一つとなって行くでしょう。
そうした動向や必要は、たとえコロナ禍によって旅行熱に冷水があびせられたとしても、もはや変わるものではないはずです。
こうした選択の問題としての国が多面的に扱われることこそ、『「自‘遊’」への旅』の主テーマであり、不選択が強要されればされるほど、ますます、「自‘遊’」が求められることとなるでしょう。
3 変貌する科学、進む量子理論
「両生学」という人生実践知識
前章でオーストラリアへの留学体験を契機にした「両生学」構築の経緯を述べました。それは、その名称上、なにがしかの「学問体系」であるかの体裁をしています。しかし、それはそう呼称するのが手っ取り早い――留学体験という学問環境の影響もありましたが――というだけのもので、むしろその実内容は、実践体験から学んだ知識の整理法です。
そういう便宜本意の「両生学」」だったのですが、ただ、その構築の途上において、既存の学問体系の大枠を俯瞰できたのは大きな収穫でした。つまり、過去において、人間がどのような知識体系を組み立ててきたのか、その眺望をえたかの体験でした。
そのようにして、たとえば、自分が日本の大学で修得した知識、ことに工学知識が、職業的に有益ではあるものの、すでに大いに古典的であることも知ることとなりました。
それに加えて、自分が教育によって得てきた知識が、まさに時代の要請にはそうものであったものの、自分が現在に生きて行く自分の生身の必要に関する知識については、まるで「裸の王様」で、何も身に着けていないも同然であることも判りました。
こうして、人間が生きて行くに必要な知識のおおむねの全体構造を自分向けにカバーしたものが、この「両生学」です。ですから、いわゆる大学等の教育機関があつかう学問とはその狙いや趣旨が違います。もっと、私たちの生活に必要な実践的知識の体系です。
本書の読者で、自分に役立つ何らかの学問があるのか、あるいは、なんらかの学問領域をちょっとのぞいてみたいという場合には、この「両生学」を参考にしてみるのはひとつの方法です。
ただ、本書はここでは、そうした「実践学問体系」の詳細自体には立ち入りません。本書の目的は、そうした実践知識をも通じて、いろいろな拘束を克服する、「自‘遊’への旅」の案内です。
そこでもし読者の中で、「両生学」の中身の通覧をお望みの方は、私のウエブサイト「両生歩き」を訪問していただければ、その一部始終をチェックすることができます。ことにそのHPのメニュー欄にある「旧サイト」をお開きください。
「目からウロコ」の量子理論
さて、そのようにして、人類が築いてきた諸学問のおおむねの視界が効くようになるのですが、そうした学問知識、ことに科学の分野における、この一世紀ほどに起こってきているブレークスルー〔大きな躍進〕は実に重要です。
この「重要」というのは、むろん、人類全体においての重要性のみならず、それによって開かれてきている人間自身のものの見方が、極端な言い方をすれば、まるで「天地が逆転する」かのような変化を遂げてきているからです。
そのブレークスルーがもたらした成果を知っているかどうかの違いは、私たち自身の「目からウロコ」が取り去れるかどうかに関わります。逆に言えば、その「ウロコ」を両眼に張り付けている限り、私たちの知識は、19世紀レベルに縛られたままとなってしまいます。
その巨大な前進が起こっているのは、理論物理学のうちの量子理論においてです。
ただ、そうは確かに言えるのですが、その中身を理解するのは、実は、並大抵のことではありません。それがことに、理論物理学の一分野と言うのですから、聞くだけで、まるでお手上げ同然な気分に襲われます。
そういう量子理論をその専門性に基づいてトレースするのは、それは膨大な作業です。やもすれば、10冊の本くらいは、ゆうに必要とするでしょう。
そこで私が注目するのは、そのブレークスルーの私たちの生活にとっての「意味」です。応用です。ただ、そうした科学的前進のかなりの部分はまだ仮説の領域のものです。そして、そうした仮説が立証されるには、この先、十年、あるいは数十年のタイムスパンを必要とするでしょう。
だがしかし、私がここで採り上げる学問とは、私たちの実生活に実践的に役立つそれのことです。確かに、科学上の厳密性において、その立証には、それほどの時間を必要とするでしょうが、私たちの生活は現在進行中のことで、その立証を長々と待っているわけには行きません。
と言うより、そうした科学的立証は、言ってみれば、私たちの生活の実務上では無視できるほどの超精密な数字的厳密性においてのもので、私たちの生活のレベルには、それほどの精度は必要ではありません。
そうした立証上の厳密性より、私たちにとっては、そうした理論のベースになっている考え方の基本における違いが重要です。それこそが、私たちの生活上のものの考え方にも、決定的な関係があるのです。
そこで、その「目からウロコ」ですが、それを、私たちの日常生活へのインパクトという意味に“翻訳”して言えば、こういうことです。
科学は知られずに眠っている世界の真理を突き止め、私たちはその突き止められた真理によって教えられ啓発される立場にある、とするのが従来の考え方でした。それが、そうした真理は究極的には、観測によって決まるというものです。つまり、真理というものがあらかじめ誰にも知られずに在るのではなく、それは観測に基づくというものです。
こうした変化は、それを知っていようがいまいが、何ら、私たちの日頃の生活に関係ないかに聞こえます。
しかし、それは私たちの常識をくつがえしたにも等しく、私たちは、物の考え方の根底において、従来の拘束から解放されたのも同然です。
これを、私の友人はブログ『NEUノイsolution』に、以下のようにうまく表現しています。
最近になって量子力学による度重なる実験によって、「観る」が現象を決定づけることが解り、「観る」⇒「在る」で、「在る」⇒「観える」ではないことが証明されました。そう世界は「在るから観える」のではなく「観るから在る」だったのですね。
この科学界での転換は、私たちを大いに勇気づけてくれます。これまで、何やら、外から規定されていたかの自分が、自分で自分を規定していいんだと、無罪放免されたかの晴ればれしさです。
私の受けた教育上の体験が他の人たちにも共通しているとすれば、私たちの頭は、こうした旧式の科学思想を根拠にした教育――ことに高等教育になればなるほど――によって、ガチガチに縛られてきました。
それが、教育システムを組み立てる学問体系のてっぺんから、このようにして大転換が始まっているのです。
ただ、学校教育システムの末端まで、こうした転換の成果が行き届くのはいつのことか。自分の子供の問題として、あるいは、教育のさなかにある自分の問題として、それまでなぞ決して待ってはいられないでしょう。そうした旧式の衣服を着せられ、中国の纏足〔てんそく〕のように、窮屈で動きもとれないまでに変形されてしまってからでは、もう遅すぎます。
ましてや、そうした変調した学校の義務教育に“人質”にとられて逃げられず、あげくには生徒と教員がつるんだごときのイジメの犠牲者となって自ら命を絶つしかなかった話なぞは、この世の話などとは思えないほどです。
なお、量子理論について、これまでの私の個人的取り組みに詳細ついては、『新学問のすすめ』にまとめてあります。また、そうした量子思想の日常生活への適応の過程は、『パラダイム変化:霊性から非局所性へ』に連載しました。
「科学」と「実感」との間
先に私は、私たちの生活は現在進行形のもので、科学の仮説が立証されるまで待ってなぞいられないと述べました。
そうした仮説領域のもの、あるいはさらに、科学者の間では「疑似科学」として排除されている、仮説以上の大胆な発想をあえて取り込んだ一連の見解群があります。第1章でふれた「ニューサイエンス」もこれに当たります。
科学として扱うにはグレーゾーンにあるこうした様々な説について、私は、それはそれらを「まだ厳密な科学的真理にはなっていない途上のもの」と制限を置いた上で、使用価値をもっているものだと考えています。つまり、まだ未確定ながら一種の将来性を含んだヒントや方向として取り上げ可能だからです。
それに、それを承知で自分の人生に応用するのですから、それは言わば自己責任上のもので、他人にとやかく言われる筋合いのものではありません。
そこでですが、そうした「グレーゾーン・トピック」として、ここに、人の持つ感受性について、一連の見解を取り上げてみます。
まず、そうした見解のひとまとまりの文献が、私が著者のブラッド・オルセンの了解を得て翻訳し、オンライン出版している「エソテリック」をテーマとする二部作です。その邦訳は、『現代の「東西融合〈涅槃〉思想」』と『「東西融合〈涅槃〉思想」の将来性』で、広範な分野にわたって、今日の科学的事実の背後に眠る、奥底の知見を議論しています。
そのテーマのいくつかを抽出すれば、前者から{神々の血液」、「対抗言説」、「松果腺」、後者から「秘密政府」、「宇宙次元の極秘:UFO」、「フリー・エネルギー」などです。
なお、原題にある「エソテリック」とは、奥義とか、難題とかと訳される近代科学思想から対象外とされてきた知見で、私の邦訳ではそれを「東西融合〈涅槃〉思想」と大いに意訳してあります。と言うのは、それには古代より東西の人類が培ってきた魔術、宗教、宇宙観を含む壮大な思想体系を扱っているからです。
また、これは私の感覚にそった仮説見解ですが、自分の持つ周囲との交信能力について、ひとつの自説があります。
それは、人には、その内部に、もっとも高性能な言うなれば「スマホ」を持つというものです。
むろん、その能力は、現存するどんなスマホよりも優れているのですが、いかんせん、その全性能に自分で気付いている人はごくまれで、したがって多くは、現実界の商品としてのスマホに頼ってしまっています。
なお、こうした分野の表現は、私には論文より小説やSFが適しており、そのあたりを使い分けて、一種のSF作品として、私の『MOTEJI越境レポート』があります。
4 インフラとしての健康
近年、私がもっとも専心している分野が、この健康です。
それはもちろん、年をくってきて健康上のさまざまな障害を体験するようになったという、「失って知る有難み」がゆえ、という面はあります。
しかしなのですが、そうであるなら逆に、まだ「失っていないもの」くらいは大事にしたい、ということでもあるのです。
そして、さらに掘り下げて言えば、そうしたものを、はじめからどうして大切にしてこなかったのか、ということでもあります。
つまり、先に触れましたように、健康とは、私たちにとって、自身を足下で支えているインフラであるという見解です。都市の上下水道が私たちの都市生活の基盤を支えるインフラであるようにです。
そしてそれは、健康ばかりでなく、目を広く世界に広げれば、環境や自然についても、同じことなのです。
それを常時、正常に整備あるいは保全しておくことで、その都市、その人の働きは、目覚ましく向上するのです。
「若さは無知」で済む話ではない
おそらく、私ばかりでなく、多くの人にとって、若い時代には、それが本当は無理であるようなことを、頑張りや我慢が自分の使命や美徳のように信じてしまい、ついつい、それに熱中していたのではないでしょうか。
たとえば、私は、昔も今も山歩きが好きなのですが、20代のころは、――やや誇張を含んで言えば――目標の達成とか、逃げない自分の形成とか、恐怖に打ち勝つ強さ等々と、いかにも単純素朴なGOGO主義一色に染まり、それを達成することを誇りとし、逆に、それのできない人や考えを見下していました。
確かに、それで培われた部分はあります。しかし、そうした単色な価値観に捕らわれて、見えていなかったこと、見捨ててきたことも多々あったに違いないはずです。
というのは、たとえば、昔、日本の山々をほっつき歩き、それぞれの頂をきわめてきたのですが、そうした頂上には、決まって、小さな祠〔ほこら〕が風雨にさらされて祀〔まつ〕られていました。それは、光景として私の記憶には残っていますが、それ以上のものではありませんでした。いわば、その付近に同じように設置されている測量用の三角点標と、大した違いも意識していませんでした。
ところが近年、相変わらず山々を登っているのですが――昔とは大違いで、ひどくあえぎながら――、そこで、決定的に違うことを体験しています。
それは、その頂上に祠があったり、外国なら何らかの宗教的設置があったり、また、そうしたものの何もないただの尾根や谷を歩いていたりしていても、昔には感じられなかった、何か異なった体験があるのです。
最初それは、たとえばそこが、ヒマラヤの一帯で、その標高も、4千メートルを越え、時には5千メートルにも達しようとしている、その高度――つまりそれだけ宇宙に近い――がゆえにであるからかと思っていました。
しかし、おそらくそれも含んで、そこには、その地や環境が、言葉にはならないなにかによって、確かに、「語りかけてきている」と表現してもいいような、何かがあるのです。
言い換えれば、私はそうした感性をただ「山好きがゆえ」として、単なる好みの問題としてしか捉えてきていませんでした。しかしどうも、そんなものではなかったようなのです。
もし、20代のころに登ったそうした山々においても、同じように語りかけてくる「ささやき」を聞く耳があったとするなら、きっと、今の私は、もっと違った私であったかもしれません。
ともあれ、そのようにして、私は一種の兵士のような、克己意識や秩序を強く意識する、自分のメンタリティーが形成されたのは確かなことなのです。ですから、それで問題をおこしてきたのも多々あったと反省させられることになります。
「働き過ぎ習慣病」
私がせっかく得た就職先を、半年後に辞めたという話は先に書きました。これはどうやら、そのようにして鍛えたはずの我慢強さや克己心が、結局、あまり役立たなかったが故のようです。
そしてその後と言えば、日々は「裏街道」歩きで、やがて労働組合の仕事に就き、さらに、ひとつの労災事件に遭遇しました。それは過剰な責任負担による過労自殺のケースでした。
この労災ケースからもう40年にもなるというのに、日本社会からはいまだに過労自殺の報が絶えません。
つまり、若い時期に頑張り、いわば、将来の自分の健康を《先食い》する慣習や行動が常例化し、いまだ現役であるのに、もう健康資源を使い尽くしてしまっているのです。
「先食い」というのは、お金の問題に置き換えれば、借金です。それが後々、利子がついて、病気――過労自殺は間違いなく、病気です――となって降りかかってきているのです。
ひと昔ほど前までは、高血圧とか心臓病は「成人病」と呼ばれ、この「先食い」をある意味で容認したような認識でした。
それが、すでに故人となられましたが日野原重明先生の提唱で「生活習慣病」と呼ばれ、自分の将来から借金するような現在の生活習慣を改めるようとの、予防の考えが始まりました。
しかしながら、そうして「生活習慣病」と呼称は改められても、まだまだ実習慣は、どこか受け身的で、予防に努めることに一種の肩身の狭さすら感じさせられます。ですから、そこをもう一歩も二歩もすすめて、それを「働き過ぎ習慣病」くらいにまで名を改めてほしいものです。
若さがゆえの無知で済む話ではないですし、ましてや、それに付け込んでいい話でもありません。
身体インフラのメンテ
第2章で、「生活手段確保の鉄則」に追われるが余りに、「自己存在を支えるインフラ」としての自身のインフラが、無視されるどころか、害されがちでさえあることを述べました。
私たちはつい健康を、病気と並べて考え、一種の“病気でない状態”、と転倒させて考えがちです。しかし、そもそも健康とは、日々の生活や長くは人生それ自身のインフラストラクチャーとして、正常に機能していなければならないもので、それを失うことは、日々の生活や人生の正常な働きの足を引っ張ってしまう性格のものです。
それはたとえば、天災によって道路や鉄道が寸断された状態を考えればいいのですが、そうしたインフラの損害が、その地域や国の生活や経済活動を決定的に痛めつけるわけです。
つまり、こうした観点から言えば、健康の率先的維持は“事後修繕”よりはるかに有意義であり、身体インフラのメンテナンスをもって、不必要な休止期間をさけ、無駄のない健全な機能を続けられるということです。
そうしたインフラとしての身体は、たとえば、使わぬ機械は錆び付くように、運動をしない身体も「錆び付く」ばかりでなく、そもそもその働きが下支えしていた人間存在としての総体レベルの働きを低下させます。言い換えれば、その本人にとって、日々の体調の良し悪しどころか、毎日の生活の快適さや楽しさや仕事の上の生産性、さらには、その人の人生の意義自体までもが消え去りかねない状態に至らせてしまうわけです。
ついでながら、トヨタ自動車のTPMとよばれる総合的設備管理(あるいは「全員参加の生産保全」)は、これと同じ発想をもって、自動車生産システムを動かし、高い生産性をあげているものです。そしてその秘訣を学ぶため、アメリカのマサチューセッツ工科大学では、TPMをテーマとした授業科目があったほどです。
近年、ジムが流行ってきているのは、そうした身体インフラを快調状態に高めておくことの生活や仕事の質への効果に、人々が気付いていることがあります。
さらに言えば、いわゆるスポーツは、一種の趣味分野の活動として受け止められがちです。しかし、体を使うことが希少となった現代生活者にとって、それは趣味という嗜好――無くても構わない――の問題ではなく、食事や眠りに並ぶ、生命活動にとっての必須要素として考えられるべきものです。
脳もインフラ
かくのごとく、私たちにとって、自分の身体とは自分自身のインフラです。したがって、自分の意識や働きの中枢である脳の機能についても、それがフルに働くか否かは、身体としてのインフラがフルに働き、脳をフルに支えていているかどうかに拠ります。
またその脳自体についても、知性とか感情とか人格とかとの脳機能の現れを支えるのもインフラとしての脳組織であり、その組織がフルに働かない場合、その人自身の精神的な働きも不全や不調におちいります。
そのインフラとしての脳組織は、人体臓器の中で、もっとも解明の困難な臓器で、謎の多い部分です。それだけに、その働きに、多くの思い込みや信仰すらもが介入してくるわけです。
誰でも、自分のなけなしの脳組織を、フルに活用したいと望んでいるはずです。
そこでその活用法ですが、自らとしては、いろいろなやり方を試みて実感し、その結果、どう自分の頭が働いてくれているか、それを試行錯誤するしかありません。一種の実験と観測です。
そうした試行錯誤の中での第一は、繰り返し触れてきているように、運動の大事さであり、それによって向上する身体機能つまりインフラ機能です。早い話、健康な心臓活動なしに、脳には十分な酸素も栄養素も送られてきません。そういう酸欠栄養不足の脳が役に立つはずがありません。逆に、それが十分に供給された脳の働きより、実に快適な気分ももたらされます。
次に、近年、私が有効と判断してきている方法が、大自然、ことに太陽からの資源――あるいは恵み――を、最大限にいただくということです。
具体的には、日光浴をはじめとし、戸外での太陽光を浴びる活動を意識的に行うことです。特に私は、運動が終わってクールダウンを済ませた後、公園の芝生上にあぐらをかいて、夕日にむかってサンゲージングつまり太陽凝視をします。昔から日本には太陽を仰ぐという習慣がありますが、太陽を見つめる――昼間の太陽光は強すぎますので日ノ出、日の入り前後の1時間ほどの間で――ことで、その強い光や電磁波或いは素粒子線が目を通して脳組織に直接作用し、その活動を活発にする効果があることを体験してきています。それはことに、気持ちをおおらかにしたり、直観の働きを鋭く広範にするとの効果を感じています。
「民間保険」というまがいもの
私は、誰かから保険について、たとえば、ガン保険について入るべきかどうか相談された時、そういういわゆる「民間保険」とは、“まがいもの”の保険制度だとする自分の意見を述べています。
保険は、危険に対する保障制度で、健康保険とは、病気になった時、無料あるいは安い費用で高度な医療が保障される制度です。その仕組みは、国という最も大きな集団を母体に、比較的小さな保険料金をベースに、国民の誰もが保障を受けられる制度です。母体が大きければ大きいほど、その保障効果は大きいのです。日本の健康保険制度は、ことに皆保険制度ともよばれ、日本人の健康水準を高く保ち、寿命を世界のトップレベルに維持してきている世界でも優れた制度です。
これを、アメリカのように、「民間保険」を中心にした健康保険制度にしてしまうと、結構高いその保険料金のため、事実上、お金持ちのための制度になってゆき、貧乏人はそれに加入する余裕もなく、病気になっても医者にかかれない状態へと至ります。かつてオバマ大統領は、全国民を対象にした健康保険制度の設立を目指しましたが失敗に追い込まれました。と言うのは、それが設立すると、病気がちな貧乏人への給付が増えて全体の保障水準が下がるとして、すでに「民間保険」に入っている人たちが反対して、その「オバマ保険制度」の設立をはばんだからでした。
また、「民間保険」への加入の良し悪しについて、それを個人として考えた場合、その加入の必要は、自分自身が健康を逸したの時のためのもので、それに入っていること自体が健康をもたらすものではないことです。つまり、保険は薬や手術といった医療サービスは提供してくれますが、健康自体は提供してくれません。仮に自分の健康に絶対の自信がある人には、そうした保険は無意味です。どうも、そのへんに保険=健康との錯覚があって、民間健康保険やがん保険やいたるは生命保険までもが、「安心を提供」するといって、 自分の健康維持への努力の眼をそらさせがちです。
そういう意味では、「民間保険」にお金を払う余裕があるのなら、運動靴を買ってエクササイズに精を出すとか、自然栽培の安全な食品を買って食するとかと、健康の維持、病気の予防にお金をかけた方が、はるかにその目的にかなっているのです。
つまり、自分の労働でお金を稼ぎ、そのお金をもって、さまざまなものを買う、そういうサイクルに余りにも慣れさせられているがゆえ、健康まで、お金で買えるかの錯覚をもちがちです。言うまでもなく、健康はそうした保険資産によって得られるものではなく、直接に自分が自分の体に働きかけ、養うしかないものです。
健康はまさに「無くしてわかる有難み」そのものです。ことに、高齢になってくると、どうしても、あちこちの調子が悪くなるもので、その悪化の一つひとつが、毎日の生活から少しずつ、快適な暮らしを奪ってゆきます。
ですから私は、ことにリタイア生活に入った人は、健康のために運動をすることは、「それが仕事だ」くらいに考えてもいいと思っています。年をとっても質のよい生活が維持できるのなら、後述するように、そんな仕事くらいしても当然ではないか、ということです。
また、先の「健康とはインフラ」という話にもどれば、それは、個人にせよ、社会にせよ、その正常な機能の基盤を支えるものです。そうした大事さをかえりみず、それを酷使して傷つけ、逆に、有料道路や「民間保険」のように、あらゆるものに料金が必要にさせてしまって、折角の働きを逆回転させていいのかということです。
健康老人が築く未来社会
ここで、そうした健康というインフラの視点を、高齢者の問題において考えてみます。つまり、高齢には不健康が伴うのを当然視する認識を点検してみたいと思います。
これまでの章で述べてきたように、「生存手段確保の鉄則」に追われる結果、私たちは、現役時代にその健康資源を先食いして使い果たし、「借金」すらして、なんとかリタイア時期にたどりついた時、もう、満身創痍であったとの悲しい事例多発の現実があります。
しかし、人生に伴うさまざまな拘束をなんとか克服し、この晴れのリタイア期に、健康なままゴールインできたとしましょう。また、そういう事例は、もはや決して、仮定上でも稀な話でもありません。
すなわち、年金生活という、「生活手段確保の鉄則」から制度的に解放されたバラ色生活の到来です。
もちろん、現実は、国によって異なる制度内容によって、その「解放」のレベルは異なりますし、個人差の大きい話でもあります。
そこで注目すべきは、そうしたその鉄則からの解放状態に、それこそ、満身創痍で到達するか、それとも無傷で到達するか、その違いの大きさです。
たしかに年金の支給レベルには国による差があるのですが、そうであるのならなおさら、その時期に健康で到達し、その健康資源を元手として、その格差を補うべく、たとえばパート労働に就いて収入不足を補填できるか否かが重要となってきます。あるいは、リタイア生活によって絶たれがちな社会的接触をボランティア活動なり趣味の活動なりを通して確保し、より豊かな生活に引き上げることが可能です。また、そうした活動ができること自体が、リタイア生活の意義や生き甲斐を満たし、当人の日々の充実感を大きく高めることにも貢献します。
私は、そうした質の高い老後生活の用意こそ、どの社会もが目指す目標のひとつであるべきと考えます。なぜなら、それが将来に期待できるからこそ、現役世代が安心して、それこそフルに能力を発揮できるわけですし、その励みにもなるわけです。むろんそうした現役活動が、その社会全体の生産性を高めることにも通じるのは言うまでもありません。そして何よりも、高齢者の医療経費の軽減に直接むすびつきます。
したがって、私はリタイアした年金生活者は、自分の考え方として、先述のように「健康維持が仕事」であると受け止め、それを実行することくらいで丁度いいのではないかと、と思うのです。
つまり、リタイアした老人が、自活して介護を必要としないばかりか、家族にも、社会にも荷物にならないとするなら、誰にとってもそれほど幸いなことはなく、それがどれほどその社会総体への負担を軽減することとなるか、それの生み出す実務的、経済的な違いは、膨大な社会的資源となるはずです。
このように、老人問題を社会のお荷物に留めておくのか、新たな資源とするのか、それを分ける巨大な違いは、政策課題として実用的に研究されるべき――いまのところ充分な取り組みがされてきていない――です。そしてそれは、今後、社会の決定的に重要な分野であると思われるし、早急に取り組めば取り組むほど、その見返りも大きいものと思われます。
私はいまのところ、なんとか健康にこの時期に到達し、以上のような研究開発の可能な分野を実感しています。そして私事ながら、これまでの「両生学」の後に続くべく、この老人問題を新たな“誕生”問題と見て、そうした「越境生命学」を考察する「理論人間生命学」と呼ぶ新分野への構想を持っています。
地球の健康
本章の最後に、視点を大きく逆に広げた話を記します。それは、《健康》というものを、もはや人類は、地球規模において考えるべき時に到達しているのではないか、という見方です。
それを言うのは、健康を全人類規模で追求することに加えて、人類がもはやどんな言い訳をしようと、地球自体が自らの身体をもってその言い訳への反論を開始しているような、気候変化の尻上がりの激烈さゆえです。それは、地球が生活習慣病や過労習慣病――熱を出し、下痢をし、骨折し、出血している――を患っているような、毎年、毎季の、高温化、大森林火災、凶暴化する台風やハリケーン、大雨、大洪水、土砂災害などなどが続いているからです。
先に、私たちの身体や人生のインフラとしての自然や地球環境を述べましたが、それは言い換えれば、そのようにエコロジーとして私たちの身体から地球の身体へと一体につながっている、《健康の連鎖》といった発想をもつべきではないか、との観点がゆえにです。
私たち人間は、自分自身や家族の健康を考えて、自然の中の環境のよい所に家を建て、そこに住むことを欲してきました。そして実際にそれを実行しています。そのために、山を切り開いで道路や宅地をつくり、そればかりか、山や島を削りとって大量の土砂を運び、人工島までをも造成して、そこを市街や空港にさえしてきました。
私は、健康保持のひとつとしてのエクササイズを終わらせた後は、よく、公園の芝生の上に大の字に横たわって空を見上げます。その時、何とも言えない、自分と自然とが一体となったかの、抱擁されるような快適さを感じさせられます。それは、この言い方を使えば、まさに「健康の連鎖」のひとつとなっている自分の実感です。
これをその結果と言えば、議論の飛躍と指摘されるでしょうが、いまやコロナ・パンデミックが世界を襲い、航空需要は一夜にして蒸発し、あまたの空港が過剰能力で赤字に転落しています。つまり、コロナ禍は、たんなる大規模な感染現象なぞではなさそうです。別の場で詳しく議論しているのでここでは省きますが、人類をかくも大きく悩ませているコロナとは何かをめぐり、それを「自然の摂理」との視点で見ることも、あながちピント外れでもなさそうなのです。
私たちが自分自身を、周囲の環境ともつながったエコロジー総体を考えるなかでしか自分の健康が築けないという、《持ちつ持たれつ関係》にあるにも拘わらず、それに配慮していない証拠として、地球の側の不健康が増進しているかのごときです。コロナも含めて。
5 精神的・心理的成長へ
日本人性の起源
日本人は、なかなかユニークな民族だと思います。しかも、世界のうちで、これほど博愛精神に富んだ人々もめずらしいのではないかとも思います。日本人にとって、誰もが同じ人間であると信じることは、それほど難しいことではないのです。
そうした特徴を育ててきたのは、日本が島国であることと深く関連しています。また、1945年のアメリカによる占領まで、日本は、外敵によって占領も征服もされたことがないという、実に幸運な国であったからでした。
世界の他の国、ことに大陸の国で地続きで他国と国境を接している国間での紛争や、さらに、そこが地峡とか半島である場合、長い歴史のなかで、どうしてもそこが他民族が移動する通路になってしまい、頻繁に侵略や征服が起こり、そこに生活する人々は、そのたびに自らを守る術を身につけてきました。つまり、民族の違いに敏感となり、そうはたやすくは他者を信用せず、また、巧みな交渉術も身に着けることとなりました。
島国という周囲を海に守られた国においては、そうした危険や体験を避けることができた代わりに、世界の他の場所のことにうとく、好奇心はあっても接触体験を欠く、いわゆる「島国根性」に捕らわれざるを得ませんでした。
世界の他の国を見渡した場合、たとえば英国も島国で、日本と似た地理的条件にあるのですが、ただ、ヨーロッパの他国とは、英仏海峡という、タフな人なら泳いで渡れるほどの距離しかへだたっておらず、頻繁な侵略と交流の歴史をつくってきました。
日本の場合、アジア大陸との距離は長大で、それを渡るのは船でさえ命がけのことで、まさに運を天にまかせた行為でした。
ただ、朝鮮半島は、途中には対馬という飛び石もあって、古代からの渡来人の通路でしたし、豊臣秀吉のように、日本列島を制圧した勢いに乗じて、大陸への侵攻を試みる通路にしました。こうして、朝鮮半島は、日本人にとっての野心を実現する道具となり、逆にロシアという大国が勃興してきた際には、対ロシアの緩衝地帯とされたわけでした。
「親離れ」なき日本人
こうした日本人としての特徴に、いわゆる知識としてではなく、実感を伴って気付かされたのは、やはり、外国に飛び出してから、違う国々の人たちと実際に接して、その違いを体験的に知ってからでした。
私はそうした自分の体得を、人間の大人への成長過程になぞらえて考えさせられました。
つまり、人間、大人になるプロセスにおいて、「親離れ」するかしないかという決定的な分岐を体験します。
これは私の自説ですが、人間とそこに生きる自然条件とは、集団的なレベルで、この「親と子」の関係にあるようです。すなわち、ことに農耕を生活手段としている封建時代までは、このいわば土地と密接に結ばれた共同体関係の内にあると言ってよいでしょう。
これが、日本の場合、島国に加わるもう一つの自然条件で、ことに、その列島上に国家という支配形態が形成される過程で、その古代からの統率者である王、つまり天皇と、武士階級という新興の統率者が、共に異民族ではなく、互いに持ちつ持たれつの独特の国家形態を作ってきました。
それが、江戸末期の黒船体験によってその島国の眠りから目覚めさせられ、その近世の外敵侵襲を克服する手段として編み出されたのが近代天皇制という人為的神体構造、すなわち「国体」でした。
そこで、この天皇制を上記の「親離れ」過程と対比させてみるのですが、日本人の精神構造を形成した決定的な要素として、この「天皇離れ」の有無という分かれ目があり、明治以降、国家が丸ごと家族として天皇を大父に頂く、「親離れ」を意図的に欠かせるどころか仰ぎ従属する思想が浸透させられたのでした。それが明治維新――英語ではMeiji Restorationと訳され、その意味は「明治王政復古」――で、西欧の市民革命とは決定的に性格を異なわせるものです。
つまり、この「明治維新」は、西欧の市民革命と対比すると、西欧では、王政の崩壊、あるいは王のギロチンであったものが、日本では、そうした劇的過程はおこらず、「無血奉還」という江戸幕府の解体と天皇をトップに掲げた明治政府の結合がなされたのでした。
その際の江戸幕府と明治政府との間の内戦を、背後から操ったのが西洋列強で、ことに薩長軍に軍資金と近代武器を内密に提供し、明治新政府側の優勢を工作したのでした。
ここで重要なのは、明治維新後の日本の政治体制は、意図的にこの「天皇離れ」をさせない、国民を《未成年状態》のままに留め置くことが維持されてきていることです。つまり、「乳離れ」していない未成熟な国民を作り、国民は親がかりで戦争に駆り出され、「天皇陛下万歳」を叫んで戦死し、壊滅的惨劇を体験して敗戦したのでした。
そして、それに続いて戦後が始まりました。つまりそれは、日本国民のそうした精神構造を知るアメリカが、戦争指導者である昭和天皇をあえて罰しも殺しもせず、その日本の精神構造のトップに据え置いたまま、そうした国家的精神構造を丸ごと壊さずに占領して、日本の戦後体制の中核構造としたのでした。
司馬遼太郎の多くの小説を通じて、日本人に強い影響をなしてきているいわゆる「司馬史観」は、こうした明治維新過程にある「天皇離れ欠如」過程をそうとは見ず、逆に、日本的達成として美化させて描いたものと私は見ています。彼はその天皇が日本を戦争へと導いていった過程を「鬼胎」とあいまいには呼んだのですが、ついに、その「乳離れ欠如」については、気付いていなかったのか、言及はありませんでした。
こうして見てくると、日本の現代史は、戦前と戦後の二重の「天皇離れ欠如」の内に形成されてきていることが判ります。
したがって、私の見るところでは、日本人が行う『「自‘遊’」への旅』とは、その成果において、その意味の「親離れ」「国離れ」もする効果を体験することになると信じています。
なお、このあたりの日本人の精神構造の分析に関しては、私の別記事、「私の日本分析」をご参照ください。
食うジレンマの底には
実は、本書の第1章で述べた「生存手段確保の鉄則」の深い底には、こうした「天皇離れ欠如」に見られる「親離れ欠如」の精神構造傾向が、姿や形を変え、執拗かつ隠蔽されて形成されてきたからだと私は見ます。
私たちは、自分たちを、そのように、何とも居心地悪く強要しているものとの感触あるいは「空気」は共有できても、その出どころがいったい何なのか、そこまではなかなか視力が及ばないものです。
そのためには、どうしても、いったんその井戸の底から抜け出て、外からその風景を見る必要があります。私の留学体験が物語っていたように、それはその人を裸にさせます。そしてその裸から、自分がどんな服をまとっていたのかを覚ることとなります。
日本社会にすでに二十年前から「パンデミック」のように拡大している《暮らしにくさ》の背景には、直接的には、物的インフラの柱である経済状況が直に作用しているのですが、どうやら、日本人の誰もの奥底に、誰かに依存していることを是とする心理構造が、いつの間にやら植え付けられ、物を言わぬ大人しい日本人性を作ってきたのも、その土壌となって働いているからです。
あるいは、たとえば介護や教育やひいては貧困の問題など何かにおいても、社会共通の問題が、どうしても家族中心に考えられがちな日本的特徴も、それが社会的必要であるとの発想以前に、つい身近な親族的問題と考えてしまう習性にも、そうした親子独立していない精神構造が根底にあるからだと考えられます。
むろん家族の絆はかけがえのないものなのですが、そういう家族関係に託される問題と、社会的に解決されるべき問題は、混同されることなく、分離して考慮され対処されたほうが有効な結果が期待されます。たとえば、いい成人がいつまでも親元を離れられない「パラサイト」問題なども、そうした社会的問題が家族的引き受けに任されている典型であり、早い時期での社会的手当てが見逃された例です。
同様な傾向はさらに、職場の中にでも指摘でき、日本の労使関係は、終身雇用を前提とした年功序列制という、家主と専業主婦という家族構成を前提に、その中心構造をなしてきました。
そうした日本型雇用制度も、企業や産業による濃度差はありますが、この20年ほどの間で次第に変えられてきており、成果や職務を中心とした、欧米式の“親子独立型”が取り入れられてきています。
ことに目下のコロナ禍にあっては、テレワークを導入するためには、どうしても個々の仕事の輪郭を明瞭にする必要があり、こうした変化が加速されています。
また、今日のグローバル化したビジネス環境では、その職務自体が外国体験をもたらす、あるいは、すでに外国体験をした人間を採用するといった、地理的移動が前提となった仕事が増えてきています。
加えて、日本の国内市場の縮小に対応して、多くの企業や産業の海外進出の熱は高まっており、それに応じた海外勤務を前提にした働く口も増えています。
ただし、それがたとえ外国に出るチャンスを提供しているにせよ、それがなにせ「食うため」の必要を担っているわけですから、視野も広げる一石二鳥となるか、それとも、局所異国体験仕事で終わるのか、微妙なところと言えるでしょう。
6 思潮のパラダイム変化
世界ナンバーワンの日本
私が若いころ、魅力ある海外といえば、やはり、欧米先進諸国でした。
つまり、世界の長い歴史の中で、西洋は、世界文明の先端を切り開き、それがゆえに、世界を制覇し、殺戮を繰り広げ、世界からの富をかき集め、諸戦争に勝利し、世界的機関の中心を占め、善きにつけ悪しきにつけ、世界をリードしてきました。それがゆえ、先達として、輝くものを持っていたのでした。
そうした西洋の優勢が、端的に言って、ちょうど私の世代のほぼ一生と重なって、様々な経緯や議論を経ながら、次第な凋落期に入ってゆきました。
たとえば、私がオーストラリアに渡った1984年10月、1豪ドルは220円ほどのレートでした。それが、1985年の日米のプラザ合意で、アメリカは経済力の強まる日本に対し、日本製品の国際競争力を弱めようと円高を認めさせました。そうした円高により、ほんの数カ月のうちに、円は豪ドルに対し、百数十円にまで跳ね上がったのでした。
当時、日本で貯めた乏しい貯金を豪ドルに替えて持ちこんでいたのですが、なんとその豪ドルが、その換金の時期が数カ月遅ければ、ほとんど倍にもなっていたのでした。「こんなことなら、早く教えてくれよ」と、ぼやきたい気分でした。
その後、日本はそうした強い円を使って、文字通り、世界の資産を買いあさりました。1989年、ニューヨークのロックフェラービルが三菱地所によって買収され、ニューヨーカーの反発を買いました。オーストラリアでも、シドニーの主だったビルは、ほとんど、日本人の所有となりました。
そうして、当時世界二位の経済大国であった日本は、そのうち、アメリカを追い抜いて、世界一の大国になると豪語すらしたのでした。まさに絶頂期で、そうして膨らんだバブルがやがてはじけたのでした。
今の中国を見ていると、そうした当時の日本の鼻息とそっくりです。
ともあれ、こうした経済的趨勢がその一面を物語っているように、西洋の劣化が次第しだいに見え始めたのでした。
西洋の黄昏
こうして、前世紀の後半より、西洋の限界は広く指摘され始め、それが今世紀に入り、いわゆる「先進欧米諸国」の陰りがいろいろな分野で顕著となってきています。ことに、今のアメリカの混迷したあり様は、昔、アメリカの人気テレビ映画――「名犬ラッシー」だの「ローハイド」だの――を見て育った私の世代にとっては、見る影もないものです。
明治以来、東洋諸国のうちで、ひとり自国の西洋化を成功させ、その西洋モデルをアジアに展開して帝国主義の拡大をはかったのが日本でした。
その「大日本帝国」は、アジア各国の植民地化を展開、文明化とさまざまな禍根を残し、今日もその後始末に苦心させられています。
そこで、もはや西洋文明は衰退の道に入り、いまや東洋文明がそれに取って代わる時代となったとする見解があります。その典型が中国です。
そうした中国の独善史観は、古代からの系譜を持つ、世界の中心が中国であるとの中華思想の根幹とはいえ、今やそれが世界的緊張をもたらし、世界の不安定あるいは懸念材料の筆頭となっています。
かつて、アメリカを追い抜くと豪語した日本にバブルを起こさせ、その自沈に成功させたアメリカは、今度は、中国にさまざまな注文をつけ、その勢いをくじこうとしています。
西洋文明がその過去の蓄積を生かしてなんとか優勢を維持する努力を進める一方、東洋は、世界の新たな成長の地域となって浮上してきています。
尖閣列島をその北端とし、西太平洋は、いまやまさしく、その東西対峙の最前線となっています。
東洋が西洋を凌駕し、産業革命までの時代のように東洋が世界の中心となる時が復活するのかどうが、それはまだ、誰にも見通せません。しかし、その気配は刻々と現実のものとなってきています。
中国は、経済規模において、アメリカを抜く時を視野に入れ、今後の世界における文明モデルは中国として、対外政策としても「一帯一路」構想をもって、少なくとも周辺諸国の中国化を図っています。
日本は、戦後のアメリカの占領下そして事実上の属国としての75年間の一方、こうして拡大する中国を隣国とし、自国語への漢字使用が代表しているようにその文化的影響圏内にあって、果たしてどのような方向や位置を定めてゆくのか、いまや重要な転換点に差し掛かっているのは間違いないでしょう。
もう一つの隣国である韓国も、日本と同様な位置にありながら、一種の米中二股政策をとりつつ、そのシナジー効果というより、むしろ両国からの不信感を招いています。
この歴史的な東西バランスの変化と東アジアの緊張は、日本にとっても、判断を誤れない、実に重要な局面であるのは確かです。
東洋思想の神髄
以上のような歴史的な東西文明の関係変化が起こってきている中で、そのような東西の枠組みの内に築かれてきた思想にも、当然な変化があります。
それを、本書のテーマである「拘束」という角度において注目点をあげてみます。
そうした世界の重心が西から東への変化は、むしろ、西洋人から見た観点を取り上げた方が、東洋側のひいき目を避けた均衡ある見方となるでしょう。
ここで、そうした観点で最適な文献を以下に引用します。それは、ウィリアム・バレット(William Berrett)という元ニューヨーク大学哲学教授による著書『ZEN BUDDHIZM』(2006)の西洋人読者に向けた導入章「Zen for the West」からです。
その冒頭での、文字通り西洋人に語りかけたじつに明瞭なメッセージがこれです。
〔19世紀〕以来、東洋研究の分野において、大きな前進がなされてきたが、奇異な逆説的偏狭性が西洋をおおい、地球のありとあらゆる部分への侵入を果たしてきたその文明は、非西洋人の知恵への偏見をいまだに抱き続けている。日曜報道番組に、「ワンワールド」 といった標語がありふれたテーマとなった今日にいたっても、それは、先端の情報通信技術網によって今や全地球が一体化されているとのみ理解する、純西洋的な意味において解釈される傾向がある。だが、その標語が、東洋という対極と朋友を受け入れる必要性を意味していることは、公然と無関心のかなたに放置されているかのようである。しかし、多くの兆候は、こうした西洋世界の傾向が変化しなければならないことを物語っている。
この著作は、その題名の通り「禅」についての本で、禅師の大家、鈴木大拙の著述を解説したものです。そして、禅思想に注目する理由が、西洋文明がいかに「奇異な逆説的偏狭性」でおおわれているかであったのです。したがって、その記述は、単に西洋思想の変遷を概説しているだけでなく、仏教思想についても解説しており、今日の日本人にとっても、極めて有用なまとめとなっています。
ただ、その全貌をここに紹介するのは本書の目的ではなく、ここではそのさわりの紹介に留めます。しかし、一読に値する貴重な著述です。原書は邦訳されていませんが、その導入章の「西洋にとっての禅」については、私の拙訳が以下のアドレスで読めます。
(https://retirementaustralia.net/old/rk_0706_gaku21.html)
この導入章のなかで、同教授が強調していることは、東洋思想、ことに禅思想による特徴が、「抽象化をさけた具体的で単純な」方法であると述べています。
西洋流に言えば、直観的な発想ということとなるのですが、そういう西洋流説明でも、なかなかこの「具体的で単純」な方法には迫れません。
同教授はそこで、例を挙げてその方法を表しています。すなわち、それは、禅の公案に関してで、こう述べます。
人が禅を学ぶ前には、その人にとって山は山であり、川は川であった。禅を学びはじめると、もはや山は山ではなく、川は川ではなかった。しかし、いちど悟りの境地に達するや、ふたたび、山は山となり、川は川となった。
(『西洋にとっての禅』の「真実性の把握」)
ちょっと突き放して言えば、このように、目からウロコさえ取れれば、視界は変わります。問題は、目にウロコをかぶせている自分自身の考えであり、ものの見方です。
私が「旅」なり、食ってゆく生活実情なり、実際の体験を重視するのも、そうしたまるまるの経験の中に含まれている、分析や論理や抽象らのすべてが一緒くたになっていながら、そのいずれにも陥らず、それでいて完全体となっている何かです。
それは、ここで「山と川」というだけでも通じるものです。その辺の大きな含みを込めてまるまる保持されるものです。
ですから、逆に、西洋的な分析を通して各部分をばらばらにする考え方では、時にして大きな見落としを生み、それが自身を拘束することにもなるのです。
上記のバレット教授が「奇異な逆説的偏狭性」というのは、そうしたばらばらにされた部分のことです。だからこそ彼は、「こうした変化のすべてにかかわる実に重たい逆説は、我々西洋人の文化の奥底あるいは上層でおこっているもの」とその後に述べているのです。
歴史の変遷を一言でいえば、日本人は自らの壁を西洋化で越え、西洋人はその自らの壁を東洋化で越えようとしているとの流れです。
もうこの辺りのどこかに、折り合う融合点があってもいいはずです。
7 統合した一体へ
本書がいう「旅」とは、もちろん、「人生は旅路」であると言われる「旅」のことです。
ですから、それは、コロナ禍のために、たとえ国境が閉鎖されていようが、飛行機が飛ばないでいようが、人がどこかで生きている限り行っている「生きるための奮闘」のことです。
そうして私たちが奮闘している時、それは、本書に章を立ててそれぞれの項目が述べられているようには、個々の要素がそれぞれ別々に考えられているわけではないでしょう。
私も、本書を書くにあたって、それぞれの章は、その全体のすべてが一体となったものを、あえてばらばらにして、それこそ、分析的に書き上げたものです。
先の西洋文明の凋落で述べたように、分析的方法は、科学にせよ、西洋医学にせよ、確かに、ひとつの部分を克明に研究するには有効ですし、もともと、世界が何かを理解するにあたって、それを細かく分けていって、その素の素を見出せば、世界が理解できるといった方法論に基づいているものです。
そうした方法は、ただし、それに基づいて何かある分野を解明した人にとっては、その分野の専門家として、それは社会全体にとっても有益なことでした。そしていまやどの社会にも、そうした専門家が無数に存在しています。
だが、そうした専門家として生きているのではない、普通の人たちにとって、重要なのは、自分や家族が幸せに生きることで、言ってみれば、そのための生業が何であるのかは、さほど重要なことではありません。
ただ、現代の社会で、それなりの収入を稼ぐには、なんらかの分野の専門技でも身につけていなければ、もう、就職口さえ得られません。
つまり、それがIT技術だろうが、料理の腕だろうが、なんでもいいわけです。しかし、学校に通っている時代から、将来は何かにならなければ生きていけない、といった強迫観念を与えられ続け、しょうがないから無理をしてでも何かをすることに決め、それの準備をしてきたというのが実情でしょう。
もちろん、小さなころから、何かが好きとか、それをするのが上手といったことを発見していて、その芸が役に立つのみならず、周囲とか社会からも注目されるようになって、芸術家とか、職人とか、スポーツ選手とかとの道を選べてゆく人たちもいます。しかし、そういう人たちは、社会全体から見れば、ほんの一握りの人たちでしょう。
そうした技能のない「凡人」たちは、その選択や決定に苦労し、悩まなくてはなりません。そうしてやがて学校を卒業する時に至れば、誰もがそれに奔走する「就活」巻き込まれ、あせらされ、運よく時代が売り手市場の時に当たればいいものの、それが逆の時には、それこそ塗炭の苦しみをなめさせられます。そしてそのあげく、間違った選択をして、楽しくも何でもない仕事につくことになって挫折したり、転職を繰り返すこととなります。
そうした一部始終は、本書の第1章の「食ってゆくジレンマ」に述べた通りです。
かくして、生きて行くために、そうした多々の拘束にまみれてゆくこととなり、そのあげくには、何やら自分でない自分になっていることを見出すこととなります。
本書が「旅」と呼んでいるものは、そしてその「旅」を旅する極意というものは、そのように拘束にまみれさされる道の「逆を行こう」というところにあります。つまり、何かを選ぶしかなく、何かを演じさせられている際、そうしたたくさんの拘束によってばらばらにされている自分に敏感となり、いつも、全体のまるまるの自分の発見に努めよう、というところにあります。
ですから、望むことは、本書に述べられた諸拘束という各項目を、それをヒントに自分で点検し、排除し、その自らの全体像を見つけてください、ということです。
そうした自分の全体像がはっきりしてきたら、それこそ、ばらばらだった視点がまとまってきて、自分自身はもちろん、自分の周囲を起点にして、社会や世界が何であるかさえ、だんだん見えてきます。
逆に言えば、その時あなたは、自分の視点をはっきりと持った人物となり、ユニークで、そうした自身を仕事に投入すれば、いわゆる創造性を発揮できることは間違いないでしょう。
以上のように、本書は、その執筆のタイミングとして、コロナ禍の時期に合わせたかに述べられていますが、そうしたタイミングの問題は、基本的に関係ありません。
それがどのような時期であろうと、それが私たちの人生に重要で必要なことに変わりはありません。
日本はこれまでの歴史で、世界の先進国文明を後追いする立場にあり、それを追いつけ、追い越せと、ある意味ではゴールのはっきりした競争を勝ち抜いてきました。
それが、前世紀末、ついにそのゴールにまで達したものの、その後の新たな目標も方向も明瞭にできず、20年以上の停滞期をすごす結果となっています。
そうした停滞が示唆していたことは、日本が明治以来、永年にわたって慣れ親しんできた西洋モデルがもはやモデルではなくなり、日本が自力で自分の道を見つけなければならない時点に至り、その発見の難しさに苦しんできたということです。
その上に、いまやコロナ危機が世界をおおい、これまでの常識や秩序が、一夜にして無用と化し、新たな時代への混迷期を体験しています。
世界が懸命になって開発中のコロナワクチンが成功すれば、一気に世界の雲が晴れる期待もあります。しかし、そうした想定も含め、すべてが、机上のデザインです。
そういう意味では、本書に提唱する「旅」を念頭に、まさに『「自‘遊’」への旅』がいまだからこそ始められる好機にあります。
あとがき
「はじめに」の末尾で触れましたように、本書の出版に当たり、その表紙も自分でデザインしてみました。そのため、素人臭いものとなっているのですが、それはともあれ、そこに空を舞う一羽の鳥が、いまにもその空に開いた「窓」を通って、さらに、空のそのまた空へと翔んでゆこうとしています。
今日、時代の趨勢に流され、私たちは、その「空」を見上げるいとまさえ無くしがちです。しかし、その空にさらに窓を開けてさらなる空をみることができるのか否か。そういう「旅」が、もはや数千の旅客航空機が地上に釘付けになっている時であるからこそ必要となっています。これはけっしてレトリックでも、仮想現実の話でもありません。それは、考えようしだいで確かに手に入る、現実の話としての「旅」です。
ひっくり返して言えば、そのくらい、架空は現実的となっています。
今のコロナ禍を、ただ敵視するばかりでなく、その「お陰」を取り上げる見方も、決して少なくはないようです。
私も別の機会でその辺りを論じましたが、どうも「コロナ」の背後には人間の力ではどうしようもない「自然の摂理」といったものが働いているように思われます。それは、この新型コロナウイルスが「なかなか賢い戦略を持っている」と擬人視される驚きにも見られます。実際に同ウイルスがそうした「意志」をもっているわけではないでしょうが、解ってきている頻繁な突然変異という機会を通じて、同ウイルスの変異の結果に、何が生じてくるのか分からない、言わば「何でもあり」のあらゆる可能性を秘めているわけです。ゆえに、その変異の中には、たとえ偶然であれ、人間の思惑の及ばぬ、あるいは、まったく裏をかかれた変異の出現すらありうるわけです。
私たちは、そうした異変の結果、人間社会に積み上がってきた思いもよらぬ弱点が突かれ、人類全体が慌てふためいているさまを、いま、まさに目撃しています。
しかし、そうしたピンチは、まさにチャンスです。
本書に指摘した諸拘束も、そうした混迷の中で右に左に揺れています。
そうした時期であるからこそ、その「旅」への着手が、大いなる成功への鍵となるに違いありません。
自信をもって取り組んでください。
著者略歴松崎 元(まつざき はじめ) 1946年8月20日生。1969年、芝浦工業大学土木工学科卒。建設企業社員、建設技術者労働組合専従を経て、1984年、オーストラリアへ留学。西オーストラリア大学で労使関係学修士、ニューサウスウェールズ大学で博士を修得。以来、オーストラリアに永住。ビジネスコンサルタントを共同創業。目下、以下の二つのウエブサイトやブログを運営。 https://retirementaustralia.net/ および https://philearth.space/ |
©2020 Hajime Matsuzaki

