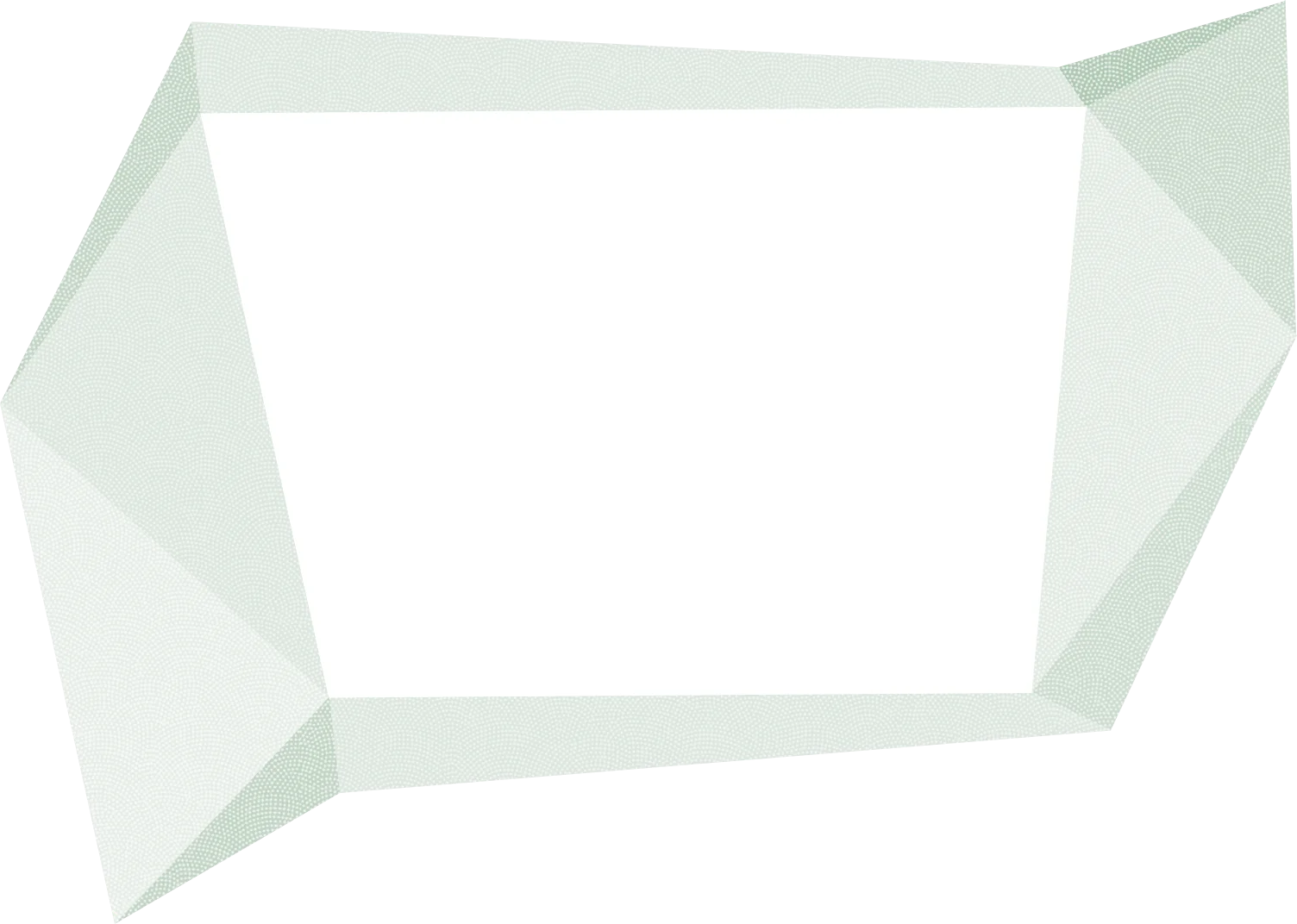この連載ではこれまで、「変容する主流パーソナリティ」、「戦争しない国はどこ」、「〈脆弱〉から〈天才〉への飛躍」と題して、人間の主要パーソナリティや社会の趨勢、そしてことに戦争状況への可能性に焦点を当てた視点を述べてきました。
今回は、そうした過去の変化への考察に立って、それならば、将来はどうであるのかという予想の視点です。
ことに国際政治にまつわって今後を見ると、トランプ政権とプーチン独裁の奇妙な親近性、そして、独裁という意味ではその度を日増しに強める隣国中国の習近平政権といい、今に至って急激に変化している世界情勢があります。それと日本の、あたかもタガが外れたような、基軸をなくした政治状況と照らし合わせてみる時、野獣の群れに包囲されたかの、悲愴的にすらならざるをえない、今後の情勢が想起されます。
ウクライナ情勢でみれば、すでに、このトランプとプーチンの両国家エゴ同士の隠然同盟化のもとで、停戦合意という大義名分のもと、事実上の切り捨て――少なくとも“現状”固定化――の動きが否定できなく見えてきます。
日本国内に目を向ければ、「台湾有事」という意味深刻なはずの表現が、日増しに頻繁に語られるようになっています。それは、受動、能動の両側の立場からの発言ではあるのですが、いずれにせよ、大国同士の都合に揺すぶられる、台湾のウクライナ化すらをも想定した、一種の「非常事態備え論」です。
さらに、トランプの反中国の鼻息も、中国側としては、トランプ独特の“ブラフ政治”が生んでいる混乱のなかで、恐れるに足らずと高をくくれているのかもしれません。
ことに、避けては通れない東アジア情勢の今後めぐり、日本のとみに無定見な政治家にとっては、従来の“アメリカ属国”を堅持するのか、それとも、“一国中国”へと重心を移すのか、その「有事」という言いようにある両天秤的な主体欠如がにじんでいます。
さらに、イスラエル・パレスチナ問題に目を向ければ、人権を無視した武力行使が繰り返され、すでに、力によるなし崩しな奪取が成立しつつある実例が見られます。
こうした一望をもって本独想を新ためて記すと、先の「戦争しない国はどこ」にも述べましたが、当然すらもの原則が無残に軽視されつつある世界の政治状況にあって、民主主義と称される民意反映の鉄則――二度にわたる世界大戦の巨大悲劇体験からの人類の遺産――をどう維持し、かつ、一握りの政治家に運命を任せてしまう過ちをいかに回避し続けてゆくのか、自分たちがいまやその分水嶺にあり、今後どちらの側に流れ下ってゆくのか、よく見定めなければない事態に差し掛かっています。
【追記 2025.07.25】
関連記事〈「右派ポピュリズム」からの脱出シナリオ〉参照