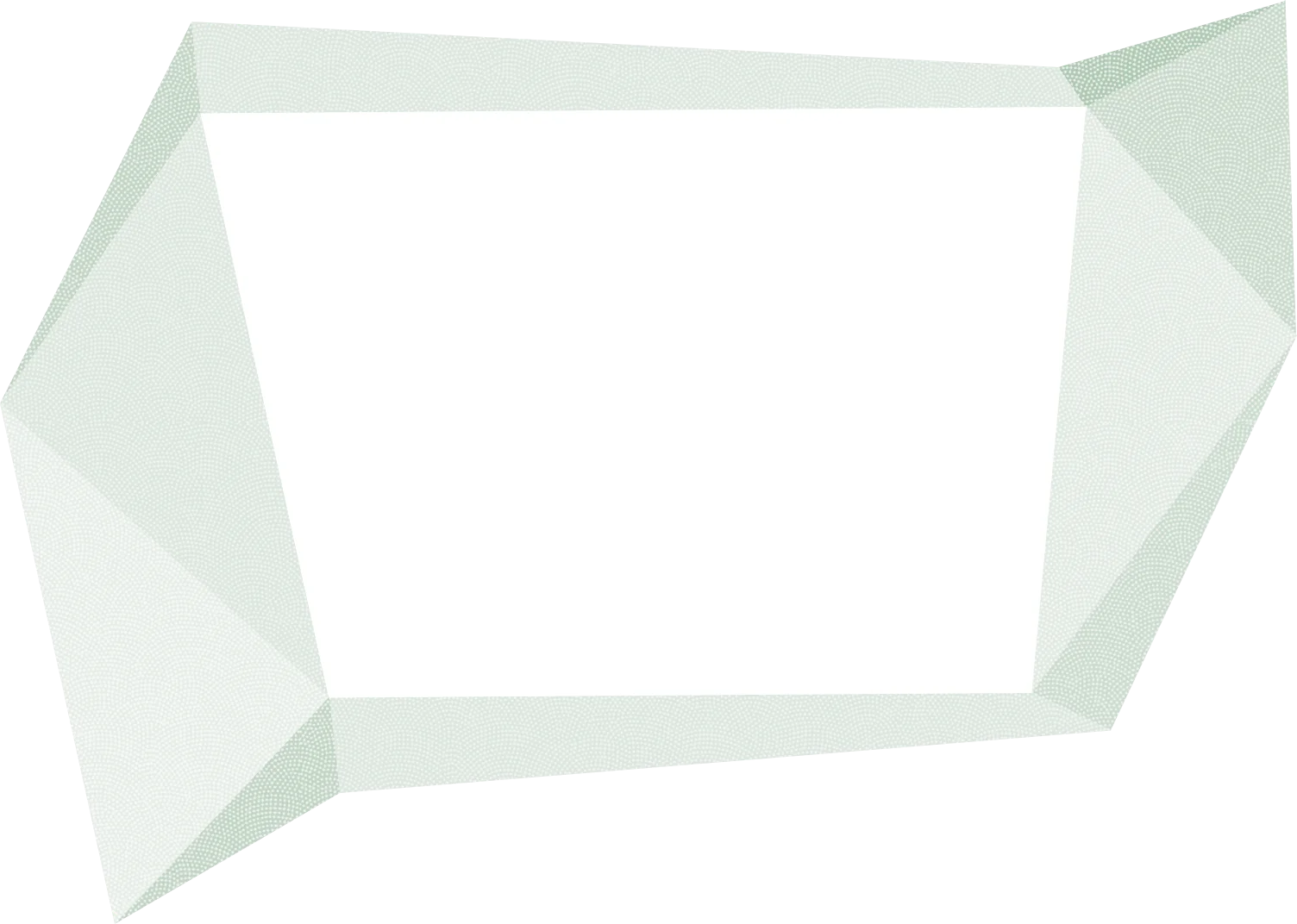これはひとりの男の私見だが、いったん男としての沽券を捨てると、この世のもやが晴れるように出現する、見通しのよい視界がえられる。
それはたとえば、女のもつ、正直言って男には到底なしとげえない、適応能力が成す風景である。
もっと言えば、世界のどこであろうと、そこを根城に棲みついてしまえる、根源的な生命力だ。
ちなみに、そんな生命力の一端を垣間見た体験談だが、海外生活を始めたばかりの三十代末、日本の女性が外国人とまるで造作なく――ともあれそう見えていた――結婚し子をもうけてゆくことに、内心、妙に意固地で焼き餅臭く、国粋主義の衣すらかぶった反発をくすぶらせていた。ひと口で言えば、「俺の国の女に手をだすな」といった劣情である。
そこで、女性のこの「根源的な生命力」がどこから来るのかを想像してみるのだが、それはやはり、生命を宿す、あるいは、それを前提として備わっている、雌としての生命機能に裏打ちされた生物力かと思う。
唐突に、こんなことをなぜ言い出したのかといえば、先に書いた中央アジアの旅において、その一員になることとなった四人組形成がかもし出す「不思議」が開いてくれた、ひとつの視界があるからだ。
そしてその視界に出現し始めていることは、40年前まで私が関わっていたその男社会の典型である業界が、ある変貌をとげてきている様相を、この長いブランクをこえて見せ始めてくれていることだ。
加えてそこには、そのキー要因として、女性の存在、あるいは、この「根源的な生命力」が、決定的に作用しているようなのだ。
そしてこれもそこに表したが、その不思議をもたらすものが、「量子理論」だの「もつれ合い」などとは述べてみた。そこに、そうした不思議を発生させる未知な働きを持ち出すそんな突飛な発想も、もちろん、的外れではないだろうとは思う。
しかし、その開かれた視界に見えてきている、もはや既存の事実にさえなり始めている光景は、そんな解明を待たねばならない必要のあるものなどではない。
つまり、その光景が告げていることは、上述のように、男の沽券がしだいに存在意義を薄れさせてきている避けられない流れだろう。そして、その結果にもたらされている、壁をとっぱらわれた後に見られる、風通しのよい風景だ。
すなわち、この〈雌としての生命構造〉に秘められた、〈雄〉には思いもつかないような異なった発想や行動が、確かに存在しそして機能していることだ。
かつて自分が抱いたような反発は、いくらなんでも過去のものだろうと願うが、男社会のこの業界に、勇敢にも参加してきている女性たちが、ほとんど半世紀を費やして、そうした宿痾に風穴を開けてきているのは間違いない。
それを男社会の論理によって、「人手不足を解消するための女子採用」などと取りつくろい、なんとか永年の沽券を保ってはきているのだろう。
だが、そうした男の納得とはほとんど無関係に、その世界に魅力を見出す若い命が、純粋な関心と希望を抱いて参画してきているのも確かなことだ。
紆余曲折はあっただろうが、そういう両者の意向が対面し合って、その男社会に新たな風が吹き始めている。
私は上述のように、今回の旅での出会いを機会に、あたかも、40年の隔たりが霧消するかのような、思いもよらぬ不思議な出来事を体験した。
そしてそれの核心は、こうした新風をおこす若い息吹の存在にあると、あらためて思わされている。
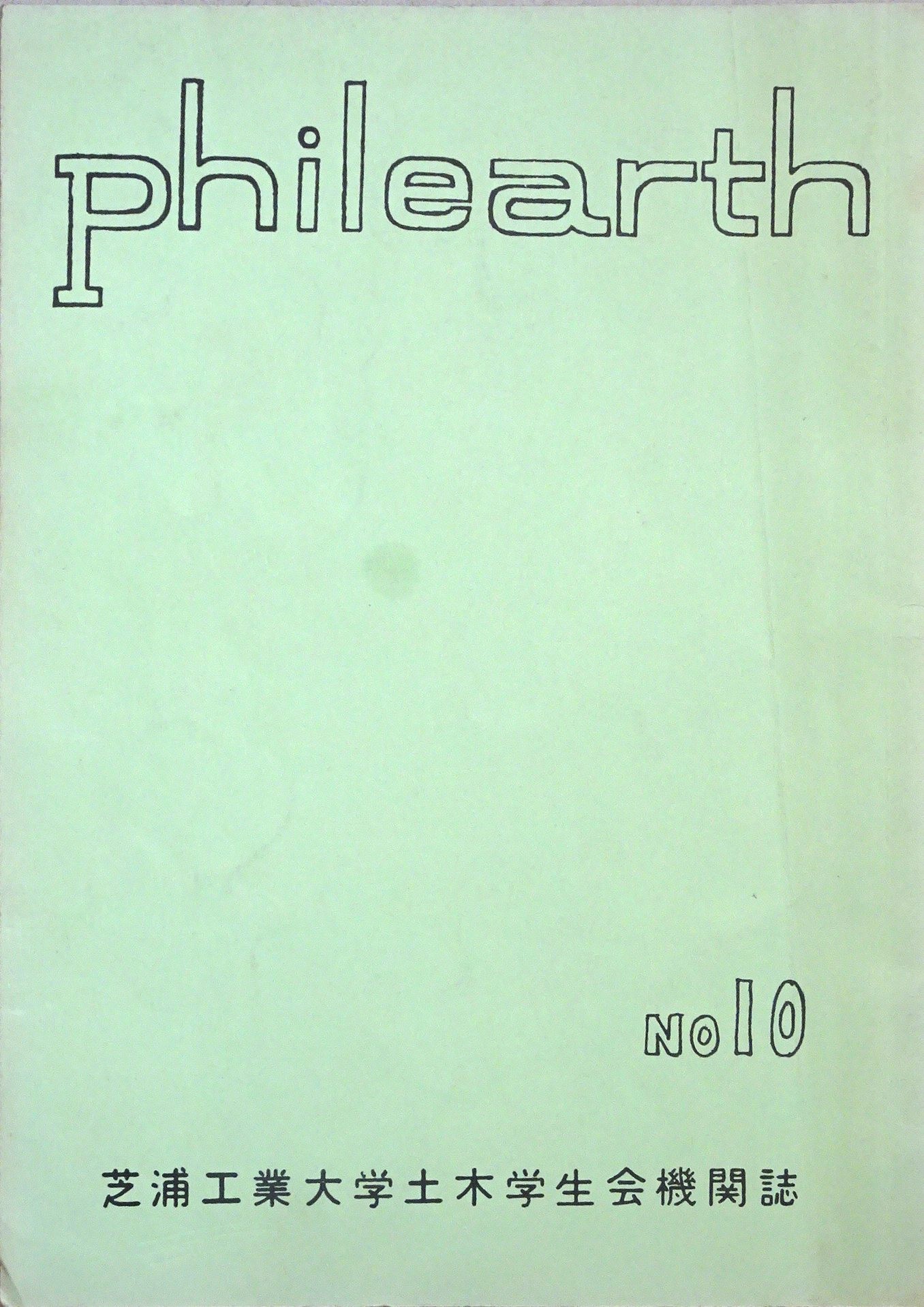
奥付には、昭和48年6月15日発行とある。
ところで、そこで想い起こすのだが、私の別サイトのタイトルの出どころである、出身校の土木学科内学生組織の機関誌の名『Philearth(フィラース)』(右写真)も、遠く1960年代末に、やはり、そうした新風のひとつとなるべく、当時の若い意欲によってそう名付けられたものである。
以下は、蛇足めくのだが、その表紙裏に掲げられたその命名の言である。
土木とは“大地”に基づく技術である。/そしてその大地を、哲学者が智を愛するごとく、愛するのである。/ここに土木学生会の機関誌の名前が生まれた。/愛智の愛を意味するPhiloと、大地を意味するEarth、この二語が結合されて、その名Philearthが生まれた。/この地とはもちろん土という意味ではない。我々人間の母なる大地として、自然界すべてを包含している。我々土木技術者がこの愛を失う時、母なる大地はその生命を危うくするであろう。
時代は変わろうとも、変化の流れはとうとうと続いている。
一方、四人組の成立をもたらした実に不思議な出会いの発生自体ついては、こうした新風の作用とは、通底はしているのだろうが、一種別の脈絡によるもののようで、ただの偶然には帰せない何らかの作用の働きとして、ことにその『フィラース』上にて、注目している。
特に今度の遭遇は、「旅」をめぐって発生しており、その「旅」とは、リアルからメタにわたる連続をも成していて、その不思議の成り立ちについての、一つの仕組みを示唆している。
そしてそれは、この「旅」の実践が文字通り自身の「健康」によって支えられていたという、リアル→メタ→リアルと、輪廻循環をなす因果にも連なっているようだ。