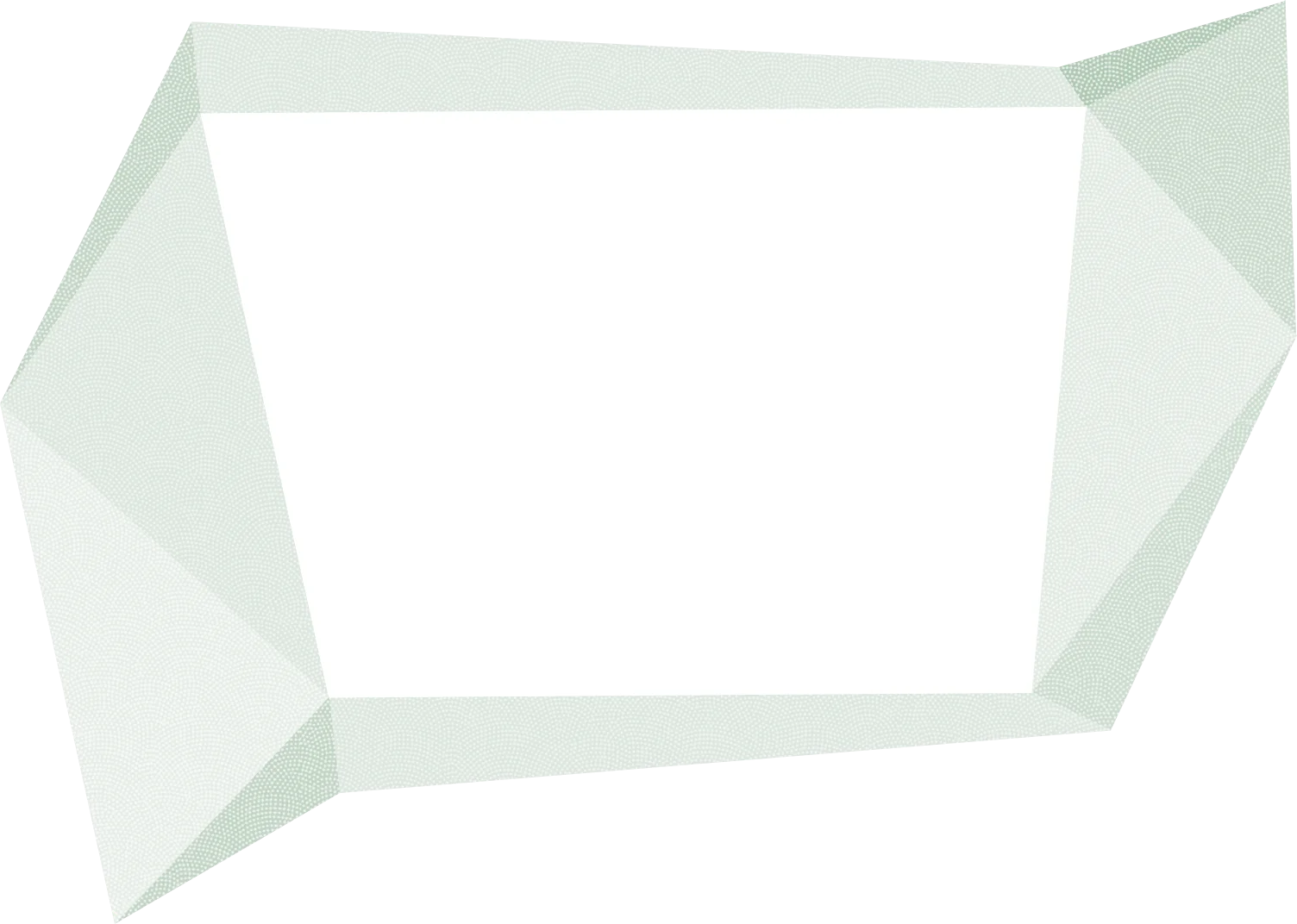20年ほど前、「相互邂逅」という半自伝を書いた。それは、自分が十代末から書き残してきた二十数冊のノートを数十年ぶりに読み直す機会があり、そのあたかも今の自分が若き自分と再会しているかのような、思いもよらぬ体験について綴ったものである。
それらのノートは、それが記されたその時点では、数十年後の自分が、まさかそれを手に取って開きそして読むなんてことは想像すらされておらず、あくまでもその時の自分の胸中を独白したものだ。他に何の意図もない、「一人称」の書残しである。
そうしたノートの再読体験を通じて、その時その時の自分が日々感じ、考えていたまさに生のメッセージに接し、その書き手が今の自分と同一人物であるのは確かだとは言え、それを書いている当時の私は、まるで初々しいほどに真摯な若者で、そういう彼にそのように接しながら、ひとりの新たな若き知己を得たかのような、実に新鮮な感慨を抱かされていた。
加えてその体験は、そこにまさに生きている彼の息遣いが生々しいほどに伝わってくるリアルなもので、よってそういう彼にまさに教えられるように、その彼がいまの自分の礎となっていたのだと改めて認識する、自分らしさの系譜を見出すものとなった。
それは、もちろん想念上の出来事なのだが、たとえそうであったとしても、時代を隔てた二人が出会う、事実上のタイムスリップと言ってもよい体験でもある。加えてそれは、そのようにして時間を超える移動体験を実際にし得るのだと納得するにも充分なもので、なにも「超自然能力」などとことさらに騒がなくとも、現の自分がそのままにして所有する、自然な交信能力の存在として実体験しえていたものだった。
1
さてそこで、そうしたタイムスリップ実体験を下地にして、自分が持つあたかも時間軸にそって縦に長くつらなる自分自身の存在感を、改めて発見することとなった。
そしてそれを《越時間アイデンティティ》と呼ぶとすると、この《越時ID》は、今の自分がこの先の未来にわたっても存在し続ける感覚を持つことにも通じるものだ。
つまり、こうして書き残している話も、将来の自分が再読することはもとより、自分との個体が死んだ後も、その《越時ID》が、さまざまの存在にも伝わりうるものとなるだろうことが、実際に想定できるものでさえある。
かくして、私たちの誰もが語るそうした「一人称」のストーリーも、すでにそう語ったその時点で、未来の誰かと交信する「二人称」のストーリーへと共感発展できる潜在性を秘めている。
すなわち、このようにして生まれている「一人称」の「二人称」へとの発展は、何らかの媒体すら存在すれば、時間を隔たった伝達性を発揮するものであり、私の過去の「相互邂逅」体験を未来への反照させたかのような、「未来邂逅」体験と呼んでもいいような、一種の交信回路が存在しうるということである。
一方、実は、生命と意識をめぐる有限と無限という「二重性」をテーマとして、こうした未来への伝達については、別記事でも述べてきた。
すなわち、自分の書き残したこの「未来邂逅」たるメッセージの受け手であるべき、未来に生存している新たな生命、つまり、子孫、あるいはもっと広く、次世代、次々世代の存在とのつながりである。これは言い換えれば、生命についてのそのような連続性、永遠性ということであり、そのようにして、生命の有限性を超える無限性が、現実的かつ日常的なものとして、存在しうるものと認識できるものである。
そこで、こうした「相互邂逅」から「未来邂逅」への体験をさらに発展させれば、こうした体験をもって、それを私たちが持つ、俗に言う「超自然能力」の実証としてよいのかどうか。
そこにはむろん異論も多いだろうが、少なくとも私は、こうしてさまざまに書き残すメッセージを、そうした時間軸に沿う縦の伝達性に乗せて、現在の自分の存在意義にしえると考えている。つまり、私という《越時ID》は、今に、孤独に存在しているわけではないのだ。
ところで私たちは、過去を想い起せば、いわゆる「むかし話」とか「おとぎ話」として、あるいは、おじいちゃん、おばあちゃんからの口伝えとして、そうしたいろいろなメッセージを聞いて育ってきたはずである。
たとえば、母親を通じ、“おばあちゃんがお前のことをこう言っていたよ”といった、世代を通じたひとつのメッセージを受け取ることは、それが幼い自分の心にストンと落ちて根付き、やがて芽吹いて実をむすぶ、 誰しも一度や二度に限られない、そんな触れ合い体験があったはずだ。
それは別面、文化の一部をなすものなのだが、ともあれそのようにして、先祖から自分そして子孫へと伝えられる、綿々と続くメッセージは存在するのであり、むしろ、そうした「伝え」として、生命の連続性の「情知」面の内実が存在してきていると言える。
再び言うが、人は今に、孤立して存在しているのではないのである。
2
そこでだが、本号に「《健康道》のすすめ」と題した別記事を掲載しているのだが、その中で、いわゆる健康寿命についての考察を述べている。
そこで私は、健康寿命というものを、単に、命の時間的な延長を意味するだけでなく、さらに、その延長をもってしての、人生の新たな次元の始まりを意味していると考えている。
そういう意味では、先に述べた「三周目」の人生とは、この「新たな次元の始まり」のことを意味していると言い換えてもいいかも知れない。
すなわち、人生経験(E)×健康(H) とは、人間性にいっそうの深みを創造する方法論とも言える。
これを、E×H=Vと表現すれば、この数式の V の意味するものは、健康な高齢者を抱える社会の力量のことを意味していると言えるだろう。
そしてこのVを「時空価値」と呼ぶとすると、たとえば、GNPという国民総生産自体は、時間軸上のある時点の断面における総生産、つまり一種の断面積であるのだが、この「時空価値」は、そこに「時」という奥行を掛け合わせた、時空に立体的なボリュームと考えられる。つまり、今と過去の価値が同時存在しているのだ。そしてそれがいっそう大きいということは、その社会のもつ、包容力と時系的深さといった、これまでの経済的概念では計れない、新たで血の通った社会的財産を意味するものと言えるだろう。
つまりこれは、上に述べた「未来邂逅」の、具体的な内容のひとつであり、その効果と言ってよいものだ。
そこで以下は、そうした「時空価値」に支えられた社会が今後生まれてくると考えた場合に想像できる事柄である。
3
たとえば、これから飛躍的に高度化する情報社会にあって、若い世代が、その高速な社会システムに馴染めば馴染むほど、物的な生産性も大いに高まるだろうが、人間を育てると言った人間サイズ速度がゆえに遅れがちな部分、あるいは、手仕事でしか片付けられない、美的、倫理的、そして教育的分野において、そうした「時空価値」の存在は、その遅れを満たし、それに従事する人材面でもの厚みのある社会を意味するだろう。
これをもうちょっと子細に言えば、男女等しく生産にあたる社会において、その生産性の拡大が家庭部門の役割の相対的縮小をもたらしがちな関係にあっては、ある時点をもって生産からリタイアした人たちのこの「時空価値」のボリュームが、社会的に子供たちの育成に力量を注ぐといった仕組み直しも可能だろう。ことに何らかの弱い持ち味を課題とする子供たちを手をかけてケアするといった、物や金銭的社会保障では救い切れない、血の通った温かい手によるあらたなセクターとして、社会的生誕の機会を用意してゆく、そうした新次元の社会機能の創生である。
そうした社会が、まさか、世界のもめ事を軍事力によって解決する、ことに核抑止力などという終末的な発想や手段に立脚するとは考えられず、生命の持続やそれが開花させる多様な可能性に価値を置く、新世紀の人間社会の出現を意味するだろう。
ちなみに、すでにもうその気配は、世界中からのインバウンド旅行者として、単なる物見遊山にはもはや魅されず、日本の伝統文化に触れることに価値を見出す、次世代の旅行者を惹きつけるところに、芽生え始めている。
まさしく世界の先端を行く日本の高齢化社会が、今や現にかもし出し始めているこうした次元は、そのようにも、人の世界に根源的に、新しいものとなって行こうとしているのである。