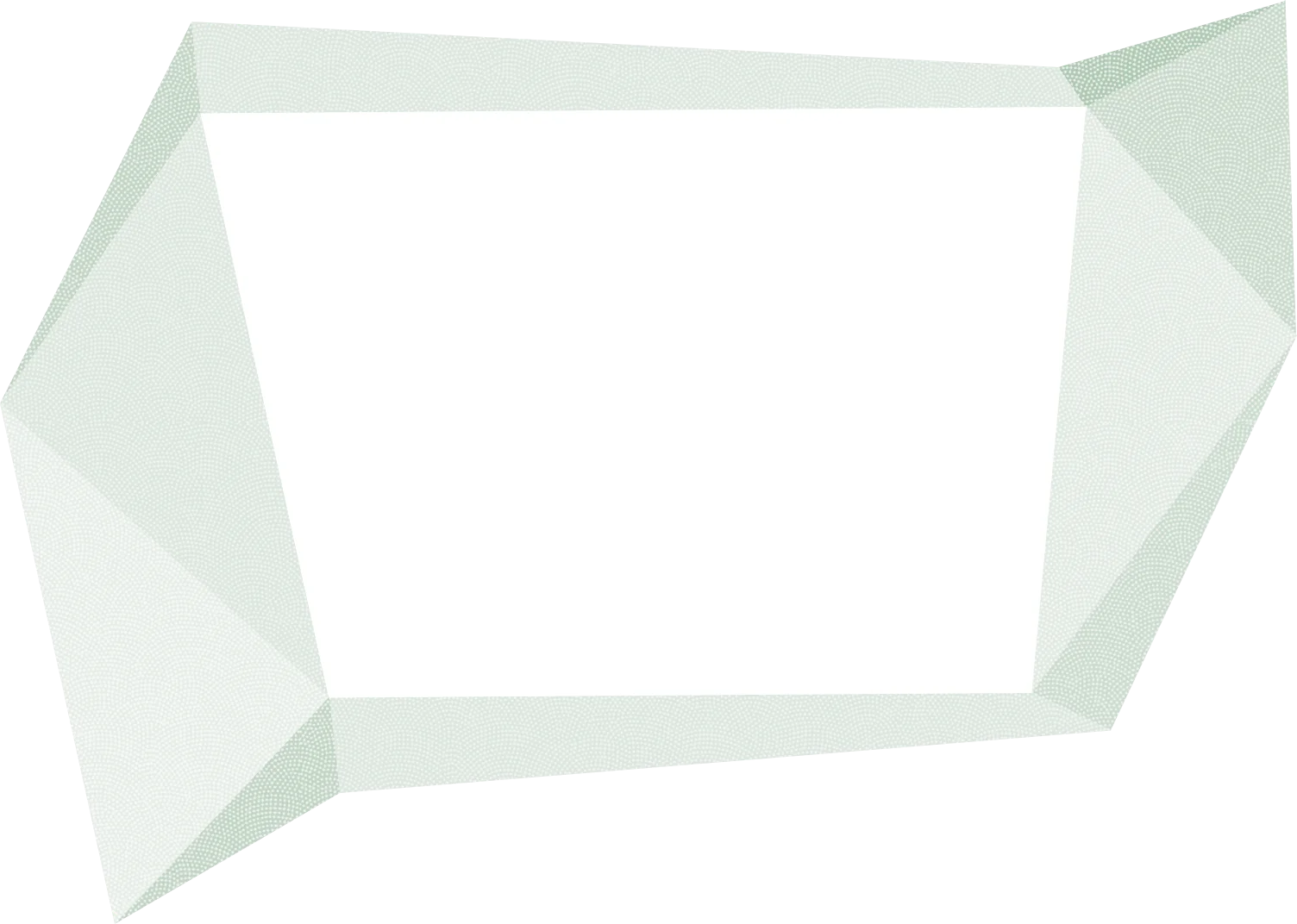二重国籍を認めない日本を報じる最近の記事
新聞報道で、二重国籍を否定する日本政府を訴えた裁判が、相次いて敗訴していることを知った。それはたとえば、仕事の必要上、外国での永住ビザ滞在から国籍をその国に変更した人が、その時点で日本国籍を強制的に失うとしている国籍法を違憲とした訴えである。
私の知人にも、外国籍を取りながら、事実上の二重国籍としている人がいる。それに、世界の主要7か国(G7)で、二重国籍を認めていないのは日本だけである。
そこでだが、私の場合は、もう40年——人生の半分——も外国生活をしていながら、それは、初期数年の学生ビザとその後の永住ビザによる滞在で、日本国籍はそのままで変えてはいない。
そこでこの永住ビザだが、それはおおむね、経済上はその国の国籍者と同等の権利や義務があるが、政治的な権利や義務は大きく制限されている。従って、選挙の投票権も、立候補権もない。
そんな、人間としては片手落ちの状況の上に長く生活してきているのだが、それは必要上やむを得なかったものとは言え、異例で不公正なものであるとは思う。
それでも、当地での選挙の際には、誰に投票するかの意見くらいはその都度はっきりさせており、意識上の参政権はしっかり行使している。よってそうした体験は、それはそれで、実際の選挙結果との相違が実に興味深いものとなって、それなりの関係を深めてくれはする。またその一方、日本の国政選挙の海外投票は、欠かさず実行している。
よって、選挙民としてこのようにあることは、日頃の生活基盤と投票意思の反映先という意味では、確かなねじれがある。
私の外国暮らしは、そういう不規則性に拠っている。
その40年ほど前、私が永住ビザを取得した時、オージーの知人より「次は国籍を取るんだろう」と、ごく当たり前のように聞かれたことがあった。その際、私は彼に、「自分の国籍は、自分の外見や顔立ちや名前と並んで、自分の選択の対象になるものとは考えていない」と答えた。つまり、自分の生まれや育ちそしてそれに基づく心境、つまりアイデンティティーは、日本人のそれであり、それは変える変えないの問題ではない、という認識であった。
その考えは今でも変わっておらず、だからこそ、当シリーズの〈半分外人-日本人〉というテーマが生まれてきている。すなわち、上記の「ねじれ」の産物のひとつである。
自分が生きるための場をどこに選択するのかは、たとえばそれが外国となったとしても、日本国内を移動し、県境を越える選択の感覚と何らの違いもない、自然で連続した発展におけるものである。
それは、子供から大人へと成長する際、たとえば、村の小学校から町の中学へ、そして県の高校、やがて都市の大学へと移動して行ったように、その都度の手続きの違いはあったものの、そうした移動自体は連続的で自然なものだった。そしてその延長上に、外国への越境をしたのであって、同心円をなす水紋が広がってゆくようなその拡大現象の各々に、何らの本質的な違いはない。
それが、実際の国外への移動となれば、その越境の手続きは格段にかつ不自然に変化する。それこそ、パスポートだのビザだのとの書類を必要とする厳格な手続き上の違いが出現してくる。
ところが、生活や人生の上の必要を追い求めて移動するという意味では、県境も国境もいずれも地理上の便宜上の線に違いなく、そもそもそこに「籍」という異形なものが付随するということ自体、異質で人為的である。だいたい、お前の「村籍や県籍は何か」などとは問われたことなぞない。それらはただ行ったり来たりする、住所上の小区切りである。
つまり、私に限らず、いまや多くの人々の生活範囲は、国境に留まらず、その外へとはるかにはみだしてきている。
そこで得る実感は、国という存在自体が人為的な拘束、というものである。
むろん現実問題として、そうだからと言ってその存在は容易には無視できず、必要とされる限りの範囲で手続きには応じざるをえない。
だから、そうした生活実感にしてみれば、たとえば戦争をめぐって「お前は何人か」とことさらに問い詰められた際には、あえて「地球人」としか答えようがない。国にまつわる「籍」とはそれくらい、実生活観とはチグハグな設定である。
そして今や、その国という「人為的設定」をめぐって、片や戦争行為から他はインバウンド旅行者の行儀の違いまで、大小の摩擦が生じている。
ところがそうした違いの起こりといえば、それは、この地球上のそれぞれの土地がもつ固有の違いが人々間の違いとなって現れているがゆえのものであって、それが風土であり、ひいては、風習、文化である。
そうした違いは、それを発見し、理解し、時に感心するものではあっても、何も、それを理由に、憎み合ったり、殺し合いにまで発展させるものではない。
たしかに数百年も昔なら、日本国内においてさえ、領国の違いに発する戦はあった。しかし、今となってはその違いをもって、誰も、殺し合うまでには至らない。せいぜいあっても、プロスポーツの地元意識くらいだろう。つまり、当時はそれくらい、暮らし自体が土地に直結していた。
今ではそれに代わって、私たちの暮らしはもう土地自体には縛られておらず、マネーという、容易に世界を飛び交う、数字によっている。そしてむしろ、土地に由来するそうした自然な違いは、それを探索し、味わう、風情ある趣向となって、旅と呼ばれる人間的な行為となっている。そしていまやそれはもう、国境を越えることこそにその醍醐味が見出されるものとなっている。
そうした世界に昨今、「何々ファースト」と、土地への執着を第一としうるかの偏狭な風潮が叫ばれてきている。だがそれは、上記の同心円上の「村意識」や「小学生心理」への回帰としか見えない。マネーという数字の魔力に心の拠り所を奪われた人々が、根も葉も浅はかな、もっともらしいノスタルジアに操られている。
それにしても、男にしても女にしても、ガキ大将のような御仁たちが、どうして国のトップとして選ばれるのか。そこにはどうも、選びようもない、あるいは、選んじゃいけないものが選ばされているという、政治的選択に絡んだトリックが使われているようだ。
文化や風土の違いはあって当然のものであり、それを円満にまとめ上げることが、国を統一するということであり、それがその「人為」として、国の指導者の必須の能力として問われ、許されてきたはずのものだ。
ここに至って人類は、かつてのあまたの「村々」へと、先祖帰りしようとしているかのようだ。