私の今の立場といえば、もはや現役の一専門職からは退きながらも、いくらかのパートタイム働きにかかわることで、幸いに心身健康な年金生活人であることです。ただ、「人生100年」などとミスリードされる“絵空”年金談義には一線も二線も画さざるをえず、くしくも達したこの境地ならではの精神的自由度を存分に活用したいと望んでいます。また、たとえ興味本位であろうとも、新たな挑戦にはたゆまずひるまず臨みたいところで、なかでも、これまでにも取り組んできた「『し』という通過点」をめぐる「越境問題」は、この場に至ったがゆえの、そしてこの“辺境”ならではの、アプローチ可能な関心事でしょう。
「“KENKYOFUKAI”シリーズ」第3回の今回は、そうした立場や関心から、現代理論物理学の最先端の仮説である「ひも理論」をとりあげ、「KENFUKA」してみようとするものです。
そこでなぜ、私がこの「ひも理論」に傾注するかですが、それは、この理論が人類の目下の最先端の科学的知見であるという“新し物好き”であることと、同理論と私の人生体験からの無形資産とも言うべき「両生論」とが、何やら類似し合っている気配があり、さらに、その最先端知見がもたらす新たな世界観の幕開け、つまりそういうパラダイム変化に、私も是非ともあやかってみたいと望むからです。
「両生論」の起こり
ではまず、その私の人生の「無形資産」たるものですが、それを私は上記のように「両生論」〔「両生学」とか、もっと広く「両生空間」とも〕と名付けています。そしてそれは、人生の各ステージにそって微妙に推移して、各々違ったバージョンを遂げてきました。
それを「両生」と呼ぶその発端は、学業を終えて“社会に出て”、最初に出くわした問題が、食い扶持を稼ぐ必要とそこに苦い妥協が避けられないといった、当時の認識で言う「理想と現実」という葛藤、言い換えれば「生存の二重性」でした。人生体験の皮切りであると同時に、先にも述べた「パワハラ」との遭遇の時期でもありました。
そして三十台半ば、そうした時期に節目が来たのを機にオーストラリアに渡り、初めての外国生活を体験し始めて新たに生じてきた二重性が、「地理的二重性」でした。生まれ育つ中で身に着けてきた出自体験と、自らが選んだ異国環境体験が織りなす、まったく新バージョンの二重性です。言ってみれば、所与条件と自主選択という異なった二視点がもたらす両眼視野の形成でした。
そうしたオーストラリア生活が、留学生から永住者へと進化するに伴って、こうした両眼構造による立体視野がもたらす二重性は、やがて、移動がもたらす物理的に二つの違った角度から見る異視野の形成という手法に根ざすことに気付きます。それが「両生論」という自分なりの探究分野および方法論の発見でした。(なお、以上の推移の詳細に関しては「相互邂逅」を参照。)
そうした「両生論」は、当初、物理的な二重視点を根拠とした、言うなれば《古典物理学対応》の時期でした。やがてそれが、文化や歴史、ひいては思想や観念といった非物理的分野を含んだメタ二重性へとも発展し、最近ではそこに男女とか、老若とかと言った生物的あるいは時間的な複眼視野も入ってきて、より拡張された「両生論」、即ち《学際的対応》の時期へと至りました。(なお、こうした「両生論」の発展の足跡は、本サイトの「両生学講座」の諸議論を参照していただければ、一望できます。)
こうした人生体験の中で組み立てられてきた「両生論」には、さらに、個的体験の範囲には収まり切れない、もっと普遍性のあるものへ変態の予感が訪れました。それに加え、近年、事故によって遭遇した自分の臨死体験が、この世・あの世といった「非局地的」二重性への視界をもたらし、さらにそれは、地球vs宇宙といった科学的視野の方向へと発展しました。
かくして私の「両生論」は、ついに《古典物理学》の枠組みには収まらなくなり、近年の量子理論への関心――前回で触れた「関係論」的な視野――の助けも得て、これまでの二重性の視点とは、やもすると物質の素の素である素粒子に見られる「対称性」にも似ている、との着想に至りました。こうして、私の近年の関心は、量子や素粒子理論――《量子物理学対応》の時期――の探究へと至ってきています。
こうした一連のマルチ視野的「二重性」体験の結果、さらにそれを巨視化したいくつかの二元的枠組みをも見るようになってきています。その一つは、西洋と東洋という二元関係で、これはことに私の出自と移住体験のもたらした産物と言えるものです。
その第二は、科学と宗教、ことに上記の「ひも理論」という物理学理論と仏教――世界の宗教で唯一、神の存在を説かない――との二元関係です。これは、第一の西洋と東洋との関係ともからまって、何やらもっと深い形而上的あるいは理論的関わりを示唆する一対関係を表しています。
私は、これらのいくつかの二重あるいは二元的関係を、さらに位相を変えた視点より、後述の物理学用語を用いて、「双対〔そうつい〕性」――同じ対象が見方によって対となった二つの違った姿をもつこと――の現れではないかと見ています。しかもそれが、様々の局面に潜んでいるという。
以上のように、「両生論」とは、自分自身の出生を中心に、自己体験の同心円的拡大からの知見を自流に体系化したものです。
また、私たちの日常生活が、物理学の歴史的発展のどの段階に対応しているかなどは、おおよそ日頃の関心にものぼらない観点です。しかし、それを意識するかどうかに拘わらず、その対応関係は基本的に私たちの生活の基盤を左右しており、いわば、文化や文明の進歩とは、そうした発展段階と相まって推移してきたと言えます。
そこでもしそれが事実であるなら、私たちの現文明は、いったい、今後どの方向に向かって行こうとしているのか。そのヒントは、世界の最先端の研究の動向に潜んでいのではないかと考えます。まさに私は「新し物好き」であるようです。
「ひも理論」とは
さてそこで、対する「ひも理論」ですが、それは、理論物理学――論理的厳密性を誇る――において、数学を実に高度に駆使した発展の途上で登場してきているものです。率直に言って、その専門領域での奮闘の過程は、本稿ような門外漢ブログにおいて、とうてい扱い切れるものではありません。そこで申し述べておきますが、そうした数学的発展の経緯について、ここではその詳細に踏み込む意図はありません。それよりむしろ、その発展がもつ歴史的あるいは思想的意味を探り、ことにそうした意味の私自身にとっての意義――専門の迷路に自失することを避けつつも、その成果にはあやかりたい――を見定めることを主眼とするものです。
そういう次第で、こうしたねらいは最終的には、極めて私的な関心の域を越えるものではありません。そうではあるのですが、それと並んで上記のように、私の人生において、「古典物理学」から、新物理学というべき「量子物理学」へと、類似した対応関係が見出されてきたことも見逃せないところです。
それは、かつて学業的岐路において理工系コースに進んだ人間として、だからゆえの宿命的関連性とでも言えるものでしょうか。
以上のような含みを念頭に、私がその専門領域に踏み入って行く作業をこなす上で手掛かりとしたいくつかの文献を紹介しておきます。下に写真でも示しましたが、それらは、大栗博司著の『超弦理論入門』(講談社ブルーバックスB-1827)と、大栗博司・佐々木閑著の『真理の探究;仏教と宇宙物理学の対話』(幻冬舎新書438)、そして大栗博司著の『素粒子論のランドスケープ2』(数学書房)です。また、その背景となる数学上の見解については、「「虚数」という異次元へのポータル」で紹介した文献が役に立ちました。
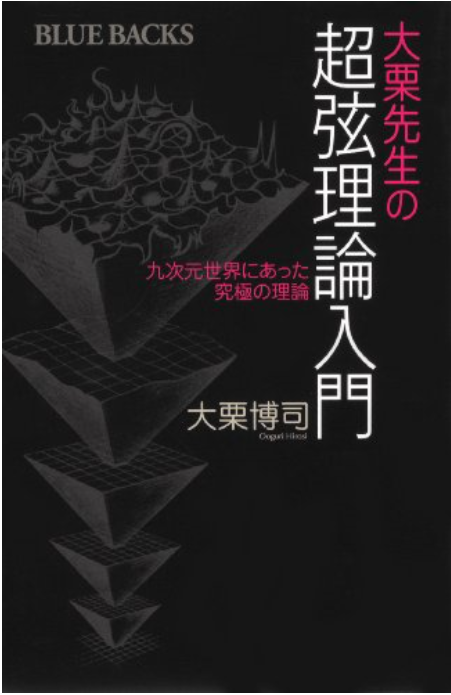 |
 |
 |
さて、ここよりいよいよ、本シリーズの手法であるKENFUKAを、この難解な分野にフル動員してゆく段となります。
古典物理学――私の世代では中学校で学んだ幾何学を基礎――と新物理学を分けたのは、20世紀の初頭、アインシュタインが二種の相対性理論を発表し、それまで、変化しない絶対的条件と考えられていた空間や時間がゆがむ――すなわち変化する――との発見です。つづいて、宇宙は膨張しているとの観測結果から、ならば時間を過去へとさかのぼれば宇宙は縮んでゆくのであり、遠い遠い昔のある一瞬では、宇宙は一点であった時があったはずとなります。ある意味で、実に単純明快な理屈です。これが138億年前の宇宙の誕生論、「ビッグバン説」の考え方の発端です。
「ビックバン」で思い出す話ですが、 この説が提唱されてまだ日も浅い中学生時代、提唱者の一人ガモフが書いた子供向けの本を読み、想像をかきたてられていました。当時、模型工作が好きで、学校の科目の理科で電気が始まるのを楽しみにしていましたが、家族の引っ越しで転校すると、転校先の中学では、電気はもう済んでいて習わずじまいでした。それでも高校入試は何とか通過し、大学も工学方面に進みました。もし、電気を教科として正式に習っていたら、違った興味を見つけ、もっと違った進路を選んでいたかも知れません。
その後、ミクロ物理学の分野で、物質の素の素が何か――還元論の根元視点――の探究の中から、究極の物質の構成要素が17種の素粒子であることが解明されてきます。しかし、素の素が17種もあるというのは不自然との考えから、それらを統一する考え方の追究がなされ、その産物が、素粒子を点と考えず、別のものとすれば統一は可能ではないかとの考えに至り着きます。これが点ではなく、長さをもつ「ひも」との着想です。
「ひも理論」までの発展の途上、素粒子は文字通り「粒子」と考えられていました。それが、諸実験によって実証されてきた「波動」としての性格も併せ持つことから、素粒子とは、粒子でも波動でもない、あるいはその両方であるとの、常識的には何とも納得し難い存在であることが事実と認識されるようになりました。それはほぼ一世紀前のことで、その二重な特性が、上でも触れた「双対性」との名称で呼ばれて注目されるようになりました。この用語は言うなれば、波だの粒だのといった名称とは、単に地球上の言語でのみに通用する区分であり、それは広大な宇宙界にあっては極度にローカル(局地的)な区分名称に過ぎないという、異次元世界の在り方を示唆しています。
そこで、そうした「双対性」を矛盾なく表現できる「宇宙言語」たる数学上での発展が求められ、粒子を表す「点」としての定義に、長さを表す「ひも」としての定義を持ち込むことで、そうした現象がほぼうまく表現できること――しかしまだ完璧にではない――が発見されてきました。
それというのは、素粒子の観測実験を重ねるうちに、その位置と時とが特定――古典物理学の根元的常識――できないとの不確定性が確認され、その存在は確率的なもの――量子的「ゆらぎ」――とされ、それを振動と捉えたわけでした。そして、その「ゆらぎ」は波動と数学的に「近似」され、その波動現象を起こせるものとして、一定の長さをもつ振動する「ひも」というアイデアが生まれてきたわけでした。
そこでなのですが、上述のように、物理学の世界には、対象そのものの素を扱う「還元論」としての立場と、その対象と周囲の環境を扱う「関係論」としての立場があります。それを演劇にたとえれば、前者は役者に注目し、後者は舞台に注目するそれぞれの視点とでも言えます。
そうした演劇に置き換えた発想で言えば、「ひも理論」としての上記の見方は、役者をどう捉えるかに当たって、それを従来の「点」から「ひも」へと変化させての見方です。しかし、実際には、そうした役者観が「点」から「ひも」へと変われば、そうした変化を受け入れるその舞台も合わせて変化して関連付けられる――点から見る世界と線上を移動して見るひもの世界の違い――ことが避けられませんでした。この役者とともに舞台の変化も含めた関係論的変化をつき詰めて考え直されたものが「超ひも理論」〔「超弦理論」とも書く〕と呼ばれているものです。言わば、役者の次元が高まれば、舞台の次元も高度化するというわけです。(私の見方を言い添えれば、私の移動に伴う両眼視野との類似性がここに見られるわけです。)
そこで、この「超ひも理論」の「超」たるところですが、それは、上記の「関係論」関係を数学的に矛盾なく説明するため、数学の様々な技法や原理を駆使して、その舞台に、9次元とか、25次元の条件を与えて幾つかの異次元の諸舞台を設定し、それから、その設定がもたらす、かかえる課題や矛盾がもっとも少ない解を選びだした結果の、極めて特異な舞台であるということです(言うなれば、考えうるあらゆる想定の計算を実行し、その結果のうちから在りえないケースを振るい落とす消去法の解)。
むろん、そうした舞台は地球上には存在せず、あくまでも、「宇宙言語」とされる数学が描き出すもっとも矛盾の少ない理論上の世界です。しかし、もし、数学が宇宙の言語として有用なら、その言語が描写する世界も、宇宙では実在するはずに違いない、ということとなります。
ちなみに、初回で見た「対称性の自発的破れ」というのは、そうした矛盾――あるべきはずの物理学的「対称性」(+や-、あるはスピン)がない不可解な現象――を解決する途上で考え出された考えです。あたかも素粒子を擬人化した――“意志”を持つ――かの「自発的」現象として受け入れようとする奇抜な(私に言わせればKENFUKAな)発想でした。そしてそれを逆に解釈すれば、人間も素粒子も同列に、その振舞いを扱おうとするかの超合理的試みです。ということは、それほどに、地球人のもつ信念が揺らがざるをえない、あるいは揺るがす必要のあることが、想定されていたアイデアと見れるわけです。まさに脱地球して、宇宙に羽ばたいて行くアイデアです。
また、そうした対称性、つまり素粒子内の「スピン」とよばれる対要素が、距離も時間も無関係に結び付いている――「エンタングルメント」あるいは「もつれ」――性質を利用して、目下、量子コンピュータが開発されつつあり、その桁違いの処理速度が実用化されようとしています。
こうして、数学的に設定された9次元の理論が、「超ひも理論」と特称され、最適なものとして注目され、目下、最も有効な仮説とされています。そして、こうした最先端の仮説は、今後、その確からしさが、さまざまな実験結果と照らし合わされて、科学的事実かどうかと検証されてゆくはずです。
以上のように、こうした仮説設定の重要な手掛かりとなったのが「双対的」なさまざまな現象です。そしてそうした諸現象は「双対性のウェブ」と呼ばれ、言わば追究の“金鉱脈”となっており、それを数学的にどう体系化するかに苦闘した結果が、そうした多次元の想定でありました。そして、そうした「双対性のウェブ」には、どうやら、私の「両生論」も含まれそうだとの発想を持つにいたるわけです。
専門的には、この「超ひも理論」とは、重力理論と量子理論の矛盾を統一する可能性を秘めた「美しい」理論と“非物理的”にさえ表現されています。
他方、私は、KENFUKA手法との極めて場違いなアプローチをもって、同じく「美しい」解釈を求め、その醍醐味を楽しみたいと念じています。そして、私が「両生論」と「ひも理論」との間に類似する気配を感じるというのは、その両者に、まさにそうした「双対性」の「美しい」ほどに新奇な現れが見られると考えるところにあります。
かくして、二重性や双対性は、そこに類似性という手掛かりを起点とした視野で見渡す時、何やら新しい世界、それこそパラダイム変化がそこに潜んでいることが見えてきます。
次回は、そうした類似性のダイナミズムに、さらに踏み入ってKENFUKAしてゆきます。
【つづく】
【その2へ】

