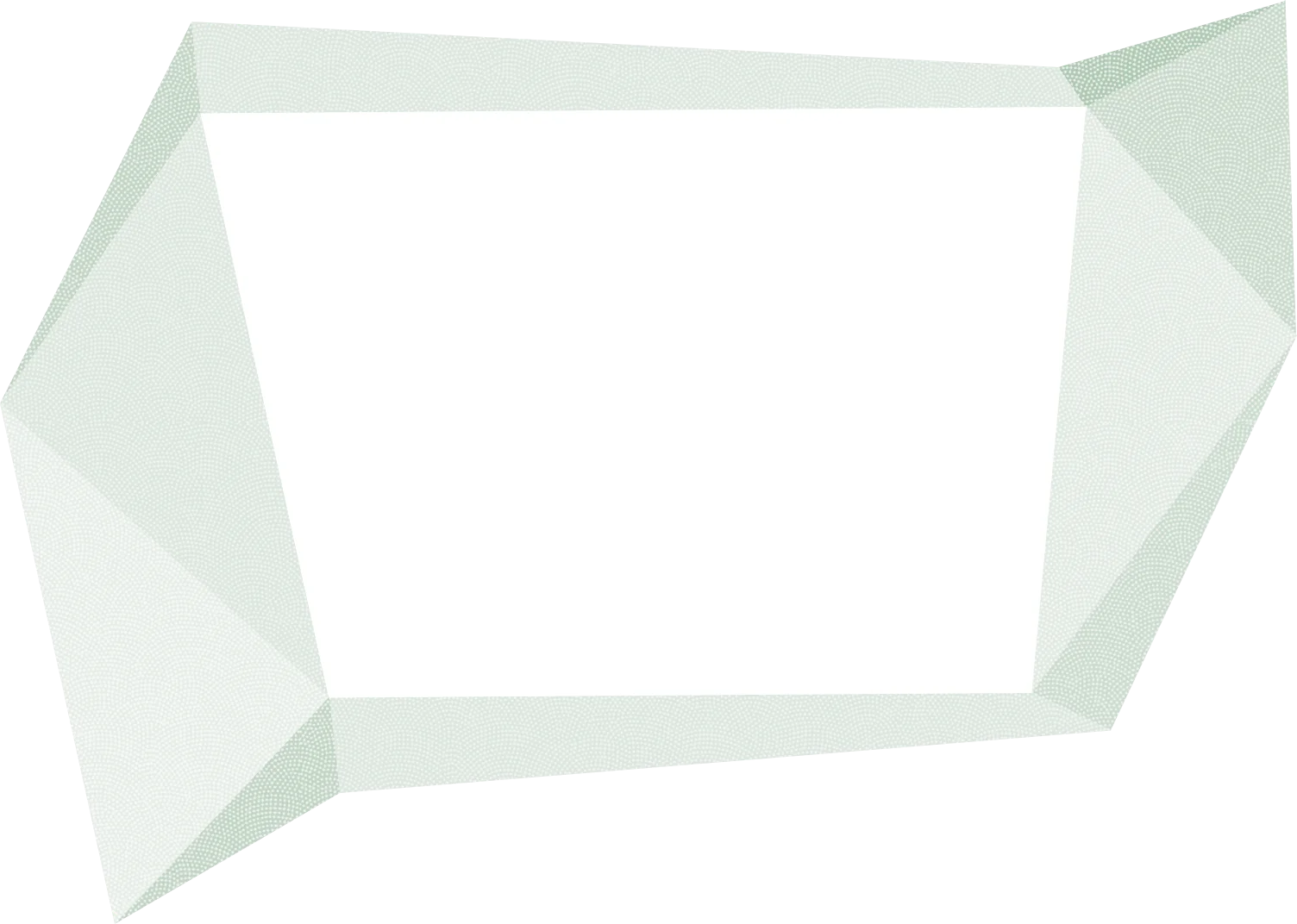当サイトでは、2023年11月7日号に〈「坑夫」の「工夫」〉とのタイトルの記事を掲載した。引退したトンネル技術者が、その専門世界に注いだの自生涯を集約した専門誌への投稿記事を紹介したものである。
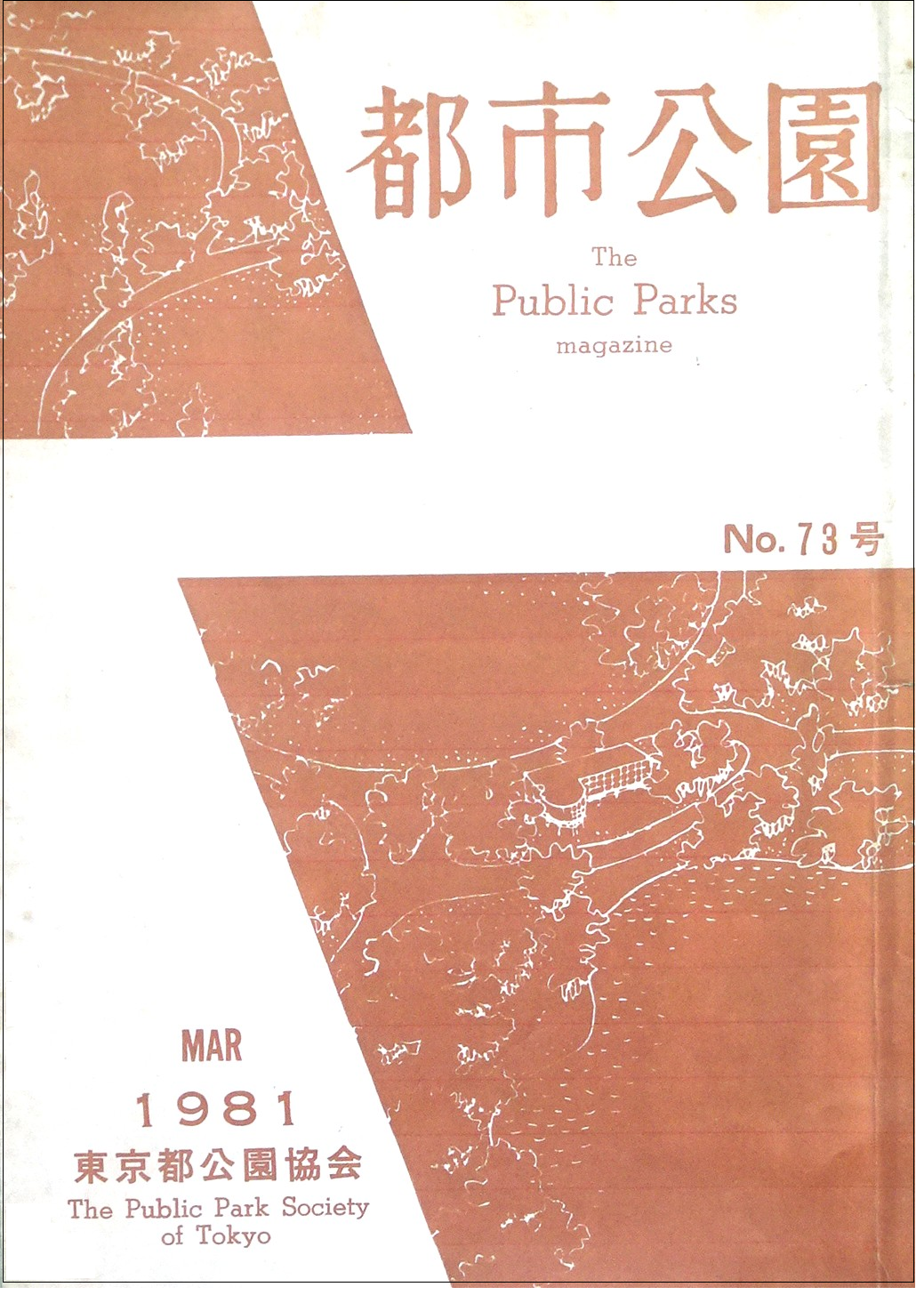 今回は、同じ土木技術の世界であるのだが、都市での公園建設を専門とする技師の手になる、これも専門誌(右写真)中の論文記事の紹介である(二名の執筆者のうちの一名より当記事は寄贈された)。そしてこの論文は、その技師の生涯にわたる仕事を集約したものというより、大学を出たのちの十年ほどの、いわば「新進」時代のひとつの取り組みを著したものである。そのためか、この論文には、学研による研究記録のようなスタイルと趣きがある。
今回は、同じ土木技術の世界であるのだが、都市での公園建設を専門とする技師の手になる、これも専門誌(右写真)中の論文記事の紹介である(二名の執筆者のうちの一名より当記事は寄贈された)。そしてこの論文は、その技師の生涯にわたる仕事を集約したものというより、大学を出たのちの十年ほどの、いわば「新進」時代のひとつの取り組みを著したものである。そのためか、この論文には、学研による研究記録のようなスタイルと趣きがある。
なお、当サイトでは他にも「土木工学、半世紀も経れば」において、近年の土木技術界の話題を取り上げている。
私は、この論文の内容を技術的に専門の見地より評価したり解説したりする立場にはなく、上記のように私の個人的視点からここに取り上げる。
そしてそれを、この〈半分外人-日本人〉シリーズに掲載し、「非ノーマッド志向」と題しようと思う。すなわち、先の中央アジア旅行をまとめた、人間の持つ「ノーマッド」志向にからめ、むしろその逆の生き方との着眼をもって、このシリーズに取り上げるものである。
その技師は、東京都の職員であるがゆえ、その在職中に臨んだ仕事の地理的範囲は、むろん東京都内に限られているはずだ。その意味で、たとえ世界地図でなくとも、たとえばアジアの地図を広げて、その働きの範囲を確かめてみれば、それは視覚的には点でしかないだろう。
しかし、本稿で述べたいことは、そうした面積上の観点ではなく、その働きの移動性か固定性かという違いである。ある意味では、面としての広がりか、点における深さか、の違いである。
ここで想い起すのだが、この技師がこの投稿記事にある工事に従事し始めているのと同じころ、私の友人が、当時は「無賃旅行」と呼ばれた、世界放浪の旅に出発していったことがあった。
その頃私は、その友を見送りながら、そのように母国を後にし、世界へ旅立ってゆくことに、どこか懐疑的だった。むろん一人の若者として、何に出くわすかも知れないそうした冒険旅行に、喉から手が出るように魅かれるものはあった。ところが、その他方で、外国どころか、自分の国や社会に問題が山積みされていることも間違いなく、それを見限って外に出かけてゆくことに、自分としてなら、どこか卑怯な姿勢を感じていた。裏返せば、自分のうらやましさと勇気のなさから、そう逆照射していた心理だったのかもしれないが、ともあれ当時の自分は、その友のように「ノーマッド」になることに意義は見出さず、固着した無移動者の立場を固辞していた。
当時の私は、最初の仕事を辞めた後、今で言う派遣員として、いかにも胸糞の悪い労働をしていたのだが、やがて労働組合の仕事に出合って、それこそ、日本社会の宿痾の問題に、当初はライフワークとの覚悟で、じっくりと取り組むこととなった。
そこでなのだが、どうも人間には、自分が生きて行く舞台の選択にあたって、偶然というか運命というか、自分だけでは決められない、一種のめぐり合わせによる作用が関係していることが多いようだ。
ここで、そうした選択決定の分かれ目を、ことに「ノーマッド」か否かというふるいをもって見ようとするのだが、そこには、二つの形態があるようだ。
そのひとつは、早生で過敏な才能がゆえか、人生の早い時期に、所与の現実に限りを見出してそこを後にし、その「ノーマッド」な習性を早くして発現する場合である。
他は、その逆に、自分に与えられた環境にひとまずじっくりと取り組んで、一定の体験をへた後、それからの成果と納得を土台に、次の課題に乗り出してゆくケースで、その意味で「非ノーマッド」なタイプである。
私は、この論文の著者は、こうした二分論で言えば、後者の一人だと見る。しかも、別掲のその投稿記事のように、その技師は、まだ駆け出しと言われてもよいだろうその時期に、おそらく、当時のその分野の技術的通念を大きく越えたただろう、広範囲かつ一種の哲学的な見地と取り組みをもって、その海浜公園のプロジェクトに従事した様子が読み取れる。
当時の土木工学の世界では、たとえば、建設相や首相を歴任した田中角栄が推進した「日本改造」論にもうかがえるような、自然を改造あるいは加工するのが同工学の、少なくとも実践上の、通念であった。
そういう時期に、自然に「手をつけるという行為の意味を技術者としてどう構築できるのか」と問い、それを任務として、責を負った海浜公園の工事に当たっている。私はその分野の専門知識に乏しいが、おおいに異例、あるいは異端であったのではないかと思う。
私の場合、上に触れたように、30代の後半、その「固着した無移動者の立場」にひとつの節目を付けて日本を後にした。そしてそれ以降、おのれのノーマッドな性向を発見し、そして発展させてきた。その産物の一つが、いかにもノーマッドな性向をタイトルに込めた、このサイト『両生歩き』である。
そうしたノーマッド性を旨とする本サイトが、こうした非ノーマッドな働きの記録を掲載することに、上記の二分論にもそい、人間の両面に触れるという意味で、大いに意義を感じるものである。
では、その投稿論文はこちから。