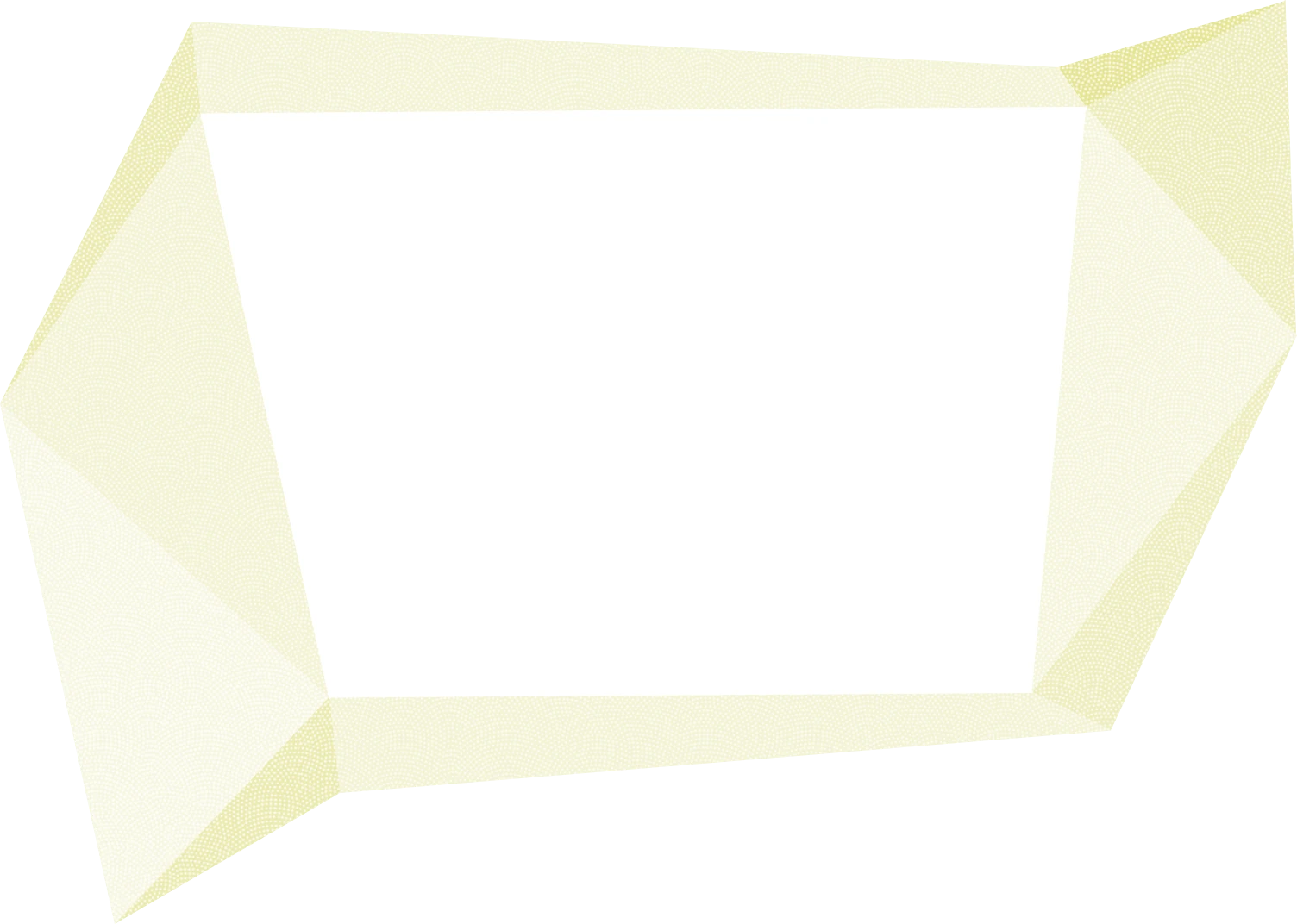1.「穴埋め労働」でいい
(前回)
2.「市場外行為」の貴重さ
最近の日本の報道を見ると、深刻な人手不足のために、高齢者層にもその供給の掘り起こしが広がっているようです。そうした人手不足対策という意味では、そうした動きは、経済用語で言う「市場内」での動向と言えましょう。
しかし私は基本的に、《働く》という行為は、人間が生きて行く上での必須かつ根源的行為で、「食」や「呼吸」と同じように、死ぬまで――何やら“暗い響き”が伴いますが――続けられるものと考えています。むろんこの《働く》とは広い意味で、たとえ収入の伴わぬ働きであっても《働く》ことに変わりません。そういう観点では、この《働く》という行為は、経済用語で言う「市場外行為」を特に意味します(そこで《》を付けてそれを区別しています)。
私は、いわゆるリタイアメントとは、定義的には市場行為からの脱退で、この「市場外行為」である《働く》を意識しうる人生最大のチャンスと見ます。つまり、通常、リタイアメントに伴い年金収入を得られるようになり、それまでの現役生活でいやというほど付き合わされてきた、収入のための働きというものと、基本的に、縁が切れるようになるからです。
むろん、年金収入には個人差があり、それによって「縁の切れ方」も違ってきます。そうではありますが、程度の差こそあれ、自分のうちに、収入のための働きから解放された部分、あるいはそのプレッシャーの軽減が生まれることは確かです。
そしてさらに、それでも《働き》続けることで生じる現象が、年金生活者と現役の共存です。つまり、お金のプレッシャーにさらされる度合いの異なる人たちが同じ職場で混じり合って《協働》することになる意義に注目します。言うなれば、お金の必要という「世知辛さ」に違いがある人たちが、互いに生き方や思いをその《協働》のうちに交換しあうことになる、その大事さです。
以下は、主に私の体験をもとにした見解ですが、その効果の筆頭は、価値観の多様性がもろに混じり合うことの意義です。
そうした世代と人生経験を異にした人々のミックスは、一眼的でシンプルな職場の雰囲気にある種の幅の広さをもたらします。つまり、同世代同士ですと、どうしても価値観が似通い、狭い範囲の仲間意識や、逆に、競い合い関係に取り込まれがちです。そこに、違った世代が混じっていると、そもそも、、仲間になろうにも話が合わず、互いに競争を持ち込もうにも競争がなり立たず、むしろ、競争し合うことが“無意味”にも見えてきます。
総じて、多世代混じった職場では、一種なごんだ雰囲気ができます。そして潤滑油が注入されたように、人々の関係が滑らかになります。
むろん、多世代協働がうまく行かない例や、建設現場のような高齢者には危険な職場もあるでしょう。しかし、サービス業や、技術革新による業態の変化など、従来の“常識”の切り替え次第では、多世代のミックスできる環境は、多々、発見できるはずです。
そうした結果の《協働》のもたらす、そういう円滑さや大らかさは、労働市場に縛られる――つまり自分の売り買いに終始する――環境には、生じにくい産物です。
それに、歴史的に働くことを見てみると、今日のような労働市場――雇用されること、言い換えれば、自分を売ることが不可避――が成立したのは、ごく近代になってからです。
産業革命がおこって分業が進み、封建時代までは自然環境や土地と結びついてきた生活が壊され、労働を売るしか生きる手段をもたない労働者階級が生まれます。そして、分業はいっそう高度となり、各々の専門の訓練や教育ともあいまって、労働の売買はいっそう複雑、高度となって、今日に至っています。
そうした、誰もが市場に拘束されているという条件が、リタイアメントをもって基本的に消滅します。そこに、市場外行為としての働きが発生しうる新たな環境が生まれます。
そういう歴史の経過を見ても、働くことが、市場内だけで終始、完結するわけではないことを明らかにしてくれるのです。
(ちなみに、これを「十分な老後の蓄えを備えた悠々自適なリタイア期」として理想化する向きもあります。しかし、その時期が、現役時代の稼ぎで買った“無働の時間”と受け止められる限り、それは市場内行為であることに変わりはありません。そうして、死ぬまで続く“消費”として、売買行為に巻き込まれてゆくのでしょう。)
そう考えてくると、外見上それは「死ぬまで働く」ことであるとしても、それが、市場内でそうさせられるのか――そこは“暗い響き”が伴う――、それとも、市場外でのもっと生き々々はつらつとした働き方においてそうするのか、そこに、雲泥の違いがあることがはっきりしてきます。