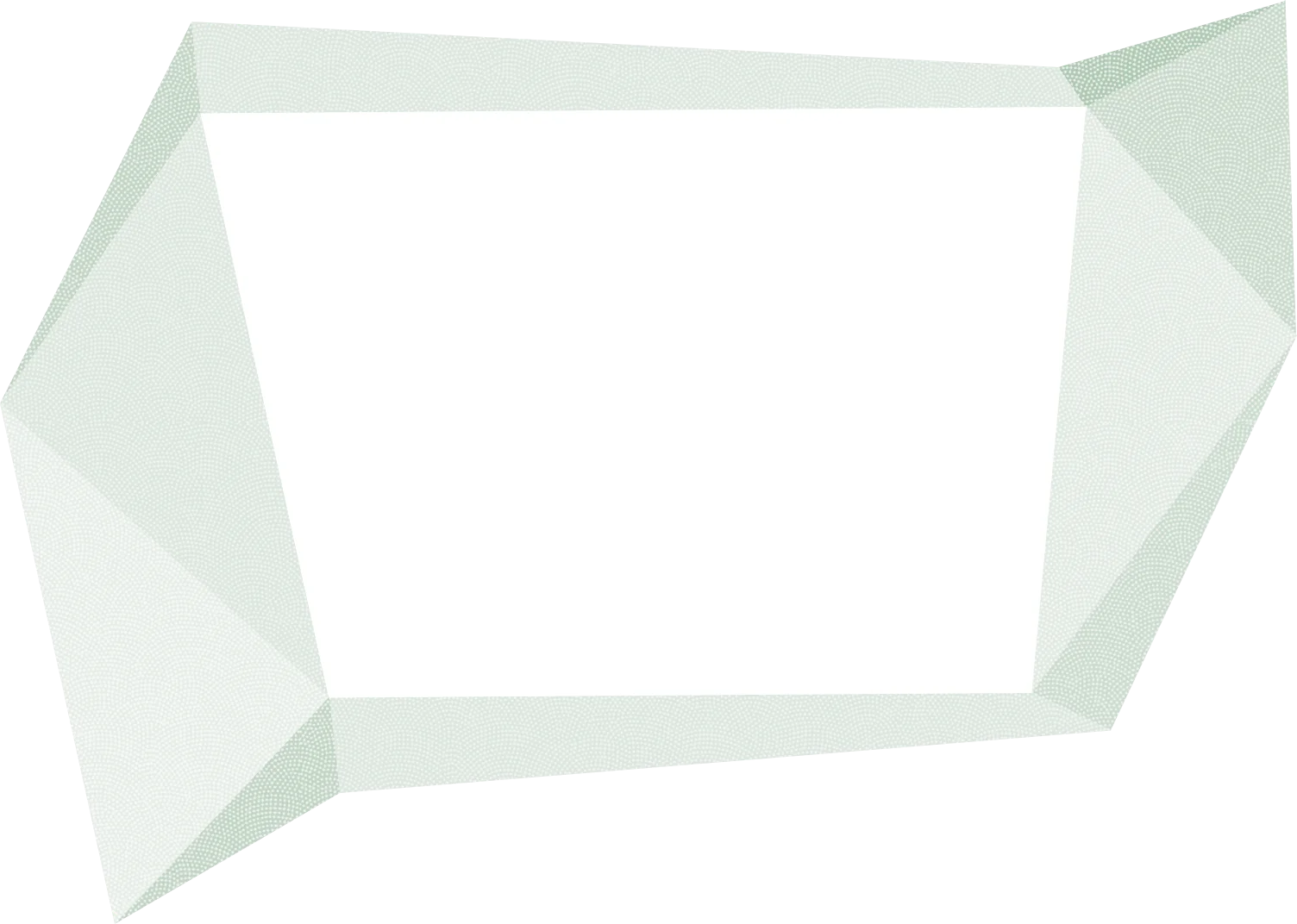大江健三郎の郷里を訪ねたその実感をひとことに凝縮すると、まさに、〈ノーベル賞級の深い森〉があったとなる。

大瀬に至る旧道の鬱蒼たる木々 .
大江の小説には、谷間の村とそれを取り囲む森という舞台設定がよく登場する。しかもその「森」というのは、私の想像できる「森」とはかけ離れていて、なにやら、おどろおどろした得体の知れない存在としての、私にはなかなか実感できない、長年の謎であった「森」である。
それが、今回の正月休み中、働くミカン園のある吉田町より、彼の郷里、内子町大瀬(別掲の地図参照)を実際に訪れてみて、それがどういうものかを実感した。
ならばそれはどういうものか。
都会育ちの私には、自然や森と言い表せるものは、都市の郊外の実におだやかな、ある意味で「飼い慣らされた」、もしくは、レクレーションやスポーツの場との自然環境としてのものである。
むろん、山なぞに登っていると、それは雄大な自然のふところ中に入り込むことで、命を失う遭難の危険性すらひそむ、未踏の場ではある。
そうではあるが、それは探訪先としてでも一過性のそれであり、そのひと時を無事終えれば、安全な地帯へ帰還して行くことのできる、地理的にも時間的にも、限られた体験である。
それが今回訪れた大江の故郷は、いつの時代より人が棲み着いたのかは定かでないが、古代より山と谷川と森が形成してきた、人の居住を容易には許さぬ、深い自然の懐の中に、それこそ苦労を承知で棲みついたような場である。

谷間に「紡錘形」をなす大江の故郷、大瀬の集落 .
それは、大江の小説(例えば「万延元年のフットボール」)に、「谷川沿いの紡錘形の村」と表現されている、細い旧道の両側にそのような形に発達した、いかにも頼りなく危なっかしい棲みつき場所にすぎない。
1930年(昭和10年)に大江が生まれたそのような場所は、11年若い東京生まれの私が、上記のようにレクレーションだのスポーツだのの場として体験した自然とは、時代も土地も根源的に異なる、それこそ、日々、自然の脅威にさらされ、おびやかされた場であったろうと想像される。
考えてみればおかしな表現なのだが、それを「ノーベル賞級の深さ」と形容して、そういう自然との関係がそれ程のゆえと代言したのが表記のタイトルだ。
今回、こうした大江の故郷を訪ねた体験は、同県内のミカン生産農業の片りんの体験とセットになったものだ。それは別記のように、自然相手の農業がもたらす人間と自然とのフィジカルな接触ぬきにはありえないもので、それに私自身の健康創生としての運動体験を加味し、そうした一連の体験より、人間社会にとっての一種の未来性を予見し、それを独自に「哲学農業」とか「フィロアグリ」とかと呼んでみようとしている。
私は、若い頃、大江の作品を読んで、おおいに啓発されるものを得てきた。そうした大江の作品表現に、まさか、私の得てきた上のような体験に並ぶ様なことは表わされていない。
直接的にはそうなのだが、作品総体を、その作者の表現したいことの一連の〈比喩〉だと捉えるならば、そうした比喩が私の体験につながっていないとは、決して言い切れないだろう。なにやら、そういう深いところで、共有するものがあるのだ。
あるいはむしろ、ノーベル賞委員会がその授与を決定した根拠に、その賞に値するがゆえのものとして、人類にとっての普遍的価値がゆえの、その決定であったのだろうと判断される。
そういう人類的価値をめぐって大江が「森」と表現するものがあるのだが、まさに「ノーベル賞級」の価値とされた大江のそうした表現対象は、そうであればこそ、「森」と代表される自然の深さを、人類の未来へのそれほどの価値をも物語るものとして、まさに相等しいことなのだろう。
そして、以上のような意味において農業の果たす役割は、農耕の着手から手工業の発生をへて、工業生産という第一次産業革命から、到来しつつあるAIの普及による第四次産業革命へとの人間社会発達の流れの中において、その新規性をも示唆するものである。
そこで、これは個的な視野ではあるのだが、私の「人生三周目」において、そのモチーフのひとつにするに充分なものと受け止められのである。