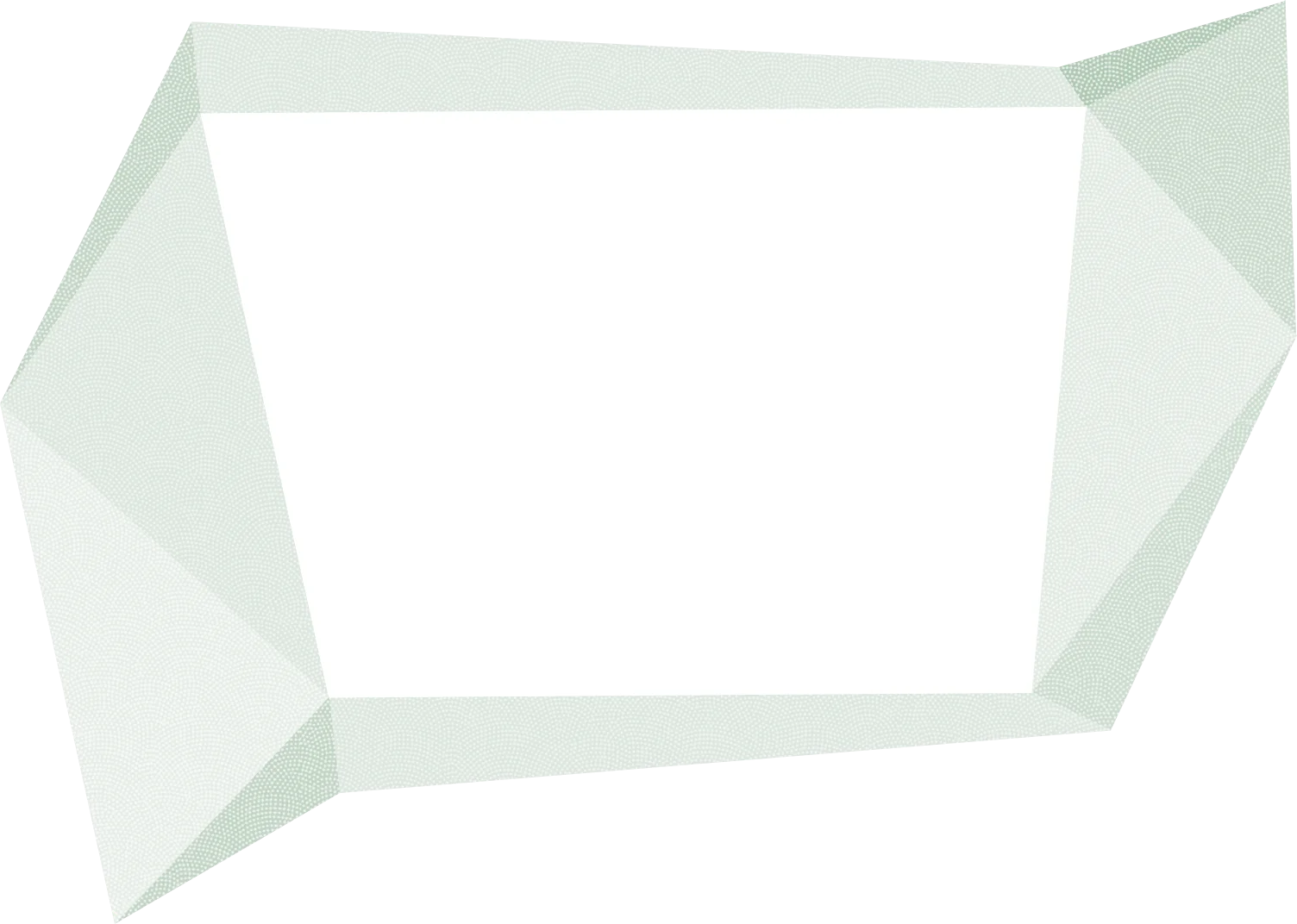今回の帰国で、大江の郷里、内子町大瀬を訪ねつつ、同時並行して彼の小説『万延元年のフットボール』を読んでいた(前号参照)。そうした彼の生誕の地に実際に入り込み、かつ、その彼による作品――そこを舞台にしたその奇態な物語――の鑑賞という現実とフィクションにまたがる二重な体験をしてみることで、ノーベル文学賞に至るその世界的才能を生んだ環境が何かを探った。そして、同賞という異論のない成果を遂げながら、逆にそこに、あるいはそれだからこそ、その職業的創作者という生き方に、一種の仕組み上がった閉合された世界を見るという、思わぬ発見をしていた。
というのは、これまではむろんそういう会得にまでには達しえていなかったのだが、今回の現地訪問と作品鑑賞を重ね合わした立体的体験は、私に、それまでの滞っていた限界を破る領域をもたらしてくれた。
そして、彼のいかにも複雑な物語り構成に託されているを意味を解読するように、彼の抱く60年安保闘争とその傍観者であった主人公のもつ負い目意識に加え、その後の私生活に生じた遭遇、すなわち、障害ある子供を持つ父親になるという二重の負荷を負った人物が、そうした社会的な所与条件を、自らが創生した創造的世界を通じて克服してゆくという、「乗り越える」と彼の“命名”〔上掲書電子版「著者から読者へ」より〕する働きについて、彼と私との二つの体験を相対して見ていたのであった。
すなわち、私はまず、彼がそうした苦難突破方法を作り出す才能を形成したものが何であったのかという点で、その「森」に包囲された大瀬の自然環境を採り上げる。そして、ノーベル文学賞というその世界トップレベルへの到達という成果において、彼をも含め、生きる人々があまねく経験しているであろう人生上の苦難が、片やたとえ偉大な成功物語に到達したものであったとしても、それが商品経済社会中に取り込まれてしまっている、そんな形での未完の働きと見られることだ。
いうまでもなく、それぞれに生きる人々は、それぞれの職業を通じて至るままに全うするのであり、まして賞の獲得などとは全く無縁に過ごすのが通例である。
そういう通常な人生と、そうした「森」という自然が生み出した才能ですら、そう「未完」に尽きさせる残酷な仕組みが、その職業的作家として、かつその賞の授与として、現代社会の強固な既存構造となっている。それが、そういう大江健三郎にとってさえ、それに捉えこまれてしまったかとの思いが、上記の発見であった。
別の記事に詳しく記したが、その作品の中でのひとつのキーワードが、「本当のことを言おうか」である。その「本当のこと」とは、それがいくらその作品中に奇態にも描かれていたとしても、それはフィクションとしての驚かしに過ぎないと見る。描かれるべきは、そうした仕組み自体であったのではないだろうか。