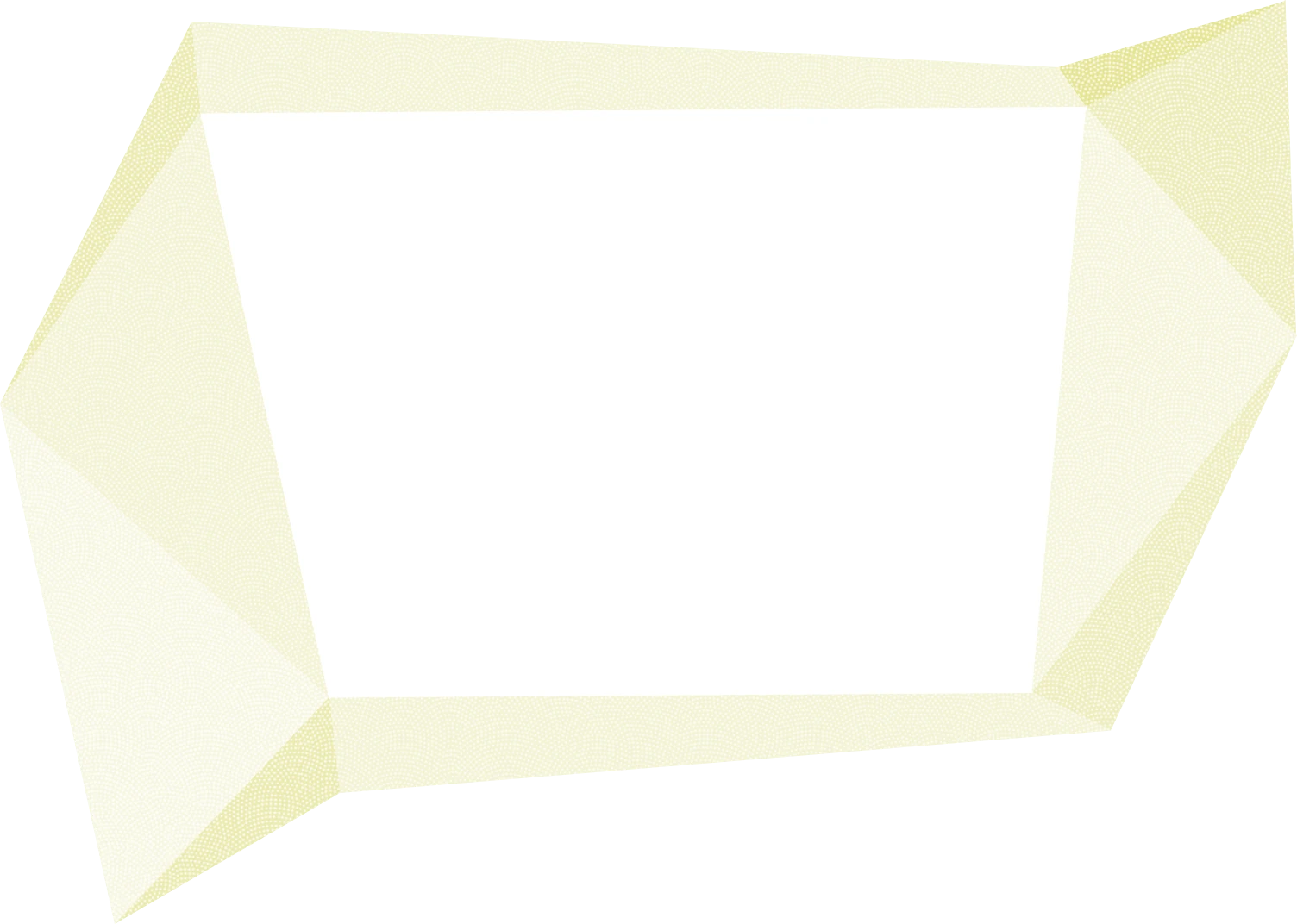3.「自活」という「生産」の二つの意味
表題のように「生産」と書くと、何物かを作り出す行為のように解釈されがちですが、こと高齢者、つまり現役から退いた世代のそれは、マイナスのマイナスはプラスといった意味での「生産」です。
また、「自活」とは、自力で積極的に生きてゆけるという意味で、単に、病気ではないとか、介護の世話が不必要という受け身の意味ではありません。
言うなれば、《“半”現役》生活という展望が、現実的にしうるということです。
一般に高齢化とは、病気治療とか介護の必要とかで、生産人口から消費人口への移転を意味します。しかし、もし、そうした人口の健康度が向上し、そうした消費出費が削減されるなら、「マイナスのマイナス」は「プラス」であり、国民経済収支バランス上では「生産」の意味を持ちます。
さて、以上は、《“半”現役》における「生産」について国民経済という観点で見た、社会的視点です。
しかしその一方、こうした健康・自活・高齢個人の存在可能性は、上記のような社会的意味に加えた、その当の本人における個人にとっての意味があります。
まずはっきり指摘できることは、こうした個人の登場は、世代としては歴史的にも初めてのことで、その人生としては、先立つモデルがないことです。つまり、それを生きる個人にとって、何もかもが初体験である、言い換えれば《先頭ランナー》であることです。
そういう視点では、いい意味で「何でもあり」ということで、予断を排除したいろいろな試行錯誤が展開され始めています。
ただ、そこで重要なのは、そうした生き方が実行できるのは、言うまでもなく、健康という条件を満たした場合のみであることです。
そこでですが、それほどに重要なその健康を維持するということは、いわば日々のひとつの目的にすることもありうるほどのことです。つまり、それが生活の100パーセントを占めるわけではないにしろ、日々の主要な部分となることです。たとえば、運動とか食事の準備とかリラックスとか、そうした健康維持のための活動に、日々のそうとう大きな時間を割いてしかるべきだということです。
当初私は、そうした時間を、必要ではあるが、自分のメインの必要という点では二次的なものとして受け止めていました。したがって、何らかの緊急事態が生じた際は、優先的に削減される対象でした。それに、そうした二次性がゆえに、それ自体をたとえば楽しむといったことはなく、ある意味では、多少は我慢をしてでも実施しなければならなような“応急処置”的なところがありました。
しかし、そうした時間自体が、毎日のかなりメインの部分におよぶようになると、それとの関係も、もっと近しく常態なものに変化してきます。ある意味では、それを楽しみながら、あるいは、それを行うこと自体に一種の“特異性”を意識する必要はなくなってきます。
たとえば、寿司シェフとしての週三日の労働は、5、6時間を立ちづめで働き、腰には大きな負担となります。そのため、どうしても腰痛に悩まされることになり、その対策が不可欠となります。以前はそれは、一種の病的状態として実際に医者の世話にもなるという《治療問題》でしたが、どうもそういうことではなく、そうした労働と見合う身体が必要であるという《健常問題》と考える必要があると考えるようになってきています。言うなれば、週三日の労働を維持するには、他の週四日に、それに備える体力強化は不可欠ということです。つまり、そうした二種の日常は、セットにして実行するものである、ということです。
むろん、寿司シェフの仕事以外に、机に向かって行う仕事も多く、それはそれで、また、別の角度からの運動を必要とします。
つまり、そうした自活の毎日には、いろいろなメニューの組み合わせが必要であり、多彩な要素を含み込むことが必須であるということです。そう、現役時代がそうした多彩なメニューで満たされていたように。
こうした多要素を、楽しみをもって、継続的に実行してゆく、それは、若い時代の現役生活――とかく単一機能に収れんされ過ぎていた――とは、大きく異なるスタイルです。これは一体どういうことなのでしょうか。
私はこれを、人間史上で初めて、現役生活で完全に摩耗されなかった、言い換えれば、その人生を完全に搾取されなかった、そういう《搾取労働からの生還者》が、初めて実際に存在し始めている、ということではないかと考えています。
すなわち、それは、国民経済的には「生産」と見なされるということですが、そういう「お国のため」との視点ではなく、私たち一人ひとりの個人という視点において、何とか搾取のトンネルを生きて抜け出れたという生還物語です。
そういう意味で、私はこうした《“半”現役》生活の現実社会での実行を通して、現役の人たちに、《生還する大事さ》を感じ取り、展望してもらえればと願うものです。