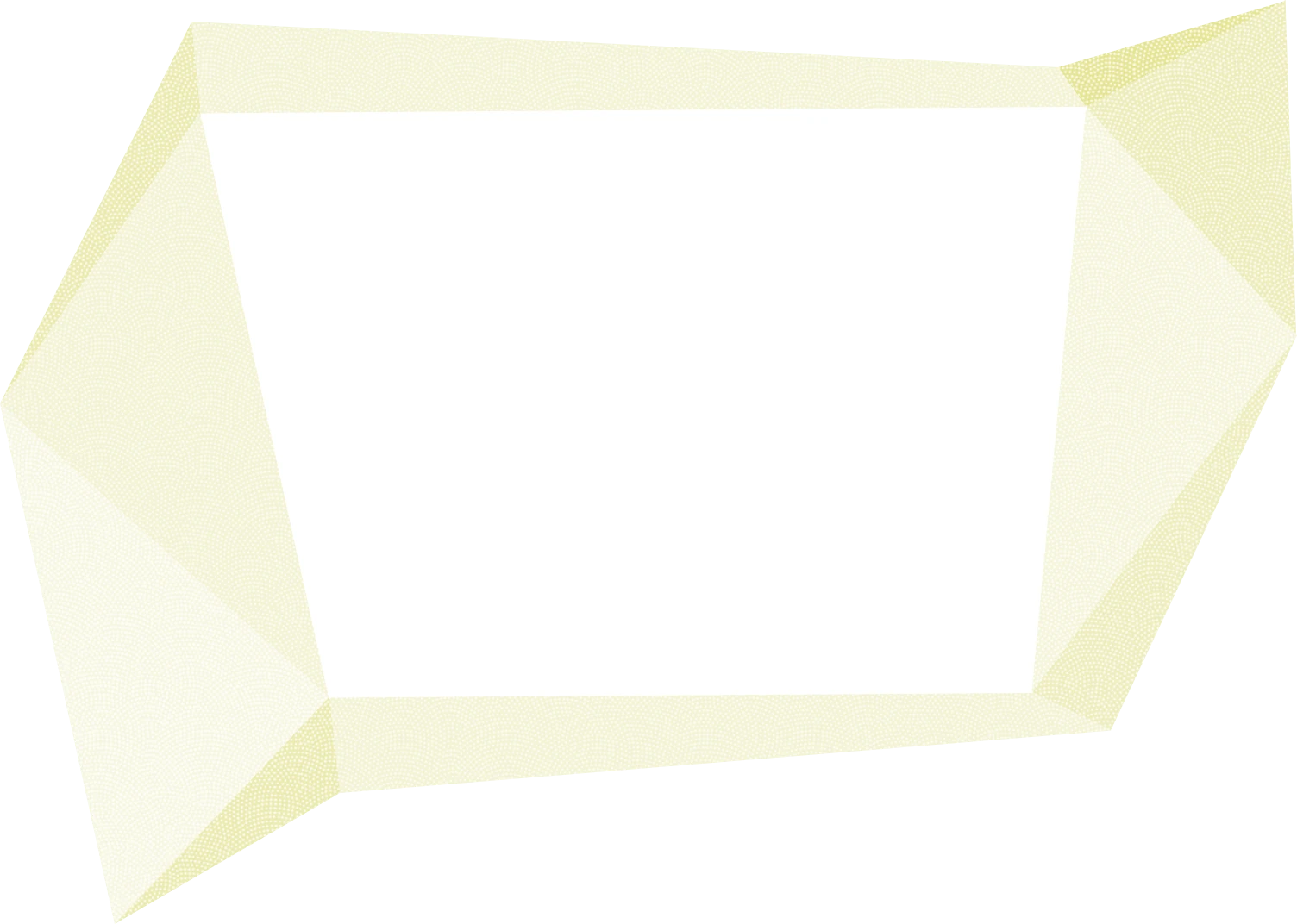第二次大戦末期の1945年、同じ枢軸国同士でありながら、原爆はなぜ、ドイツにも、イタリアにも投下されず、日本のみに対して使用されたのか、という疑問があります。
これに答えたものに、シンプルな人種差別観の逆転したものと思われる、「白人は白人には原爆を使えなかった」というものがあります。
あるいは、もっと時間的精密さをもった現実的なものとして、イタリアもドイツも、それぞれ43年7月と45年5月と早々と降伏し、その時にまでにはまだ、米国の原爆の開発は完成していなかった、という事情もあります。つまり、それからの数カ月間、戦争状態が継続されたことが決定的だったというものです。
あるいは、日本の降伏をみこした戦後の世界戦略に立って、米国はソ連に先んじて、この決定的武器の威力を見せつけておく必要があったというものもあります。
原爆開発については、他方の日本も当時、まったく手つかずの状態であったわけではなく、基礎段階ながら取組みはあり、軍からも開発命令は下っていました(その中心は、理研の仁科研究室)。そして、ドイツの降伏で中断した、ドイツから日本への、ウラン235の極秘の運搬作戦も実行されたようです。
こうした原爆開発競争について、その成果が米国のみに与えられた経緯に関し、知っておくべきストーリーがあります。
それは、当時の先端をゆく各国の物理学者たちが、少なくとも理論的にはあり得るとされていたその究極の武器の開発に関し、人道上のモラルの観点から、そうした驚異的な致死力のある武器開発に携わるかどうかについて、主に二つの流れがあったことです。
そのひとつは、そうした極限の残酷さを発揮する武器の開発をするべきかどうかをめぐって、すべきでないというものと、他は、敵も開発に成功する可能性もある戦況にあって、善をつらぬくために、悪に対する使用であるならそれは許されるというものでした。
先に『新学問のすすめ』の第4章で引用したハイゼンベルグ著『部分と全体』の第15章に、原爆開発に関し、それがナチスドイツにわたらぬよう、彼がいかに対処したかの経緯が述べられています。その冒頭は次のような記述で始まります。
1941年の終り頃には、われわれの“ウラン・クラブ”では、原子エネルギーを技術的に利用するための物理的基礎は、かなり広範囲まで解明されていた。われわれは自然のウランと重水とから、エネルギーを供給する原子反応炉を建設し得るということ、そしてそのような反応炉の中で、結果としての生成物の一つとしてウラン239が生ずるにちがいないこと、それはウラン235と同じように原子爆弾に対する爆薬として適していることなどを知った。(p.289)
つまり、ヨーロッパの物理学者の間では、上記のような知見には達しており、おそらく日本の先端をゆく物理学者も、こうした情報は得ていたと思われます。ただ、理論上はそうでも、それを実際に開発することはまた別問題でした。上記の記述はこう続きます。
ウラン235を獲得することに対しては、ドイツで、しかも非常時に、技術的に実行可能な費用で、ある程度問題になり得る量のウラン235を生み出せそうなやり方を、当時われわれは知らなかった。原子炉から原子爆弾を作るにも、その実現には明らかに巨大な原子炉の長年にわたる運行を必要としたから、原子爆弾を製造することは、いずれにしろ莫大な技術上の出費を要することだろうことは、われわれには明白であった。そこで以上をまとめると次のように言えるだろう。この時点では、われわれは原理的には原子爆弾は作り得るということを知っていたし、一つの実現可能なやり方も知っていた。しかしわれわれは、それに必要な技術上の出費を、実際に要したよりも過大に考えていた。そこでわれわれは、政府に対して問題の現状を全くありのままに報告でき、同時に、ドイツでは原子爆弾の製造を真剣にやれ、という命令は下されないだろうことを確信していられるという幸運な状態にあった。というのは、ほとんど信じられないような未来の目標に対して大きな技術的出費をすることは、ドイツ政府にとって、切迫した戦況下ではとうてい受け入れられないものであったから。(p.289-90)
そうした見通しにハイゼンベルグたちあったのは確かでしたが、しかし、それに安住していられる状況でもありませんでした。同書はこう続きます。
それにもかかわらず、われわれは一つの非常に危険な科学的かつ技術的発展に参画しているという感じをいだいていた。特にカール・フリードリッヒ・フォン・ワイツェッカー、カール・ビルツ、イェンゼン、ハウターマンたちと、私は、時折、われわれが着手している仕事を継続するこの可否についても相談した。ダーレムのカイザー・ウィルヘルム物理学研究所の私の部屋で、イェンゼンと入れ違いに入って来たカール・フリードリッヒと交わした一つの対話を、私は思い出すことができる。カール・フリードリッヒは、次のような確認から話しはじめたと思う。
「われわれはたしかに、さしあたり原子爆弾に関してはまだ事実上危険地帯には入っていない。なぜなら技術的な出費は、本気で手をつけるためにはあまりに大きすぎるようだからね。しかしこれも時間がたつと変わるかも知れない。だから、われわれがここでさらに仕事を続けることは正しいことだろうか? そしてアメリカのわれわれの仲間たちはどうしているのだろう? 彼らは全力をあげて原爆に向かって邁進してはいないだろうか?」
私はつとめて彼らの立場に立って考えようとした。
「アメリカにおける物理学者、とくにドイツから移住した者の心理状態は、たしかにわれわれのものとは完全にちがっている。彼らは海の向うで、悪を排し善のために戦うべきことを決意したにちがいない。殊に移住者たちは、彼らがアメリカによって暖かく受け入れられたということから、アメリカのために全力を捧げることを当然義務づけられているように感じているだろう。しかし、一度でもって、おそらく十万人の市民を殺害し得るような原子爆弾は、他の武器と同じに考えてよいだろうか? われわれは、古くからあるがしかし問題のある原則、すなわち、“悪のための戦いに許されない手段も、善のためにはすべて許される”という原則を適用してもよいのだろうか? つまり原子爆弾も悪のためにではなく善のためなら作ってもよいのか。それは世界史上で、残念ながらいつも繰り返され、押し通されてきたものだが、かりにこの立場に立つとして何が善で何か悪であるかということを、いったい誰が決めるのか? たしかに今の場合には、ヒトラーとナチスのすることは悪いと断定することは容易だろう。しかしアメリカのすることはすべての点において善であろうか。(中略)とはいっても、アメリカにおいても物理学者は原子爆弾を製造するためにそれほど必至の努力はしないだろうと僕は推測している。しかし、彼らはもちろん、われわれがそれをやっているかも知れないという不安に駆られて、せきたてられることはあり得ることだ。」(p.290-92)
・・・事実、戦争中の経過も、ドイツにくらべればその研究に対する外的な条件は比較にならないほどめぐまれていたアメリカにおいてすら、原子爆弾はドイツとの戦いが終わるまでには完成しなかった・・・。(p.293)
・・・われわれにとって、すなわちドイツにおける“ウラン・クラブ”の組合員にとっては、状態は基本的にかなり簡明なものであった。政府は(1942年6月)原子炉計画の仕事は、無理のない枠内においてのみ継続されるべきであるということを決定した。原子爆弾の製造のための実験は命令されなかった。この決定を修正するように努めるべき何らの理由も、物理学者はもたなかった。それによって、ウラン計画の仕事はそれ以後、戦後における平和的な原子技術のための準備となり、それは戦争の最後の年における荒廃にもかかわらず、なお有用な実りをもたらした。(p.293-94)
以上のようにして、ドイツは潜在的に原爆の開発能力はありながら、国内物理学者らの冷静な取り組みで、それを追究することにはならず、しかも、アメリカによる開発が完成する前に降伏となり、自国がその被災をこうむることはありませんでした。
アメリカの原爆開発には、上記にあるように、ドイツから亡命した物理学者の貢献もふくまれているわけです。そういう意味では、その使用が元の祖国に行われようとした場合にはそれなりの抑制がかかったかも知れません。ともあれ、その恐ろしい武器の開発をモラル上許したのは、それが善のために悪に対してもちいられるという点でした。
さてそこで日本なのですが、そういう「悪」にたいする「善」の用いるやむを得ない手段として、日本への原爆の投下が決定されたのは確かです。そして、その道義的意味についても、「戦争の早期終結」を大義名分とした決定であったことは、今日までも、正当な判断であったとしてアメリカ社会ではゆるぎなく引き継がれています。
そこで確実なことは、日本ももし、ドイツが降伏した1945年5月頃の段階で降伏を決定していれば、原爆の投下はありえなかったことです。
そうした意味では、戦争状態の引き伸ばしが、両国の指導者レベルで――日本の場合は天皇制の維持のため、国民の徹底した戦争消耗が行われた(『天皇の陰謀第28章』及び「罪意識の共有」参照)――望まれた状況があったわけです。
むろん米国には、上記のように、戦後の世界戦略上の対ソ牽制のねらいもあり、ともあれ、いくつもの意味をもって“必要”と判断されたのが、「ヒロシマ・ナガサキ」であったと言えましょう。
日本への原爆投下とそれを契機とした戦争終結には、争い合う二国間の勝った負けたとの視点を越えて、上記のように、人間社会の道義の問題として、なされるべきでない行為が実際になされたという、今日でも人類史上それ以外に例のない、異例かつ非道を承知の上の歴史的惨事であったわけです。
さらに、戦争全体として見れば、この戦争により、「ヒロシマ・ナガサキ」や各大都市への無差別絨毯爆撃、そして南海の孤島に食糧支援すら断たれて飢え死にした多くの兵士を含め、日本側でおよぞ三百万人、アジア・太平洋全体では二千万人と推定される死者をもっての戦争終結であったわけです。
憲法第9条とは、むろん米国の戦後日本支配の道具とする意図は込められたものですが、そうした無数の命の損失に加え、各国指導者によるもろもろな政治的いきさつが引き起こす、そうした歴史的惨事を体験した事実がゆえの誰しもの反省としての宣言であり、そこには、それほどの規模の死者となった声なき声の集積としての願いの託されたものであるわけです。
そういう意味では、憲法第9条とは、それは、法規というより、そういう事実の表記であり、記憶され続けるべき銘記としての条文と見るべきものだと思います。そしてさらに、それは一国の憲法の条文にもかかわらず、人類的な規範を規定した宣言です。よってそれは、改正うんぬんという問題の対象になるべきものではない内実を持っているわけです。
ゆえにそこには、さまざまの「解釈問題」としての紆余曲折が試みられるしかなく、その他の詳細条項の変更をもって、事実上のその精神の曲解が図られているのだと思う次第です。