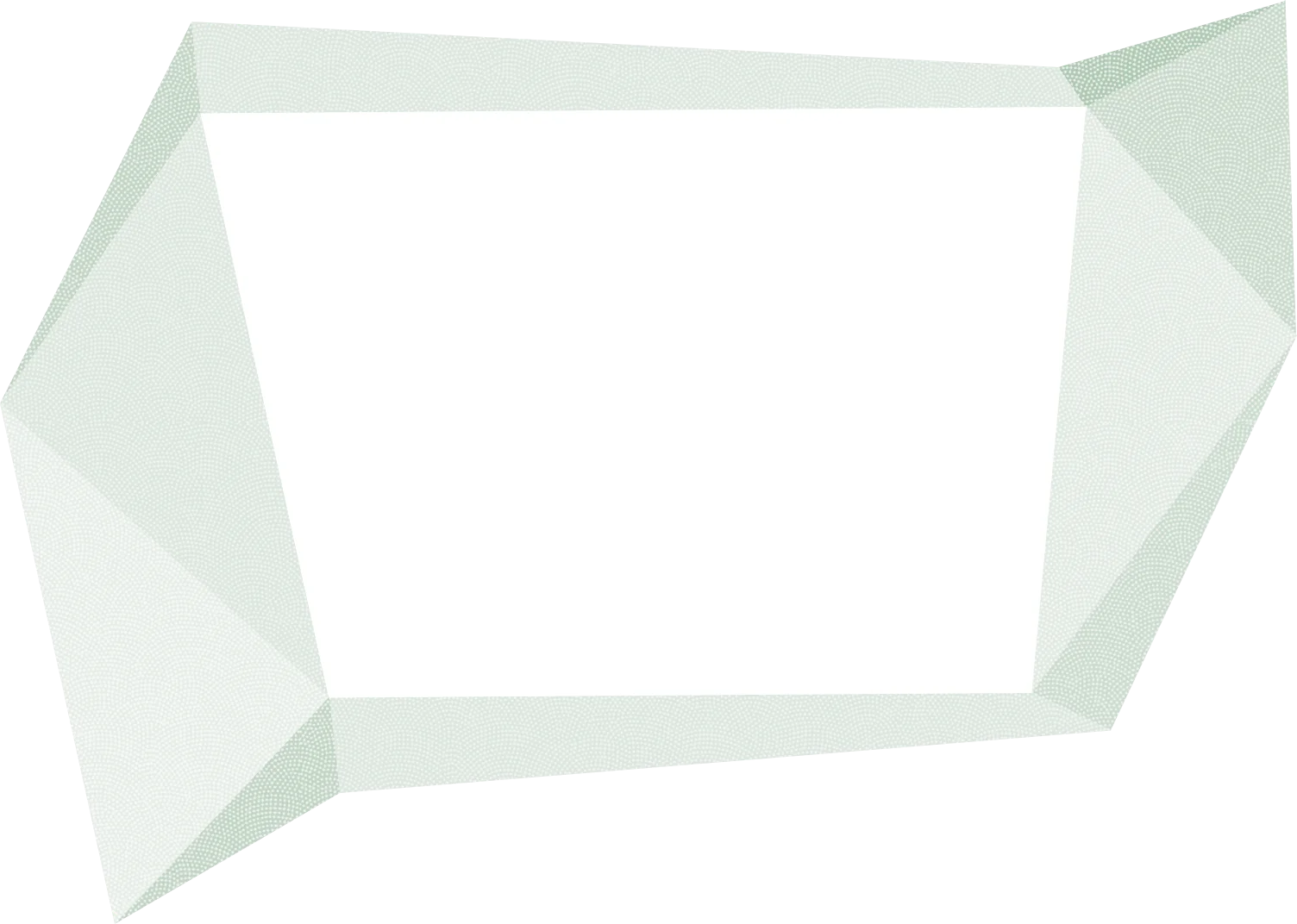この《独想記》は、既述のように、前立腺ガンという――遅行性ながら――致命的「災難」との遭遇に始まる一種の闘病記との役割は持っています。しかし、それに終わらせず、それを契機に、自身のこれまでの思想的取り組みである〈非科学-科学〉構想とを結び付けた、言うなれば、「自分実験」のまたとない機会であり、それを是非とも生かしたいとするものです。
私はこの前立腺ガンになるまで、健康との観点で自分を実験台にするとの発想はありました。それが、この罹患を境に、たとえガンであろうとその実験内容の重要なテーマとなることを覚らされました。それが「ガン付き健康」との認識です。むろん、それが命に関わるものであるだけに、その切迫度は、一般的な健康意識とは別格のものがあります。
そうした「自分実験」の観点も含めた今後への方向として、この闘病と思想的発展と言う「両面」狙いの課題について、前号では、以下のように《双対(そうつい)的》という用語をもってさらなるテーマを提示し、ひとまずの結語としました。
この「両面」という課題は、この独想記の第3号や『フィラース』掲載の「生命情報」最終章で述べた《双対的》という用語をもって言及される、二つの要素が絡み合って働く特異な現象に――ことに量子論との関連を含め――ついて、さらに新規な観点を提供しています。そうしたいまや最先端な知見ついては、号を改めて述べるつもりです。
そこでですが、先に進む前に、ここでちょっと説明をはさんでおきますと、私はこれまで、自分の表現の場として、この『両生歩き』と他に『フィラース』という二つのサイトを設け、活用してきています。そして、これら二つの自己表現上の“道具”を、前者つまり本サイトを具体的な日常的テーマを扱うそれとし、後者を主に思想的に掘り込むそれとして、それぞれに使い分けてきています。
さて、ここに私は、この思想的な掘り込みのひとつとして、この《双対的》という用語を採り上げます。そして、この「両面の課題」の打開のための、日常的具体性と、理念的な構想とを合体させることによる可能性に期待しようとしています。
いうなれば、自分を実験台とした取り組みにあたって、具象的には、ガン細胞の消滅というゴールを狙えるかもしれない機会とし、また理念的には、私独自の思想的取り組みである〈非科学-科学〉構想とも絡めた、「両面」的な視点での自分実験アプローチです。先のたとえ話で言えば、「山頂なき登山」をする二つの違った登山道をへて達するべき「究極のゴール」への過程です。
そこでなのですが、ここで想い起すことがあります。
私が二十代半ば――1970年代初め――の時、定職を放棄し、今で言う「フリーター」という不安定職を自分で選びながら、それが余りに暗澹とした細道と思い知らされていた頃、古い書物を通じて知ったある至言があります。それは、昭和十年代の愛国/軍国主義による弾圧の中に生き、また殺されもした当時の善良な精神が告げていた、「悲観し過ぎもせず、楽観し過ぎもしない」 という、ひとつの心構えを自分なりに肝に銘じさせてくれた言葉です。
以下は、その若き自分が、そのようにして戦前の「善良な精神」から受け取ったメッセージを、それから40年後、再び想起し、あらためてノートした部分からの引用です。
ことに、 『昭和文学の可能性』 に当時発見した、広津和郎の 「みだりに悲観もせず、楽観もせず」 との言葉は、そうした戦前を生きた精神が伝える戦後世代の私へのメッセージであるかのように受け止められ、私の胸に強く響いたのでした。ちなみに、戦後、大江健三郎が原爆病院長重藤文夫のすがたを描いて 「絶望しすぎず、希望をもちすぎることもない」 との表現をしているところにも、同質のものを感じます。(「昭和文学の可能性」の文末部分より)
つまり、私が受け止める《双対的》とか《双対性》という用語は、以上のように、自分の人生を通じて培ってきた精神に通じるもので、苦しく重たい「板挟み」にある自分をその渦中からなんとか冷静に脱出させようとする際の、自分を勇気付け方向付ける言葉でありました。
私は、こうした人生体験から、それが否定的であれ肯定的であれ、対峙する二極の価値観に挟まれて身動きとれないような事態を、一種の既成の価値体系から脱出する機会と捉え、そうした前向きの姿勢を《双対的》とか《双対性》という言葉に託すようになりました。
つまり、《双対的》とか《双対性》は、たんに二者錯綜する概念にとどまらず、現状を突破する、ブレークスルーの機会を示唆している言葉なのです。
ここで視点は大きく変わるのですが、以上のような私個人の思想的発展の一方、そうした《双対的》とか《双対性》といった観点が、現代科学のまさにそのど真ん中でも注目されています。

「量子もつれ」を特集する『日経サイエンス』2023年12月号
それは、最先端科学の量子理論において、素粒子という超微細な世界における、物質の素がもつ、相対峙する二つの要素があることです。
それは、原子でなら、プラス電子とマイナス電子、磁界でなら、N極とS極といったように、素粒子がもつスピンとよばれる二種の性質です。つまり、自然を構成する物質のその素の素に存在している《双対性》なのです。
そうしたスピンが、上向きスピンと下向きスピンと言った具合に二別して名付けられ、しかもそうした二つの特性が、従来の科学の発想を逸脱する振る舞い――あのアインシュタインでさえ、それを「幽霊のような」と呼び、理解し切れないでいた――を示すのです。
これが、「量子もつれ」とか「量子エンタングルメント」と呼ばれる現象です。
私はここで、その現象の詳細には立ち入りませんが、自然界は少なくとも素粒子レベルで、従来の私たちの常識を破る振る舞いを示すのです。そして私が特に注目するのは、この「量子もつれ」とは、「量子テレポーテーション」とも呼べる、距離の離れた間での瞬時の相互の呼応関係を示すことです。
もちろん、こうした発見は、素粒子というミクロレベルに限られた現象で、それが、私たちの身体のようなマクロレベルでも起こる現象であるとはいまだ検証されていません。
しかし私はこのマクロレベルでもの「量子もつれ」の現象を、私の人生上の体験を根拠に、それが実際に「起こっている」と受け止めています。そういう〈観測〉をしています。そしてその現象を先取りもして、人間レベルでもその要素が働いているに違いないと仮説を立てます。
それが、私が《量子センサー》と呼ぶ、私の内部で働くある種の感覚器です。
そしてさらに発展させて、その仮説としての《量子センサー》の働きを体系付けたものが、東洋医学でいう〈経絡(けいらく)〉だと踏んでいます。
この経絡思想については、いま、ここに詳述すべき、ことに最新の材料はないのですが、まもなく、それを特集した、鍼灸医学界の雑誌が発刊されます。
そこで、この続きについては、その発刊をまって、さらに論じてゆきたいと思っています。
【バックナンバー】
1号「全摘、是か非か」
2号「山頂なき登山」
3号「『究極のゴール』、私の場合」
4号「次の十年紀へ」